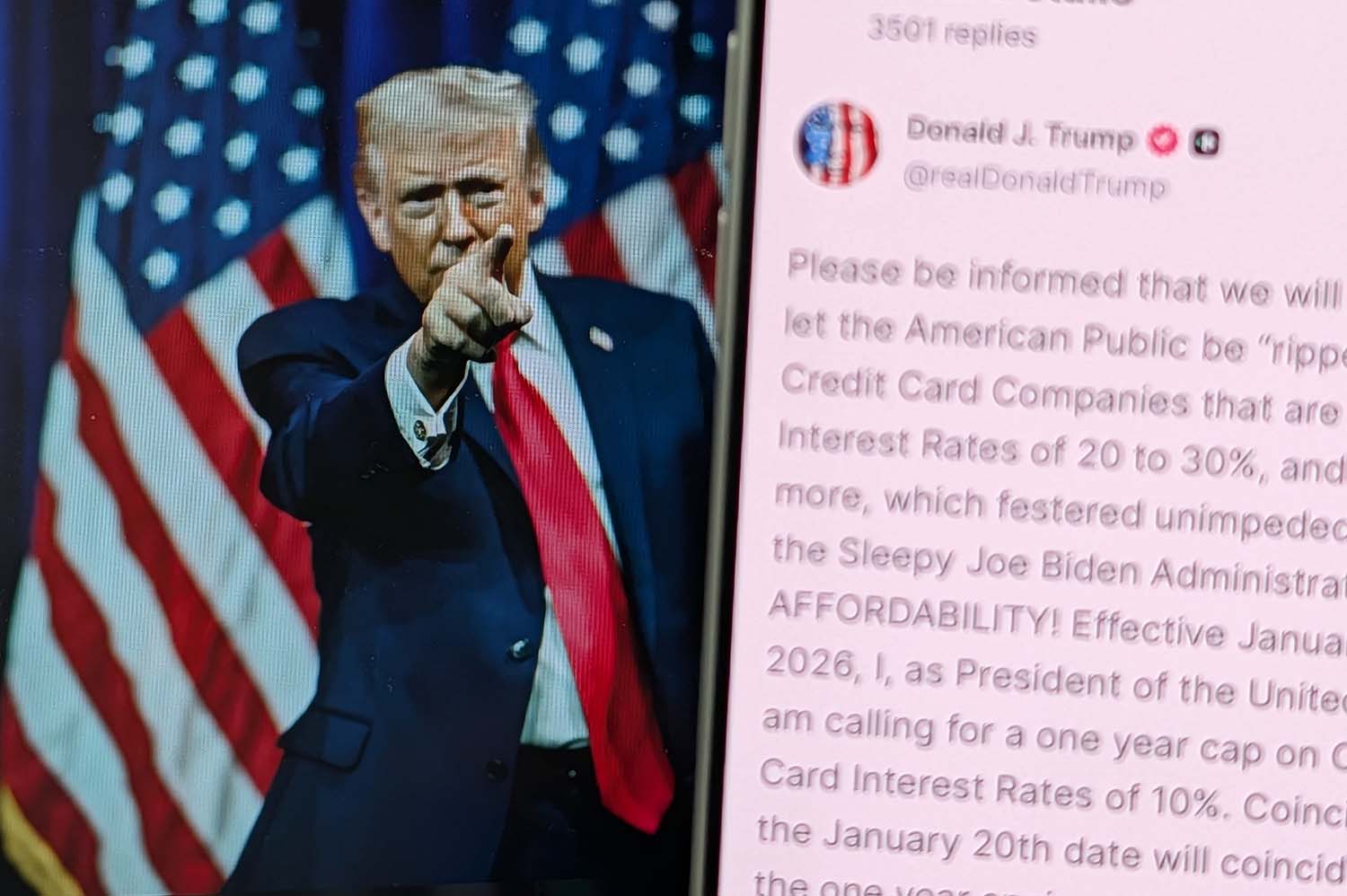【コラム】米経済、スタグフレーションで済めば幸運-ダドリー

トランプ政権が世界からの輸入品に課す関税によって米国経済が打撃を受けても、連邦準備制度理事会(FRB)が救済に動くことは期待しない方が良い。今や問題は、被害がどれほど深刻になるかだけだ。
トランプ氏による自由貿易への攻撃は、その範囲と規模、細かい配慮の欠如という点で、まさに異例と言える。加重平均関税率は今年、従来の3%未満から25%に上昇する公算が大きい。この増加は、トランプ氏が1期目に行った関税措置の10倍余りに相当する。
その影響は壊滅的なものになろう。今後6カ月で年率換算のインフレ率は5%近くまで上昇する可能性が高い。関税が輸入品の価格を押し上げるだけでなく、競争から保護される国内生産者もその状況に便乗して値上げを行うとみられるからだ。
一方で需要は減退することになる。関税がどのくらいの期間や範囲で続くのか、諸外国・地域からの報復措置はどの程度になるのかが不透明な中、企業は投資を先送りするだろう。関税措置は実質的に6000億ドル(約88兆8000億円)超の増税に相当するが、それに対応するため消費者も支出を控えることになる。こうした状況は、たとえ議会が減税措置で打撃を緩和しようとしても避けられそうにない。なぜなら、減税効果が表れるまでに相当なタイムラグがある上、低中所得層では関税による打撃の方が減税による恩恵を大きく上回るからだ。
さらに悪いことに、他の要因で経済の成長力そのものが損なわれる見通しだ。強制送還や移民の急減によって労働力の供給が弱まる一方、生産性の伸びは鈍化するとみられる。これにより、実質国内総生産(GDP)の成長率は昨年の2.5-3%から、およそ1%にまで落ち込むことになるだろう。
以上を踏まえると、スタグフレーション(景気停滞とインフレの同時進行)はむしろ楽観的なシナリオであり、より可能性が高いのは、インフレ加速を伴う本格的なリセッション(景気後退)に米経済が陥るという展開だ。
そうした中、金融当局に何かできることはあるのだろうか。通常であれば利上げによってインフレと闘うが、それでは不況を深刻化させることになる。パウエルFRB議長は、物価上昇が一時的なものであり、将来のインフレ期待に影響を与えないのであれば、利上げの必要はないかもしれないと示唆している。議長のこうした姿勢は投資家に一定の安心感を与えた。
しかし、FRBがその姿勢を続けられるかどうかには疑問の余地が大いにある。まず第一に、インフレ率は長期にわたって目標の2%を上回って推移している。仮に5年連続でインフレ率が当局目標を上回り、さらに加速するようであれば、インフレ期待が制御不能になるという重大なリスクが生じることになる。
次に、ショックの性質が問題だ。トランプ関税のように生産性を損なうタイプのショックは、インフレとインフレ期待により長期的な影響を及ぼす恐れがある。1970年代の2度のオイルショックを考えてみよう。2度のリセッションにもかかわらず、インフレは根強く残った。最終的に当時のFRBはボルカー議長の下、政策金利を20%に引き上げ、経済を深刻な景気後退に陥らせることでようやくインフレを抑え込むことができたのだ。
FRB自身の行動がインフレ期待に影響を与えるという点も重要だ。FRBがインフレ圧力を無視して経済成長ばかりを重視していると受け止められれば、その認識だけでインフレ期待は上昇することになる。
インフレ期待は、実際のインフレと闘うためのコストを左右するうえで極めて重要な役割を果たす。過去5年間と同様にインフレ期待がしっかりと固定された状態であれば、当局はあまり失業率を上昇させることなくインフレを管理することが可能だ。しかしインフレ期待が上昇してしまえば、犠牲率は急激に高まることになる。例えば1970年代のオイルショックのような状況では、インフレ率を1ポイント下げるためには、失業率が長期的な水準よりも2ポイント高まってもやむを得ないという厳しい調整が必要になる。言い換えれば、景気後退がFRBにとって唯一の選択肢になるということだ。
この非対称性は、米国経済が苦境に陥る中でFRBが非常に慎重な対応を迫られることを意味する。インフレ期待を刺激するような金融緩和を行えば、後になってより厳しく、より高コストな金融引き締めを余儀なくされることになるだろう。だからこそ筆者は、金融当局による救済について投資家は楽観的に過ぎると考えている。それどころか、リスクバランスと経済的不確実性の高さを考慮すると、当局の一段と慎重な対応こそが正当化されるのではないか。
成長鈍化、インフレ加速、動かないFRBという組み合わせは、株式市場にとって好ましい状況ではない。まさに勝ち目のない状況だ。企業が輸入コストの上昇分を消費者に転嫁すればインフレはより長期化し、金融当局はタカ派色を強めることになる。半面、価格転嫁ができなければ企業の利益率は縮小し、業績が圧迫される可能性が高くなる。諸外国・地域からの報復関税のリスクは言うまでもない。
債券市場で焦点となるのは短期金利の動向だ。現在、市場では年内100ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)の緩和が織り込まれている。それが現実的になるのは(かつ正当化されるのは)、実際に景気減速が起きた場合に限られると筆者は考えている。今は2019年とは違う。当時はインフレ率が当局目標を下回っており、リセッションに対する「保険」として先回りの利下げを行う余地があった。現在、世界で最も影響力のある中央銀行であるFRBでさえ、対応の余地はほとんどない。
(ニューヨーク連銀の前総裁、ウィリアム・ダドリー氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストです。このコラムの内容は、必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:Stagflation Is Now America’s Best-Case Scenario: Bill Dudley(抜粋)