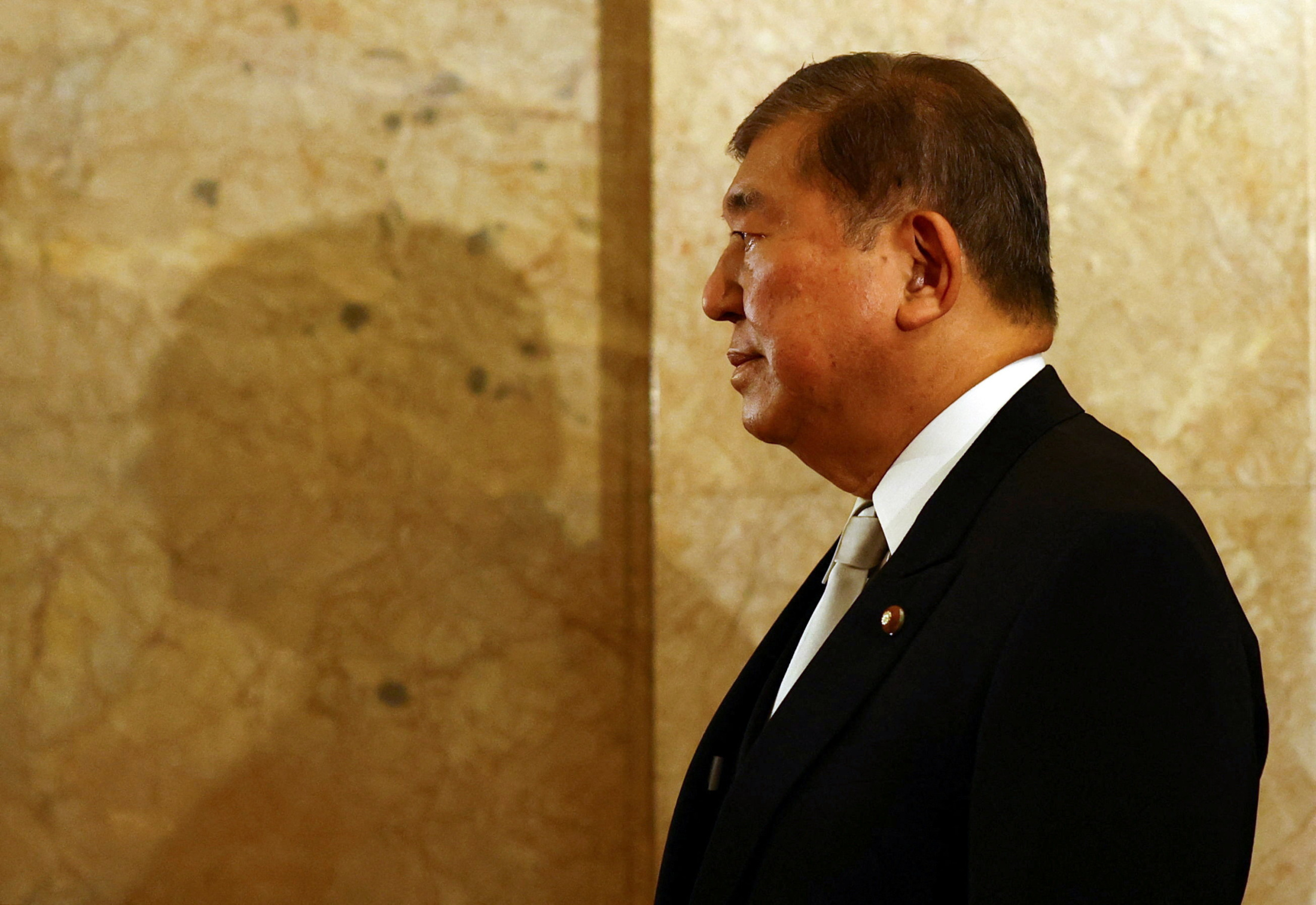最古のRNA配列、4万年前のマンモスの最期の詳細を明らかに

シベリアの永久凍土から発掘されたマンモス「ユカ」の展示/Valeri Plotnikov
(CNN) 現在のシベリアで約4万年前に死んだ若いマンモス「ユカ」から古代のリボ核酸(RNA)が採取された。こうした生物学的な遺物が、マンモスの最期の瞬間に関する洞察を提供している。
今回のRNAは、永久凍土で何千年も極めて良好に保存されていたミイラ化した脚部の組織から抽出された。これほど古いRNAが解析された例は初めてで、研究者は死亡時にどの遺伝子が活性化していたのかを明らかにしようとしている。
「生物のすべての細胞は、脳細胞でも肝細胞でも筋細胞でも同じDNAを持っている。だから、これらの細胞を互いに区別するものは、本質的にRNAだ」と語るのは、ストックホルム大学古遺伝学センター教授(進化ゲノミクス)で、論文の筆頭著者であるラブ・ダレン氏。ダレン氏は「これは、異なる細胞種においてどの遺伝子がどのようにオン・オフになるかという問題だ」と語った。今回の論文は科学誌セルで発表された。
DNAとRNAはすべての生物に存在する。DNAが生命の「ハードコード」であるのに対し、RNAはDNAから指示を読み取り、細胞がたんぱく質を作るのを助ける「メッセンジャー」として機能する。
古代のDNAは100万年以上残存し、過去に対する理解を大きく変えてきた。一方、RNAは「すぐ消える」と考えられてきた。今回の手法が例外的に保存状態の良い試料以外でも有効なのかは、まだ分かっていない。
研究チームは凍結したマンモス組織の筋肉や皮膚など10点の試料を分析し、3点からRNAの断片を検出した。そのうちひとつだけが、死亡時にマンモスの遺伝子がどのように機能していたかを解明できる詳細な配列データを提供した。その試料が2010年にシベリアで発見されたユカの遺体だった。
データからは、メッセンジャーRNAとマイクロRNAが確認された。これらを組み合わせることで、「このマンモスが死ぬ直前に細胞内で起きていた生物学的現象」の一部が明らかになったと語るのは、論文の主著者でコペンハーゲン大学グローブ研究所のポスドク研究員エミリオ・マルモル・サンチェス氏。
「この個体は死期が近かったと仮定しており、それは筋肉の代謝にあらわれている」(マルモル・サンチェス氏)
研究によれば、マンモスの組織における「遅筋線維の優勢」が示されており、これが「最終脈動」だった可能性がある。
「マンモスの組織から見つかった筋肉特異的なマイクロRNAは、古代において遺伝子調節がリアルタイムで行われていたことを示す直接的な証拠だ」とストックホルム大学准教授で、論文の共同著者であるマーク・フリードレンダー氏は述べた。「こうした成果は初めてだった」
シベリアで見つかったマンモスの死骸(Love Dalén)
世界最古のマンモスのDNAを解析したダレン氏は、チームが開拓した技術は過去に対する科学的研究の新たな道を切り開く可能性があると語った。
「これらの10点の試料はいずれも非常に良質で独自性があり、その中でも特に優れた3点だけがうまくいったので、一見するとかなりニッチなように思える」「私の直感では、手法は改善されるだろう。世界中にRNAに関心を持つ研究室がたくさんある。RNAを回収するための、はるかに優れた方法が開発されると確信している」(ダレン氏)
この手法が広く応用可能になれば、RNAの形でしか存在しない多くの古代ウイルスの進化を研究する道が開けると、ダレン氏は述べた。古代細菌のDNAを配列解析することで、ペストや梅毒といった細菌性病原体の遺伝的起源と進化を研究できているのと同じ理屈だ。
マンモスのRNAは、科学者がこれまでに回収した中で最も古いものだが、初めてというわけではない。2023年にはスウェーデン自然史博物館に所蔵されていた130年前のタスマニアタイガー(フクロオオカミ)のRNAの配列を解析する研究が行われた。