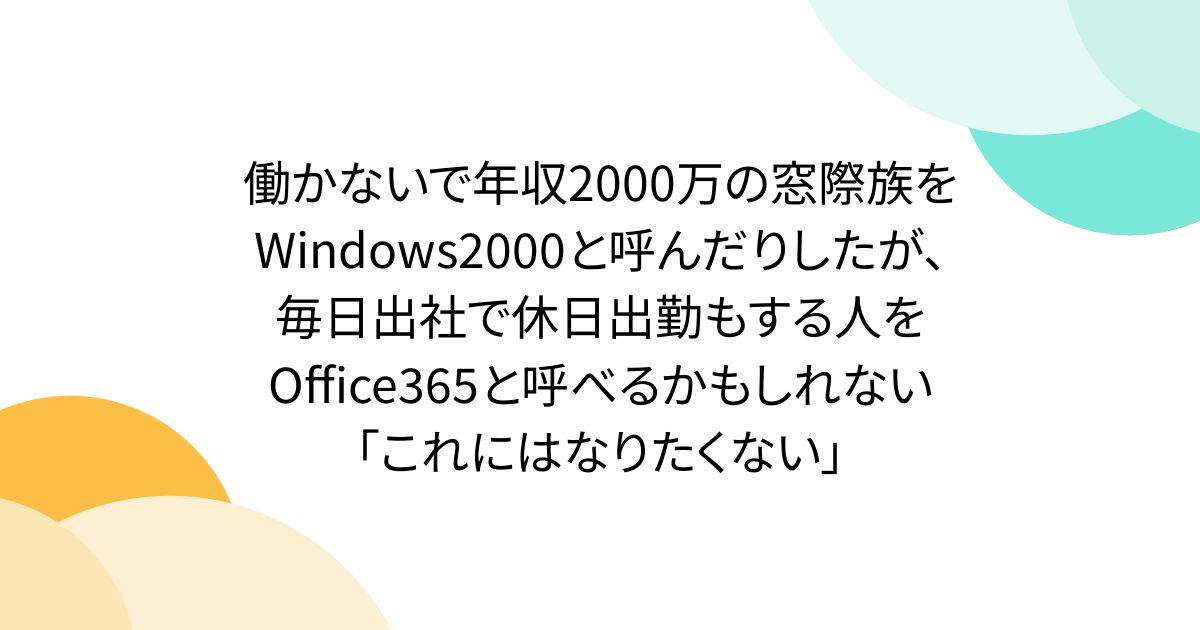【西川和久の不定期コラム】Ryzen AI Max+ 395とメモリ128GBを搭載したミニPC「GMKtec EVO

アクセスランキング
Special Site
PC Watch をフォローする
最新記事
Impress Watchシリーズ 人気記事
おすすめ記事
Ryzen AI Max+ 395搭載ミニPC「GMKtec EVO-X2」の初回ロットの出荷が始まってから時間が結構経ってしまい、出遅れ感があるものの、編集部からついに実機が送られてきたので試用レポートをお届けしたい。今回はいつものレビュー編、次回はLLMや画像生成などAI系編と、2回に分けて掲載したい。
過去の連載で同社の「EVO-X1」を扱っているが、これはRyzen AI 9 HX 370を搭載し、メモリLPDDR5X-7500 32GB/64GB、ストレージは1TB。筐体はコンパクト、価格も10万円台中盤前後と、なかなか魅力的な1台だった。
そして今回ご紹介するのは「EVO-X2」。ぱっと見、X1かX2かの違いで大差なさそうに見えるが、本機に関しては凄まじい差がある。
最も大きな違いはプロセッサがRyzen AI Max+ 395になり、メモリもLPDDR5x-8000で128GB(64GBと96GBもある)であることだ。その分、筐体は大きくなっている。つまりEVO-X1と比較すると、1か2か……という数字どころの違いではなく、完全に別もの的なミニPCとなる。主な仕様は以下の通り。
プロセッサはRyzen AI Max+ 395。最近よく見かけるRyzen AI 9 HX 370のさらに上のSKUとなる。16コア32スレッドで16x Zen 5。クロック最大 5.1GHz。キャッシュ L2: 16MB、L3: 64MB、TDP 55W(cTDP 45-120W)。最大50TOPSのNPUを内包する。
メモリはオンボードでLPDDR5x-8000 128GB。一般的なPC用途としては現時点で最高速で最大容量。iGPUのパフォーマンスやLLMの推論速度など、いろいろな場面で結構効いてくる。
以下の画面キャプチャはHWiNFOを使ったものだが、負荷をかけた後のメモリ読み取り帯域が約172GB/s出ている。DDR5-5600だとデュアルチャネルの場合、理論値が最大89.6GB/s、Apple M4が最大120GB/s、Apple M4 Proが最大273GB/sなので、結構頑張っているのが分かる。
ストレージはM.2 2280 2TB SSD。M.2スロット自体は2つあり1つ空きだ。OSはWindows 11 Pro。24H2だったのでこの範囲でWindows Updateを適用し評価した。
グラフィックスはプロセッサ内蔵、Radeon 8060S Graphics(40コア)。外部出力用にHDMI、DisplayPort、USB4 2基を装備。
ネットワークは2.5GbE、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4。そのほかのインターフェイスは、前面がUSB 3.2 Gen 2 2基、USB4、SDカードスロット、3.5mmジャック。背面がUSB 3.2 Gen 2、USB 2.0 2基、USB4、3.5mmジャック。これだけ大きい筐体なので2.5GbE 2基やOCuLinkも欲しかったところだが、とはいえこれだけあればまず困らない。
サイズ193×185.8×77mm、重量は実測で1,678g。価格は39万3,990円(Amazon調べ)。執筆時-9万5,000円のオフクーポンがあるほか、10月26日までクーポンコードなどを併用すると28万円台で購入可能だ。ちなみに公式サイトでは、クーポンコード「GMKX2PR」を利用すると5%割引となり、64GB/1TBモデルは20万9,753円、96GB/2TBモデルは26万5,383円、128GB/2TBモデルは28万716円といった具合だ。
ミニPCとしては高額だが、(いろいろ性能なども異なるものの)たとえば筆者が所有するM4 Max 128GB搭載MacBook Proだと80万円。クーポン適用可能であればかなり安い!という評価になる(笑)。
筐体はご覧のように少し変わった形状をしており、サイズの異なる2つの筐体が合体したような雰囲気になっている。大きさはiPhone 16 Proとの比較からも分かるが、これをミニPCと呼んでいいのか?という感じだ。重量も実測で1,678gと重い。
前面は、3.5mmジャック、USB 3.2 Gen 2、USB4、SDカードスロット、P-MODEボタン、電源ボタン。P-MODEボタンは本機の動作をハイ/ノーマル(デフォルト)/ローと切り替えるもので、後述するベンチマークテストはノーマルの状態で行なっている。
背面は、USB 2.0 2基、HDMI、DisplayPort、USB4、USB 3.2 Gen 2、2.5GbE、3.5mmジャック、電源入力。2.5GbEの上には“初期起動時は接続するな”的な黄色いシールが貼られている。これは以前指摘したが、Windows Updateが始まると時間単位でかかり、初心者だと故障か?と思ってしまうWindowsの欠陥でもある。メーカーがここまでしないとならない状況を、Microsoftはどう考えているのだろうか?
付属品は、ACアダプタ(サイズ約150×73×25mm、重量534g、出力19.5V/11.8A/230.1W)、HDMIケーブル。BIOSは起動時[DEL]キーで表示する。iGPUのVRAMはデフォルトで64GB。
内部へのアクセスは、ゴム足の部分に1+2本(2組)のネジがあり、2本を外すと裏側のパネル、4本を外すとロゴのあるパネルが外れる。前者に関しては外したところで交換可能なものはなく、中型?のファン2つと、若干の部品が見えるだけ。
後者に関しては大型のファン1つ、その下にM.2 2280のスロットが2つ見える。うち1つはSSD装着済み、もう一方は空きなので増設可能。スペースもあるため装着も容易だ。
なお、ロゴのある面の上側に[FAN-MODE]ボタンがある。これは上記の大型ファンが7色に光り、その発光パターン切り替え用だ。
ノイズはこのサイズのファンが3つあるとそれなりに音がする。といっても筐体へ耳を近づければ的なレベルであり、あまり気にすることはないだろう。
発熱はベンチマークテストなど、プロセッサに負荷をかけると、背面パネルのスリットから(火傷はしないが)結構熱い風が出る。設置する時、後の状況を少し考えた方がいいかもしれない。
初期起動時、壁紙などはWindows標準のままだが、デスクトップにAIPCというショートカットがある。このアプリの説明は後編にするが、構成が構成なだけに、普通のデスクトップPCより速いのでは?と思える快適な環境となる。
M.2 SSD 2TBは「Lexar SSD NM790」。仕様によると、シーケンシャルリード 最大7,400 MB/s、シーケンシャルライト 最大6,500MB/s。CrystalDiskMarkの結果もほぼそのまま出ている。C:ドライブのみの1パーティションで約1.9TBが割り当てられ空き1.52TB。
2.5GbEはRealtek Gamming 2.5GbE Family Controller、Wi-FiはRZ717 WiFi7 160MHz、BluetoothもRZ717が使われている。
ベンチマークテストは、PCMark 10、PCMark 8、3DMark、Cinebench R23、CrystalDiskMarkを使用した。EVO-X1(Ryzen AI 9 HX 370)のスコアも併記したので参考にして欲しい。
なお、iGPUが強力なので普段はテストしないSpeed Way、Steel Nomad、Solar Bay、Wild Life、Port Royal、Night Raidも掲載している。
予想通りPCMark 10はDigital Content Creation関連、3DMarkは全般的に本機の強力さが伺える結果。ざっくりEVO-X1の倍のスコアを叩き出している。これならゲーミング用途でも結構行けるのではないだろうか。
[Read] SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 7090.992 MB/s [ 6762.5 IOPS] < 1182.38 us> SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 4867.686 MB/s [ 4642.2 IOPS] < 215.29 us> RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 841.724 MB/s [ 205499.0 IOPS] < 151.46 us> RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 68.076 MB/s [ 16620.1 IOPS] < 60.07 us>[Write] SEQ 1MiB (Q= 8, T= 1): 6574.285 MB/s [ 6269.7 IOPS] < 1273.91 us> SEQ 1MiB (Q= 1, T= 1): 5535.020 MB/s [ 5278.6 IOPS] < 189.29 us> RND 4KiB (Q= 32, T= 1): 721.392 MB/s [ 176121.1 IOPS] < 179.07 us> RND 4KiB (Q= 1, T= 1): 209.043 MB/s [ 51035.9 IOPS] < 19.52 us>以上のようにGMKtec「EVO-X2」は、AMD Ryzen AI Max+ 395/128GB/2TBを搭載した少し大きいミニPCだ。ベンチマークテスト結果からも分かるように、iGPUのパフォーマンスは圧巻。価格はクーポン適用時、28万円台と、高価ではあるが、内容を考慮するとかなり安い。
後編は今回触れなかったLLMや画像生成などAI関連について書く予定だ。お楽しみに!(つづく)。