「電場」が人間にとってわかりにくい「納得の理由」…「電場」とは一体何なのか?(田口 善弘)
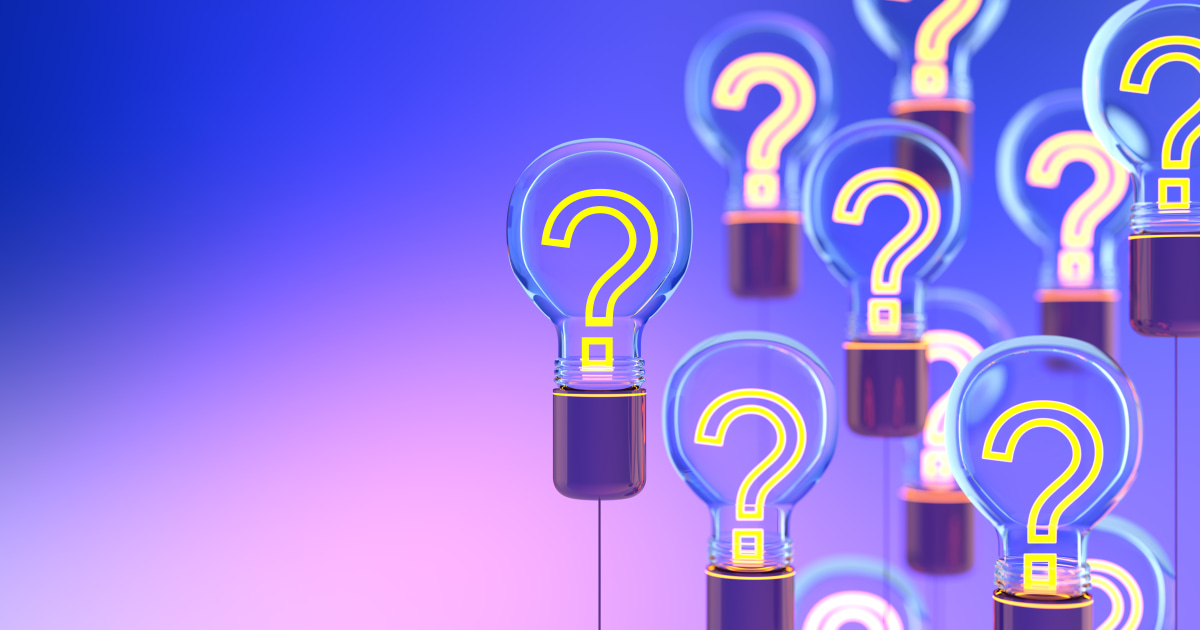
物理に挫折したあなたに。
大好評につき5刷となった講談社現代新書『学び直し高校物理』では高校物理の教科書に登場するお馴染みのテーマを題材に、物理法則が導き出された「理由」を考えていきます。
読み物形式で、納得!感動!興奮!あきらめるのはまだ早い!
本記事では〈「ブラウン管テレビ」はどのように動いていたのか?…「ブラウン管」で知る「電場」の謎〉に引き続き、電場についてくわしくみていきます。
※本記事は田口善弘『学び直し高校物理 挫折者のための超入門』から抜粋・編集したものです。
電場とはなんぞや?
電磁気現象を引き起こす源ともいえる「電荷」に働く力は、次の式で規定される。
実のところ、この「電場」という代物はわかりにくいことこのうえない。まず、電場は目に見えない。人間は静電場(時間によらず、変化しない電場をこう呼ぶ)を感じる器官を持たないので、電場があってもそれを感じることはできない。電荷を置いてみてそれに作用する力の大きさを見ることでしか感じることができない。
また、電荷というものは正負があるうえに、正と負の電荷は引きあってお互いのそばに集まりやすいので、正または負の電荷だけを集めることが難しい。それゆえ人間が感じられるほどの大きさの力を発生できるだけの正電荷や負電荷の塊を目にすることはまれなので、私たちは、目に見えない電場を電荷に作用する力を通して感じる機会にも恵まれない。結果、電場は人間にとって、とってもわかりにくいものになった。
電場は「水の流れ」みたいなものだと思うとちょっとだけわかりやすい。ただし、「川の流れ」のように時々刻々変わるものでなく、用水路のように水流が一定方向に、同じような速度で流れている状態を思い浮かべてほしい。
川を水が流れているときには川が水で満たされている。流れを作っているのは、「水」という実体を持つ物質である。これに対して電場は、何か実体のあるものが流れているわけではなく、「電場」という流れのようなものが存在しているだけなので流れがなくなると電場もなくなってしまう。
この実体は何もないのに流れは存在するというのはとってもわかりにくい。実際、物理学者は目に見えない何かが流れることによって電場が発生するのだとずっと思っていた。電場が何もない真空の中を「流れる」ことができるということに物理学者が気づいたのは、電場が発見されたかなり後のことである。
なので「流れる実体がないのに流れだけ存在するという電場はよくわからない」と感じても当然のことで不安に思うことはない。物理学者だってほかの可能性が全部否定されて初めて電場は何もないところを「流れて」いるんだとようやく納得したのだから。
水の流れに、何か物体を浮かべれば、水の流れに沿って移動していくだろう。ここでもし、その何かを流れに逆らってその場にとどめておこうとしたら何らかの力を加える必要がある。この力の大きさが静電気力で、川の流れの速さが電場の大きさ、川の流れの向きが電場に相当するものだと考えると、イメージが湧くかもしれない(もっとも、実際は電場に沿って何かが流れているわけではけっしてないのだが……)。感覚的な説明に違和感を覚える向きもあるだろうから、教科書的な説明をしておこう。
もう一度、クーロンの法則の公式をご覧いただきたい。
正電荷が2つあるとき、外側に置かれた電荷に働く静電気力は2つの正電荷の積を距離の2乗で割ったものに比例することがクーロンの法則でわかっている。
次にこの静電気力で電場を定義することにする。電荷と電荷の間に直接力が働くのではなく、一方の電荷が電場を作り、その電場がもう一方の電荷に作用することで力が発生する、と考える。するとそのもう一方の電荷に働いている静電気力は、静電気力=電荷×電場と書けばいいことになるので電場=静電気力/電荷と定義できる。
中心の電荷が正電荷の場合、電場の向きも、外側に置かれた電荷に働く静電気力の向きと同じなので外向きとなる。静電気力の大きさは距離だけによるので、電場は正電荷の周囲に放射状に発生していることになるが、目には見えない。
一方、中心の電荷が負電荷になると外側に置かれた電荷に働く静電気力の向きも反対になるので、電場の向きも反対になる。つまり、負電荷の周囲の電場は同じ放射状だが、内向きになる。



