AIが職を奪う「常識」疑え、勝者は若手-敗者は経験豊富なベテラン幹部
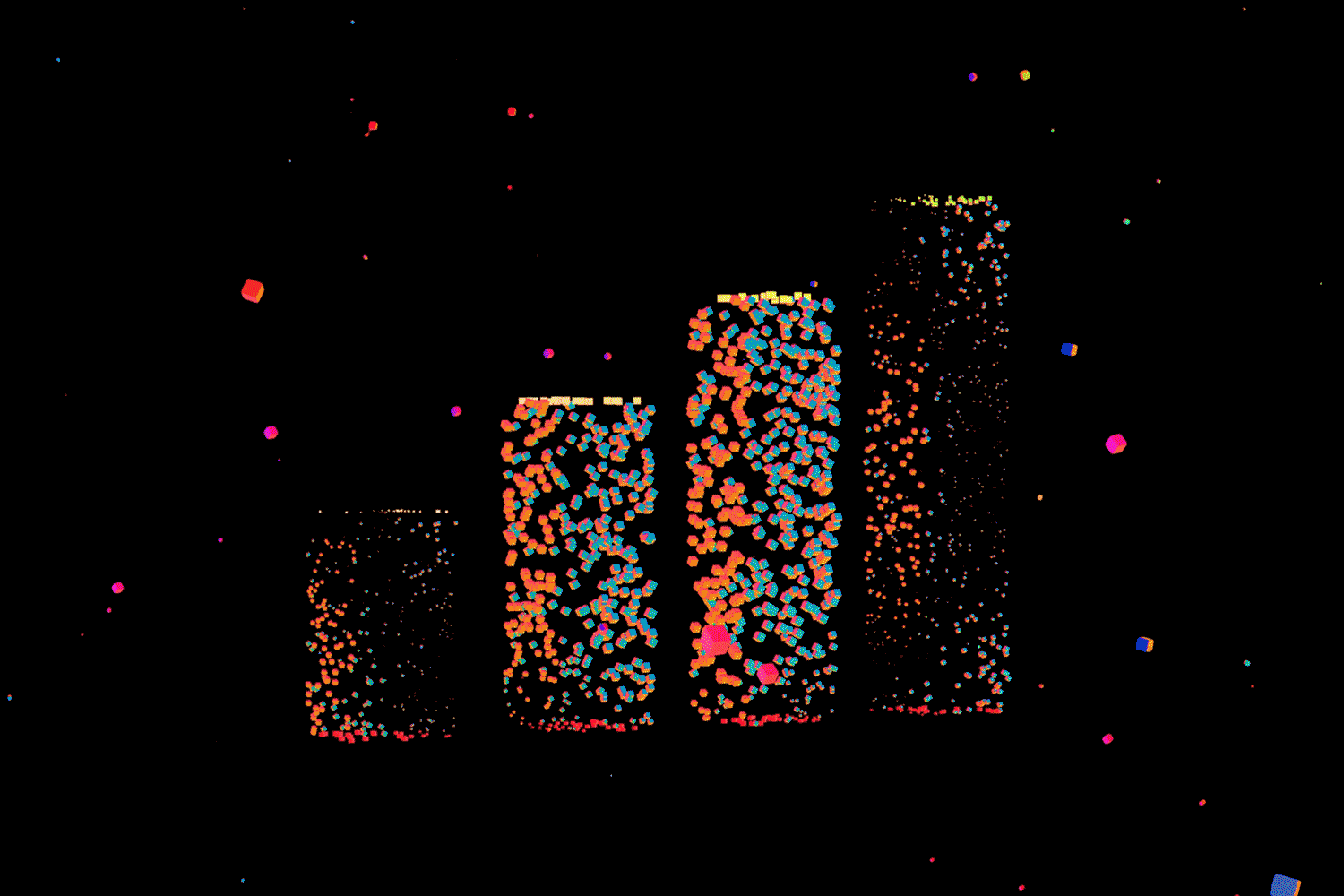
人工知能(AI)が進化する中、米国でAIが代替できる職の雇用情勢が悪化している。特に22-25歳の若手への影響が大きい。
この状況を受けて、AIが若い人材のキャリアを断ち切ってしまうと警告する声が後を絶たない。入社後すぐに担当するレベルの業務がAIに奪われ、若者がキャリアを積み上げられる雇用にありつけないという。
しかし、必ずしもそうとは限らないようだ。
AIがエントリーレベルの雇用を脅かすという報道はあまりにも多い。もはや「常識」のように語られているが、新しい技術が最も悪影響を与えるのは若者だという経済法則は存在しない。むしろ逆であることが多い。私たちは数年後、いまの厳しい雇用情勢は一時的なもので、AIによってキャリアが台無しになったわけではなかったと振り返るかもしれない。
米リンクトインの共同創業者、リード・ホフマン氏はAIがエントリーレベルの職を奪うというのは「物理法則ではない」とポッドキャスト「Possible」で指摘している。
AIスタートアップ、アンソロピックのチーフエコノミスト、ピーター・マッコリー氏は「AIの影響は全体としてまだ小さいと思われるので判断を下すには早すぎる」と語る。
また、ハーバード大学の労働経済学者でデービッド・デミング氏は大学での講演で「過去1世紀において、破壊的イノベーションは一般的に若者や高学歴人材に有利に働いてきた。柔軟に新しいやり方を吸収できるためだ」と述べている。
仮にAIが若手に悪影響を与えているとしても、一時的な影響にとどまる可能性があると一部の専門家は指摘する。テクノロジーは雇用側が求める職種と労働者が身につけるスキルの両方を変えるからだ。長期的には、AI時代に最も適応できるのは若い労働者である可能性がある。
採用控える原因
米国の労働市場は冷え込みつつある。失業率は2021年以降で最悪の水準だ。しかし、AIがその要因だと示す根拠は乏しい。
イェール大学予算研究所のエグゼクティブディレクター、マーサ・ギンベル氏は「労働市場ではいま確かに多くの変化が起きているが、タイミング的にAIとは関係ない。以前から変化が始まっていた」と指摘する。
一方で、ハーバードとスタンフォード両大学の経済学者による最近の研究は、AIによるキャリアの崩壊が現実に起きている兆候を示す。AIを最も応用しやすいソフトウエア開発やカスタマーサービスなどの職種で若い世代の雇用が減っているという。
この研究に対しては懐疑的な声が少なくない。金利や関税などさまざまな要因が背景にあるため、AIのせいにしすぎることに多くの専門家が懸念を持っている。
では仮にAIが若者の雇用に影響を与えているとすれば、その理由は何だろうか?
最も一般的な説明は、年齢を重ねた労働者がAIで代替できない専門知識を持っている一方、キャリアを始めたばかりの若手は比較的単調な仕事に従事しているというものだ。ハーバード大の大学院生セイエド・ホセイニ氏とガイ・リヒティンガー氏が論文で指摘した。
また、トロント大学の経済学者のチームによると、スライドの作成やデータ整理、要約など「実行」に優れるAIは、新たな機会を見極める判断力や決断力に欠けるという。
要するに、経験によって培われる専門性と判断力はAIでは代替できないというわけだ。
こうした説明は一理あるかもしれない。しかし、疑念も生じる。 まず、上司の仕事はAIにはできないほど難しいことを前提にしている。しかしAIは予測不能で常に進化するため、若手ができることしか代替できないとは限らない。
スタンフォード大で研究する経済学者バラット・チャンダー氏は「企業がAIによる生産性向上や人件費削減を試行する間、採用を取りやめている可能性がある」と語る。企業がAIの活用法を理解すれば、若手の採用を再開する可能性もあるという。
AIを使いこなすとは
この2年間、多くの企業が従来業務の一部あるいは全てをAIに担ってもらえることに気づいた。しかしそれが実際に何を意味し、どのような新しいスキルが必要になるのか必ずしも把握しているわけではない。
ハーバード・ビジネス・スクールのカリム・ラカニ教授は、企業がAIを早く導入しても、業務プロセスを再設計して新しい役割を定義し新たなチャンスを見つけるには時間がかかると指摘する。
関税や政治的なリスクも重なる中、現状では採用を一時停止する動機が企業に働いている。こうした厳しい雇用情勢の下では、企業に採用されない限り職に就けない若手が特に打撃を受けやすい。
しかし、この状況が永遠に続くわけではない。
時間がたてばプロセスは洗練されて新たな職種が生まれ、若手は新たなスキルを身につけるだろう。OpenAIは最近、AIスキルを持つ求職者と企業をマッチングさせる新たな求人プラットフォームを立ち上げると発表した。
若い方が新たなスキルを習得することに長けているのは歴史が示している。デスクトップコンピューターが登場した時に最も打撃を受けたのは中高年層だった。若手ほどコンピューターに慣れ親しんでおらず多くがタイピングに苦労した。
実際ChatGPTを活用しているユーザーの46%は18-25歳が占めている。
複数のアンケート調査では若年層のほうが年齢の高い層よりもAIに仕事が奪われることを懸念する結果が出ている。
しかし実務でテクノロジーに触れる若手労働者ではその傾向が弱まる。例えば18-24歳のプログラマーの15%がAIに脅威を感じると回答したが、その割合は55-64歳の13%とほとんど差が見られなかった。調査はStack Overflowが行った。
こうした中、AI導入を理由に若手の採用を減らしていた企業の中には方針転換の動きがみられる。
カナダの電子商取引会社ショッピファイは、社員数を増やす前に自動化を検討するよう求める社内メモが拡散した企業だが、いまではインターン生の採用を増やしている。AIを最も興味深い方法で使いこなしていることなどが理由だという。ベンチャーキャピタルのファーストラウンドが報告している。
教育内容もAIで変化
大学教育もAIで変わってきている。
米アメリカン大学コゴッド・スクール・オブ・ビジネスの学部長デビッド・マーチック氏は「若手の雇用の半分がAIで消えるという予測は大げさだ」と語る。さらに「AIで消える仕事もあるが、同時に新しい仕事や機会も数多く生まれる」が、それには「新しくてこれまでと異なるスキルセットが必要だ」という。コゴッドでは9割の教員が授業でAIを取り入れている。
トロント大の経済学者であるアヴィ・ゴールドファーブ氏はMBAの授業を刷新した。以前は授業でマーケティングプランを作るという課題を与えていたが「昨年の時点でChatGPTの方が、ほとんどの学生より優れたプランを出すことが分かった」という。
現在は学生がマーケティングのキャンペーンを考案したあと、AIを活用して実際にそれを1人で実施していくという課題を与えている。学生からはマーケティング会社は1人で業務を行うわけでないと批判もあったものの、最優秀の学生は驚くような成果を見せたと、ゴールドファーブ氏は語った。
AIが知識労働に与える脅威を軽視はできず、1人でマーケティング会社を動かすことも今後はあり得る。これが現実になる世界では仕事の大部分をAIが担い、私たちは仕事を失う可能性もある。しかしそれは若手のキャリアが断絶し、ベテランだけがうまく生き残る世界とは大きく異なる。
ハーバード大のラカニ教授は、AIへの理解を深めようとしている企業の多くの幹部はそれを使った経験がほとんどないため、苦戦していると指摘する。つまり、テクノロジーを取り入れて新しいチャンスを見つけられるのは、こうした幹部の下で働く若い部下たちなのだ。
マーチック氏は「組織が望むかどうかにかかわらず、若者は適応している」と指摘している。
(原文は「ブルームバーグ・ビジネスウィーク」誌に掲載)
原題:Younger Workers Will Win the AI Economy: Essay(抜粋)
— 取材協力 Jo Constantz



