「日本人ファースト」→なぜ?日本人の心に響いたのか 社会で広がる様々な“〇〇ファースト“がメンタルに与える影響とは【心理学の専門家が解説】
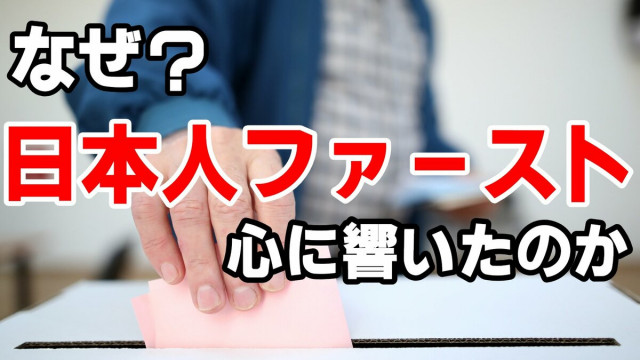
「日本人ファースト」→なぜ?日本人の心に響いたのか 社会で広がる様々な“〇〇ファースト“がメンタルに与える影響とは【心理学の専門家が解説】
世界中にあふれる“○○ファースト”の言葉
7月20日に行われた“参議院選挙” で「日本人ファースト」を掲げ支持を集めた参政党。選挙区で7人、比例代表で7人が当選し、14議席を獲得し躍進しました。
最近では何かしらの支持を得るために「○○ファースト」、例えば“カスタマーファースト”“従業員ファースト”、さらには“自分ファースト”に至るまで、実に様々な”〇〇ファースト”という言葉が多く聞かれるようになり、言葉の受け取り方も人それぞれ多様な状況です。
日本人は農耕民族が成り立ちで、共同体意識が強いとされています。
7世紀、聖徳太子【画像①】が定めた十七条憲法の冒頭に記された“和を以て貴(たっとし)しとなす”の言葉のように、古来より“協調性” “人との輪を大切に”ということが美徳とされてきました。
【画像①】そんな、日本人に“俺たち・私たちが優先されるべき”という、「ファースト=一番」という言葉がなぜ心に響くのか?川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科 の進藤貴子教授は、「『ファースト=あなた方は大切にされるべき人です』というメッセージは、『これまで社会や他者のために、自分の利益を二の次にして頑張ってきた人々に、ねぎらいや共感の言葉として響いたのでは』」と言います。
一方で「ファースト」は、心理学用語の「内集団(ないしゅうだん)びいき」を強めることにもつながると言います【画像②でさらに詳しく解説】。
【画像②】進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)「内集団びいき、つまり自分と仲間を高く評価できることは、精神的満足感や絆をもたらし、お互いの身を守るための本能的な傾向といえます」
「ただし行き過ぎると、閉鎖的・排他的になり、外集団(がいしゅうだん)を敵視し、遠い存在の人々の痛みは無視できてしまうという危険性もあります」
「こうなると、外集団への不信を拭えず、『食うか、食われるか』の不安と隣り合わせの心理状態がもたらされてしまいます
」「ファースト」はなぜ注目を集めたのか?
筆者がファーストという言葉をよく聞くようになったのは、現在のアメリカ・トランプ大統領が2016年、一期目の選挙戦で掲げた『アメリカファースト』【画像③】というフレーズでした。
【画像③】進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)「トランプ大統領が“アメリカファースト”と公言するのを聞いて、他国の者は、不快や不安など複雑な思いにさせられました」
「しかし、トランプ氏の言葉はアメリカ国民が抱いていたかもしれない『不当な思い、報われたいという思い』に対して、共感的に、また、ねぎらうように、響いたのではないかと思います」
日本で広がる“ファースト”の波
政治から社会、生活においてまで、英語の“ファースト”が日本人に浸透しています。受け入れられるようになった理由はどんなことが考えられますか?
進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)「どんな人も人として尊重される、一人一人の国民の暮らしを大切にする、という人権意識の広がりとともに“ファースト”は馴染んできていると思います」
「一方で、日本人の共同体への心が少しずつ変わってきていると思います。共同体のために個が犠牲になる世界の国々が“自国第一主義“のナショナリズムを出しているなか、『うかうかしていると権利を侵害される、という不安をいだいた日本人に響くフレーズ』だったと思います」
大切なのは“心のファースト”
発達心理学【画像④】の視点で見ると、まず“自分が大切にしてもらうこと“が前提にあり、そこから、他者への思いやりとつながっていくことが、バランスのとれた心の育ちの順序と進藤教授は言います。
自分の“心”を大切にされることを基盤として、周りの人を幸せにする。周りの人たちが幸せになり、自分がより幸せになる、というサイクルが、「自分ファースト」の望ましい形だということです。
【画像④】進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)「一枚のパイを皆で分け合うとき、自分が優先的に欲しいだけ取り、他の人は損をしても構わないという他者排除の考え方は、不信と孤立につながり、結局、満たされなさが残りますよね。逆に自分を置き去りにして、他人のためだけを考えるのも、不健全な状態をもたらします」
日本社会で今、受け入れられている“○○ファースト“という言葉―
進藤教授は、利害の優先順位としての「ファースト」ではなく、人として尊重されるオンリーワンとしての「ファースト」が、社会不安や分断の中でもろくなりがちな自己肯定感を支えてくれているのかもしれないと話します。
進藤貴子教授(川崎医療福祉大学医療福祉学部 臨床心理学科)「社会生活を送る上で、心の健康を保っていくためには、利益配分というファーストよりも、愛情や信頼関係のファーストが欠かせません」
自分の心を犠牲にしていると感じている人たちに『あなたはファーストなんですよ』と伝えることは、砂漠で喉が渇いている人に水というくらいの力がある言葉と筆者は感じました。
進藤教授に話を聞き、心の健康を築いていくためには『自分の心は自身でねぎらい、そして周りの人たちを幸せにしていくことが重要』なポイントだと思います。
RSK山陽放送の他の記事も見る もっと見る 続きを見る


