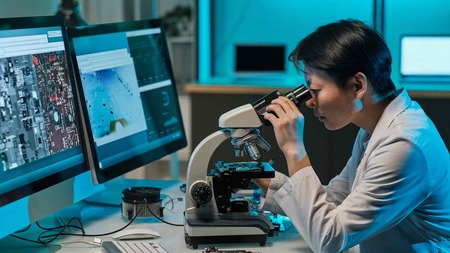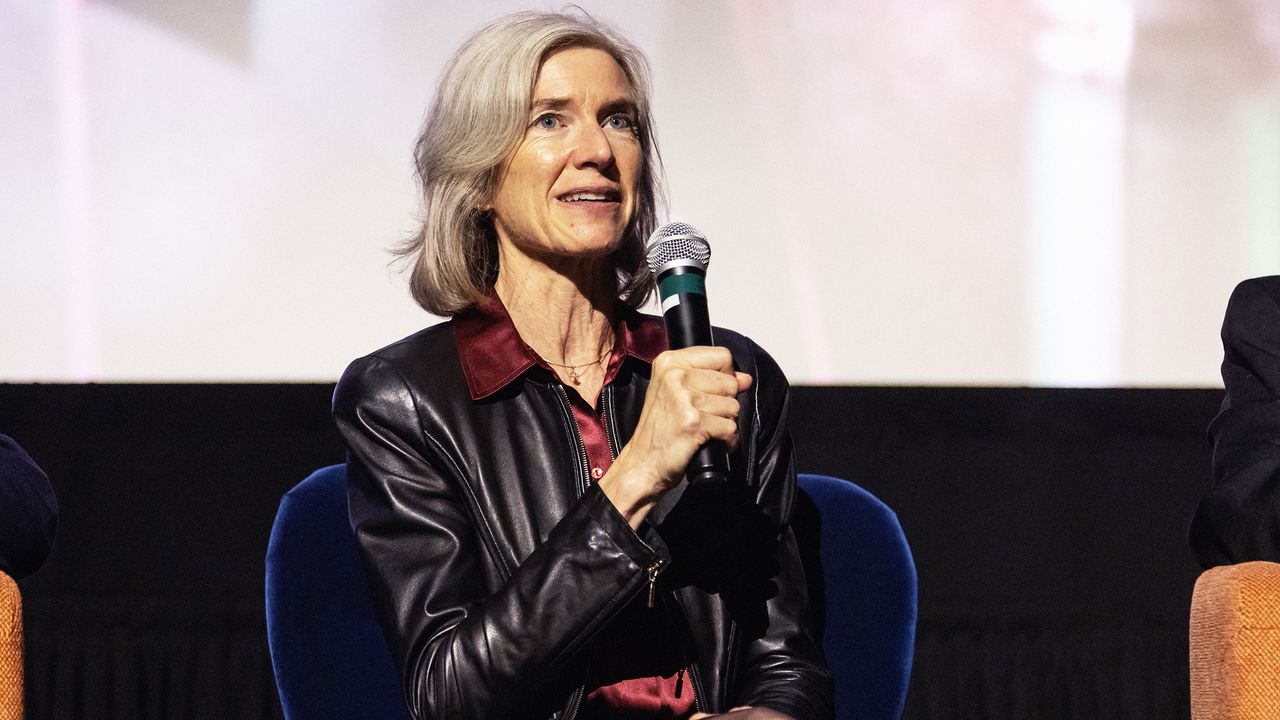「お騒がせして申し訳ありません」は謝っていない…形式ばかりの"謝罪会見"が世にはびこる根本原因 心理学的にベストなお辞儀は「45度で2秒」

それに、理不尽なクレームをつけてくる人には理屈が通じない人が多い。いくらていねいに説明しても、なかなか納得してもらえない。
本などをほとんど読まず、読解力が鍛えられていないと、文章の読解問題が解けないだけでなく、人の話もなかなか理解できない。そのため、苦情が見当違いであることをいくら説明しても、ごまかしているなどと思うようで、納得してもらえない。
そこで、最悪の事態を想定し、理にかなったクレームかどうかに関係なく、とにかく謝罪しようといった感じもある。事を荒立てず、ものごとを円滑に進めるために、ホンネではこちらに非があると思っていないのだが、とりあえず表面的に謝る形式的謝罪が増えている。いわゆる自己呈示としての謝罪の一種である。
冷静に考えたら謝罪など必要ないだろうと思うのに、店員や企業の該当部署の人が謝罪することが多いのには、そうした事情が関係しているのである。
ただし、近頃はあまりに理不尽なクレームをつける客もいて、店員が困惑するばかりでなく、心を病むほどに責め立てられるケースも出てきているため、カスハラなどという言葉さえ用いられるようになり、その対応の整備が急務となっている。
「45度で2秒程度」のお辞儀が最も効果的
このように、うっかりクレーム対応に失敗すると、ネット上で悪評を広められて苦境に追い込まれることもあり得るからこそ、まずは謝ろう、たとえ相手が理不尽なクレーマーであっても、むやみに刺激せず、とにかく謝ろう、といった感じになっている。
ただし、謝罪の仕方を誤ると、せっかくの謝罪も逆効果となり、相手をますます怒らせたり、ネット上に悪評を書き込まれることもある。ゆえに、そうした事態に陥るのを避けるべく、効果的な謝罪の仕方を戦略的に求める企業側の需要が高まっている。
そんな時代ゆえに、「謝罪力が明暗を分ける」などといって、効果的な謝罪の作法を指南するコンサルティングなどが商売として成り立つようになってきた。
企業の危機管理部門や企業トップなどが、効果的な謝罪の作法を学ぶのだ。効果的かつ責任追及を免れるための謝罪の言葉を頭に叩き込み、お辞儀の仕方も練習する。
心理学の領域でも、効果的なお辞儀動作の研究が行われている。
心理学者の柴田寛たちは、お辞儀が与える印象に関する研究のなかで、屈体角度と屈体後の静止時間に関して、謝罪の気持ちを伝えるお辞儀としてどれくらいが適切かを評定させている。
その結果、屈体角度は浅めの15度より深めの45度のほうが適切と判断されやすいことがわかった。また、屈体後、つまりお辞儀をしたままの静止時間については、2秒程度がもっとも適切とみなされやすく、静止しなかったり、静止時間がそれ以上に長かったりすると、適切とみなされにくくなることが明らかになった。
Page 2
このような誠意に欠ける形式的な謝罪が世にはびこっているため、とりあえず謝りはしても、反省がないため、その後また同じようなことが繰り返されるということになりがちである。
榎本博明『絶対「謝らない人」 自らの非をけっして認めない人たちの心理』(詩想社新書)
政治家の不祥事にしても、芸能界やメディア業界の不祥事にしても、一般企業の不祥事にしても、表沙汰になって謝罪会見が行われたにもかかわらず、似たようなことが繰り返される。
それは、謝罪の作法に則った謝罪会見を行いながらも、「とにかく謝罪すれば事態は収束するはず」、「神妙な表情で謝罪すれば炎上は防げる」などと思っており、心から反省しておらず、「こんなこと、どこでも(だれでも)やっているだろうに」、「自分だけ(ウチだけ)バレるなんて、運が悪い」といった思いが強いからだろう。
あくまでも戦略としての謝罪であって、「謝罪の作法を踏まえて謝ればうまくいく」といった発想で動いているだけで、誠意などどこにもない。「謝ってすむなら警察はいらない」という子どもがよく口にするセリフがぴったりあてはまる事例と言える。
ときに加害側とみなされている人が自分は悪くないと思っており、謝罪する必要もないと思っているのに、事態を収束させるため、意に反して謝罪させられることもある。
あるいは、なんの反省もないのに、早急に事態を収束しないと面倒なことになりかねないといった考えから謝罪が行われることもある。
その場合は、組織の戦略として謝罪しているだけで、反省の気持ちは微塵もないため、その後の改善は期待できない。重要なのは、謝罪をするかどうかではなく、心からの反省があるかどうかだ。それがなければ、その後の改善もあり得ない。