非アルコール性の肝炎「MASH」発症に関わる遺伝子特定…有効治療法確立につながるか
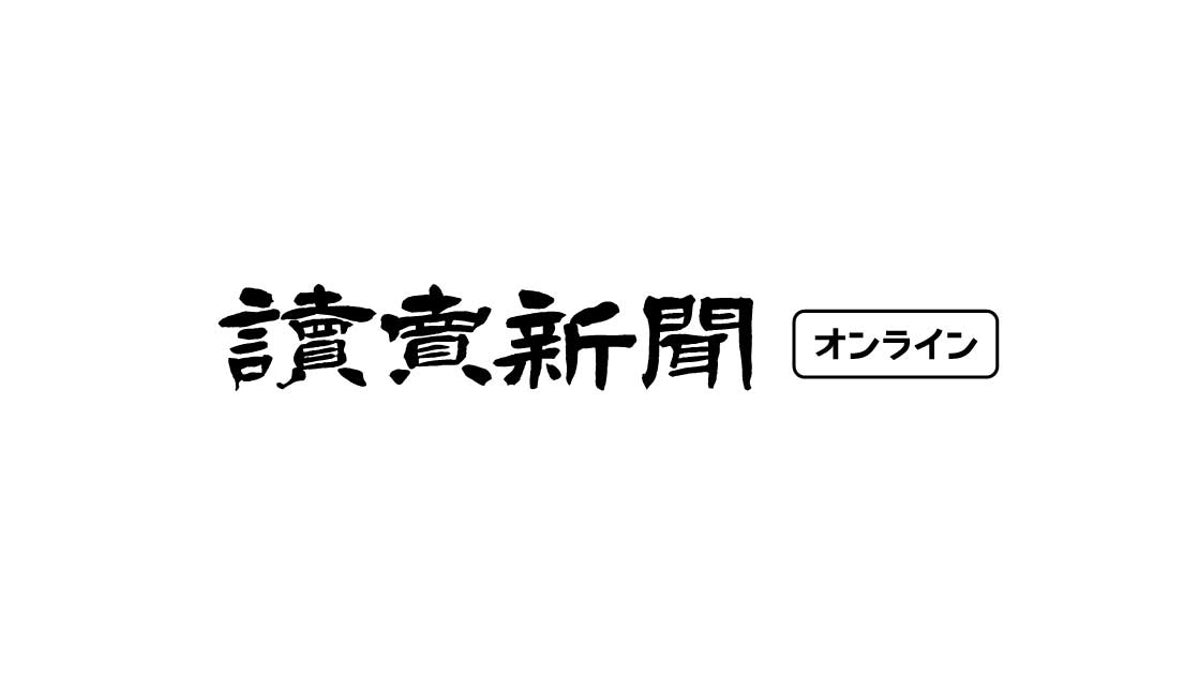
あまり飲酒をしない人にも起きる肝炎「代謝機能障害関連脂肪肝炎( MASH ( マッシュ ) )」の発症に、免疫細胞で特定の遺伝子が関わっていることがマウスの実験でわかったと、和歌山県立医科大などのチームが発表した。発症を抑える治療薬の開発につながる可能性があり、論文が国際科学誌に掲載された。
MASHは酒量が少なくてもコレステロールなどの脂質が肝臓に過剰にたまって炎症が起きる病気で、昨夏までは「非アルコール性脂肪肝炎( NASH ( ナッシュ ) )」と呼ばれていた。国内の患者は300万人以上と推定される。肝硬変や肝がんに進行することもあるが、発症メカニズムは不明な点が多く、有効な治療方法は確立されていない。
同大学の安芸大輔講師、東京理科大の吉村昭彦教授らは、高脂肪の餌を与えてMASHを発症させたマウスの肝臓の免疫細胞を詳細に調べた。
その結果、炎症を促すたんぱく質を分泌する免疫細胞の一つ、「ヘルパーT細胞」で活性化していた遺伝子のうち2種類を働かなくした状態にすると、MASHの進行が遅くなった。
2種類の遺伝子が働かない時、炎症を抑える機能を持つ別の免疫細胞「制御性T細胞」が増えていたこともわかった。
安芸講師は「2種類の遺伝子の働きを抑える化合物を開発することができればMASHの治療が可能になるのでは」としている。
尾野 亘 ( こう ) ・京都大教授(循環器内科学)の話 「MASHの発症とT細胞の関わりや、関連する遺伝子を明らかにした重要な成果だ。治療薬開発の手がかりとなる可能性があり、更なる研究に期待したい」



