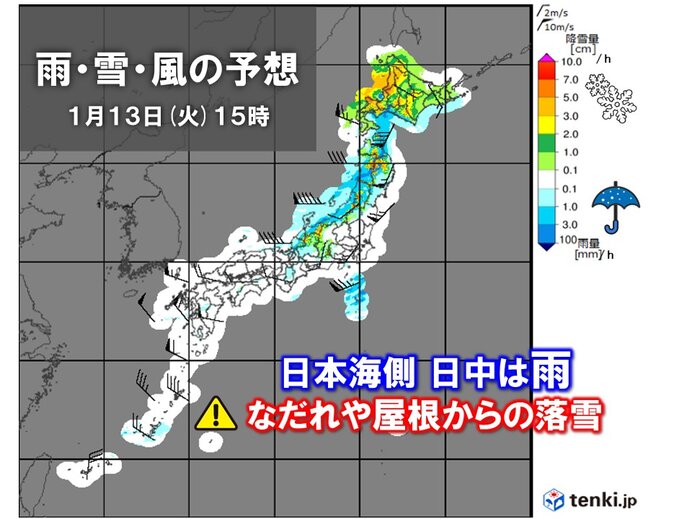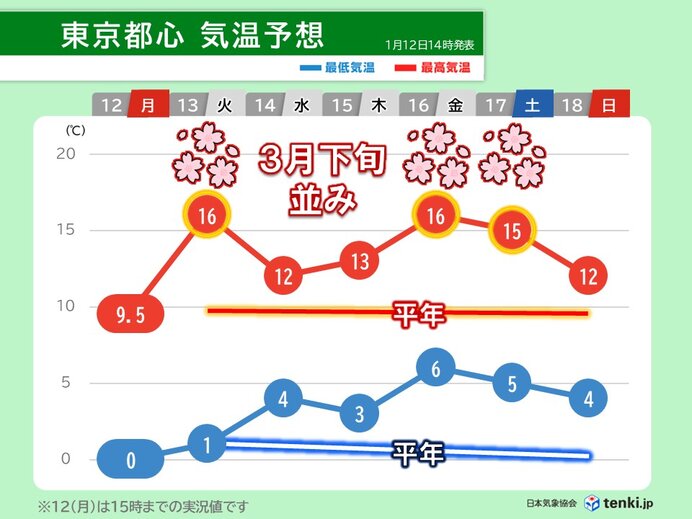戦艦「大和」撃沈から80年、最新技術詰め込んだはずが「時代遅れだった」…元乗組員が痛感した戦争のむごさ

戦艦「大和」が撃沈されてから今月で80年となる。日本海軍の象徴となった世界最大の戦艦だったが、急速に発達した航空機の前になすすべもなく敗れた。大和の建造に携わり、乗り組んだ人たちは、戦争の非情さを今も忘れずにいる。(波多江一郎)
1941年10月、高知県の宿毛沖で「公試運転」をする戦艦「大和」=大和ミュージアム提供太平洋戦争が始まる直前の1941年10月下旬、当時17歳だった中倉勇さん(100)(広島市)は、高知県・ 宿毛(すくも) 沖で試験航海中の大和の船底にいた。
当時は軍需工場「呉海軍 工廠(こうしょう) 」(広島県呉市)で働いていた。大和の海軍への引き渡しを控え、性能を確認する「公試運転」に立ち会っていたのだ。
戦艦大和の公試運転の様子を語る中倉勇さん(1日、広島市佐伯区で)=東直哉撮影全長263メートルの船体が時速約50キロの最大速力で海面を押し分けて進む。 舵(かじ) やスクリューにほど近い船底の後部に陣取り、 操舵(そうだ) に関わる油圧シリンダーの動きを記録した。
面舵(おもかじ) (右)や取り舵(左)がいっぱいに切られるたびに艦はぐぐっと急旋回し、息詰まる緊張を感じた。ガガガガガと耳をつんざく音が響き、大和の力強さに圧倒された。
海軍工廠の見習工になったのは38年。通勤の途中、目隠しされた造船用のドック( 船渠(せんきょ) )から鉄板を 鉄鋲(てつびょう) で接合する音が響いてきた。建造時は「1号艦」と呼ばれた大和がそこで造られていた。その姿を初めて見たときは「横幅がとにかく広い。魚雷が1、2本命中してもびくともしない不沈艦だ」と思った。
Page 2
日本海軍は、戦艦同士が砲を撃ち合う艦隊決戦に備え、大型戦艦を建造した。しかし大和が完成するわずか8日前、海軍は自らの手で、航空機が戦艦の優位に立つことを証明する。ハワイ・真珠湾への攻撃で、日本の航空機部隊は停泊中の米戦艦8隻を撃沈・撃破した。
「最新技術を詰め込んで造った大和はすでに時代遅れの存在になっていた」。中倉さんはそう振り返る。
その後、新兵教育を担う海兵団に入って終戦を迎え、戦後は、原爆の人体への影響を研究する米国の原爆傷害調査委員会(ABCC)で聞き取り調査にあたった。
後遺症に苦しむ人の姿を見て、戦争のむごさを痛感した。時代に取り残された戦艦に乗り、戦死した兵士たちの命の重さにも思いをはせる。
中倉さんは戦争を知らない世代にこう訴える。「今の平和が当たり前と思ってほしくはない。国際情勢を学び、戦争について考えてほしい」
航空機に太刀打ちできず
木村功さん「とにかく大きく、エレベーターがあることにも驚いた」。1942年、大和の乗組員になった木村功さん(104)(徳島県石井町)はそう話す。冷暖房もあり、寝室にはハンモックではなくベッドが置かれていた。巨大な艦内の移動は「旅行」と言われた。