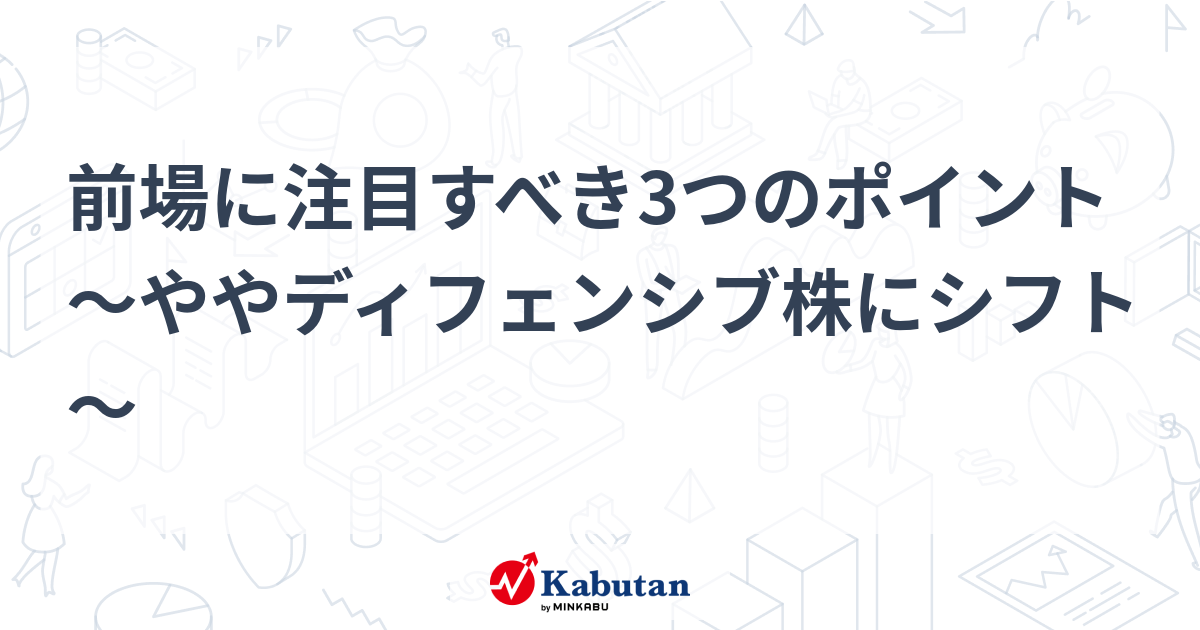コラム:対米直接投資80兆円の意味、日米交渉はここからが正念場か=佐々木融氏

[東京 28日] - 日米関税交渉で日本が約束した5500億ドル(約80兆円)の対米直接投資に関して日米両政府が「共同文書」を作成することになりそうだと報じられている。これに関し、赤沢亮正経済再生相が訪米する予定だったが、28日の土壇場で取りやめとなった。ラトニック米商務長官はこれより先に、今週後半に何らかの発表を行うとの見解を示していた。
7月23日に日米関税交渉が合意に至ったとのニュースを聞いた時に、筆者が為替相場への影響という観点から最も気になったのは、関税率の引き下げではなく、5500億ドルという巨額の対米投資に関する約束だった。その利益の90%を米国が受け取るという主張も奇妙な話だとは思ったが、驚いたのは5500億ドルという巨額の数字だった。
まず、米国側のデータによると、2024年末時点で日本の対米直接投資残高は8192億ドル(119兆円)となっている。つまり5500億ドルは残高の7割近くに及ぶ。赤沢氏は5500億ドルの投資はトランプ大統領の任期中、つまり3年半の間で行うとして、その為に各省庁に号令をかけると発言している。ちなみに、過去3年間の日本の対米投資額の年平均増加額は203億ドル(約3兆円)程度だ。3年半で5500億ドルの投資を行うのであれば、最近の平均の8倍近くのペースで投資を行っていかなければならない。
石破茂首相は今年2月にトランプ氏と会談を行った際、対米直接投資残高を1兆ドルにする約束をした。この時の約束通りであればあと1800億ドル程度の投資で済んでいたはずだが、一気に3倍に増えている。
5500億ドルの対米直接投資がどのようにして行われるのかに関して、日本の政府系金融機関による出資、融資、融資保証と説明されているが、誰がファイナンスするかはともかく、誰がその投資を行うのかという方が重要だろう。それだけの額の対米投資を短期間で行う企業はあるのだろうか。
誰がファイナンスをして、誰が投資を行うのかは置いておくにしても、5500億ドルのうちどれだけの分が円売りを伴うのかという点が為替市場にとっては最も重要となる。信用力が高いとは言い切れなくなっている日本は、もはやそれほど多額のドルを政府系金融機関や民間金融機関がマーケットから調達できるとは思えず、相当部分は円建てでファイナンスが行われ、円売り・ドル買いを伴う可能性があると考えられる。仮に半分でも円売りを伴うようであれば40兆円の円売りが行われることになる。
よくこうした話が出ると「円相場に対するインパクトはどのくらいか」と聞かれる。もちろん為替相場は様々なフローが影響するため、一概には言えないが、かなり大雑把な相関関係を試算してみると、「1兆円=ドル/円相場1円の変化」と言えなくもない。つまり、40兆円分の円売りがかなり短期間に行われ、それ以外の要素が変わらないようであればドル/円相場を40円も押し上げるような効果があってもおかしくはない。
なぜこのような多額の投資で合意したのだろうか。その問いには7月の時点でラトニック氏が答えている。「25%の関税は(日本の自動車産業にとって)『アメリカで作れ』ということを意味する。しかし、15%の関税はギリギリのラインだ。つまり、日本の自動車メーカーはまだ日本で生産を続けることができる。そして、それこそが日本側が買いたかったものだ。一部の車の生産については日本にとどまることができる。日本はそのラインを買いたかったのだ」。つまり、80兆円は日本の自動車産業が日本国内で生産を続け、米国に輸出を続けることを認めてもらう対価のように聞こえる。
そして、ラトニック氏は、「日本は、アメリカに対してプロジェクトを選び、決定し、実効する権限を与えることになる。もしトランプ氏が『アメリカで抗生物質を作ろう』と決定すれば、日本がそのプロジェクトに資金を提供することになる」とも発言している。つまり、対米投資は日本企業主導で自然体で行われるものではなく、米国側が決定したものに日本側が資金を提供するという理解となっている。さらにラトニック氏は、日本はこの投資に関して「オペレーターではなく、資金提供者であり、銀行家だ」とも付け加えている。つまり、この投資の主体が日本企業ではなくても良いという理解だ。こうなると、もはや日本企業の対米投資に政府が融資するなどということなどでは無く、トランプ氏が決めた投資プロジェクトを米国企業が実行する時にも日本が資金提供をするような理解に聞こえる。
こうした条件を共同文書にするのだろうか。かなり無理な要求のように聞こえるので、文書でこうした条件を明記し、署名することは日本にとっては無理なように思える。日本がそれを拒否した場合、自動車に対する関税は25%(正確には恐らく27.5%)に引き上げられるのだろうか。為替市場にとっては、ここからの日米交渉の行く末が最も重要になってくるのかもしれない。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*佐々木融氏は、ふくおかフィナンシャルグループのチーフ・ストラテジスト。1992年上智大学卒業後、日本銀行入行。調査統計局、国際局為替課、ニューヨーク事務所などを経て、2003年4月にJPモルガン・チェース銀行に入行。2010年にマネージングディレクター就任、2015年から2023年11月まで同行市場調査本部長。23年12月から現職。著書に「弱い日本の強い円」、「ビッグマックと弱い円ができるまで」など。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab