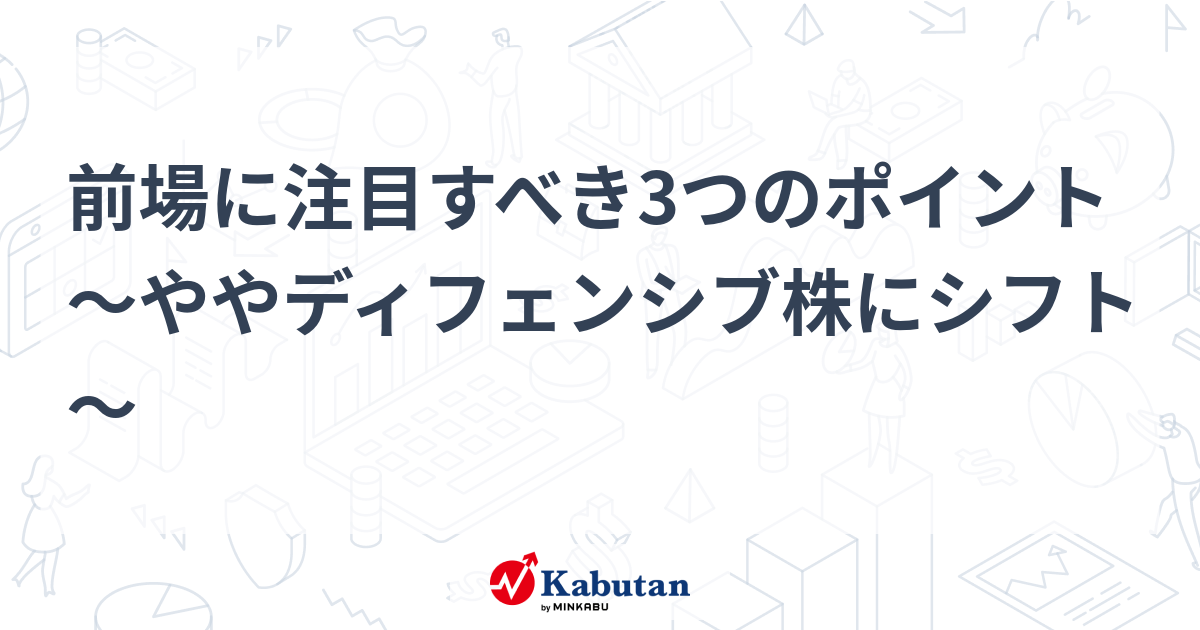トランプ氏のFRB攻撃、背後に潜む思惑に危うさ-財政優位への道

トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会(FRB)への影響力を強めようとする中で、投資家の間では中央銀行が本来扱うべきではない問題、つまり膨張する米国の債務負担への対策としてFRBの政策手段が使われるのではないかとの懸念が広がっている。
トランプ氏は26日、FRBのクック理事の解任を巡り法廷闘争を辞さない構えを示し、FRB理事の「過半数」を掌握することを楽しみにしていると語った。これによりトランプ氏は、自らが掲げる金利引き下げの方針を前進させることができるかもしれない。同氏は利下げによって「数千億ドル規模」の節約が可能になると主張している。
米国の債務コストが近年急増している背景には、財政赤字拡大と金利上昇という2つの要因がある。負担を軽減するには、少なくともどちらかを反転させる必要がある。大半の経済学者は、借り入れコストを下げるためにFRBに頼るのではなく、歳出削減と増税の組み合わせによって借入額そのものを抑えるべきだと指摘する。
政府の債務負担軽減のための利下げという道筋は、インフレ抑制を目標とする金融当局にとって危険なものだ。政治家が財政出動によって経済を過熱させ続ければ、物価上昇を抑える作業は一段と困難になる。そこへ、物価圧力を抑えるための主要な手段である金利が政府の財政を維持するための道具になってしまえば、金融当局の役割を果たすことはほぼ不可能になる。
そうした状況を、経済学者は「財政優位(fiscal dominance)」と呼ぶ。通常は、金融政策が政治の影響を受けやすい新興国に関連付けられる概念だが、トランプ氏によるFRBへの攻勢が強まる中で、多くのアナリストは米国も同様の方向へと傾きつつあるとみている。
バージニア大学の経済学教授で、元FRBエコノミストのエリック・リーパー氏は、米国は既に財政優位の状態にあると指摘する。
「インフレを抑制するには、正しい形で財政政策が機能している必要がある」のに対し、「現在聞こえてくるのは、利払いが膨張しているから金利を下げるべきだという声だ。これは、当局が財政政策を自律的に改善させる意思がないことの表れだ。だからこそ別の抜け道を探しているわけで、まさに財政優位だ」と同氏は解説した。
現時点では、FRBの金利決定が米国の財政状況に左右された形跡はない。パウエルFRB議長は経済見通しに基づいて政策を判断していると繰り返し強調しており、ジャクソンホール会合(カンザスシティー連銀の年次シンポジウム)での講演でも姿勢は変わらなかった。先月の記者会見では「政府の財政事情を考慮して金融政策を決めるのは望ましくない。先進国の中央銀行でそんなことをしているところはない」と述べていた。
それでも、FRBがまさにそうした政策運営に踏み切るのではないかという懸念は高まりつつある。
FRB議長の任期が来年5月に切れるため、トランプ氏はパウエル氏の後任を指名する権限を得ることになる。既に、空席となっていたFRB理事ポストに大統領経済諮問委員会(CEA)委員長のスティーブン・ミラン氏を指名しており、さらに、住宅ローン申請を巡る不正の疑いを理由にクックFRB理事の解任が実現すれば、もう1枠の空席が生まれる。
トランプ陣営は米連邦準備制度の体制をより大きく見直す構想を示唆しており、12の地区連銀への影響力を強める手立ても模索している。その背景には、利下げを求める声が絶え間なく続いている。
ドイツ銀行の外国為替調査グローバル責任者ジョージ・サラベロス氏は26日のリポートで「FRBは現在、財政優位のリスクが強まる局面にある」と指摘した。「驚くべきなのは、市場がこの問題をそれほど深刻視していないように見えることだ」ともコメントしている。
同日、トランプ氏がクック理事の解任に向けた動きを強めたことを受けて、30年物米国債とドルは下落した。ただ、米国の貿易政策や財政計画を巡る懸念が広がる中で記録した安値に比べれば、なお高水準にある。
FRBの政策スタンスが変わるとの懸念が強まれば、ドルはさらに下落し、債券利回りは大きく上昇する可能性がある。また、暗号資産(仮想通貨)や金への関心が高まる要因にもなると、スタンダード銀行のG10通貨戦略責任者スティーブ・バロー氏は指摘する。
バンク・オブ・アメリカ(BofA)が最近実施したファンドマネジャー調査では過半数が、次期FRB議長は政府の債務負担を軽減するために量的緩和(QE)やイールドカーブコントロール(YCC)に踏み切ると予想した。
原題:Behind Trump’s Bid for Fed Dominance Lies a Dangerous Debt Idea(抜粋)