キスをするだけで感染することがある…50年に一度の大流行期に入った"梅毒"の恐ろしさと治療法 早い段階で適切な治療を受ければ、必要以上に怖れることはない
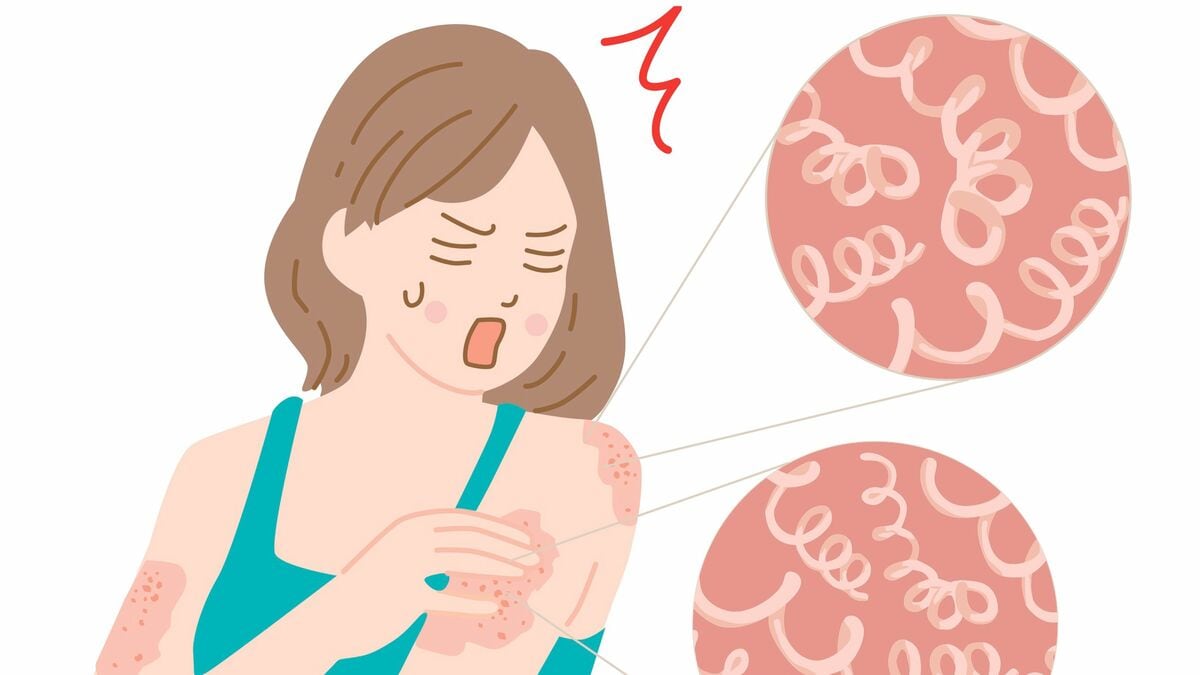
梅毒に罹ったらどうすればいいか。鳥取大学医学部医学科感染制御学講座細菌学分野准教授の小幡史子さんは「梅毒は、たとえば唇などに皮膚症状がでていれば、キスをするだけで感染することもある。1期や2期の段階で病院に行ければ、すぐに治る。だが3期になってしまうと、すでに骨や神経に変性が起こっていて後遺症が残ってしまうこともある」という――。
※本稿は、鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 19杯目』の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/recep-bg
※写真はイメージです
感染経路の半数以上が、性風俗の利用者または従事者
日本国内における「梅毒」の感染者数は、1967年に約11000人が報告されて以降、長期にわたり減少傾向が続いていた。
梅毒は撲滅されたと言っていい水準にまで減少していたため、一時期は医療者ですらほとんど出会うことのない“過去の病気”となっていたという。
しかし、近年は〈ほんの15年ほど前までは〉という但し書きがつくようになった。
2011年頃、梅毒感染者は再び増加に転じ、2021年以降は急激な伸びを見せている。2023年の報告数は14906⼈に達し、50年に⼀度の⼤流⾏期に⼊ったと言われている。
梅毒は“5類感染症全数把握対象疾患”に定められており、診断した医師は7日以内に管轄の保健所に届け出ることが義務付けられている。つまり、医療機関で治療を受けた患者の数を正確に把握することができる病気である、はずだ。
実情はそうなっていないと首を振るのは、鳥取大学医学部医学科感染制御学講座細菌学分野准教授の小幡史子だ。
「治療に来ない方もいますので、感染者が実際にどれくらいいるのか、正確には把握できません。鳥取県では2023年の報告数が年間で約30件、少ないように感じますが、その10年前は0件でした。国立感染症研究所の県別感染者数データによると、人口比の感染者数は大都市でも山陰のような地方でもほとんど変わらない」
データからいくつかの原因、傾向は読み取れる――。
「まず、感染経路の半数以上が、性風俗の利用者または従事者であること。男性の年代別感染者は10代から60代と広範囲なのに対して、女性では20代が突出して多い。性風俗に関わった人の感染リスクが高いということが言えます」
2016年と2023年の「男女別・年齢に対する梅毒の分布」のグラフを比較してみよう。まず目につくのは、16年時点ではほとんどいなかった高齢の感染者が23年のデータでは増えていることだ。
「7年前に感染していた方が、そのままスライドしていると思われます」
グラフの形はほとんど同じであり、一見するとあまり変化がないように感じられるが、感染者数の数字――総数が大幅に増加している。
「10年後、40代や50代の男性も増えていき、そのぶん女性もさらに増えていくということが予想できます」
Page 2
梅毒で最も気をつけなければならないのは妊婦である。
女性診療科教授の谷口文紀は、日本産科婦人科学会では梅毒の危険性の啓発活動に力を入れているという。
「感染した女性が妊娠すると、⼦宮内で胎児に母子感染する『先天梅毒』が起こる。生まれた子どもに目の炎症や難聴など先天異常の症状がみられたり、流産や死産の原因にもなる。山陰ではまだ感染者数はわずかですが、特に大都市圏では⼥性感染者の増加に伴い、梅毒に感染している妊婦も急増しています」
もっとも、出生前検診には梅毒の検査が含まれている。
「もし梅毒に感染してしまっても、出産前に適切な治療を受ければ先天梅毒の⼼配はありません。治療せずに出産してしまうと、赤ちゃんが感染してしまう」
近年、「プレコンセプションケア(Preconception care)」という考えが広がっているという。これは妊娠を考えるカップルが、将来の生活や健康に向き合うという取組みである。
「⾚ちゃんを守るためには、妊娠前にパートナーと一緒に検査を受けて、ともに感染していないか確認しておくことが大切です」
そもそも梅毒が疑わしいとき、私たちはどの診療科を受診すればいいのだろうか。
感染症内科講師の北浦 剛は、まずは初期症状が出た部位を専門とする医療機関に相談するのが望ましいという。
「陰部の症状であれば、男性は泌尿器科、女性は婦人科。口腔の性交渉でもうつるので、もし口に症状が出た場合には皮膚科や口腔外科などを受診する。梅毒以外の病気である可能性も考える必要があるからです。そのため感染症内科では、必要に応じて各科と連携して診療を行なっています」
免疫ができたからもう大丈夫という病気ではない
特に自覚症状はないが感染の心配があるので検査したいという場合は、多くの保健所で無料の梅毒検査を行なっている。プライバシーに配慮して匿名で受けられる上、梅毒と複合感染する可能性がある性感染症のHIVとクラミジアの検査も同時に受けることができる。
鳥取大学医学部附属病院広報誌『カニジル 19杯目』
「免疫ができたからもう大丈夫という病気ではない。過去に治療をして1回治った人でも、再感染することは結構あります。そして性風俗などに関わっていないとしても、性的接触があれば誰にでも十分感染の機会はあります」
インターネットを検索すれば、梅毒の検査キットを見つけることができる。しかし、それらの検査の精度は保証されておらず、病院や保健所で行う検査とは意味合いが違うと北浦は言う。
梅毒に限らず、性感染症は恥ずかしいから人には知られたくないという意識があるために、発見や治療を遅らせ必要以上に怖い病気になってしまう。
その意識とはつまり、感染した人に対して自分がどう思っているのかということだ。私たちが見直すべきなのは行動だけではなく、自分が持っている病気に対する偏見なのかもしれない。
(取材・文=西村隆平)



