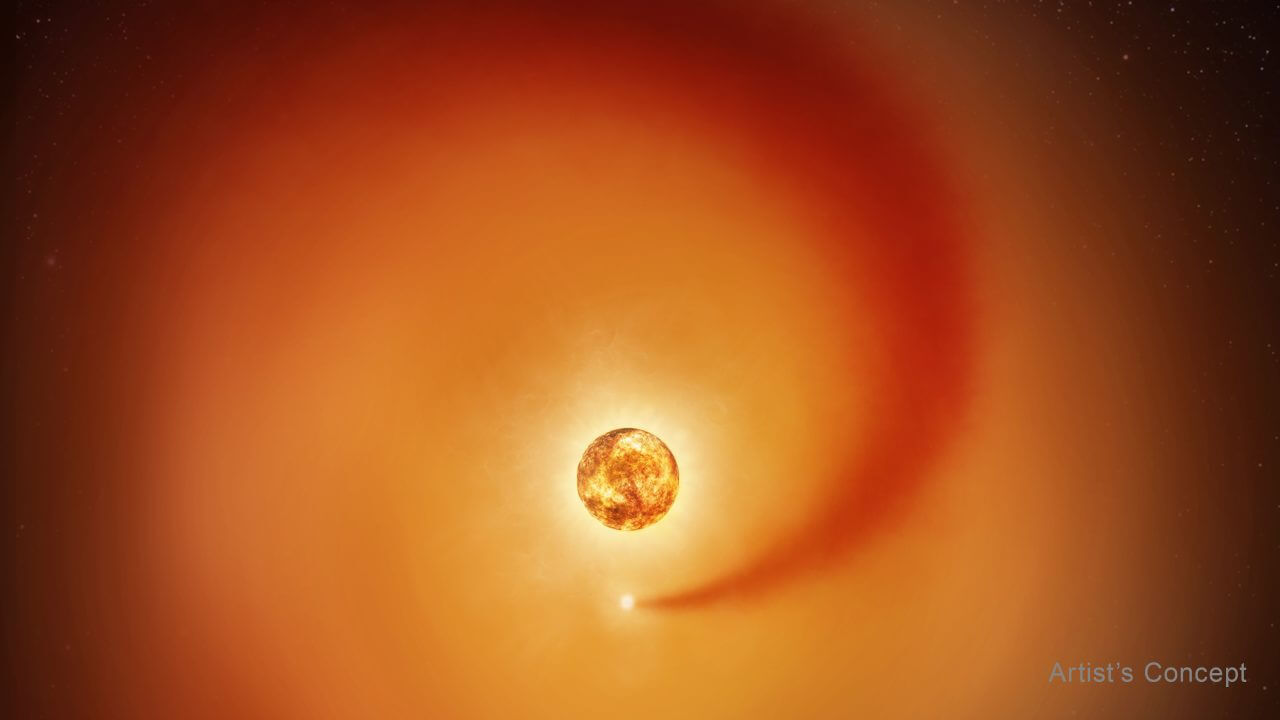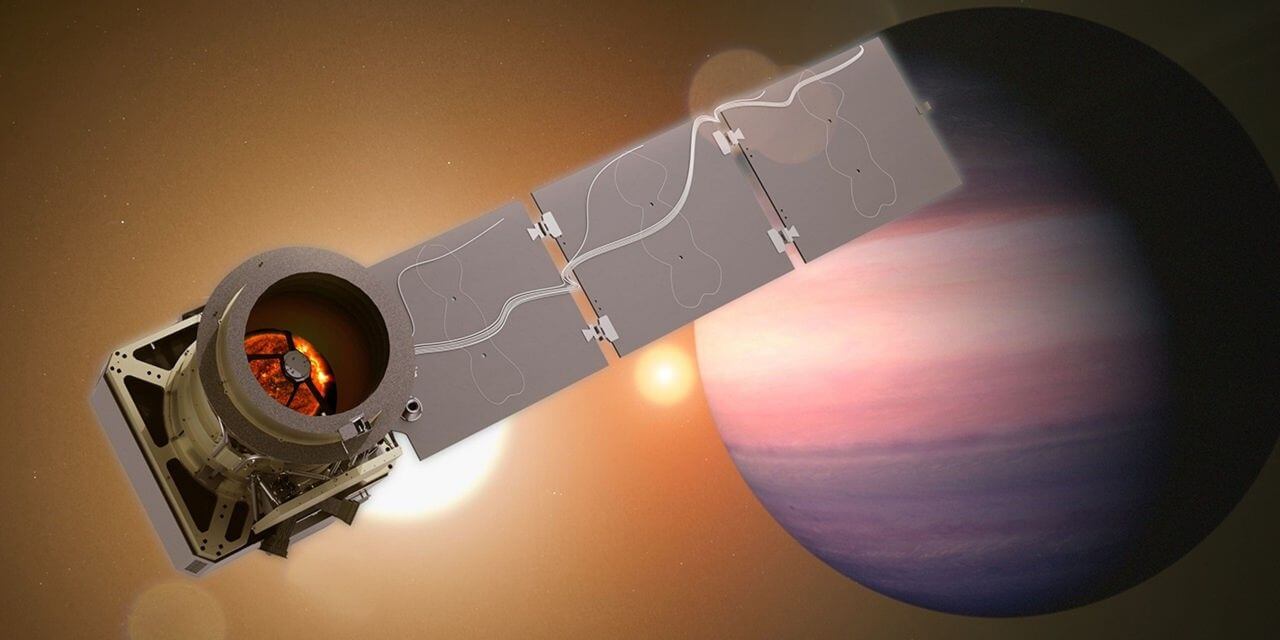騙す方が悪いが、騙される方にも落ち度がある

黒坂岳央です。
「騙すほうが悪い」というのは言うまでもないだろう。しかし、叩かれる覚悟で伝えたいのは、「騙される側にも防げた可能性があるケースが少なくない」ということだ。
この意見は一部の人から反感を買うだろう。もちろん、これは騙された人を道徳的に責めるものではない。むしろ、「今後騙されないための備え」を社会全体で共有することを目的とした話である。
DNY59/iStock
騙す人を減らすことはできない
まず大前提として、騙す行為は倫理的にも法的にも許されない。詐欺は犯罪であり、加害者が最も責められるべき存在であることは言うまでもない。
だが、騙す人間を社会から完全に排除することは現実的に不可能である。なぜならいつの時代も逮捕や社会的制裁というリスクを前にしても、それを超える「利益」や「動機」をもって行動する者が後を絶たないからだ。これはどれだけ法を整備しても、ゼロにはできない現実だ。
だからこそ、被害者を減らすには、「騙されにくい社会」をつくる必要がある。
騙される側にも落ち度がある
ここで重要なのは、「騙される人=知識がない人」だけではない、という視点だ。
筆者はこれまで「騙されやすい」と感じる人をリアルでもネットでも見てきた。彼らの共通点は依存心が強く、他人の言葉を鵜呑みにしやすい。また、楽して儲けたい、努力せずに結果を求めるテイカー気質である。自分の頭で考えたり調べたりすることをとにかく面倒くさがり、行動力や自助努力に乏しい人も少なくない。
たとえば、「すぐに稼げる」「簡単に成功する」といった甘い誘い文句に飛びついてしまうのも、こうした性質の延長線上にある。筆者は過去に知らない相手からお問い合わせフォーム経由で「突然ですがお金をください」と無心されたりしたこともあった。
「本当の弱者は救いたくなる姿をしていない」という言葉がある。この言葉は残酷だが、社会的現実として一定の示唆を与える。
支援を必要としている人が、必ずしも周囲の同情や信頼を集めやすい振る舞いをしているとは限らない。たとえば、自分勝手な態度、攻撃的な言動、過去に支援を踏みにじった経験などがあると、周囲は「またか」と距離を置きたくなる。
これは一見冷たく映るかもしれないが、支援する側にとってのリスクや心的負担も現実に存在する。
弱者が闇バイトや特殊詐欺に応募する理由
特殊詐欺や闇バイトに手を染めてしまう背景には、単なる犯罪志向ではなく、心理的・経済的な脆弱さがある。
心理学では、以下のような認知バイアスが詐欺被害と関連すると言われている。
- 確証バイアス:自分に都合のいい情報ばかり信じる
- 権威バイアス:著名人や肩書に弱い
- 損失回避性:損をしたくない心理で焦り、誤判断
- バンドワゴン効果:みんなやっているから大丈夫と思い込む
詐欺師たちは、こうした人間の心理的スキを的確に突いてくる。
弱者は反省しない
人は長い人生を生きていく上で騙される経験をする。筆者もお金を貸して逃げられたこともあったし、詐欺商品を買わされたこともあった。何度も騙される中で、「世の中にうまい話はない」ということを心のそこから理解することで、相手の得になるポイントが見えない話には一切乗らなくなった。
しかし、すべての人がそうとは限らない。高齢者や認知的なリスクを抱える人、強い信念や固定観念に縛られた人の中には、「反省」というプロセスそのものが機能しにくい場合もある。
筆者のリアルの知人に高齢の経営者がいる。彼はとにかくスピリチュアルや宗教的な思想にハマりやすく、何度も何度も騙されてきた。この記事を書いている時点でも「7月5日に世界が滅びると聞いて、保有している株式をすべて利確して備えた。あなたもそうした方が良い」と提案されたばかりである。論理的な説得は彼らの耳には届かない。だから救えないのだ。
◇
厳しい現実としてすべての弱者を救うことは難しい。だが、騙される人を減らすことは可能だ。学校や社会、家族間で粘り強い啓蒙と教育を続けることである。一部の人にはその声が届いて弱者から抜け出せる人も出てくるだろう。全員は無理かもしれない。だが、一部の人は救えるのだ。
■最新刊絶賛発売中!