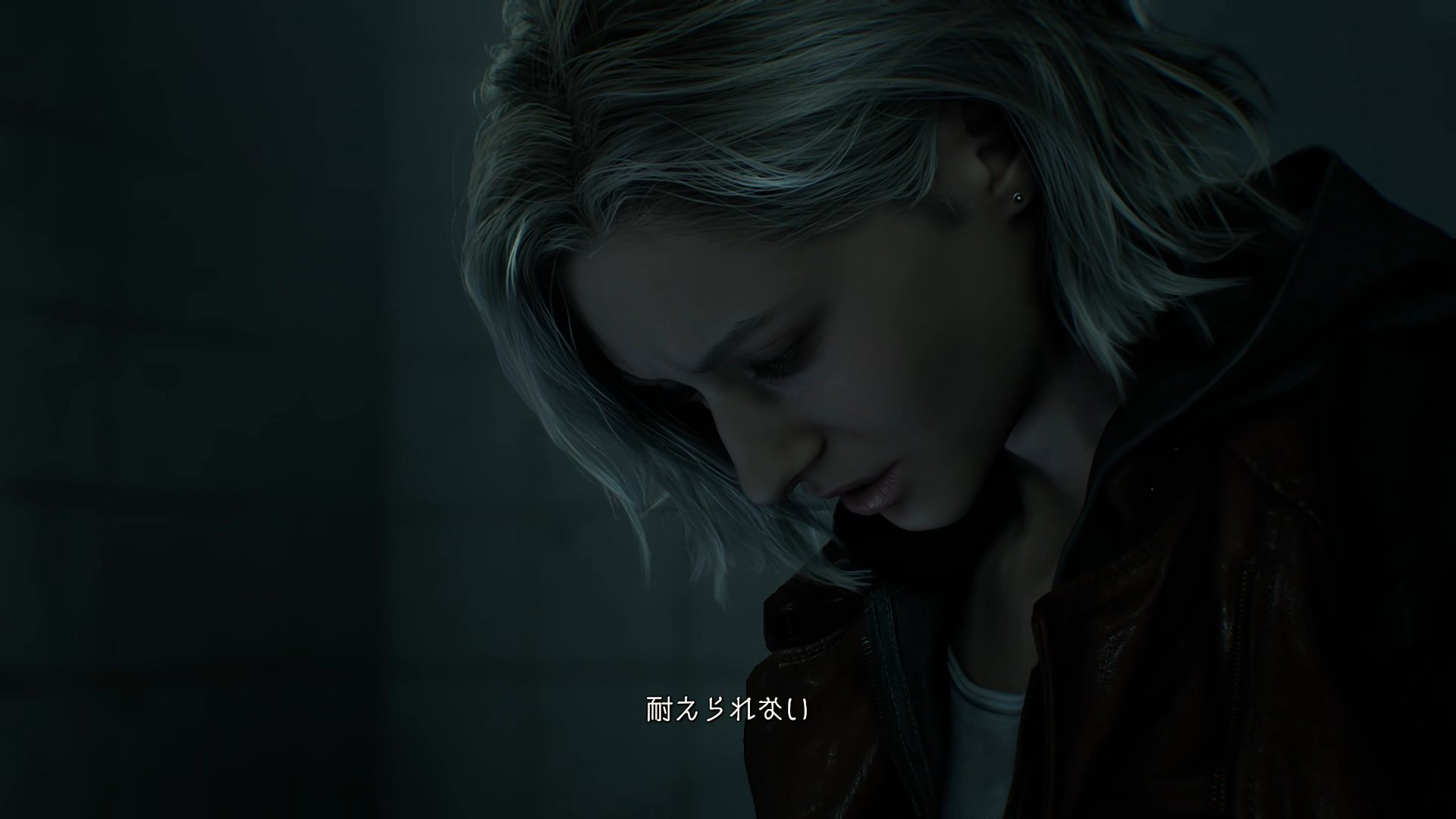【大河ドラマ べらぼう】第31回「我が名は天」回想 この世の地獄、最愛の妻子の無惨な死 「もう逃げない」と覚悟した新之助 利根川洪水の背景にあの大噴火

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第31回「我が名は天」。歴史的大洪水に翻弄される市井の人々の悲哀が、見る人の胸に突き刺さりました。時は天明6年(1786)7月のことです。(ドラマの場面写真はNHK提供)
江戸市中を濁流が覆いつくす
現在の暦では8月上旬にあたります。長梅雨後半の集中豪雨だったのか、あるいは台風だったのでしょうか。関東一円で大雨になり、まず神田川など市中の中小河川が逸水。さらに時間差で利根川中流域で決壊。荒川、隅田川も大水となり、江戸の街の至るところを濁流が覆いつくしました。
米価がまた高騰、流民も
子どもが生まれたばかりの新之助(井之脇海さん)とふく(小野花梨さん)の夫婦。住んでいた深川(江戸の東部)は洪水の被害がとりわけ大きかった地域で、家を流されたり、職を失ったりして多くの住民が生活困難に陥りました。さらに生活できなくなった近隣から流民も大挙、江戸に押し寄せました。施しは満足には届きません。物価の高騰は著しく、米は洪水前には1両で8斗2~3升買えたのが、4斗と2倍近く跳ね上がりました。
長い付き合いの蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)の支援が受けられる夫婦は、それでも周辺の人々よりはいくらか余裕がありました。それがあだになるとは誰も想像できなかったでしょう。
神々しいまでのふくの施し、それが…
困った時はお互い様。ふくは栄養が足らず乳が出ない母たちにかわり、赤ん坊にお乳をあげていました。
食うや食わずの母親たち。乳が出ないのも無理もありません。赤ん坊の「死」に直結する危機的状況です。
ふくの営みには神々しいものさえ感じさせました。
ふくはただ善良というだけではありません。現実を見通す鋭い知性も持っていました。庶民から集めた金で大名に資金援助する「貸金会所令」について、蔦重が「よく出来た仕組み」と理解を示すと、ふくは真っ向から反論。「私らみたいな地べたを這いつくばっている奴に結局はツケが回ってくる。それが私が見てきた浮世というやつなんだよ」とずばり本質を突きます。蔦重は言葉を失ってしまいました。
頭脳明晰で情に厚いふく。そんな魅力的な人物が変わり果てた姿になってしまいました。しかも赤ん坊のとよ坊まで命を落としました。
あまりに切ない人生の終わり方でした。
捕まった下手人は妻と乳飲み子を抱えた貧しい男でした。
「この世の地獄」が眼前に
「わたしがあの家にはお米があるんじゃないか、って言ったもんで。この人、魔が差しちまって」とその男の妻。傍らで泣きじゃくっていた乳飲み子は、ふくがお乳をあげていた赤ん坊のひとりでしょう。その泣き声が耳から離れません。これをこの世の地獄と言わずして何が地獄でしょうか。
「何に向かって怒ればよいのか」 新之助の慟哭
妻同様、世間のことをよく知り、正義感の強い新之助です。まかり間違えば自分もこの夫婦と同じ立場になりかねなかったことは痛いほど分かっています。「この者は俺ではないか。おれは、どこの何に向かって怒ればよいのか」。
最愛の妻子を失った新之助に、蔦重は深川を出て、日本橋の耕書堂に来ないか、と水を向けました。しかし新之助は、墓石はおろか、卒塔婆ひとつ立てることができない無数の土まんじゅうを前にその申し出を断ります。
「もう逃げない」 それが妻子への手向け
「もう、どこまで逃げても逃げ切れぬ気もする。いや、もはや逃げてはならぬ気がする。この場所から」。これまで見て見ぬふりをしてきた社会の矛盾や不公平に、正面から向き合うしかない、という決意でした。それが妻と子への手向けでもあるでしょう。
満足なセーフティーネットもなく、脆弱な環境に置かれていた当時の市井の人々。そして災害などの非常事態が起きると、真っ先に女性や子供たち弱者が「死」に直面しました。そうした実情を見事に描いた強烈なエピソードでした。
新之助とふく 愛あふれ、波乱の人生の道行き
新之助とふく。その道行きは波乱に満ち、また愛にあふれたものでした。
第2回「吉原細見『嗚呼御江戸』」から。実は早い回から登場している2人。この時期から今も出続けている登場人物は田沼意次、将軍家治、一橋治済など一握りです。新之助は世話になっていた源内のお付きで吉原へ。そこで素朴な美しさをたたえた女郎のうつせみ(のちのふく)に一目ぼれします。真摯な新之助にうつせみも夢中になります。
第9回「玉菊燈籠 恋の地獄」から。女郎が入れ墨に痛がる様をみて喜ぶ変態客の求めでした。しがない浪人で、決して懐具合が豊かとはいえない新之助。吉原に頻繁に通う事はできません。そこでうつせみは自分で「揚代」(女郎と遊ぶ際の代金)を支払い、新之助と逢瀬を重ねました。売上のためにおかしな客の求めに応じて、嫌々入れ墨までいれるハメに。この状況に新之助、うつせみに足抜けさせることを決意します。
しかしあっという間に追手に見つかってしまいます。
うつせみを厳しく折檻した松葉屋の女将のいね(水野美紀さん)。その辛辣な言葉が、吉原に生きる女性の現実を改めて見せつけました。
「こんなやり方で幸せになれるわけないだろ。この先、どうやって暮らすつもりだったんだい。追われる身になって、どこに住むんだ。人別(戸籍)は?食い扶持は?あいつはあんたを養おうと博打、あんたはあいつを養おうと夜鷹(下級の売春婦)。成れの果てなんてそんなもんさ」。
「祭りに神隠しはつきもの」あの名シーンも遠く
しかし互いに思いあう気持ちは変わることはありませんでした。そこに「べらぼう」屈指の名シーンが誕生しました。
第12回「俄なる『明月余情』」から。視聴者、涙涙の場面でした。吉原が街を上げてのお祭り『俄』の日。「もしかしたら」と淡い期待を描いていた2人は、喧騒の中に互いの姿を認めます。しかし女将の言葉が頭をよぎったのか、足を前に出せないうつせみに、同僚の松の井(久保田紗友さん)がドン、と背中を押しました。「祭りに神隠しはつきものでござんす。お幸せに」。
雑踏に紛れて足抜けに成功。平賀源内の世話でとある農村で暮らすことになりました。
第17回「乱れ咲き往来の桜」から。物品の調達のために江戸を訪れ、蔦重に無事を知らせるためにこっそり吉原に足を運んだ新之助。江戸時代半ば過ぎ。都会へ逃げ出す人が増えたり、凶作が続いたりで荒廃が進んでいた農村は人手不足が著しく、働き手になってくれるのであれば身元はうるさく言われなくなっていました。お百姓の子弟に読み書きも教えていた新之助、蔦重に健在なのを伝えたことで、蔦重が「往来物(子供向け教科書)」のビジネスアイデアを思いつく一幕もありました。
ようやく、夫婦2人で安住の地を見い出したと思ったのもつかの間。
第25回「灰の雨降る日本橋」から。新之助とふくが身を寄せた村は、よりによって浅間山の麓にありました。天下を揺るがす大災害に遭遇します。浅間山の麓近くに住んでいた2人。天明3年(1783)7月の大噴火で被災者に。生活苦になると、村から最初に追い出されるのはよそ者という悲しい経験もしました。餓死寸前まで追い詰められながら、蔦重の元に駆け込み、なんとか命を繋ぎました。
歴史的な大噴火。直接の被害はもとより、大量に放出した火山灰や泥流は洪水などの原因にもなり、信州や関東などの広い地域をその後も長く悩ませることになりました。この浅間山の噴火、夫婦をどん底に突き落としたその後の洪水とも深く結びついているのです。
歴史的な利根川洪水、浅間山噴火が直接影響
この時期の利根川は梅雨時の集中豪雨や台風で洪水になることがあり、広大な流域を抱えていることでその被害も大きかったのです。中でも今回の天明6年の洪水は、寛保2年(1742)の時とならんで、江戸時代最大級の洪水とされています。
「安政風聞集」国立公文書館デジタルアーカイブたびたび風水害に見舞われた江戸の町。こちらは安政3年(1856)の水害を描いた作品。なぜ大洪水になったのでしょうか。3年前の浅間山大噴火が大いに影響していました。火山灰が遠くはなれた佐倉(現在の千葉県)でも10センチ程度積もるなど、この大噴火で降った灰の量は4億立方㍍に達したとされています。これは渡良瀬遊水地の容量の2倍に相当します。また浅間山の麓の鎌原村(現在の群馬県)を全滅させた泥流は吾妻川を通じて利根川に流れ込みました。これらの降灰や泥流によって利根川は全流域で河床が上昇。水を流す能力が低下したことなどから、増水によって堤が壊れるケースが増え、噴火以前では洪水は10年に一度程度だったのが、噴火後は3~5年に一度と激増しました。
「安政風聞集」国立公文書館デジタルアーカイブドラマで描かれた大洪水では中流域の中条堤や権現堂堤が破堤し、濁流が江戸の市中まで押し寄せました。本所、深川、下谷、浅草、千住、向島、牛込、小石川などの低地まで浸水。冠水の深さは場所によって3~5㍍に達し、隅田川にかかる永代橋は一部流出し、両国橋は大破しました。浅間山の噴火はこのように長く、人々を苦しめたのでした。
印旛沼の干拓も洪水で挫折
ドラマの中でもこれまでに何度か話題になっていた「印旛沼の干拓」。意次らが期待を寄せていた一大プロジェクトでしたが、こちらもこの大洪水でご破算になってしまいました。
現在の千葉県北部にある印旛沼。干拓計画は、利根川と繋がっている川を仕切り、江戸湾(東京湾)方向に新たに放水路を作って湖水を流すという大工事でした。水害防止と米の増産を狙って田沼時代に工事が始まり、順調に進んで天明6年までには全体の3分2ほどが終わっていたのですが、折からの大洪水、そして意次の失脚によって中止に。結局、干拓は昭和になるまで実現しませんでした。多くの人々の運命を変えた大水害でした。
家治の死、意次の失脚、定信の躍進 すべてはあの人の掌中?
大水害の発生に「時が来た」と欣喜雀躍したのが一橋治済(生田斗真さん)。いよいよ目障りな存在を片付け、息子の家斉を将軍に就ける時期がきた、という意味だったでしょう。そして自らの手で歴史の針を進めていきます。様々な陰謀はドラマ上のフィクションではありますが、必ずしもすべてが作り話とも思えないほど、この時期に一気に権力構造が変わったのも事実です。
50歳を目前に体調が思わしくなくなってきた将軍家治(眞島秀和さん)。
それを聞いた側室の知保の方(高梨臨さん)が「醍醐」という高級の乳製品を献上。「滋養があります」と勧めてきました。
実際に調達してきたのは大奥御年寄の大崎(映美くららさん)。もともと一橋家に仕えて次期将軍・家斉の乳母でした。
大崎は治済と近く、「薬」に詳しいとされ、これまでも将軍の後継者だった徳川家基、老中の松平武元の暗殺など、様々な陰謀に加担したように描かれてきました。
家基は満16歳の若さで急死。それまで健康だっただけに、陰謀があったとする見方は昔からありました。 家基が身に着けていた手袋に着目し、家基の死の真相に近づいた武元でしたが… 陰謀の察知を危惧した何者かによって武元は無きものにされました。証拠の手袋も持ち去られてしまいました。ついには現役の将軍にまで毒牙にかけるとは……。醍醐を将軍の口に入れさせるまでに、将軍の周辺にいるどれほどの人間を手懐け、あるいは脅したのでしょうか。治済サイドの恐るべき組織力と実行能力です。
「あやつは天になりたいのよ」
口にした醍醐のせいで、深刻な体調不良に陥った家治。裏で糸を引いているものが誰かは分かっていました。巧妙な陰謀で真相を解明するのはまず困難です。まして将軍家に最も近い御三卿が関わっていたことが表沙汰になれば、幕府の権威は失墜します。いずれにせよ手が出せない存在でした。
「あやつは天になりたいのよ」。治済の狙いについて、家治は意次にそう語りました。「あやつは人の命運を操り、将軍の座を決する天になりたいのだ。将軍の控えに生まれついた、あの者なりの復讐であるかもしれぬ」。視聴者にもなるほど、と思わせる治済の内心に関する分析でした。
死の床の家治を見つめる次期将軍の家斉。在位50年、さらにその後も大御所として実権を握り続けました死の間際、家治は最後の力を振り絞り、言葉の一太刀を治済に浴びせました。「よいか、天は見ておるぞ。天は、天の名を騙る驕りを許さぬ。これからは余も天の一部となる。余が見ておることをゆめゆめ忘れるるな」。
亡くなった我が子である「家基」と呼びかけ、意識が混濁したように装いつつ、「おれは、お前のやった事のすべてを知っているのだぞ」と治済に伝えた最後のメッセージでした。もちろん、治済も家治の意図はすべてお見通しだったでしょう。
しかし死んでしまった者の思いなど歯牙にもかけないのが治済です。キングメーカーとしていかに幕府に君臨するのでしょうか。その動向にはこれからも目が離せません。
失権の意次、しかしただでは転ばない
相次ぐ天変地異、物価の高騰、跡取り息子の意知の死、後ろ盾になっていた将軍家治の退場と、それまでの我が世の春がウソのように四面楚歌となった意次です。これまで意次べったりで、実務は頼り切りだった首席老中の松平康福(相島一之さん)は、雲行きが変わったのを見てとって、「自ら身を引け」と老中を辞するよう迫ります。敵対陣営や、反意次に舵を切り始めた大奥に取り入るための「土産」が必要だったのです。掌を返すように、とはこうした事でしょう。
もうこれまで、と老中職の辞職願を差し出した意次。いよいよ田沼時代の終焉、と誰もが感じたことでしょう。
実際、ここに至るまでの出世も異例中の異例なら、下降線に入ってからの落ち方も尋常ではありません。まるでジェットコースターです。
600石の旗本から出発し、一代で5万7000石の城持ちまで上り詰めましたが、失政の責任を取らされる格好で老中を辞めてからは城を取られ、禄を剥がされる一方。最終的に、田沼家としては1万石という最低線の大名家の家格を守るので精一杯でした。一族も家臣たちもどれほどの無念だったでしょうか。しかし、一方でここで簡単に土俵を割らないところが意次の真骨頂でした。意次演じる渡辺謙さんも「落ち目になってからの意次こそ見せ場」と話しています。次回以降、その意地の見せ方がドラマでも注目されることでしょう。
(※)参考図書:「天明の江戸打ちこわし」(新日本新書)、「江戸の災害史」(中公新書)、「江戸水没 寛政改革の水害対策」(平凡社)、「田沼意次の時代」(岩波現代文庫)
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから