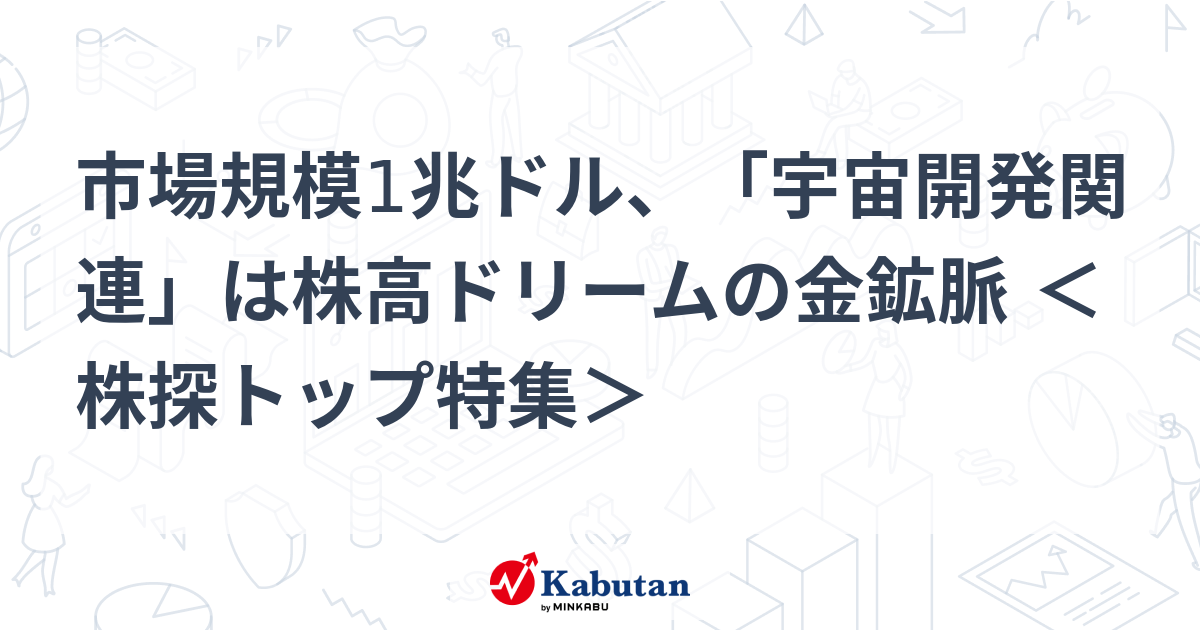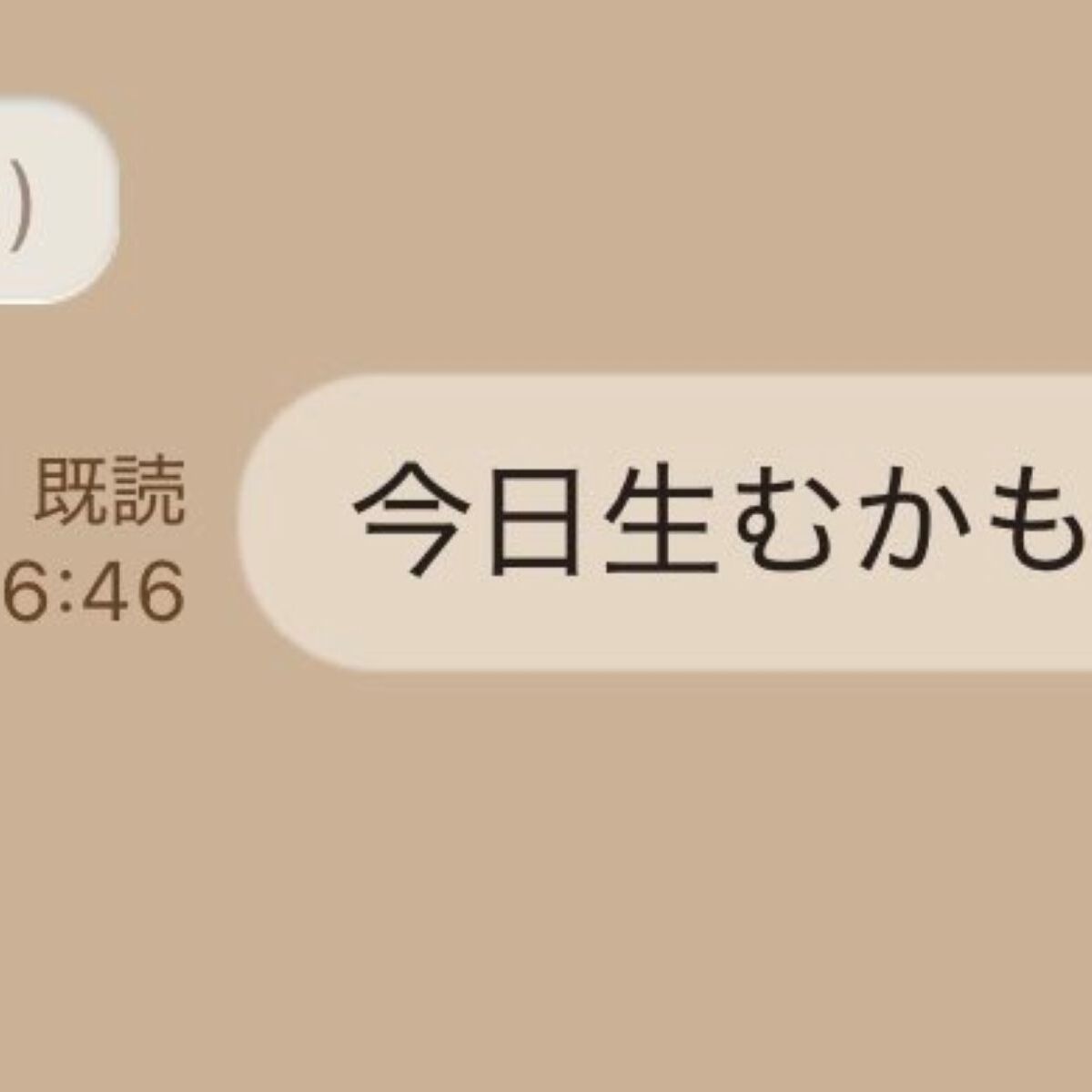コラム:ドル安・債券安が示すトランプ政策「自滅の選択肢」=熊野英生氏

[東京 25日] - トランプ政権の経済政策の目論見に、狂いが生じているようだ。大統領自身、「債券市場はやっかいだ」と述べて、相互関税に留保期間を設けて7月上旬までは10%の税率にする修正を行っている。
なぜ、「債券市場はやっかい」なのだろうか。
トランプ氏は、一時は米連邦準備理事会(FRB)に利下げを求めて、パウエル議長に辞任を迫るほど不満を募らせていた。自分で関税をかけておいて、景気悪化への対処はFRBの利下げに押しつけようとしている。利下げをして景気を良くしたいと思っているからこそ、長期金利上昇の反応に困るのだ。
通常、株価が急落するとき、投資資金は安全資産とされる債券にシフトして、長期金利は低下する。今回、米国では債券シフトもせずドル自体が売られ、トリプル安の様相になっている。ドルを保有すると、これから値下がりすることが怖いので、投資家はリスク資産と化したドル資産を減らそうとしている。トランプ政策がころころと変わり、それがインフレリスクにつながる危険性が高いことによって、ドル資産が敬遠されているのだ。債券は代表的な安全資産のはずだが、一度インフレが加速しそうになれば、債券価格が下落して魅力が失われることになる。
トランプ関税は、スタグフレーションの引き金になる可能性があって、米国の経済政策を機能不全に陥らせるとみられている。通常であれば、「株価が下がればFRBが利下げで救済してくれる」というセーフティネットが機能するが、今回は、インフレリスクを感じてFRBは動けないとみられている。ドル売りを誘発しているのはこの機能不全への警戒感なのだろう。トランプ氏がインフレリスクをあまりに軽視してきたので、債券が売られるかたちになって、手痛いしっぺ返しを受けている。債券売りまでコントロールできないことが「やっかいだ」という発言の真意だろう。株価下落には「今は我慢のときだ」と静観できても、債券下落にはどうすることもできない。長期金利上昇は、トランプ政権のアキレス腱にみえる。
<悪いドル安>
貿易赤字を改善したいトランプ政権にとっては、ドル安は都合がよいという見方は成り立つ。トランプ氏はこれまで一貫してドル高を嫌い、ドル安を歓迎してきた。ドル安は、米国からの輸出を押し上げて、輸入を減らしていくという考え方からだ。
しかし、ドル安については、「良いドル安」と「悪いドル安」の2種類がある。「良いドル安」とは、FRBが金利を引き下げて、米国経済の成長につながっていくケースである。金融緩和が為替レートの減価を通じて、輸出増というかたちで成長支援につながっていく。国内生産能力に余剰があって、ドル安によって海外の輸入相手国からみて、米製品が割安になったから輸入量を増やしたいと思われるケースでもある。
ところが今のドル安はそれとは違っている。FRBが金利を引き下げると、インフレが加速して個人消費は減速するだろう。成長加速につながるドル安ではなく、インフレによって成長悪化が予想されて、それが原因になってのドル安である。悪いドル売りと言ってもよい。
「悪いドル安」を引き起こす原因は、まさしくトランプ関税にある。コストプッシュ圧力を生み出し、インフレ圧力を強めている。それがスタグフレーションの犯人であることを正しく認識すべきだ。政権が目指すべきは、貿易赤字の解消ではなく、経済成長の方である。米国民も豊かになり、海外の貿易相手国とも共存共栄ができる。
今、「悪いドル安」はさらなる弊害を生み出そうとしている。日本からみれば、ドル安は円高であり、日本の輸出企業に打撃を与える。トランプ関税で採算が悪化したところに円高が加わると、輸出減・収益減で日本経済を苦境に立たせる。
同じことがアジア各国でも起こるだろうから、「悪いドル安」は世界経済を巻き込んで、景気後退リスクを拡散させていると言ってよい。トランプ氏さえ翻意すれば、この危機はなくなる。何とか考え方を見直してほしいものだ。
<凋落する米国>
トランプ氏は、貿易が失業者を生み出し、製造業を凋落(ちょうらく)させているという世界観で話をしている。しかし、米国で製造業が国内総生産(GDP)に占める割合は1割に過ぎない。失業者が街にあふれているようなストーリーを語るが、米国で4%台前半の失業率は完全雇用に近い。実体経済に対するイメージが現実とかなりずれている。関税によって輸入コストが上がると損をするのは消費者であり、非製造業部門である。たとえディールを通じて国内直接投資や農産物輸出を増やすことができたとしても、恩恵は大きなものではない。
スマホでも人工知能(AI)でも、米国企業が国際分業を通じて低コストで製造できているので、トランプ関税を高くすることは自国のハイテク産業の足を引っ張ってしまう。おそらく、関税があるから米国で製造しようとする海外企業よりも、米国以外の取引先にシフトしようとする海外企業の方が多いだろう。これはドルの経済圏を縮小させ、ドルの通貨需要を減らすことになるだろう。いわば、ドルの凋落にもつながりかねない。
米国は巨大な貿易赤字を毎年のように生み出しているから、資本収支の黒字も膨らんでいく。トランプ関税で強制的に貿易赤字が削減されると、資本収支の黒字も減ってしまう。米国債の発行が、ドル資金で各国が資金運用する金融市場の拡大に貢献するのならば、米国の財政が黒字化すればそうした金融市場も成長しにくくなる。昔から「強いドルは国益」と言われてきたのは、資本収支の黒字を継続できるためのメカニズムとして、ドルは強い方がよいと考えられてきたからだ。今、ドルがリアルの世界で弱体化し、ドル価値が低下しようとしていることは、米国への資金還流システムを破壊しようとしていることにもなるだろう。米国債がより高金利でないとドル投資を引き付けられない状態になり、今度は米国の経済成長もまた脅かされる。貿易赤字を問題視してドル安を歓迎するトランプ氏の発想は、まさしく自滅する選択である。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*熊野英生氏は、第一生命経済研究所の首席エコノミスト。1990年日本銀行入行。調査統計局、情報サービス局を経て、2000年7月退職。同年8月に第一生命経済研究所に入社。2011年4月より現職。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab