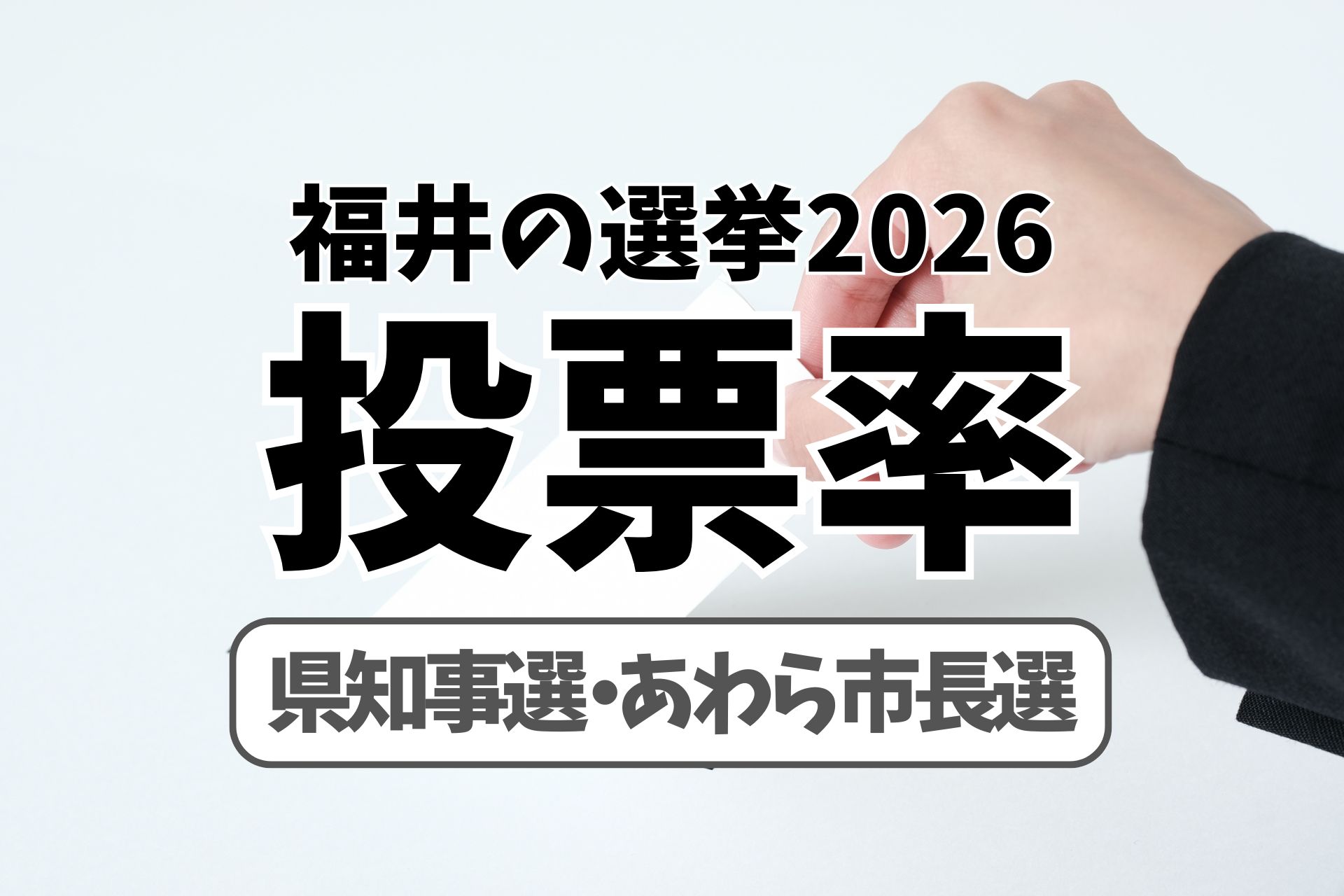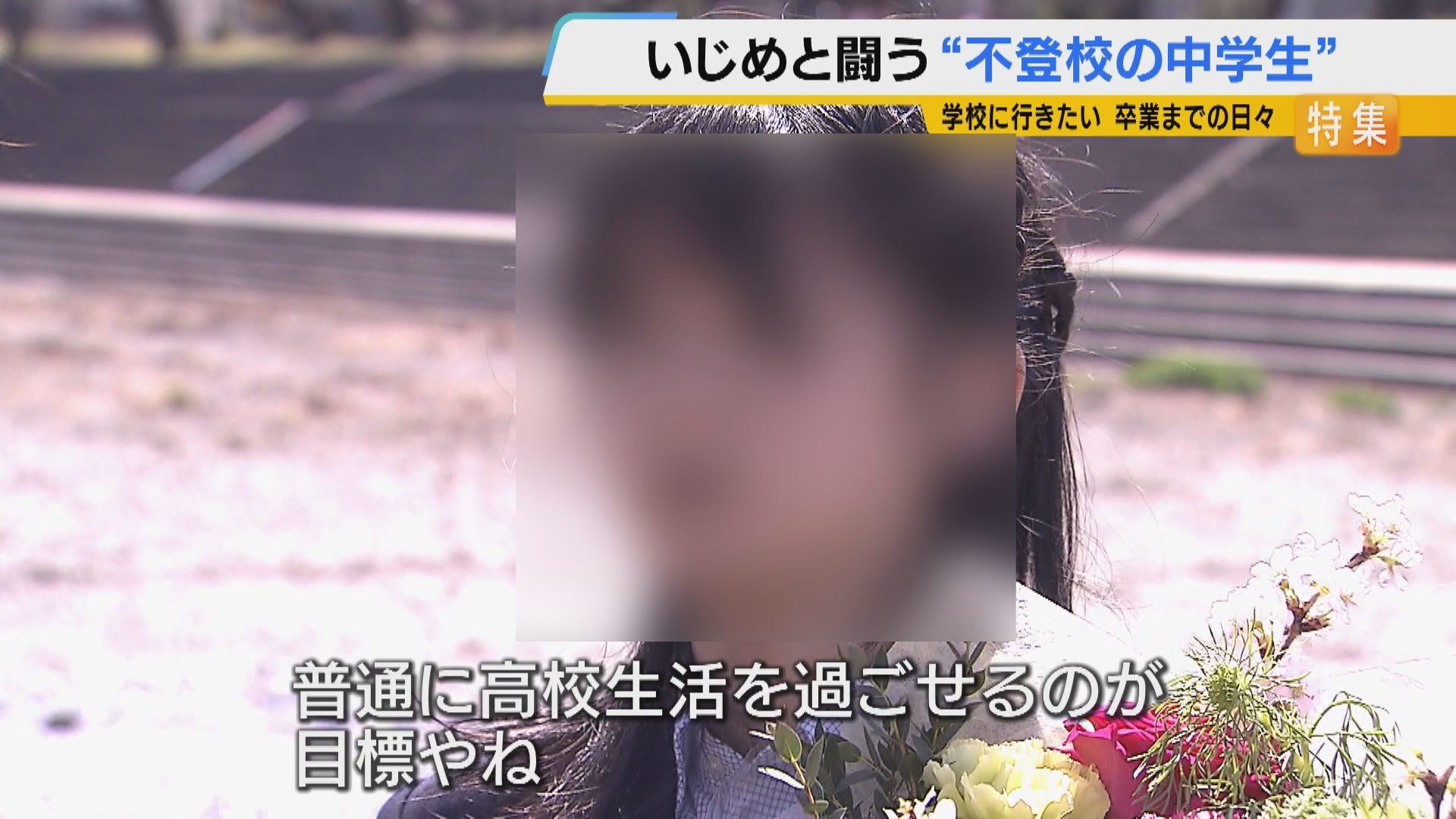「戦争国家」の暴走を許さない 志位・共産党議長が熱論 「国民を守る政治」へ

対米従属と大企業優遇に特徴づけられた自民党政治は、国民生活から乖離し限界を超えたと喝破する志位和夫共産党議長。軍備の拡張、極右排外主義の跋扈、世界的に現出する資本主義の弊害など、国民を脅かすかつてない危機に、生活者からの視点で斬り込む――。
国民と野党で「民主主義のための連帯」を/マルクスは人間解放の原点
永田町には「政治家望楼」と呼ぶべき見晴らし台がある。
いくつかの望楼からの定点観測で、日本政治の動きをウオッチしてきた。望楼は高いほど展望が効くし、遠目が届く。高さはその政治家の永田町でのキャリア、政治家としての闘いぶりが関わる。小欄では、ある時は小沢一郎氏の望楼を訪ね、またある時は石破茂氏の望楼から世を眺め、さらには、山崎拓氏の望楼に時を借りてきた。保守系の望楼もあれば、リベラル系の望楼もある。右もあれば左もある。左側では圧倒的に聳(そび)え立つのが共産党・志位和夫氏の望楼である。
志位氏といえば衆院議員11期、1990年から2000年まで書記局長、そこから24年まで委員長だった。野党の中でこれだけ党首級ポジションを長期に務めた人はいない。数限りない党首討論、国会論戦、選挙の洗礼を受けてきた。
06年には共産党委員長として初めて韓国を訪問、08年、ネットで国会質問が「CGJ(志位グッジョブ)」とされ、10年、歴代党委員長として初訪米、党の体質、路線を時代に合わせてモデルチェンジしてきた人である。「何でも反対」純粋野党路線からの転換も模索、09年の鳩山由紀夫政権への交代時には「建設的野党」の立場を強調、そして15年、集団的自衛権の行使解禁を謳(うた)った安保法制の国会審議を巡る政局では、同法廃止に向けて野党結集を提唱、他野党との選挙協力推進による国民連合政府作りを目指すことを明確化するなど従来路線を一転した。亀井静香氏に「最大の政局アクター」と言わしめた。
その志位望楼を久しぶりに訪れた。『共産主義と自由』(24年7月)、『いま『資本論』がおもしろい』(25年8月 いずれも新日本出版社)の2部作を完成させたばかりという。その志位氏に過去、現在、未来にわたる三つの問いを発したい。安保法制10年をどう総括するか。参院選結果と政治の排外主義化をどう見るか。マルクスブーム再燃の中で資本論から何を学ぶか。
安保法制ゴリ押しにより倫理が崩壊した
まずは安保法制10年だ。
「戦争国家作り暴走の10年だった。安保法制は集団的自衛権の行使、つまり戦争国家作りを法制面で整備したが、実践面で推進の青写真を描いたのが、22年12月の岸田文雄政権の安保3文書改定だ。自衛隊の空前の大軍拡、日米共同の戦争体制作り、敵基地攻撃ミサイルの全国配備、軍事費2%、さらに3・5%にするという。日米の指揮統制機能一体化も重要なポイントだ。対中国を念頭に置いた日米合同演習を今年すごい規模で行った。軍事対軍事の悪循環が加速、非常に深刻な事態を作り出している」
「今やるべきはこれを転換し、外交の力で平和を作ることにある。私たち共産党は、東アジア平和構想でASEANと協力した平和の枠組み作りを提唱している。対中国も日中関係打開のための提言を行い、日中友好議連メンバーとして参加した4月の訪中でも中国指導部に伝え、肯定的な反応を得た。転換が必須だ」
「もう一つ指摘すべきは、安保法制ゴリ押しのため安全保障の根幹で憲法解釈を一夜にして変えてしまったことが、あらゆる法的秩序の解体を招き、深刻な政治のモラルハザードを起こしていることだ。憲法は国家権力を縛る基本原理だ。それを平気で壊すようではある意味怖いものなしとなる。それが安倍晋三政権時代の『森友・加計・桜を見る会』スキャンダルや、裏金事件であれだけのことして全く反省をしていない姿勢につながっている。戦争国家化を止めるだけではない。日本の政治に健全なモラルを取り戻すためにも安保法制廃止は緊急課題だ」
「同時にこの10年は、市民と野党の共闘の10年だった。15年9月19日、安保法制廃止の国民連合政府を作ろうと選挙協力を呼びかけた。我が党として、清水の舞台から飛び降りるつもりで、史上初の道に踏み出した。それから10年、共闘はいろんな攻撃に遭いジグザグも余儀なくされた。しかし、いま何よりも強調したいのは確かな成果をあげ、今に生きていることだ」
どんなジグザク?
「出発点は16年の参院選だった。2月の野党5党首会談で、安保法制廃止で選挙協力すると合意し、初めて32の1人区で野党を一本化、11で勝った。17年衆院選は直前の都議選で共産党が躍進、次は政権交代を目指そうと構えた。だが突然民進党が希望の党への合流を決め一瞬のうちに野党第1党が消えた。安保法制容認と改憲が踏み絵だった。我々は何とか共闘を再構築しようと力を振り絞り、発足したての立憲民主党と協力し、32の小選挙区で勝利し共闘をつないだ」
「これで18年の国会が様変わり、野党共闘が国会内で発展、合同ヒアリングを随分やった。その流れで19年参院選は共闘がさらに発展、共産党が一方的に候補を降ろすだけでなく相互支援が始まった。高知・徳島、鳥取・島根、福井は共産党候補で一本化した。気持ちのいい共闘で10で勝った」
「この流れを踏まえ、21年の衆院選はいよいよ政権交代に挑戦しようと、20項目の政策合意をかわし、立憲との間では、限定的閣外協力という形での政権協力も確認した。その結果59小選挙区で勝利、石原伸晃、甘利明氏ら自民有力者を次々に落とした。中盤までは善戦、政権交代の背がぼんやり見えたが、その後の激しい共産党攻撃でそういかなかった。閣外協力でも共産党参加の政権ができたら大変だ、何としても潰さねば、と日本の支配勢力がとことん恐怖を感じたと思う。その後も攻撃が強まり、22年の参院選は野党共闘が大幅後退、1人区で勝ったのは四つだけだった」
参政党は大企業規制を一切口にしない
で今年の参院選だ。
「あまりメディアが書かないが、野党共闘は17選挙区で一本化、12で勝った。16年は11、19年は10、22年は4だったから過去最高だ。野党共闘はどっこい生きていた。しかも今回は党首会談できちんと政策合意した上での共闘だった。市民生活を犠牲にする大軍拡反対、企業・団体献金廃止などの政策合意を掲げて勝ったことを軽く見るべきではない。自公過半数割れにつながる原動力になった。同時に危険な逆流も伸長した」
参政党の台頭どう見る?
「欧米ですでに起きている現象だ。ネオリベラリズム(新自由主義)とそれに基づくグローバリゼーションがごく一握りの超富裕層と大企業に巨額の富を集中させながら99%の人を貧しくし、目が眩(くら)む格差を広げ、破綻に直面している。極右排外主義の台頭は、そのことに対する時代の反動的あらわれだ。欧州では08年のリーマン・ショック以降極右が台頭、新自由主義の行き過ぎに対する不安、批判を掬(すく)いあげる形で勢力を広げてきた。でも彼らもまた新自由主義だという実態を見落とすべきではない」
「参政党にしても反新自由主義、グローバリゼーション反対と言うが、大企業への規制、負担拡大は一切口にしない。社会保障はもっと切り捨てろ、終末期医療の全額自己負担をと言う。新自由主義批判の衣を被(かぶ)った新手のより野蛮な新自由主義とも言える。ただ欧州極右との違いは、…