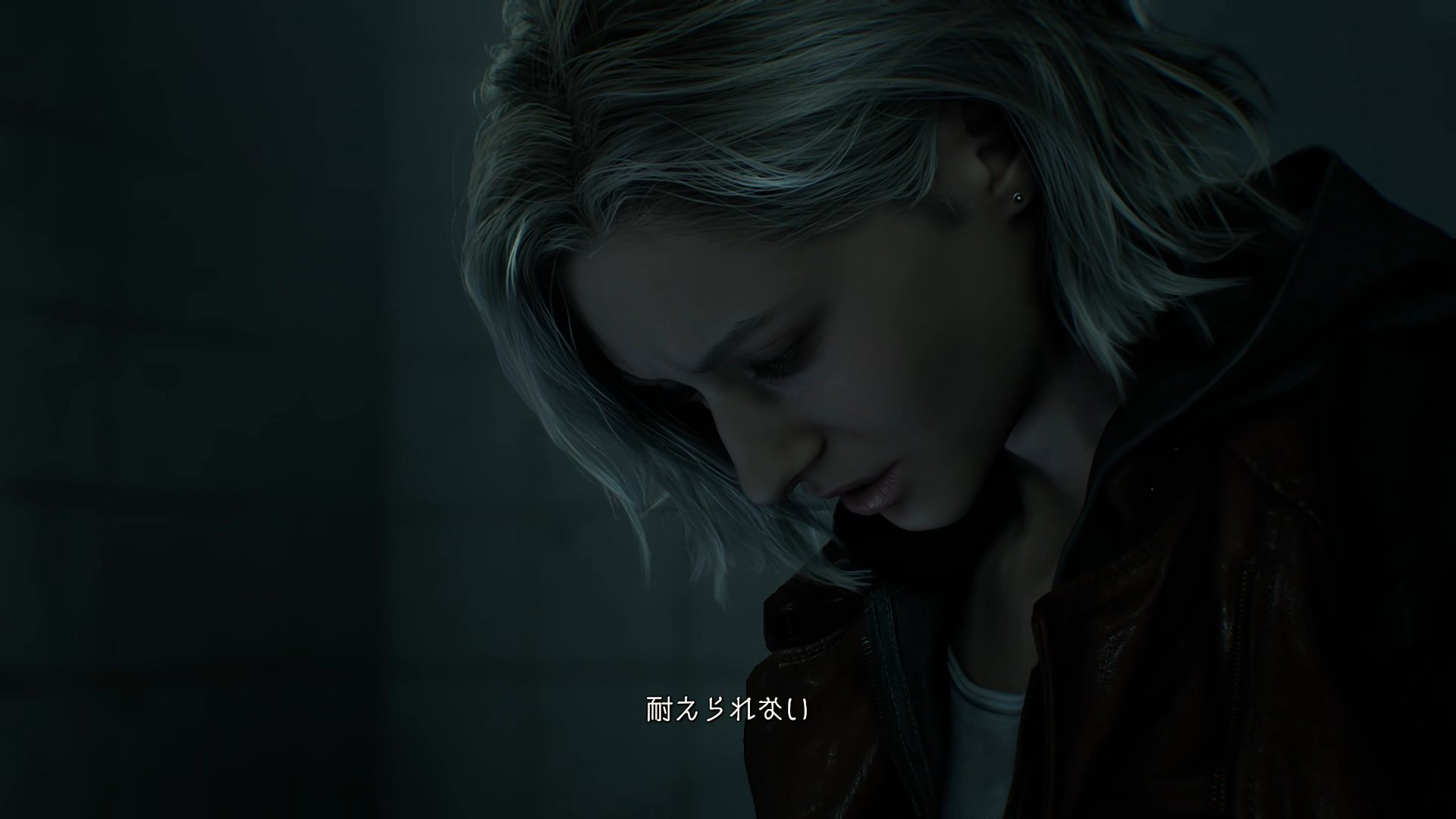【大河ドラマ べらぼう】第34回「ありがた山とかたじけ茄子」回想 蔦重と共に時代の精神を体現した意次、ついに退場 隠密を駆使、町の動向を注視していた定信

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の第34回「ありがた山とかたじけ茄子なすび」では、第1話から主役の蔦重(蔦屋重三郎、横浜流星さん)とともにこの時代の精神を体現し、ストーリーの柱を担ってきた田沼意次(渡辺謙さん)がついに退場となりました。(場面写真はNHK提供)
「同じ成り上がりであるからな」 励ます意次
第1回「ありがた山の寒がらす」で接点を持って以来、蔦重に対しては常に強い関心と共感を示していた意次。ただし、あくまで武士と町人という「一線」を越えることはありませんでした。町人である蔦重を政争に巻き込んではいけない、という思いも強かったのです。しかし今回は「俺もお前と同じ成り上がりであるからな」と似たような人生の歩みだったことをあえて言葉にして、蔦重を励ましました。意次は齢70に届くところで、もう生きて顔を合わせることもないかも、という思いもあったのかもしれません。
「田沼さまの作り出した世が好きでした」 感謝の蔦重
重い決意を胸に意次を訪ねた蔦重。「田沼さまが作り出した世が好きでした。皆が欲まみれでいい加減で。でもだからこそ心のままに生きられる隙間がありました」と田沼びいきの姿勢を明確にします。この時期、すでに世間から袋叩きにされていた意次でしたが、「私は書をもってその流れに抗いたく存じます。ただ、そのために田沼さまの名をさらに貶めてしまいます。そこはお許しいただけるでしょうか」
「我が心のままに生きろ」 源内の言葉を胸に
蔦重の思いを真正面から受け止めた意次。「許さぬなどと言えるはずがない。そんなことを言えば、あの世から源内が雷を落としてこよう。好きにするがよい。自らに由って我が心のままに」。共に敬愛する源内の言葉を餞に贈りました。
「田沼さま、ありがた山のとんびがらすでございます!」と蔦重がいえば、「こちらこそ、かたじけ茄子である」と意次。この台詞、第1回「ありがた山の寒がらす」の名シーンを思い起こさせます。
“起業家精神”を意次から学んだ蔦重
宿場などにある非公認の遊里が栄え、苦境に陥った吉原を救おうと単身、意次邸に乗り込んだ蔦重。公儀による取り締まりの強化を訴えた蔦重に、意次はこう語りました。「人を呼ぶ工夫が足りぬのではないか。お前は何かしているのか。客を呼ぶ工夫を」。
雷に打たれたかのような蔦重の表情が印象的でした。「他人や権力を頼るのではなく、自分の力で状況を変えてみせろ」という問いかけは、足軽の家から這い上がり、老中にまでのし上がった意次でなければ言えない言葉でした。ゼロから事業を創出するアントレプレナー(起業家)の精神は、この自由な田沼時代にこそ相応しいもの。蔦重がその生きる姿勢を意次本人から伝授されたシーンは、ここまでの「べらぼう」全編の背景となる重要なものでした。
「田沼さま、お言葉、目が覚めるような思いがいたしました。まこと、ありがた山の寒がらすにございます」。この時は、感謝の言葉を振り絞った蔦重に、視線を送ることなく広間から立ち去った意次でした。
「忘八!」と意次に詰め寄ったことも
何度なく、真剣なやり取りを交わした蔦重と意次。第16回「さらば源内、見立ては蓬莱」では、源内を助けようとしたなかった意次に、「忘八!」と厳しい言葉を浴びせた蔦重でした。源内は一橋治済らの謀略によって、無実の罪を着せられていたのでした。
実は源内を救い出そうとしていた意次。しかし甘んじて蔦重の怒りを受け止めました。
この2人にしか分からない葛藤をいくつも潜り抜けてきました。
そして最後の場面では、意次は蔦重の目をしっかり見つめ、手を握り、熱い言葉をかけました。蔦重の歩んできた道のりの確かさ、そして「あとを託したぞ」という意次の思いが浮かび上がるシーンでした。渡辺謙さんの確かな存在感に支えられ続けた「べらぼう」でもありました。
ちなみ、第1話に登場して今も残るキャストは長谷川平蔵(中村隼人さん)、次郎兵衛(中村蒼さん)、九郎助稲荷(綾瀬はるかさん)、高岳(冨永愛さん)、知保の方(高梨臨さん)、松平康福(相島一之さん)らとずいぶん少なくなりました。
徹底的な田沼つぶし
老中の座を追われてからの意次の失墜ぶりは強烈なものがありました。
(牧之原市の資料を基に作成)1代で600石の旗本から、5万7000石もの大名に栄達。居城の相良城(静岡県牧之原市)も新たに築城したのに、あっという間に石高は1万石に減らされ、田沼家として最低限の大名格を維持するのがやっとでした。相良城も破却を命じられました。
現在、城跡に足を運んでも、遺構らしい遺構はあまり残っておらず、徹底的な破壊が行われたことが伺えます。松平定信ら反田沼派の恨みがいかに強烈なものだったか。あらためて当時の政争の激しさを実感できる牧之原の街です。
それでも近隣のお寺などにかつて城にあったとされる襖絵や太鼓、石垣の一部などが残っています。大澤寺だいたくじ(牧之原市波津)では、床下にお城の部材と思われる木材が使われており、「何とか田沼家ゆかりのものを残したい」という当時の領民の気持ちが伝わってきます。
地元の古刹の平田寺へいでんじ(牧之原市大江)に安置されている田沼家代々の位牌では、意次と意知だけ、厨子に家紋が入っていません。家紋を入れることを憚ったのでは、という見方があり、晩年の意次が置かれた境遇がいかに過酷なものだったかを物語ります。
「遺訓」に垣間見える意次の人柄
「田沼意次遺訓」という文書が残っています。前文と全七条からなります。「相良町史」に基づき、一部を紹介します。相良町は旧静岡県榛原郡、現在は牧之原市の一部となっています。
第一条には「まず第一に主君に対する忠節のこと。仮りにも忘却致すまじきこと。当家(田沼家)においては、九代将軍家重候、十代将軍家治候には比類のない御厚恩を受けているのであるから、両代の御厚恩を決して忘れてはならない」と将軍家に対する忠誠を最優先事項として挙げています。
「遊芸もよし」「百姓町人に無慈悲なことをするな」
人柄がよく出ているのが第五条で、「武芸は懈怠なく心がけ、家中の者たちに油断なく申しつけ、若い者は特別精を出し、他所から見ても見苦しくない芸は折々に見分させ、自身が見物することもよい。且つ、武芸に心掛けた上で余力があれば遊芸を楽しむのも勝手次第である。」としており、余裕があったら遊ぶのも結構、とは自由を謳歌した田沼時代のリーダーらしさが出ている箇所でしょう。
そして最後の第七条は、わざわざ別紙を付けくわえて、無駄な出費をしないように心がけることを強調。「領内に無体な年貢を申しつけ、これによって財政不足を補うことは筋の通らないことであるから、慎むべきである。すべて百姓町人に無慈悲なことをすれば、必ず御家の害になるものである。いくえにも正道を以て万事にあたるべきである」と結んでいます。バランスの取れた指導者像が浮かび上がってきます。政治家としての評価には様々な見方があるでしょうが、天変地異が続いた時代に責任ある立場になったことが不運な人ではありました。
隠密を駆使、情報戦を重視した定信
意次に代わり、あの吉宗公の孫、を全面に押し出しさっそうと登場したのが松平定信(井上祐貴さん)でした。
自分にとって都合のよい情報を読売(かわら版)で広める一方、市中の情報もつぶさに報告を受けている様子が描写されました。
あながちフィクションとは言えません。定信が大衆の動向を重視し、情報収集に力を注いでいたことは事実だからです。
「よしの冊子」という文書が残っています。定信の信頼の厚かった水野為長という家臣が、隠密らを使って情報を集め、それを定信に伝えるためにまとめたものです。
「よしの冊子」をまとめたもの[駒井乗邨] [編]『鶯宿雑記』巻四百五十二、巻四百五十三,写. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/10303794幕府内部から市井まで幅広く情報を集め、真偽不明のものもたくさんありますが、当時の状況をよく伝えている史料です。「武士の人事評価」(新人物文庫)によれば、意次が所領のうち2万石を没収され、江戸や大坂の屋敷も取り上げられた際には、「武家はもちろん町家の者まで大変によろこび、そうあるべき事だと誰もが喜んでいます。とりわけ憎んでいた者は、この二日に仰せつけられたのも遅いぐらいだと言ったということです」などと記録されています。意次の失脚は、市井の人々も歓迎していたということが裏付けられます。打ちこわしの恐怖、民衆を軽くみられない
民の動向をしっかり把握しなければならない、と定信が考えたのは、やはり「天明の打ちこわし」が念頭にあったからでしょう。意次が老中を辞してから、定信が老中に就任するまで1年余りの空白があり、田沼派と反田沼派の間で激しい権力闘争がありました。結局、最後に反田沼派が勝利したのは「打ちこわし」の失政によって、田沼派の幕臣が次々に失脚したことが決定的だった、という見方があります。結果的に定信の味方になってくれた庶民ですが、その矛先がいつ、自分の所に向かってきてもおかしくない状況です。一見、歓迎ムードに包まれて順風満帆にみえた定信の船出。しかし定信はこれからも幕府内だけでなく、市井の人々の風向きも踏まえながら、難しいかじ取りを迫られることになります。
表現者にも強い圧力がかかる時代に
こうした定信の厳しい監視は、社会に対する影響力の大きい文芸の世界にも当然、及んでくることになります。まして日本の古典や漢籍をはじめ、同時代の黄表紙などにも通じた「文芸オタク」と言ってよい定信です。文芸の力をよく知っているだけになおさらだったでしょう。当時のこの世界の第一人者といっていい、大田南畝(桐谷健太さん)も幕府の高官に呼ばれて詰められました。
「世の中に 蚊ほどうるさき ものはなし ぶんぶといふて 夜も寝られず」
定信を揶揄したこの時代の狂歌として名高いものです。
「下勢おのずから上を凌ぐ」 定信の危機感を刺激した狂歌
経済的に苦しく、札差ら金持ちの商人に頭を下げて金を借りることが日常になっていた当時の武士。さらに「打ちこわし」が実証したように、町人の力の増大は火を見るよりも明らかです。「下勢おのずから上を凌ぐ」と表現するほど、この事に対する定信の危機感は強かったのです。定信は借金を帳消しにする「棄捐令」を出す一方、町人たちに軽んじられないよう、武士に対しては武芸や儒学などの「文」を奨励し、試験や顕彰の制度を設けるなどしたのです。「世の中に 蚊ほどうるさき」の歌はこうした風潮を笑ったものですが、定信側がこの歌に敏感に反応したのも当然でしょう。
大田南畝の歌、といって紹介されることも多かった「世の中に」の狂歌ですが、ドラマで本人が否定していたように、誰の作品かは実際は分かりません。しかし現実に「たかが狂歌一首」で当局に呼びつけられ、処罰まで仄めかされたら、普通のクリエイターは震えあがってしまうでしょう。南畝も「筆を折る」と明言しました。
権力に「筆」の力で立ち向かう蔦重
こうした公儀の姿勢に、真っ向から立ち向かう方針を明確にしたのが蔦重でした。「倹約を心掛け、遊興に溺れず、分を務めろっていうのは、裏を返せば贅沢すんな、遊ぶな、死ぬまで働けってこと。そんな世、誰が面白えんです?面白いのはただ1人だけ、世をてめえの思う形にしたふんどし野郎(定信)だけじゃねえですか」と本質を穿つ名セリフでした。さすが無一文からのし上がった蔦重。胆が据わっています。
「だから俺はこの流れに書をもって抗いてえと思います」。蔦重の本気を目の当たりにしたクリエイターたちも、「やるしかない」と決意を固めます。
「持ち上げて、実はからかう」高度なテク
もちろん、ずばりとご政道を批判することはできません。蔦重が考えたアイデアは「一見、持ちあげているとみせて、実はからかう」という高度なものでした。田沼政治を批判し、現在の政治を褒めるかのごとく表現しながら、裏では舌を出すような作品を作っていくぞ、というものです。意次にあらかじめ「あなたを貶めてしまいますが」とお断りを入れたのもそういう狙いがあったからです。
そういう狙いを秘めた「危険な」作品が続々と耕書堂に並びます。果たしてどんな反響が待っているのでしょうか。
ドラマでも繰り返し制作シーンが出て来た狂歌絵本「画本虫撰」もついに完成しました。歌麿が絵を担当し、彼の代表作として評価されることになります。
美しい本の仕上がりに、ドラマのスタッフの素晴らしい仕事ぶりを見ることができました。師匠の鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)も満足そうでした。
巻頭に並べた酒井抱一と大田南畝
「画本虫撰」はドラマにあったとおり、鳥山石燕が文を寄せています。「歌麿が著す虫中の生を写すは是心画なり」などと絶賛しています。
そして本文は蜂と毛虫の絵から始まります。ドラマで紹介された大田南畝(四方赤良)の狂歌「毛をふいて 傷やもとめん さしつけて 君があたりには ひかかりなば」が紹介されています。「毛を吹いて瑕を求む」は韓非子から。人の欠点を強いて暴こうとすること。毛虫が夜這いを掛けようとして、うまくいかない、というような情景でしょうか。含みが多い歌です。
「画本虫ゑらみ」喜多川歌麿 筆 宿屋飯盛 撰 国立国会図書館デジタルコレクションそのひとつ前の冒頭の歌は「尻焼猿人」の作。こちらは美術ファンにはおなじみの酒井抱一の狂号です。「こはごはに とる蜂の巣の あなにえや うましをとめを みつのあぢ」とあります。ちなみに「あなにやし えをとめを」は古事記で、イザナギがイザナミに語りかけたプロポーズの言葉(なんと素晴らしい女性だろう)です。「あなにえや うましをとめを」はそれに引っかけたのでしょうか。なかなか露骨な色恋の歌ですが、古典の教養も見せているのかもしれません。酒井抱一はよく知られているとおり、姫路藩主の酒井家の生まれという高貴な血筋でした。冒頭に抱一と南畝の歌を並べた蔦重の意図も、時代状況を合わせて考えると興味深いものがあります。
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから