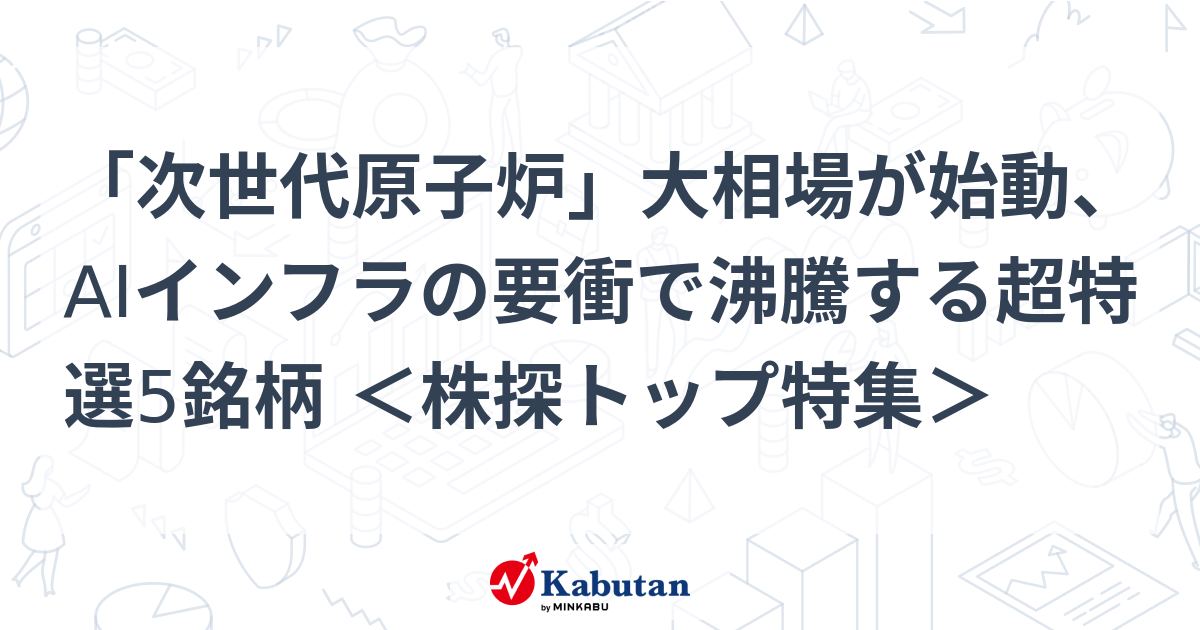【為替】株高・円安「アベノミクス相場」振り返り

2012年12月に第2次安倍政権が発足すると、大胆な金融緩和、機動的な財政政策、成長戦略の「3本の矢」を柱とする経済政策に取り組むとして、それを「アベノミクス」と呼んだ。これに対して過敏に反応したのは為替相場だった。それまで1米ドル=80円近辺で戦後の円最高値に近いところで推移していた米ドル/円は、一気に90円を超える米ドル高・円安に向かうところとなった(図表1参照)。
円安に沿う形で株高も急拡大した。それまで9000円前後で低迷していた日経平均株価は、米ドル高・円安に連動して一気に1万円を大きく超える上昇に向かった(図表2参照)。以上のように見ると、「アベノミクス相場」において、最初に主役を演じたのは明らかに円安だっただろう。ではなぜ、急激に円安が進むところとなったのか。
「アベノミクス」が始まる前、為替相場は1米ドル=75円という戦後の円最高値に近い水準で推移していた。それを5年MA(移動平均線)かい離率で見ると、マイナス20%前後であり、米ドル安・円高の「行き過ぎ」懸念が強いことを示していた(図表3参照)。以上のように見ると、「アベノミクス」は、「行き過ぎた円高」是正のきっかけになったことから大幅な円安をもたらし、それが大幅な株高にもつながったということが基本的な構図だったのではないか。
第2幕の主役は「異次元緩和」=円安・株高が再加速
次に円安・株高「アベノミクス相場」第2幕の主役を演じたのは「3本の矢」のうちの1本だった「大胆な金融緩和」だろう。新しく日銀総裁に就任した黒田東彦氏は、2013年4月、最初に出席した金融政策決定会合で、それまでの次元を超えたという意味の異次元緩和策を決定した。この「サプライズ緩和」をきっかけに、円安・株高は再加速するところとなった。
その後、2013年後半から2014年にかけて、米ドル/円は100円前後、日経平均株価も1万5千円前後で比較的落ち着いた小動きがかなり長く続いた。「アベノミクス相場」と言えば、大幅な円安、株高という印象が強そうだが、その意味では「アベノミクス相場の中休み」と言えそうな状況もあったのだ。
その「中休み」に終止符を打ち、円安・株高の再加速、「アベノミクス相場」最終幕の主役を演じたのは、またしても日銀の金融緩和だった。しかもそれは、「禁断の緩和」と呼べるものだったのかもしれない。
最終幕の主役は「禁断の緩和」=実質的にはルール違反の「近隣窮乏化策」
2014年10月末、日銀はいわゆる異次元緩和第2弾を決定した。これを受けて米ドル/円は110円、さらには120円も超えて米ドル高・円安が急拡大に向かった。そしてそれに連れるように、日経平均もいよいよ2万円の大台を回復するところとなった。このように異次元緩和第2弾に対し、円安、株高が大きく反応したのは、それが常識的にはありえないとの意味で「禁断の緩和」だった影響が大きかったのではないか。
異次元緩和決定の直前、米ドル/円の5年MAかい離率はプラス20%を大きく上回るまで拡大していた。それはむしろ、経験的には円安阻止介入を行う可能性のある「行き過ぎた円安」を示していた。そうした中でさらなる円安をもたらす可能性の高い異次元緩和第2弾が決定された。客観的には自国通貨安誘導として国際ルール違反に位置づけられた「近隣窮乏化策」の批判を受ける可能性のある金融政策、その意味では「禁断の金融緩和」だったわけだ。
この政策決定を主導した黒田日銀総裁に「禁断の金融緩和」の自覚があった可能性を感じさせるのは、それから半年余り過ぎたところで黒田総裁が自らの発言で円安幕引きに動いたことだった。国際ルール違反の強い批判が表面化する前に、「禁断の緩和」がもたらした円安の歯止めに動いたということが真相だったのではないか。そしてそれは同時に円安、株高「アベノミクス相場」の幕引きにもなった。
まとめ=高市版「アベノミクス相場」で円安・株高が続くかは不透明
米ドル/円の5年MAかい離率は、足下でプラス12%程度、ユーロ/円は同18%程度。2024年までに行われた円安阻止介入を再開するほどの「行き過ぎた円安」ではないものの、なおそれに近い状況が続いていることを考えると、貿易相手国の通貨安誘導に過敏なトランプ米政権が続く中で、再びの「禁断の緩和」は不可能だろう。
「アベノミクス」を継承すると主張する高市政権が登場すると、円安、株高が急拡大する「アベノミクス相場」の再現のようになった。ただこの先も円安、株高が続くかはまだ不透明ではないだろうか。