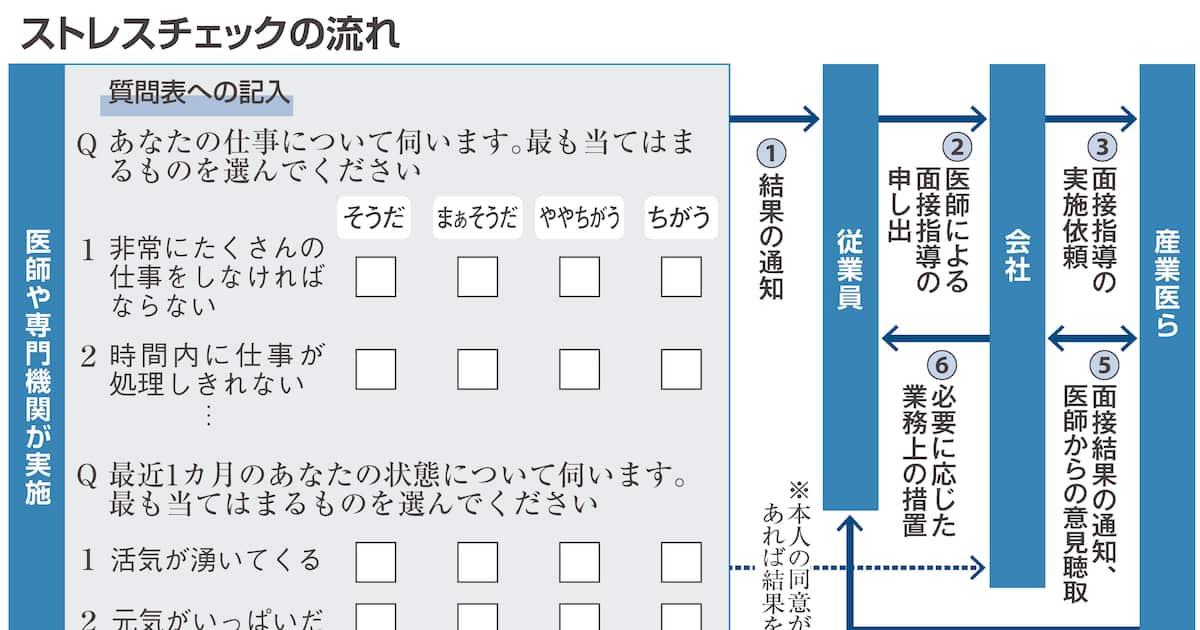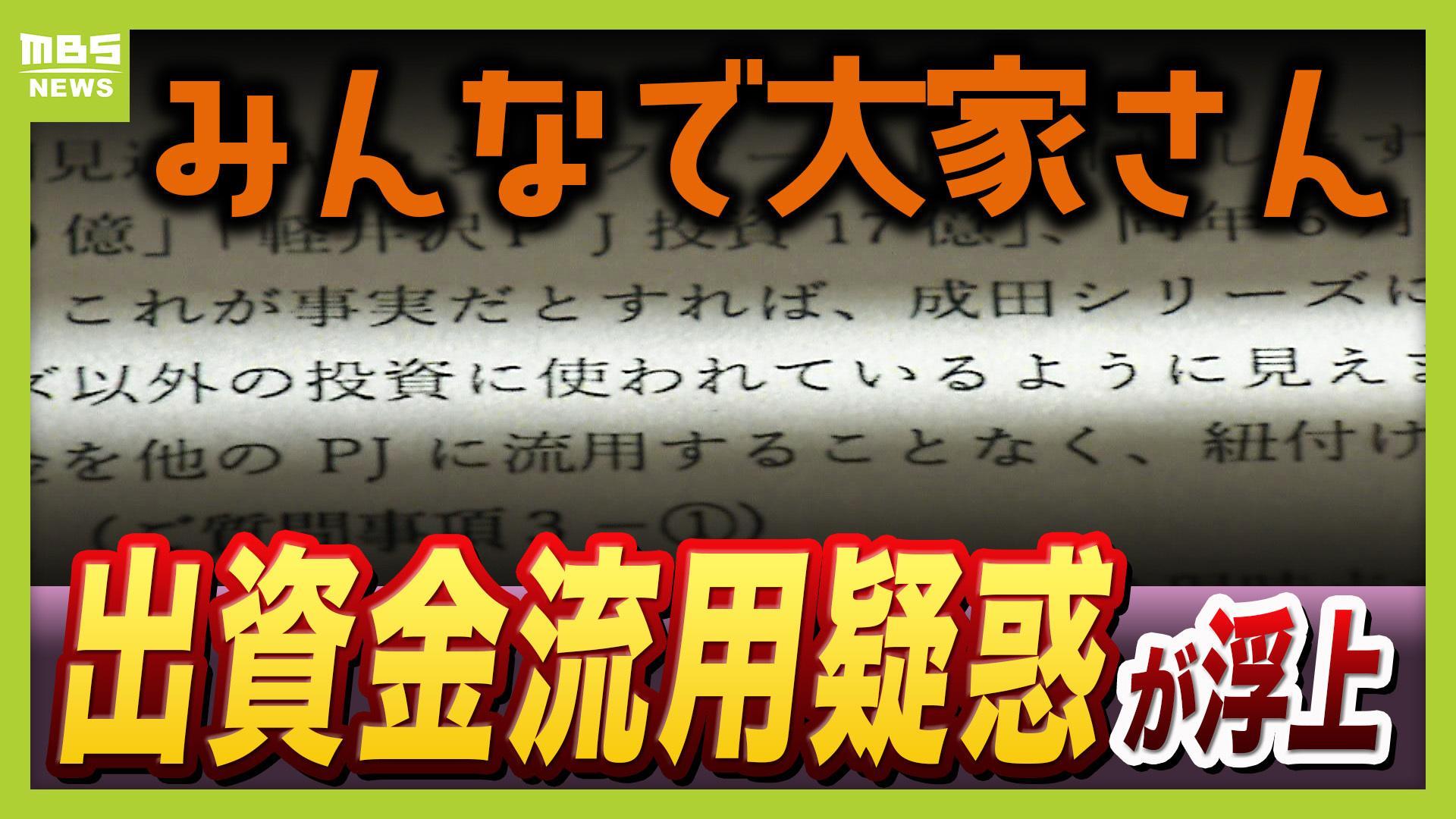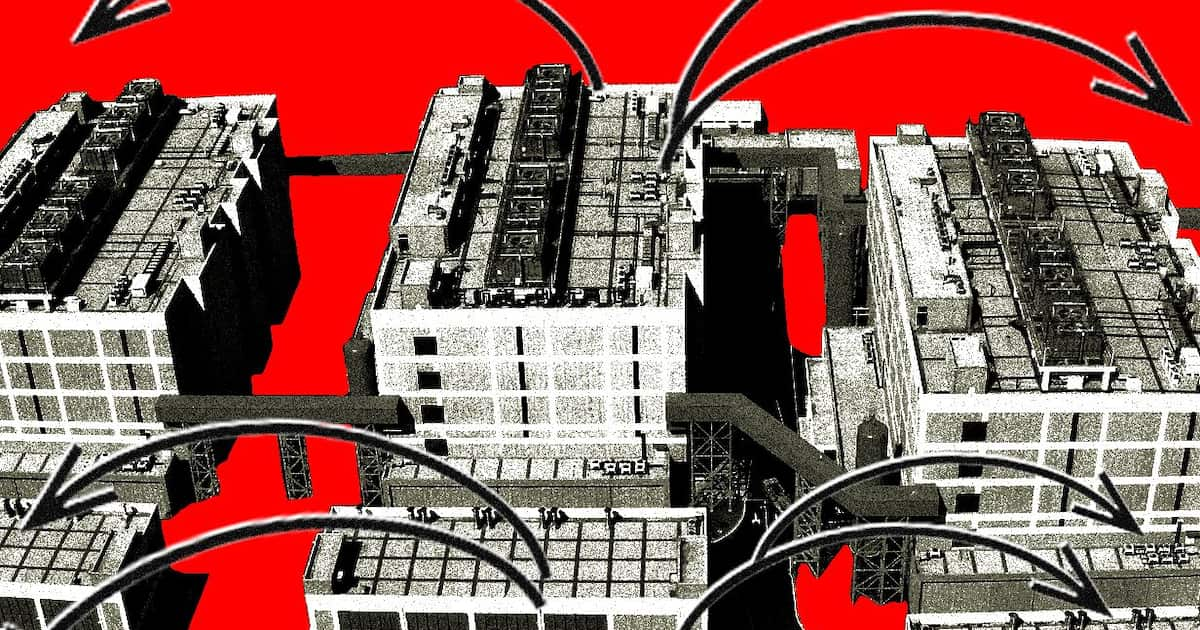AIの「タダ乗り」許さず--Wikipedia、AI企業に無断利用の停止と支払いを要求

「Wikipedia」を運営する非営利団体ウィキメディア財団は米国時間11月10日、AI企業に対し、AIモデルのトレーニングを目的としたデータ収集(スクレイピング)を停止し、同団体の有料APIを利用するよう求める声明を公開した。
同財団によると、AI企業はモデルの機能を維持するために、人間が精査した質の高い情報を必要としている。Wikipediaの幅広いボランティア編集者のネットワークが情報の信頼性を担保しており、そのコンテンツは300以上の言語で提供されている。
一方で、Wikipediaの運営には多額の費用がかかる。Semrushによれば、Wikipediaは現在、世界で7番目に訪問者数の多いウェブサイトだ。ウィキメディア財団の監査報告によると、2024年度の運営コストは1億7850万ドルに上った。財団は主に寄付によってWikipediaの運営を維持しており、広告は掲載していない。
しかし、AIは人々の調べものの習慣を変えつつある。人々はWikipediaで物事を調べる代わりに、AIに質問して回答を得るようになっている。Wikipediaの利用は無料だが、もし人々が「ChatGPT」などを使ってWikipediaを(間接的に利用しつつも)迂回するようになれば、Wikipediaのホームページ上部に表示される寄付の呼びかけを目にすることがなくなり、サイトは資金を得られなくなる可能性がある。
ウィキメディア財団はAI企業に対し、同団体の企業向けAPIを有料で利用するよう求めている。これにより、企業は「Wikipediaのサーバーに過度な負荷をかけることなく、大規模かつ持続的にWikipediaのコンテンツを利用できる」ようになり、同時に「われわれの非営利団体としての使命を支援する」ことも可能になるという。
Google、OpenAI、Meta、Perplexity、Anthropic、Microsoft、DeepSeek、xAIの各社にコメントを求めたが、すぐには回答を得られなかった。Wikimediaの担当者からも、すぐにはコメントを得られなかった。
Googleは2022年、Wikipediaのコンテンツに商業的にアクセスする契約をウィキメディア財団と結んでいる。
現在、オンラインのコンテンツ制作者らは、AI企業が許可も支払いもなくデータを利用している状況に反発している。Penske、The New York Times、News Corpといったオンラインパブリッシャーは、著作権侵害でAI企業を提訴している。一方、Associated PressやReutersなどの企業は、AI企業とライセンス契約を結んでいる。
AIブームの中、大手ハイテク企業の株価は急騰している。NVIDIAは10月末、一時的に世界初の時価総額5兆ドル企業となり、MicrosoftおよびGoogleの親会社Alphabetは2025年に入って4兆ドルの壁を突破した。
ウィキメディア財団の声明この記事は海外Ziff Davis発の記事を4Xが日本向けに編集したものです。
Amazonのアソシエイトとして、CNET Japanは適格販売により収入を得ています。