「メタボリックシンドロームの診断基準となる腹囲」は何cmか? 医師が解説!
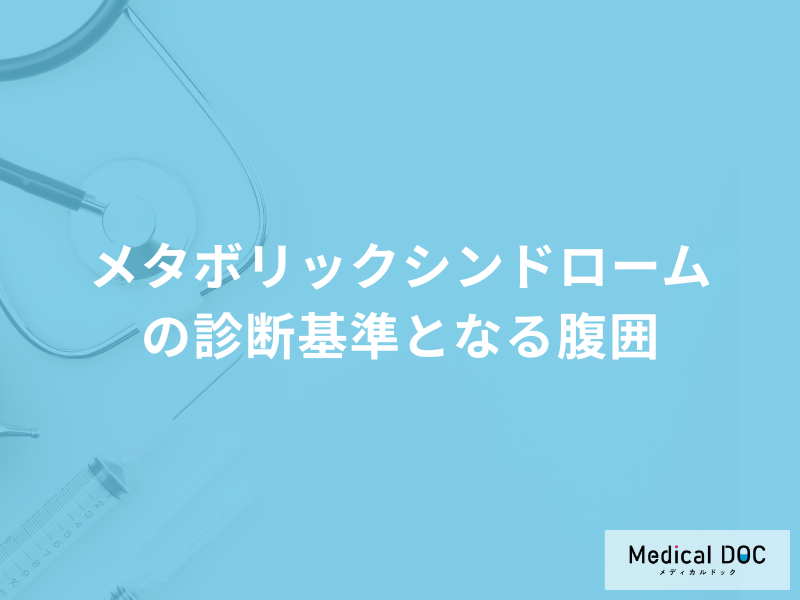
メタボリックシンドロームと診断される腹囲は何cmから?メディカルドック監修医がメタボの対処法や注意したい病気・何科へ受診すべきかなどを解説します。
監修医師:木村 香菜(医師)
プロフィールをもっと見る
名古屋大学医学部卒業。初期臨床研修修了後、大学病院や、がんセンターなどで放射線科一般・治療分野で勤務。その後、行政機関で、感染症対策等主査としても勤務。その際には、新型コロナウイルス感染症にも対応。現在は、主に健診クリニックで、人間ドックや健康診断の診察や説明、生活習慣指導を担当している。また放射線治療医として、がん治療にも携わっている。放射線治療専門医、日本医師会認定産業医。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加え、血圧や血糖値、脂質などの異常が加わったものであり、さまざまな病気の原因となります。健康診断を受けることで、メタボリックシンドロームかどうかがわかります。 この記事では、メタボの診断基準や腹囲の測り方などについて解説します。
健康診断でのメタボ検査
健康診断では、血圧・血糖・脂質といった生活習慣病のリスクを確認する項目とあわせて、腹囲(ウエスト周囲径)を測定します。これらのうち、腹囲が一定値を超え、さらに2つ以上の項目が基準から外れた場合にメタボと診断されます。 腹囲は内臓脂肪の蓄積を示す重要な指標であり、外見だけでなく体の内部で進行する代謝異常の早期発見につながります。
健診での腹囲の測定方法とは?
健康診断で腹囲を測るときには、立った状態で、軽く息を吐いた状態で、おへその高さで測定します。 一般的な腰のくびれ(ウエスト)とは異なる点には注意が必要です。
お腹に脂肪が多くついていて、おへその位置が下がってしまっている場合は、正確に測るために「肋骨(あばら骨)の一番下の位置」と「腰の骨(上前腸骨棘:骨盤の出っ張った部分)」のちょうど真ん中の高さで腹囲を測ります。
メタボリックシンドロームと腹囲の関係性
腹囲は、内臓脂肪の量の目安となります。つまり、腹囲を計測することによって、メタボリックシンドロームの主因となる内臓脂肪の蓄積量を推定しうるのです。
メタボリックシンドロームの診断基準となる腹囲
メタボリックシンドロームは、腹囲測定によって内臓脂肪が蓄積されているとみなされることが診断基準の根幹となります。以下で示す腹囲は、男女ともに腹部CT検査では内臓脂肪面積が100cm2以上に相当する値です。
メタボリックシンドロームに該当する女性の腹囲
女性では、へそまわり90cm以上が診断基準に当てはまります。
メタボリックシンドロームに該当する男性の腹囲
男性では、へそまわり85cm以上が診断基準に当てはまります。
何故男女でメタボの診断基準となる腹囲に差があるのか
栄養過多などによる健康リスクが増加するとされる腹腔内脂肪の量は内臓脂肪の面積で表されます。この内臓脂肪面積は男女ともに100cm2とされています。その内臓脂肪蓄積に対応する腹囲が、おへその高さの腹部CTスキャンによって判定され、結果として男性では85cm、女性では90cmとなりました。このため、メタボの診断基準には男女差が生じているのです。 一般的に、女性は男性よりも皮下脂肪が多い傾向があります。そのため、内臓脂肪面積が同じだったとしても、女性の方が男性よりも腹囲が大きくなります。
腹囲以外のメタボリックシンドロームの診断基準
メタボは腹囲だけで決まるものではありません。腹囲の基準を満たしたうえで、以下の3項目のうち2つ以上が基準値を超えている場合に診断されます。
血圧
男女ともに、以下の基準値となります。
・収縮期(高い方の血圧、心臓が血液を全身に送る際の血圧)130mmHg以上 ・拡張期(低い方の血圧、血液が心臓に返ってくる際の血圧)85mmHg以上
これらのいずれか、または両方を満たす場合、高血圧の疑いがあります。
血糖
男女ともに、空腹時血糖110mg/dL以上が診断基準です。 糖尿病と診断されるのは、空腹時血糖126mg/dL以上の場合です。しかし、メタボリックシンドロームの場合は境界型に該当する、糖尿病一歩手前の状態が診断基準になっています、
脂質
男女ともに、以下が基準となります。
・中性脂肪150mg/dL以上 ・HDL(善玉)コレステロール40mg/dL未満
メタボリックシンドロームでは、中性脂肪の増加とHDLコレステロールの減少が問題となります。
メタボリックシンドロームの診断基準に身長・BMIは関係ある?
BMI(体格指数)は肥満度を示す指標ですが、メタボの診断基準には直接関係しません。BMIが正常でも内臓脂肪が多い「隠れメタボ」も存在するため、身長や体重だけで判断するのは危険です。 腹囲の測定は、体格差を超えて内臓脂肪リスクを見逃さないためのスクリーニング手法といえます。
40歳から74歳まで受けられる特定検診とは?
特定健診とは、40〜74歳の方を対象に行われる、生活習慣病を早期に見つけて予防するための健康診査です。お腹まわり(腹囲)や血圧、血糖、脂質などを調べ、メタボリックシンドロームのリスクを確認します。
特定検診とは?
「特定健康診査(特定健診)」は、メタボの予防・早期発見を目的に実施される健診制度です。対象は40〜74歳の医療保険加入者で、血圧・血糖・脂質・腹囲を中心にチェックします。 一般の健康診断よりも生活習慣病予防に特化している点が特徴です。
特定検診でメタボと診断された場合は?
メタボまたはその予備群と判断された場合、「特定保健指導」が行われます。栄養士や保健師が中心となり、食事・運動・生活習慣の改善計画をサポートします。放置せず、早期に生活習慣を見直すことが将来の合併症予防につながります。
「メタボリックシンドローム」で気をつけたい病気・疾患
ここではメディカルドック監修医が、「メタボリックシンドローム」に関する症状が特徴の病気を紹介します。 どのような症状なのか、他に身体部位に症状が現れる場合があるのか、など病気について気になる事項を解説します。
心筋梗塞
心筋梗塞は、心臓の血管が動脈硬化などで詰まり、心筋に酸素が届かなくなる病気です。メタボによる高血圧や脂質異常は主要な原因の一つで、突然の胸の痛みが特徴です。放置すると命に関わるため、症状があればすぐに循環器内科を受診しましょう。
脳卒中
脳卒中は、脳の血管が詰まる、または破れて出血することで起こります。メタボによる高血圧や動脈硬化が発症リスクを高める代表的な疾患です。手足の麻痺や言葉の障害が突然現れたら、すぐに救急車を呼び、脳神経内科または救急科などを受診しましょう。
糖尿病
糖尿病は、インスリンの働きが低下し血糖値が高くなる病気です。メタボと強く関連し、内臓脂肪の蓄積が発症リスクを高めます。初期は自覚症状が乏しいため、健康診断で早期に発見し、糖尿病内科で治療を始めることが大切です。
肥満症
肥満症は、脂肪が過剰に蓄積し、高血圧・糖尿病・脂質異常などを伴う状態です。メタボリックシンドロームとは完全に一致するわけではありませんが、中心的要因になります。放置は重大な合併症につながります。治療は生活習慣の改善が基本です。必要に応じて肥満外来などを受診しましょう。
脂質代謝異常
脂質代謝異常(脂質異常症)は、血液中のLDLコレステロールや中性脂肪が多く、HDLが少ない状態です。メタボに伴って動脈硬化を進行させる重要な因子であり、心筋梗塞や脳卒中の原因にもなります。治療は内科での管理が基本です。
「メタボリックシンドローム」の正しい対処法・腹囲の改善法は?
メタボリックシンドローム改善の場合、6ヶ月で体重の3〜5%を減量することで効果が期待できるとされています。また、一旦体重を減量した後は、その維持が大切です。
運動で内臓脂肪を燃焼
週3〜5回、1回30分以上の有酸素運動(ウォーキング・サイクリングなど)がおすすめです。無理のない範囲で継続することが大切です。
栄養バランスの取れた食事
糖質や脂質の摂りすぎに注意し、野菜、海藻、きのこ類を多く摂るように心がけましょう。 アルコールや間食を控えることも大切です。ただし、急激なダイエットは避けましょう。
運動習慣や食事療法を継続するコツは
「頑張りすぎない」ことが継続の秘訣です。完璧を目指さず、日常生活で少しずつ改善を積み重ねることが結果的にリバウンド防止につながります。
ここまで症状の特徴や対処法などを紹介しました。ここでは「メタボリックシンドロームの腹囲」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。
木村 香菜 医師
男性で85cm以上、女性で90cm以上は腹囲の基準に該当します。ただし、血圧・血糖・脂質のうち2項目以上が異常でなければメタボとは診断されません。
木村 香菜 医師
腹囲だけでは対象外になる場合もありますが、血圧や血糖が高めの場合は「予備群」として保健指導を受けられることがあります。
木村 香菜 医師
身長が高くても低くても、内臓脂肪の蓄積があるかどうかが問題です。そのため腹囲で評価する方が合理的なのです。
まとめ 男性は腹囲85cm・女性は腹囲90cmからメタボリックシンドローム
メタボの診断は腹囲だけではなく、血圧・血糖・脂質の総合評価で行われます。腹囲の増加は生活習慣病のサインであり、放置すれば心筋梗塞や脳卒中など重大な疾患に発展するリスクがあります。しかし、生活習慣の改善で十分に予防・改善が可能です。定期的な健康診断を活用し、早めの対策を心がけましょう。
「メタボリックシンドローム」で考えられる病気
「メタボリックシンドローム」から医師が考えられる病気は5個ほどあります。 各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。
循環器系の病気
脳神経内科系の病気
内分泌内科系の病気
消化器内科系の病気
腎臓内科系の病気
メタボリックシンドロームになると、様々な病気が発症するリスクが高まります。
「メタボリックシンドローム」に似ている症状・関連する症状
「メタボリックシンドローム」と関連している、似ている症状は9個ほどあります。 各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。
関連する病気
- お腹周りのサイズがアップする
- 喉が渇く
- 尿の量が増える
- 疲れやすい
- 視界がぼやける
- 胸が痛い
- ろれつが回らない
- 激しい頭痛
- 手足の麻痺
メタボリックシンドロームでも、無症状の場合も多くみられます。しかし高血糖の人は糖尿病の症状に気付くこともあります。また、脳卒中や心筋梗塞などが引き起こされることで、これらのような症状が現れる可能性があります。



