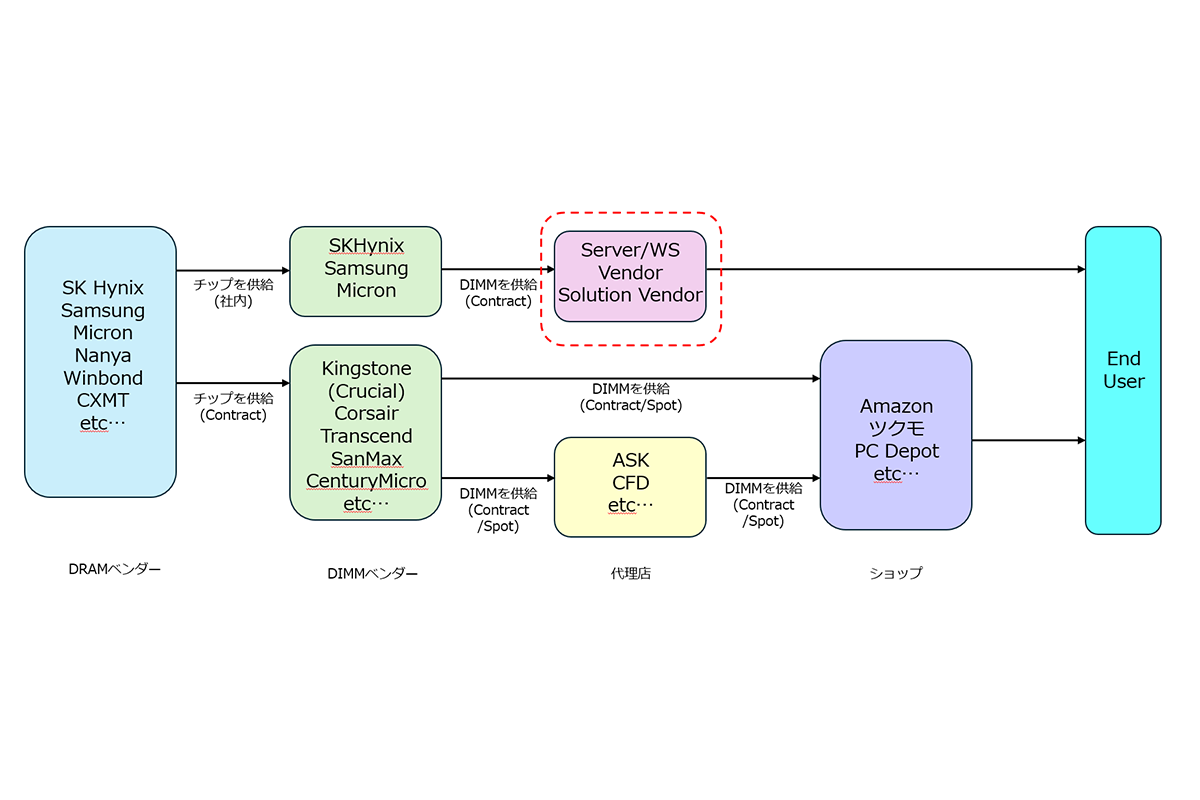コラム:調整色を強めるドル/円相場、彼岸底の展開を予想=植野大作氏

[東京 13日] - 早春の外国為替市場でドル/円相場の調整色が鮮明になっている。2月7日には一時150円93銭と、24年12月10日以来、およそ2カ月ぶりの安値圏まで下落する場面があった。1月10日に記録した年初来高値の158円87銭から、わずか4週間でマイナス7円94銭、騰落率換算ではマイナス5.0%もの調整だ。一体何が起きているのだろうか。
ドル安・円高進行の背景は明快だ。近年の為替市場で注目を集めるようになった翌日物金利スワップ(OIS)市場が織り込む日米の政策金利予想をみると、米連邦準備理事会(FRB)による年内の利下げ想定回数(0.25%刻み)は1回─1.5回前後で年明けからあまり動いていないのに対し、年初の時点で1回程度だった日銀による利上げ想定回数は、1月会合で利上げが実施されても0回にはならず、年末までにさらに1.3回程度の追加利上げが見込まれている。
主要国の中央銀行が軒並み利下げ局面にある中で、日銀だけが「孤高の利上げ」を続けていることを主因に、年明け以降の日本円は米ドルを含めた主要9通貨に対して全面高となっている。年初からの約1カ月半に限ってみれば、円は「先進国最強通貨」の座に君臨しているのが印象的だ。昨年までの4年間の平均騰落率のパフォーマンスで先進国最弱の地位に甘んじていた円の豹変ぶりは目覚ましい。
この先もしばらくの間、ドル/円相場は調整含みの展開が続きそうだ。為替需給の面からみても、毎年2月の節分過ぎから3月の彼岸前後にかけては、2月中旬に集中する米国債の利息を受け取る日本の金融機関等による円転予約が活発化するほか、日本の会計年度末を前にした日系企業による海外利益の一部円転観測が強まるため、他の条件が一定であれば、一時的には日本の第一次所得収支の円転比率が高まって、季節的にはドル安・円高が進みやすい時期を迎える。
テクニカル的にみると、足元のドル/円相場は昨年9月安値の139円台から今年1月高値の158円台までの上昇幅の38.2%押しとなる151円台を断続的に割り込む場面が散見されている。先述のような季節性を帯びたドル売り・円買い圧力に押されて心理的節目の150円台を突破した場合、上記の上昇幅の「半値押し水準=149円台」や、「61.8%押し水準=147円前後」が、次の下値めどとして意識されることになるかもしれない。日本の会計年度末を目前にした円高・株安リスクに注意が必要だ。
ただし、筆者はこのままドル/円相場の下値が柔らかくなり続けて、大きな流れとしてドル安・円高局面に向かうとは思っていない。恐らく春の彼岸を過ぎる頃にはドル/円相場は底入れする可能性が高い。以下、そのように考えている理由を2つ挙げておきたい。
第一に、昨今の円全面高の背景になっている日銀の利上げ継続シナリオは、既にかなりの水準まで市場で織り込まれている。多くの市場関係者が日銀による数年先の利上げ打ち止め水準のめどとみなしている円の2年先1年物のOISレートは現在1.08%台まで上昇している。1月に0.5%まで引き上げられた日本の政策金利が2年後までにあと2回以上利上げされる可能性を意識した上で、ドル/円相場は150円台まで下落していると推測される。
このため、他の条件が一定ならば、市場が織り込む日銀の追加利上げの想定回数が3回以上に増えない限り、ドル/円相場が心理的節目の150円を大幅に割り込む展開は想定しにくい。仮に、市場が織り込む日銀の利上げ打ち止め時の金利水準が追加3回分に相当する1.25%界隈まで上昇したとしても、日本の政策金利は現在の消費者物価上昇率である3%台や長期の物価目標2%に遠く及ばぬ実質期待値マイナス圏に水没した状況が続くため、持続的な円高圧力は発生し難い状況が続くのではないか。
中央銀行が政策金利を引き上げても、一度限りの通貨高騒動を引き起こすだけで持続的な通貨高圧力が発生しないことは、昨年50%まで政策金利を引き上げてもリラの対ドル相場の下落を食い止めることができなかったトルコ中銀の先例が示している。
これまで本コラムで繰り返し主張してきたことだが、日銀が日本円の短期金利のベンチマークとなる政策金利を最低でも物価目標2%を超える実質期待値プラスの領域に引き上げない限り、日本の金融政策のイニシアチブで円安にブレーキをかけるのは難しい局面が続くだろう。米国経済の軟着陸観測が強まる中、FRBによる政策金利の引き下げが物価目標2%より高い3%台で打ち止めになりそうな現下の局面ではなおさらだ。
第二に、日本の国際収支統計を基に、為替ヘッジ比率が低い基礎収支の需給バランスを俯瞰(ふかん)すると、最大の黒字を稼いでいる第一次所得収支は足元で40兆円近くまで膨張しているものの、日本国内での投資リターンの期待値が海外に比べて低いため、近年では円転比率が低迷、持続的な円高圧力の発生源になっていないと推測される。旅行収支の黒字は昨年過去最大の5.9兆円を記録したが、大半はアジア向けであり、対米収支の黒字は小さいため、ドル/円相場のトレンドに響くような円高圧力を発生させていないとみられる。
一方、2024年の通関貿易統計で日本の貿易収支の要因分解を行うと、ドル決済の赤字額が円決済の黒字を10兆円も上回っているほか、大半がドル買い圧力を生むと推定される輸送収支とデジタル収支等の赤字も昨年は8兆円以上に膨らんだ。昨年1月の新型NISA(少額投資非課税制度)導入を起爆剤にして、投資信託経由の海外への資金流出は年率11兆円ペースに加速しているほか、歴史的な円安局面の最中にあっても円買いを伴う対内直接投資は過去1年間の実績でゼロ兆円界隈に低迷する一方、円売りを伴う日本からの対外直接投資は過去1年間で17兆円規模に膨らんでいる。
上記諸々の円売り項目に、昨年の第二次所得収支の赤字額の約4兆円を合わせると、構造的な円売り圧力は、年率50兆円近くに達していると推測される。そのうち7─8割はドル買い圧力になっている可能性が高く、日本政府が昨年春と夏に実施した過去最大、15.2兆円のドル売り介入の効果を短命に終わらせるのに十分な規模だったと思われる。
我々が経済活動を営む際に必要不可欠な化石燃料・金属・食料原材料などを海外からの輸入に依存し、スマホやパソコンを稼働させるのに必要なデジタルインフラの基盤を米系企業に握られている近年の日本において、ドルは「生活必需通貨」の趣を呈している。第一次所得収支黒字の円転比率を劇的に上昇させるような円建て資産の期待リターンの上昇が起きない限り、当面の為替需給バランスはドル高・円安に傾いた状態が続くのではないか。
第一次所得収支の円転比率が季節的に上昇しやすい日本の節分過ぎから彼岸前後までの時期を通過して、新しい会計年度を迎える4月以降にはドル/円相場の失地回復劇が始まるだろう。今年の大みそかのドル/円相場は、年始の初値157円台より高い159円台で着地すると予想している。25年のドル/円相場は変動相場制史上で最も長い5年連続の年足陽線という新たな記録を樹立する歴史的な年になるとの見方を維持しておきたい。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*植野大作氏は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券のチーフ為替ストラテジスト。1988年、野村総合研究所入社。2000年に国際金融研究室長を経て、04年に野村証券に転籍。国際金融調査課長として為替調査を統括、09年に投資調査部長。同年7月に外為どっとコム総合研究所の創業に参画、12月より主席研究員兼代表取締役社長。12年4月に三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社、13年4月より現職。05年以降、日本経済新聞社主催のアナリスト・ランキングで5年連続為替部門1位を獲得。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab