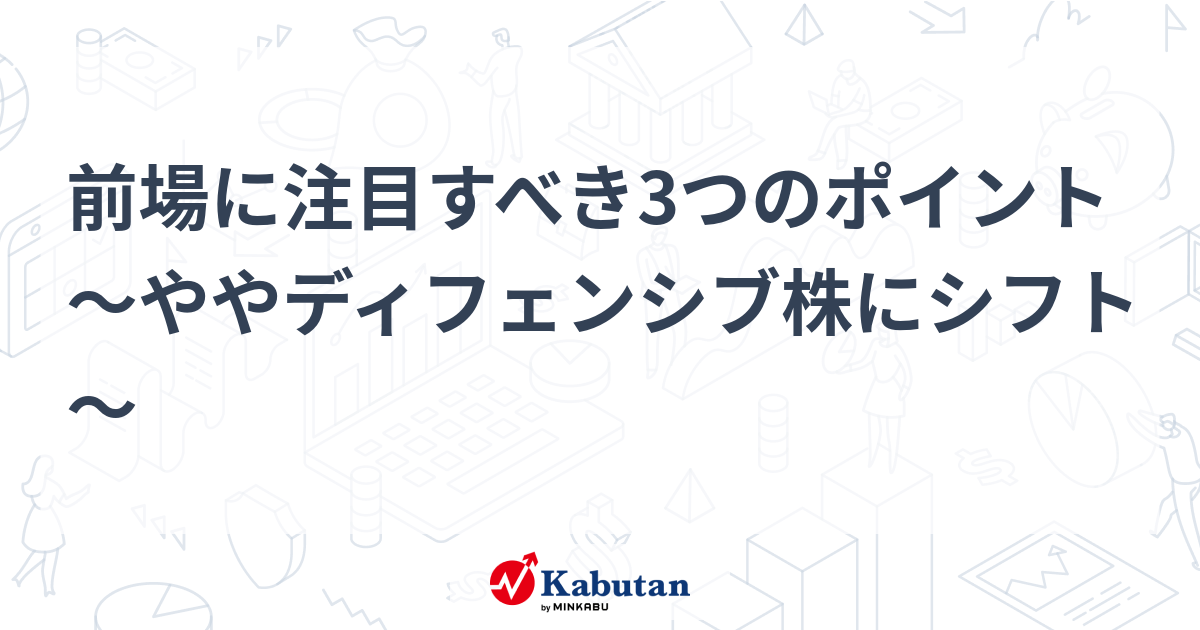イオン買収額に「安すぎる」の大合唱、ツルハHD株主総会で賛否焦点に

イオンによる買収の賛否を事実上問うツルハホールディングスの定時株主総会が26日に開かれる。両社はすでに取引に合意しているが、第2位株主の英系運用会社オービス・インベストメンツや議決権行使助言会社が買収額が安いとして相次いで反対を表明。株主の判断に注目が集まる。
オービスは、ツルハHDとイオン傘下のウエルシアHDの経営統合と、その後のイオンによるツルハHDの子会社化に反対する。ウエルシアHDに比べツルハHDの方が利益率が高く、強固な財務基盤もあるとして、株式交換比率は同社の企業価値を過小評価していると主張。イオンによる株式公開買い付け(TOB)価格の1万1400円についても、支配権プレミアムが支払われておらず、2024年にイオンがオアシス・マネジメントからツルハ株を取得した際の1万5500円に比べて安いと不満を訴える。
米インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ(ISS)と米グラスルイスも統合議案への反対を推奨する。グラスルイスは株式交換を含め取引条件を拒否したほうが株主の利益になるとリポートで言及。また株主であるノルウェー中央銀行投資管理部門も統合議案に反対する意向を示している。公表資料によると、2月時点で筆頭株主のイオンの持株比率は約19.5%、ツルハHD創業家の持ち分が10%未満と、特別議案の可決に必要な3分の2以上の賛同を得るハードルは低くない。
買収条件を巡る企業と株主の綱引きは今後増えていく可能性もある。日本の株主総会は、大きな反対もなく決議される「シャンシャン総会」と皮肉られてきた。だが足元では株式の持ち合い解消が進み、東京証券取引所が株主目線を意識した経営を後押ししたことで、物言う株主(アクティビスト)による株主提案も増えている。ツルハHDの議案が否決された場合には、こうした変化を象徴する事例になり得る。
買収条件に物言いがつくケースは過去にもあった。07年には東京鋼鉄の株主総会で大阪製鉄との株主交換比率に対し、大株主のいちごアセットマネジメントが不満を示す個人株主を代弁して反対した結果、経営統合が破談となった。一方で伊藤忠商事によるファミリーマート買収のTOB価格を巡る裁判では、東京高等裁判所が適正水準より実際の買い付け価格が安かったとの判断を下した。
会社法に詳しい学習院大学の星明男教授は、イオンが筆頭株主として阻止した経営統合案を引き合いに出し、今回否決されれば、株主の不利を理由に過去にした批判が自らに跳ね返る「皮肉な結果」になると指摘。価格や統合比率など条件を公正かつ適切に定めることが、買収の成否においてなによりも重要であることを再認識させる事例になるだろうと述べた。
オービスのブレット・モーシャル日本株責任者は、株主総会で株主側が勝利する「可能性は高い」と自信を示す。ツルハHDに投資している多数の国内機関投資家と面談をした感触は「議論は非常に前向きなものだった」と、ブルームバーグの取材に答えた。
判断を留保
一方ツルハHDは3月から4月にかけて、複数回にわたりイオンにTOB価格の引き上げを求め、最終的に4月7日の終値に24.3%のプレミアムを上乗せした1万1400円で妥結した。また上場維持を前提とする取引で、株主がツルハHD株を保有し続ける選択肢もあることから、TOB価格の妥当性について判断を留保し応募の是非は株主の判断に委ねるとした。
ツルハHD株の22日終値は1万1475円とイオンが予定するTOB価格を上回った。前日にオービスが同社株を10.3%まで買い増したことが判明したことなどが材料となった。
イオンは14日に議決権行使助言会社のリポートに対する見解として、ツルハHD買収には重要な意義とシナジーがあり、株主や顧客などのステークホルダーにとって有益だとの見解を示した。ドミナント戦略や店舗開発ノウハウの共有で収益性が向上でき、海外展開の加速なども見込めるとしている。20日に、再び買収のメリットなどを説明する声明を公表した。
岩井コスモ証券の饗場大介シニアアナリストは、株式交換が否決されたとしてもイオン側は条件などを見直して買収にこぎつけるだろうと指摘する。「数カ月程度遅れる可能性」がある程度で、影響は限定的だろうと述べた。