【緊急特集】日米関税合意・石破首相退陣報道で日本株急伸、市場が見込む政局シナリオ
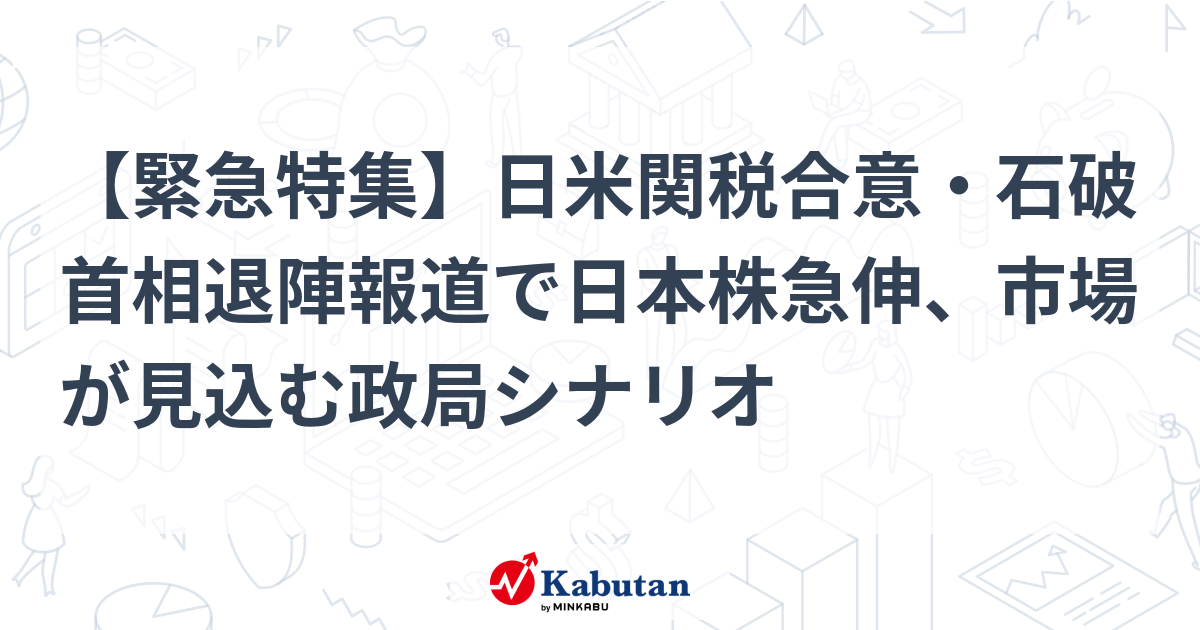
石破首相は続投の意向を示したものの、株式市場では求心力の維持は困難との見方が広がっている。
日米関税交渉の電撃的な合意とともに、石破茂首相の退陣の意向が報じられた23日、日経平均株価は前日比1396円高と急伸した。4万1000円台回復は昨年7月以来。過去最高値(4万2224円02銭)まであと1052円に迫った。関税交渉を巡る不確実性が解消した今、投資家の視線は自ずと国内政局に向かうこととなる。石破首相は記者団に対して続投への意欲を示しているものの、株式市場は次期首相と株式相場の展望について早くもブレインストーミングを始めている。
●フライング気味の高市トレード 「きょうの日本株の上昇の要因の3分の2は日米関税交渉の合意。3分の1は石破首相の退陣報道だ。首相退陣イコール積極財政化と市場は受け止めた」。三菱UFJアセットマネジメントの石金淳チーフファンドマネジャーはこう振り返る。報道通りに石破首相が退陣をした場合、次の自民党総裁が誰になるのかがポイントとなる。候補者が乱立した昨年9月の総裁選では石破氏と高市早苗・前経済安全保障担当相の決選投票となった経緯から、23日の株式市場においてはサイバーセキュリティー製品を手掛けるFFRIセキュリティ <3692> [東証G]や核融合に絡む技術を持つ助川電気工業 <7711> [東証S]が値を飛ばすなど、高市関連銘柄を早くも物色する姿勢がみられた。小泉進次郎氏の地元で百貨店を運営するさいか屋 <8254> [東証S]にも思惑的な資金が流入した。
実際の総裁候補について、現時点では予断を持って語れる段階ではないものの、参院選で大敗した自民党が国民民主党や参政党に流れた無党派の現役世代による支持を取りつけるには、従来の旧態依然とした自民党のイメージとは一線を画す「フレッシュさ」がトップに求められることとなる。その意味で両氏は一定の基準をクリアしているようにみえるが、高市氏が自民党をまとめあげるだけの側近に恵まれているかというと、そのようなイメージは乏しい。小泉氏は農水相として存在感を増したとはいえ、勝負時の発言の「軽さ」がキャリアの仇となってきた。高市氏と同様に党内をまとめる求心力を持てるかどうかも問われることになる。 三井住友DSアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは「高市氏が新総裁になった場合、野党との連携が上手く進む可能性はあるが、財政拡張策に対して円売り・債券売りが加速した場合に、日本株が耐えられるかは不透明だ」との見方を示す。 ●「コバホーク」待望論も 自民党の新総裁が次期首相に就任するには、野党の協力が不可欠となる。自民党内からは参院選の結果を受けて下野を進言する動きも表面化している。今後の党内での権力闘争次第では、自民党が分裂する可能性もゼロではないだろう。フレッシュな新体制を期待する株式市場で失望感を促す恐れがあるシナリオの一つとして、岸田文雄前首相の再登板も挙げられている。岸田氏は派閥の解散に動きながらも今やキングメーカーの一角を占めており、旧態依然の自民党のイメージを払拭するのは難しいとの見立てだ。 一方で「野党にまとまりがないのも事実であり、フレッシュさとともに安定的な政権運営が期待できる体制となれば、日本株にはプラスとなる」(アイザワ証券・投資顧問部の三井郁男ファンドマネージャー)との声がある。フレッシュさの観点で動向が注目されるのが、「コバホーク」の名で知られる小林鷹之元経済安保相だ。昨年9月の総裁選で知名度を上げ、9人の候補者のうち国会議員票は石破首相につぐ4位となった。閣僚経験は豊富とは言えないが、政策通として知られている。党内で支持基盤を構築し、安定的な政権運営を進められる人物として、株式市場ではにわかに待望論が広がりつつある。 石破首相の退陣とともに、参院選で躍進した国民民主党と自民党の距離感の変化も注視されることとなるだろう。国民民主党の玉木雄一郎代表が仮に次期首相の座を射止めることとなれば、同党が所得税減税や消費税減税を公約に掲げてきた経緯から、高市氏と同様に円売り・債券売りが促される可能性がある。世論に左右される人物としてそしりを受けてきたことを踏まえると、安定的な政権運営に対する確信をマーケット側が深められるかどうかが、株高の前提となりそうだ。 自民党にとって国民民主党の影響力は参院選を経て、経済政策の面でも一段と増大することとなった。三菱UFJアセットの石金氏は「今の自民党が国民民主党や参政党を上回るような積極財政策を打ち出せるようには見えない。自民党の経済政策に対し物足りなさが意識されるようになれば、日本株の上値を抑える要因になるかもしれない」と話す。 石破首相が続投の意向を示したとはいえ、国民からの信任の観点で求心力の維持は困難との見方が株式市場では優勢のようだ。次期首相の選択肢を巡る不透明感が台頭するなか、積極財政策に対する期待がどこまで維持できるかも、日本株の浮揚力に大きな影響をもたらす要因となるに違いない。 株探ニュース


