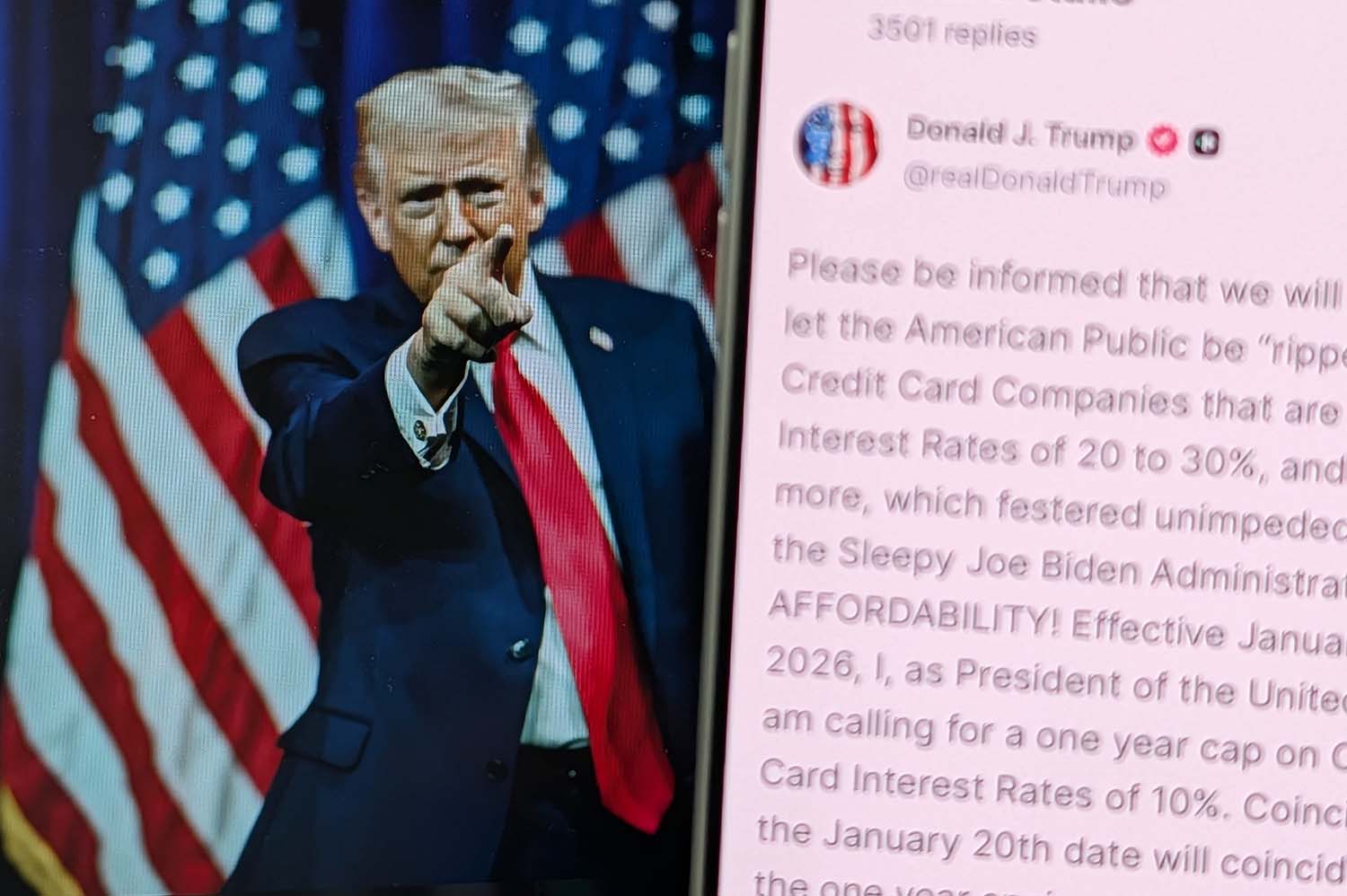芽生えた最新技術、日本の実力にできるか 勝負は閉幕後、実用化へ官民の取り組みカギ 万博未来考 総括編(2)

最新技術から「未来を予言」する万博。かつて日本は開催国としての遺産がありながら、世界市場での主導権を失った。万博を真に日本の力につなげるためには何が必要なのか。
1970年大阪万博の会場で排ガスも騒音もない静かな乗り物が注目を集めた。ダイハツ工業が他社に先駆けて開発した電気自動車(EV)の「パビリオンカー」だ。
6人乗りで最高時速15キロ。計275台が納入され、来場客らを運んで会場内を行き交った。遊園地気分を楽しめるため、子供たちにも人気の乗り物だったようだ。
採算取れず、市場で主導権失う
当時、ガソリン車の急速な普及により大気汚染が社会問題化。ダイハツが66年に完成させたEVの試作車は最高時速75キロ、航続距離80キロと破格の性能を誇った。
同社は76年に「電動車両部」を新設し、EVの開発・量産体制の確立を目指した。しかし、電池の価格が下がらなかったことで採算が取れず、やがて開発を縮小した。
「早すぎる技術だったのかもしれない」と同社担当者。立命館大経営学部の西岡正教授は「技術は優れていたが、市場をつくる構想がうまくいかなかった」と指摘する。
EVは2020年前後から「脱炭素」の車として欧米からブームが巻き起こり、中国も追随して市場が爆発的に拡大。出遅れた日本勢は苦戦を強いられている。
1970年大阪万博の会場で来場客らを乗せて走るダイハツ工業製の電気自動車「パビリオンカー」。排ガスや騒音がない車として注目を集めた(同社提供)1970年万博では電気通信館の「ワイヤレステレホン」も話題を呼んだ。2000年代にかけて「ガラケー」と呼ばれる日本独自の携帯電話につながったものの、やがて利便性を格段に向上させた米国発のスマートフォンが市場を席巻。ここでも日本が築いた技術的優位を生かせなかった。
森になる建築、ふれあう伝話…アイデアめじろ押し
一方、2025年大阪・関西万博でも斬新なアイデアはめじろ押しだ。
竹中工務店が開発したテント状の「森になる建築」。内部は天井が吹き抜けで、透明性のある壁からも柔らかい光が入る。素材は植物由来の酢酸セルロース樹脂で、徐々に分解して土に戻る。素材に木の苗を入れたり、種を含む和紙などを貼り付けることで「建物が森になる」仕組みだ。
木や土でつくられた日本古来の建築物は放っておけば朽ちて土に戻る。「森になる建築」の開発を手掛けた同社大阪本店の山﨑篤史チーフアーキテクトは、伝統工法をヒントに「日本独自の循環型経済」を提案したいという。
このほか、NTTが出展する未来の通信サービス「ふれあう伝話(でんわ)」は、音声や画像だけでなく、端末にかかる圧力などのデータを瞬時に送ることで、あたかも触れ合っているような感覚を伝えることができる。同社が開発を主導する次世代通信技術「IOWN(アイオン)」を活用。最新の光通信技術を基盤とし、消費電力を抑えながら超高速通信が可能だ。
ただ、西岡氏は「製品をつくるだけでは意味がない。市場をどう創出するかを国や業界団体で考える必要がある」と話す。万博で開花する日本人の発想力や技術力が実を結ぶために、官民一体で実用化に取り組む「万博後」こそ勝負になる。