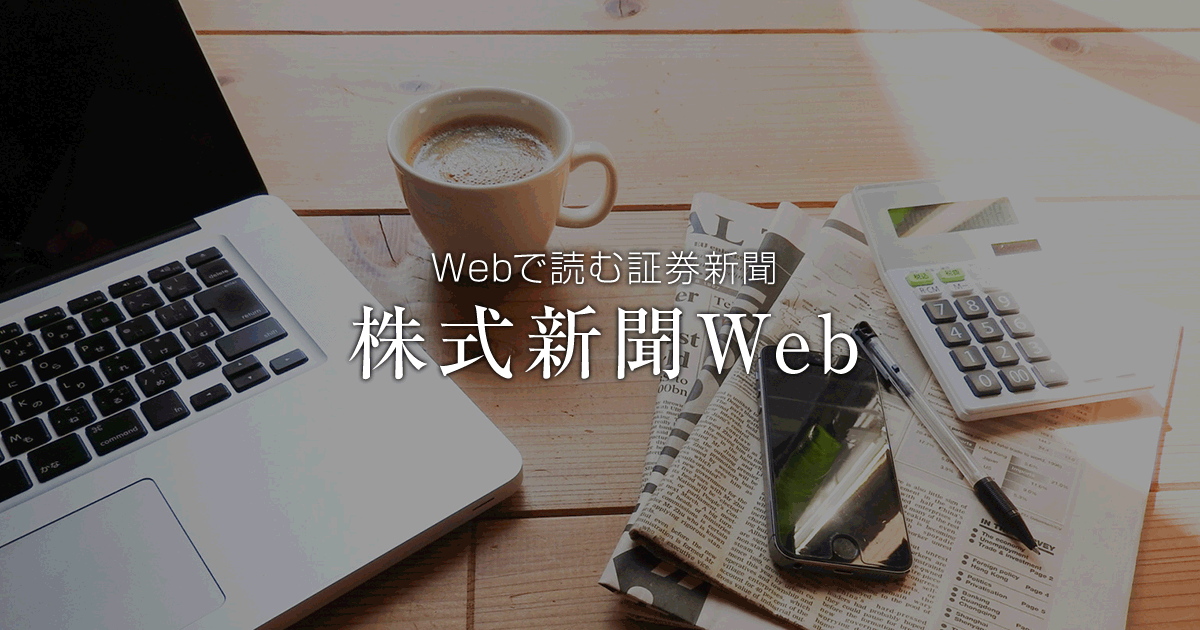コラム:ドル凋落シナリオに賭けるべきか、「国際金融体制の再編」論が促す円高・ドル安の考察=唐鎌大輔氏

[東京 17日] - 現在、金融市場では米金利上昇とドル下落の併発という稀有(けう)な事象が起きている。要するに「米国からの資金流出」である。これは円相場の対ドル、対ユーロの動向を年初来でチャートにするとよく分かる。円は対ドルで急騰している一方、対ユーロではおおむね横ばいだ。過去3年間で全面安を強いられてきた円が再評価されているというわけではなく、ドル安という敵失の中、円を含めたあらゆる通貨が押し上げられている状況なのである。
<日本の構造変化 vs. 国際金融体制の再編>
筆者はこれまで、円安の背景として「国際収支構造の変容に象徴される円の構造変化とそれに伴う弱さ」を繰り返し議論してきた。その構図は今も不変である。しかし、為替は常に「相手がある話」だ。今起きていることは、トランプ政権による戦後の国際経済秩序「ブレトンウッズ体制」の再編という壮大な野望とこれに呼応した米国離れ、それに伴うドル全面安である。既報の通りだが、ベッセント米財務長官は「ブレトンウッズ体制の再編に関与したい」と明言している。「日本の構造変化」は日本国民にとって大きな話だが、「国際金融体制の再編」を前にすれば大事の前の小事だ。しつこいようだが、円が見直されているわけではなく、ドルが自滅しているだけだ。この点は極めて重要である。
今後、このまま「国際金融体制の再編」やこれに伴うドル凋落(ちょうらく)、米金利急騰というシナリオに賭けるのであればドル安・円高は続かざるを得ない。1971年のニクソンショック、85年のプラザ合意などに肩を並べるほどの歴史的事件が起きようとしているのならば、為替に限らず、あらゆる資産価格のこれまでの予想は無効になる。
<ドル安相場の収束がメインシナリオ>
しかし、ドルの凋落はトランプ政権とて望んではいまい。相互関税の90日間停止の判断は、米国債利回りの急騰(米国債価格の急落)に促されたと解釈されている。米政権はドル安は欲するものの、それで米国債離れまで起きて欲しいとは思っていない。
安全保障面で米国に全面依存する日本は世界最大の米国債保有国として今後も安定的な投資家と見込めるだろうが、中国を含めたそのほかの投資家は日本のように従順ではない。トランプ大統領の面子を保ちながら関税政策は軌道修正が図られ、ドル安相場も収束に至るというのがメインシナリオだろう。そうなることを期待するしかない。
世界中が米国債を保有し、経済取引にドルが必要な状況があり、有事の際には米連邦準備理事会(FRB)との無制限スワップに依存せざるを得ないという状況こそドルの基軸通貨性を担保しているのである。端的には「困ったらドルが必要」という状況がドルを基軸通貨足らしめている。しかし、トランプ政権においては外国人の米国債保有に関し、課税や年限長期化を検討しているという説も取りざたされる。「困ったらドルが必要」どころか、「ドルを持つと困る」という状況であり、基軸通貨の地位を保ちたいのであれば狂気の沙汰である。保有にコストがかかり、用途が限られてしまうような通貨を基軸通貨として使うことはできない。トランプ氏もベッセント氏も基軸通貨性の放棄までは考えていまい。このような案が日の目を見ることは無いだろう。
<1985年の再現は不可能>
とはいえ、ミラン大統領経済諮問委員会(CEA)委員長が24年11月に発表した論文に沿ってマールアラーゴ合意、俗に第二次プラザ合意の可能性を懸念する向きは後を絶たない。確かに、同論文には「ドルの過剰評価」が米国衰退の一因として描かれており、その是正が求められている。
しかし、考えれば考えるほどその実現可能性は低い。85年と現在ではあらゆる条件が違い過ぎるからだ。1)為替市場の規模、2)国際協調体制の欠如、3)日本経済の弱体化の3点に絞って整理しよう。
まず、1番目の為替市場の規模だ。40年前とは為替市場の広さも深さも全く異なる。国際決済銀行(BIS)の調査によれば1日の平均取引高に関し、86年は6000億ドルであったのに対し、2022年は約7.5兆ドルと10倍以上に膨らんでいる。この取引量の拡大は市場参加者が多様化していることの結果でもある。卑近な例で言えば、1985年には個人投資家はこれほど大きな力を持ってはいなかったはずである。こうした拡がりは機関投資家についても言えることだ。市場参加者の多様化と市場自体の大規模化が進んだ結果、政府・中銀が行使できる影響力も明確に低下している。
次に2番目の国際協調体制の欠如だ。国際社会はもはや米国に「協調」などしないし、それゆえに「合意」もしない。冷戦中は「G5(日米独仏英) vs. ソ連」という分かりやすい対立があり、西側陣営の足並みは揃っていた。それは「資本主義 vs. 共産主義」という構図でもあった。プラザ合意はドル高是正により保護主義に傾斜しようとする米国議会のガス抜きを図り、自由貿易体制を守ろうという狙いがあった。しかし、現在は米国が進んで孤立し、保護主義の殻に閉じこもろうとしている。その上で相手国に「協調」してもらうために法外な関税や米国債の年限長期化などを使って脅迫を仕掛けているという構図がある。脅迫してくる相手に進んで協力する者はいない。対峙(たいじ)する外為市場が巨大化しているのに、それに対抗するための一致協力は得られないのだから、影響力はやはり限定されてしまう。
むしろ、4月に入ってからの状況を踏まえる限り、ドル安がオーバーシュートしてドル高に戻るための一致協力(さしずめ第二次ルーブル合意といったところか)が必要な日が来るかもしれない。しかし、その時、国際社会は米国に手を貸すだろうか。いたずらにドル安をあおるのではなく、ドル高で安定させる方法を今すぐ考えるべきではないか。
<円はもはや「別の通貨」>
最後に日本経済の弱体化だ。円相場の展望にとってはこれが一番重要な話である。85年と現在では日本経済を取り巻くファンダメンタルズは全く異なる。80年代は「貿易黒字にもかかわらず円安」という状況があったのに対し、現在は「貿易赤字ゆえの円安」である。当時の日本はコンスタントに年間10兆円以上の貿易黒字を積み上げていた。当然、東京外為市場でも輸出企業の円買いが圧倒的に強かった時代である。今とは真逆の状況だ。率直に言って、当時と現在で円は「別の通貨」である。80年代の日本経済は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」、世界最強の経済大国の一角だった。「強い国の通貨が強くなった」というのがプラザ合意後の円高であり、今の日本からは想像もつかない状況だろう。
トランプ政権は近年の円安相場を踏まえ、円安誘導を主張するが、そもそも日本が望んだ相場現象ではない。低金利・貿易赤字ゆえの通貨安であり、「弱い国の通貨が弱くなった」という必然の帰結である。必然を人為的にひっくり返すのは無理筋だろう。
<ドル凋落シナリオに賭けるのか>
冒頭述べたように、現時点のドル安は米国債利回りの急騰と表裏一体となっている。つまり、ここからさらにドル安を進めるということは米国債利回りの続伸を米国が甘受するということにもなりそうである。その際は130円台、120円台の円高も否定できないだろう。
だが、そうした円高シナリオは「ドル凋落シナリオに賭ける」という行為でもある。本当にそれが現実的なシナリオなのか。強い米国復活を目論むトランプ政権が基軸通貨という途方もない特権を捨てるだろうか。筆者には到底信じられない展開である。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*唐鎌大輔氏は、みずほ銀行のチーフマーケット・エコノミスト。2004年慶應義塾大学経済学部卒業後、日本貿易振興機構(ジェトロ)入構。06年から日本経済研究センター、07年からは欧州委員会経済金融総局(ベルギー)に出向。08年10月より、みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)。欧州委員会出向時には、日本人唯一のエコノミストとしてEU経済見通しの作成などに携わった。著書に「弱い円の正体 仮面の黒字国・日本」(日経BP社、24年7月)、「『強い円』はどこへ行ったのか」(日経BP社、22年9月)など。新聞・TVなどメディア出演多数。note「唐鎌Labo」にて今、最も重要と考えるテーマを情報発信中。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab
筆者は「Reuters Breakingviews」のコラムニストです。本コラムは筆者の個人的見解に基づいて書かれています。