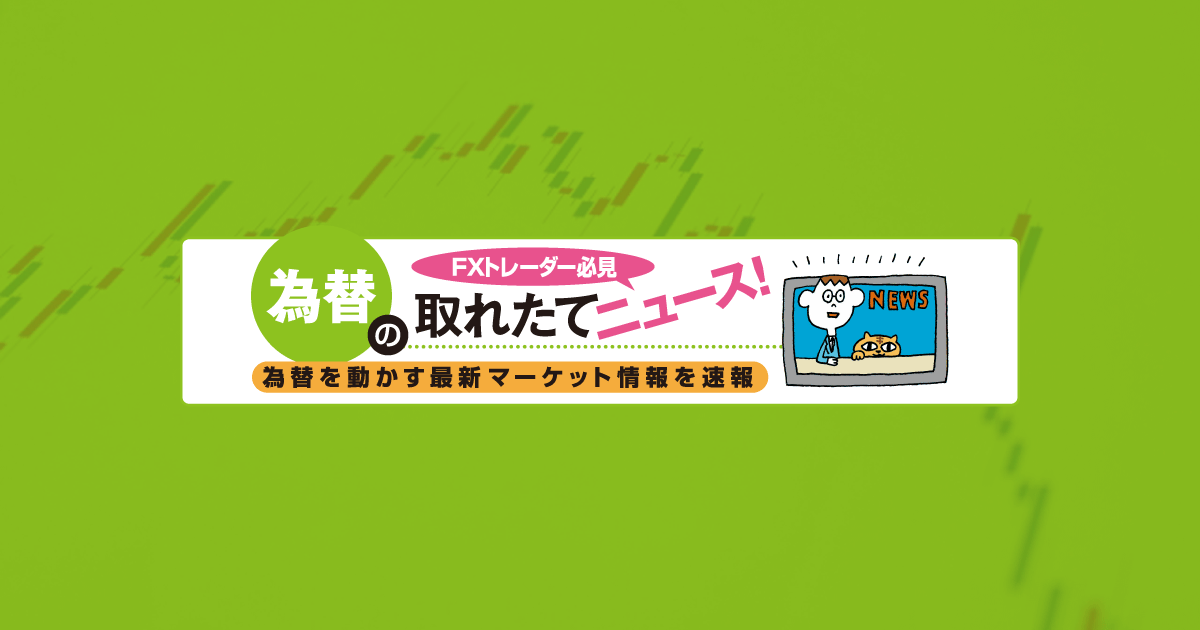従業員退職で倒産が急増した理由

黒坂岳央です。
帝国データバンク『企業倒産動向調査』(2025年8月発表)によると、2025年1〜7月期における「従業員退職型倒産」は前年比1.6倍の74件に達し、年間100件超えが確実視されている。これは、人材流出が企業の存続を左右する深刻な要因であることを示している。
SNSやメディアでは「従業員を大切にしない企業は潰れて当然」といった論調が目立つが、果たして本当にそれだけが原因なのだろうか。本稿では、経営者・従業員双方の視点を踏まえ、データと実例をもとに冷静にこの問題を捉え直す。
Image Source/iStock
「従業員を大事にしないから倒産」は本当か?
SNSでは「安い賃金でこき使っていた企業が潰れるのは当然」といったルサンチマン的意見が見られるが、実態は単純ではない。
「従業員退職型の倒産」は「会社に愛想を尽かした従業員で潰れた」だけではない。
- 某IT業…エンジニアの引き抜き、外注費の増加で利益圧迫しての破産。
- 某建設業…幹部社員の離職で施工・営業力が低下、破産。
- 某不動産業…業績悪化により給与削減→大量離職→倒産。
いずれも、待遇の問題はあれど、根本的な原因は業績不振、組織構造の脆弱さ、人材確保戦略の失敗など複合的な要素が絡んでいる。
つまり、先に「別の課題」が発生したことで従業員が辞めるトリガーとなった、というのが現実的な見方である。
従業員を雇わない起業スタイル
本件に限らず、労働市場は今後も売り手市場が続くことで雇用の流動性が高まることや、ソロプレナー型ビジネスの拡大も続く公算が大きい。そのため、これから新たにビジネス起業する者は「社員を持たない経営モデル」も考慮するべきだろう。すでにITなど省力化が容易で生成AIを活用した一人起業において非常に高い収益率を叩き出すビジネスマンは増えている。
従業員を多数抱えることは、経営面での柔軟性を損なうリスクともなり得る。筆者自身も、かつては業務委託や補助員を活用していたが、現在はAI活用でほぼ完全自動化に移行し、人的リスクを回避している。
雇用を作ること自体が大きな社会貢献で立派である。だが、すべての産業の起業家がそれをするのは現実的ではない。労働人口減少や雇用の流動性低下に直面すれば、たちまち赤信号が点灯するためだ。
去るコロナ禍において、米国では航空業界の業績悪化で迅速なレイオフを行った。一方で日本企業では解雇回避努力をした。航空現場のスタッフは別の部署へ配置転換で大量解雇をせず、危機を乗り切った温情雇用事例が海外で美談として大きく取りあげられた。
しかし、今後も非常に厳しい国際競争に勝ち続けるためには、余裕もなくなってきたのだ。「雇用しない一人起業」という選択肢は拡大しつつあるだろう。
AI時代にどう振る舞うべきか?
これからのAI時代、経営者と会社員とでは取るべき戦略が異なると考える。
たとえばAI・自動化の導入で省人化を進め、フリーランスや業務委託を活用して固定費を削減。ビジネスも省人化を意識した業務設計にするべきだろう。
一方で会社員が取るべき戦略は次のようなものだ。まず、勤務先以外に自分の事業を持ちつつ、本業では雇用流動化に対応できるだけの有力なスキル、経験を持つことだ。
もはや「雇われること」は選択肢の一つに過ぎない時代になりつつある。
◇
今後は経営者も従業員も、それぞれの立場で変化への対応力が問われる時代になる。重要なのは、「誰が悪いか」ではなく、「どう変化に備えるか」である。企業は従業員に依存しすぎず、自律的な事業モデルへの移行を進めるべきであり、従業員もまた、企業に頼らずとも生き抜く力を磨くことが求められている。
要は棲み分けであり、会社が雇用を作ればそうした人が良い人生を送る場の提供となる。
重要なのは両者の対立を煽るのではなく、変化する時代にどう対応するかを建設的に考えることだろう。
■最新刊絶賛発売中!