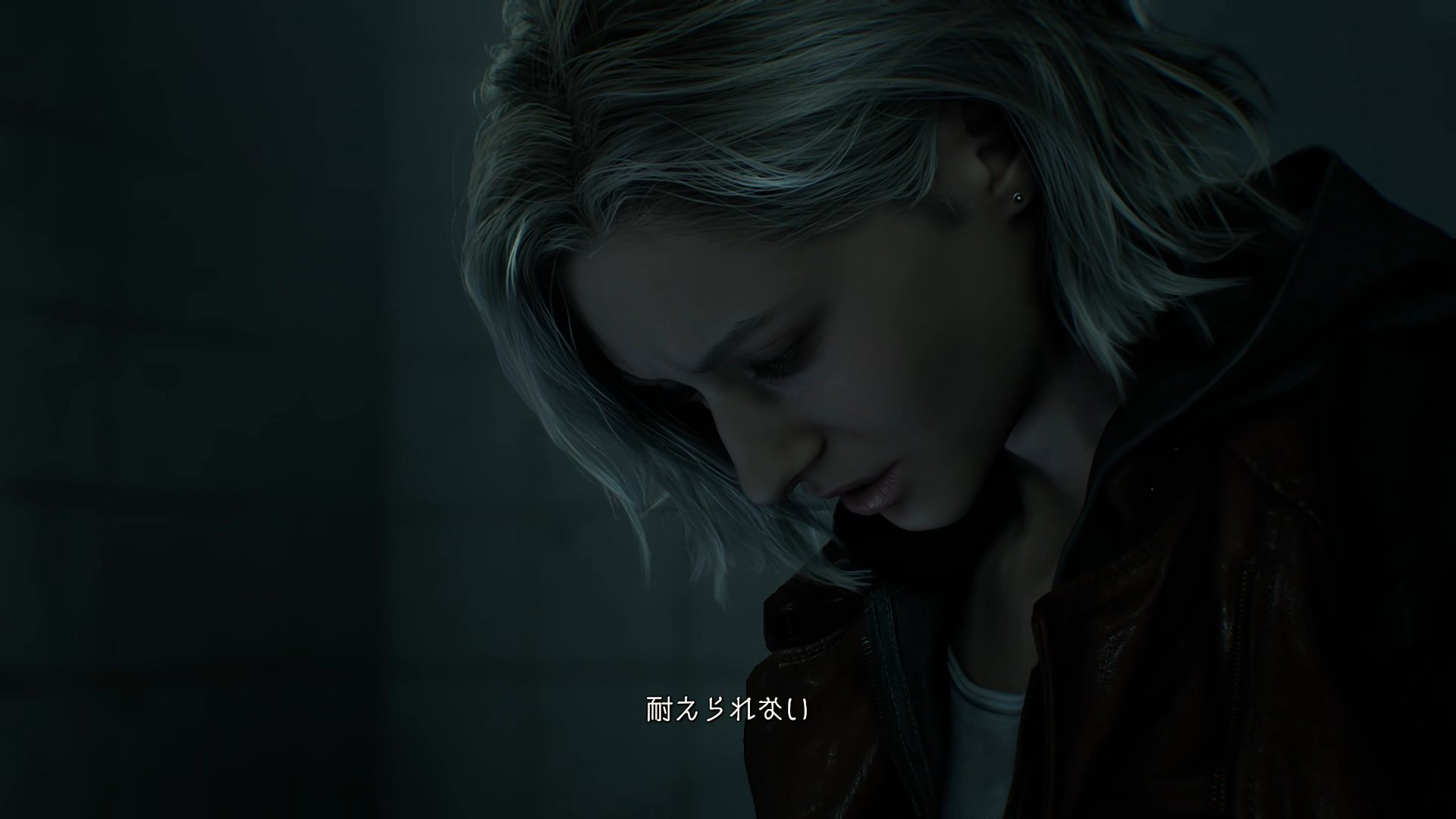【大河ドラマ べらぼう】第18回「歌麿よ、見徳は一炊夢」回想 世のどん底を知る歌麿、作品世界と繋がる人物像 蔦重の名声を高めた喜三二の「夢物語」

この世の地獄を見た歌麿の半生
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」、第18回「歌麿よ、見徳(みるがとく)は一炊夢(いっすいのゆめ)」は後世、世界的な巨匠として評価されることになる喜多川歌麿(染谷将太さん)の「誕生」までをドラマチックに描きました。蔦屋重三郎(蔦重、横浜流星さん)に彼が語ったその半生は壮絶なものでした。(場面写真はNHK提供)
母親は下級遊女の夜鷹でした。江戸時代、ござを手に街角に立ち、客を引いていた女性のことです。男が買う値段は屋台のそば一杯と同じだったという話もあり、いかに厳しい暮らしだったか想像に余りあります。
「柳原夜鷹の圖」尚古堂主人 編『江戸の花 : 温故知新』,博文舘,1890. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1081757堕胎しようとしても堕胎できず、「なんで生まれてきたんだ」と母に言われながら育ちました。七歳過ぎたら食い扶持を稼ぐため客を取らされる、という筆舌にし難い少年時代でした。
そうした日々で出会ったのがあやかし絵(妖怪絵)で知られた鳥山石燕(片岡鶴太郎さん)という絵師でした。これは史実に沿ったエピソードです。歌麿は若い時期、石燕に師事したことが分かっています。記事の後半で石燕の作品を紹介します。
絵を描くことの喜びを知り、辛うじて日常の苦行を凌いできた歌麿。
しかし石燕の元で本格的に絵を学ぶことを母が許す訳もなく、待っていたのは激しい折檻でした。「生まれて来たのが間違いだった」。絶望の淵に立っていた歌麿が遭遇したのが明和の大火、そして蔦重でした。
倒壊した建物の下敷きになった母親。「てめえだけ助かろうって肚だろ。あんたはどうしたって死なない、人の命を吸い取る鬼の子だからね」。息子だけが生き残るのは許せない、と足を離そうとしません。本当の鬼はどちらでしょう。
「このままじゃ俺はおっ母さんに殺される」。そう思い、母を見捨てる形になった歌麿を誰が責められるでしょうか。しかし激しく後悔し「やはり俺が生きててはいけない」と思い、猛火に身を任せようとした歌麿を、「べらぼうめ」と救い出したのが蔦重でした。第1回の冒頭、彼が炎の方へとフラフラと歩みを進めていたのは、こういう訳だったのでした。
蔦重の幼少期の名前にちなんで「唐丸」と名乗りました。吉原でのその後の活躍、そして暗転はご存じのとおりです。
他人のふりをするつもりだった歌麿が、「あの時の…」とつい口にしてしまった磯田湖龍斎の錦絵です。第4回「『雛形若菜』の甘い罠」での印象的なエピソードでした。少年ながら利発な振る舞いで周囲から大事にされ、「吉原は夢のようなところだった」という彼にとっても忘れられない思い出だったでしょう。
湖龍斎が描いた「雛形若菜初模様」の下絵を汚してしまった蔦重の大ピンチを、フリーハンドで寸分たがわずそっくりに描いて複製。蔦重を救いました。
しかし母親の元ヒモ、ヤス(高木勝也さん)に運悪く見つかってしまいます。「母殺し」をネタに金をせびられ、店の売り上げに手を付けるまで追い詰められてしまいました。これ以上蔦重たちに迷惑をかけられない、とヤスを川に突き落とし、自分も死ぬつもりで一緒に飛び込みます。が、生き延びます。
人別(戸籍)がなく、人に頼ってその影で暮らすしかない日々。絵の才と身体を売って生きるだけでした。
歌麿作に見える女郎への共感の眼差し
どうしてこうも徹底して恵まれない生まれ育ちにしたのか、という歌麿をめぐるストーリーでした。一方で、大いに納得できる人物の造形でもありました。浮世絵師の多くは、生まれや育ちが分からないことが多く、歌麿も例外ではありません。どこで生まれ、両親は何をしていたのか不明。亡くなったのが1806年で、逆算して1753年頃の生まれではないか、とされているだけです。つまり日本文化史上の重要人物のひとりながら、分かっている史実が少なく、フィクションで歌麿をどういうキャラクターにするかは作り手側の自由度が大きいのです。
喜多川歌麿「婦女人相十品・ポッピンを吹く娘」東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/) 喜多川歌麿「姿見七人化粧・びん直し」東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)美人画を中心に世界的に知られる数々の名作で知られる歌麿。同時代の作家とは異なるその特徴のひとつに、下記のような作品が挙げられます。
喜多川歌麿「北国五色墨 てっぽう」寛政6~7年(1794~1795) シカゴ美術館 クラレンス・バッキンガム・コレクションClarence Buckingham Collection,The Art Institute of Chicago吉原で最下級とされた「切見世」というお店で働いていた遊女を描きました。《北国五色墨》のシリーズで歌麿はこの《てっぽう》など下級遊女を描いた異色の作品を残しています。「てっぽう」の呼び名は、遊女との初回限りの関係を鉄砲を撃つことに擬えたとも、梅毒を患う遊女を、死に至らしめる毒を持ち、「鉄砲」の異名を持つフグにかけたとも。
「大吉原展」(東京藝術大学大学美術館)の図録によれば、切見世に属する遊女は多い時で吉原の遊女の二割近くを占めていましたが、「松葉屋」のような大見世の花魁とは異なり、彼女たちが画題となることは極めて稀でした。売り物になりにくいからでしょう。このように見捨てられた存在である彼女たちを大判五色揃の大首絵にわざわざ仕立てた歌麿。しかもモデルに対するまなざしの優しさ、内面に迫る迫力は画面からも明らかです。
喜多川歌麿「青樓十二時 續・午ノ刻」東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)女郎の何気ない日常を描いた作品にも、彼女たちへの共感や愛おしく思う気持ちが滲み出ているのが歌麿作品の味わいです。そうした作風を踏まえて、ドラマの作り手は歌麿の境遇を創造したのではないか、と思わせました。絵画を見ていると女郎たちと同じような辛い経験をしてきたのではないか、とつい想像したくなるのが歌麿です。親に売り飛ばされた吉原の女性たちは多かれ少なかれ歌麿と同じような、あるいはもっと酷い目に遭った人が少なくないでしょう。「どうしてお前は生まれて来たのか」と言われた人も大勢いたはず。これから歌麿が吉原の女性たちをモチーフに創作する場面が登場するでしょう。どのように表現されるのか楽しみです。
激賞された「見徳一炊夢」、蔦重の評価を高める
作家の朋誠堂喜三二(尾美としのりさん)をめぐるドタバタをまじえつつ、やっとのことで完成した黄表紙が「見徳一炊夢」でした。蔦重にとって重要な転機となる作品。いったいどんなお話なのかを紹介します。「日本古典文学大辞典」(岩波書店)など参照しました。
浅草のお金持ちの息子で、厳格に育てられた清太郎が主人公。ある日、手代の代次と話している際に蕎麦を注文、出前が届くのを待つ間に2人して居眠りしてしまいます。
喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464その夢に夢商いの店が出現し、「邯鄲の枕」で代金に応じて客に夢を見せてくれるといいます。清太郎は家から千両を盗み出し、五十年分の夢を買います。「邯鄲」とは盧生ろせいという青年が、中国の邯鄲で道士呂翁から枕を借りて眠ったところ、贅沢三昧の五十余年を送る夢を見たが、目覚めてみると、炊きかけの黄粱こうりょうもまだ炊き上がっていないほどわずかな時間だった、という有名な「邯鄲の夢」からの引用です。 喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464夢を買った清太郎は、夢の中でさらに夢の世界へ。京や大坂、長崎、唐と諸国を漫遊し、放蕩の限りを尽くします。江戸にもどって遊里で遊び、名妓を身請けします。遊里に飽きると俳諧や素人歌舞伎、能、茶道と趣味に生きます。 喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464清太郎は70歳になり家が懐かしくなりました。そのころ、店は手代の代次が跡を継ぎ、清太郎の五十年忌の法要が行われていました。ところが100万両に及ぶ清太郎の五十年分の遊興費の請求がきました。代次は全財産を処分し、支払いにあてます。そこに清太郎が帰宅します。 喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464清太郎は悟りをひらき、代次とともに剃髪して諸国修業の旅に出ます。 喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464というところで二重の夢が一度に醒め、蕎麦の出前が届きます。おしまい。 喜三二 戯作『見徳一炊夢 : 3巻』,[蔦屋重三郎],[安永10 (1781) ]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/9892464恋川春町のベストセラー『金々先生栄花夢』を下敷きに、夢のまた夢を描くという趣向を凝らしました。たとえ夢でも「見るが徳」というシャレです。今回のドラマのタイトル「歌麿よ、見徳は一炊夢」には、辛い人生であってもいっときの夢と思って生きていこうよ、というメッセージが込められているのでしょう。大田南畝が「最上級」と評価
なぜこの作品が蔦重にとって重大な転換点となったのでしょう。それは、大田南畝の黄表紙評判記「菊寿草」(1781年)で「極上上吉」、つまり最上級の作品に選ばれたからです。
鳥文斎栄之筆「蜀山人〈大田南畝〉像」 東京国立博物館蔵出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)大田南畝(1749-1813)はこの時代を代表する文化人です。下級の幕臣の家に生まれ、幼いころから漢詩などの領域で優れた才能を発揮し、「神童」と呼ばれました。清廉な能吏である一方、狂歌や漢詩、随筆など幅広い領域で作品を世に送りました。第一級の文化人から絶賛された書籍を世に送り出したことで、蔦重の名前は広く江戸市中で知られるようになりました。
「べらぼう」では桐谷健太さんが大田南畝を演じます。今後、蔦重とも大いに絡む重要な登場人物になるでしょう。注目です。
ふじ、いね、蔦重…人の情に涙
歌麿の辛い半生の振り返り、喜三二がらみのナンセンスユーモアと、目まぐるしい展開だった第18回。人の情けのエピソードにも泣かされました。
普段は万事控えめな駿河屋の女将、ふじ(飯島直子さん)。蔦重が階段で突き落とされても平然としていますが、「ここぞ」の場面では身体を張ります。歌麿を引き取るにはどうしても人別(戸籍)が必要。ふじは、手回しよく四郎兵衛(吉原の番所)から、とっくの昔に駿河屋から姿を消した元奉公人の人別の写しを取り寄せていました。蔦重が、歌麿(唐丸)の愛用品だった矢立(携帯用の筆記用具)や前垂れを大事そうに持っていたり、事あるごとに「唐丸が戻ってこないかなあ」とこぼしたりしていた様子を、ふじはよく見ていたからです。夫に負けず劣らず、彼女も蔦重を深く愛していました。
「あいつを養子になんてできねえ」と難色を示す駿河屋(高橋克実さん)に「重三はあの子をずっと待っていたんだよ。そんな大事な子なんだから、何があってもなんとかするんじゃないのかね」と駿河屋の前に立ちはだかり、一歩も引かない構えです。妻のド迫力の説得に駿河屋は応ずるしかありませんでした。
歌麿の自暴自棄とも見える生き方がどうしても納得できなかった蔦重。色の道に詳しいであろう、いね(水野美紀さん)に「好きで色を売る商いをする人っていたりしますか?」と尋ねます。 すると「たまにいるのは罰を受けたい子だね」といね。「自分のせいで色が死んだり、親が死んだり。そういう子の中には自分は酷い目に遭って当然だからこの稼業も好きだ、ありがたいって言いだすのはいたよ。自分なんか早く死んじまえばいいんだ、ってね」と振り返ります。女郎相手には常に厳しい顔をみせるいねですが、深い洞察を伴いながら、彼女たちに接している姿が伺えます。その的確な人間に対する観察眼は、蔦重に大きな気付きを与えてくれました。
「俺はお前を助ける」
そして歌麿と向かい合った蔦重。
蔦重は「俺はお前を助けらんねぇ。けど、お前が生きてえというなら、いくらでも手を貸せる」と告げます。様々な経験を経た蔦重、ひとつひとつの言葉が重くなりました。俺は人を殺めた、早く死んだほうがいいんだ、と考えている歌麿に、「俺は死んで償いたいのに、こいつに無理やり生かされたんだって。ごうつくな本屋に見込まれて絵描かされたたんだって、その言い訳にはなれる」と歌麿の思いに寄り添った言葉をかけます。「お前が悪いとは思えねえ。死んだ奴らにゃ悪いけど、お前が生きて良かったとしか思えねぇんだよ。石を投げるのは別のヤツの役目。おれはお前を助ける」と力強いメッセージでした。蔦重が言葉にしたように、源内先生や瀬川の力になりきれなかった分、歌麿にかける思いはより強かったのです。
蔦重の真剣な思いに触れて、初めて心からの笑顔をみせました。こうして誕生した「絵師歌麿」。蔦重とともに、これから江戸の町を大いに賑わせることになります。
妖怪画の偉大な先人、鳥山石燕
最後に歌麿の師匠だった鳥山石燕(∼1788)です。水木しげるさんなど現代でも根強い人気を誇る妖怪画のジャンルで活躍した先人です。古くから脈々と続くその系譜の中でも、とりわけ重要なポジションを占める作家で、「図面百鬼夜行」「今昔画図続百鬼」などの著作で知られます。後世にも大きな影響を与えました。
鳥山石燕 画『百鬼夜行 3巻拾遺3巻』[1],長野屋勘吉,文化2 [1805]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2553975鳥山石燕 画『百鬼夜行 3巻拾遺3巻』[1],長野屋勘吉,文化2 [1805]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2553975鳥山石燕 画『百鬼夜行 3巻拾遺3巻』[1],長野屋勘吉,文化2 [1805]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2553975昔から言い伝えられてきた妖怪に加え、石燕オリジナルのものも作品にしました。こうした豊かな想像力あふれる創作物が世に出た時代でした。(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから