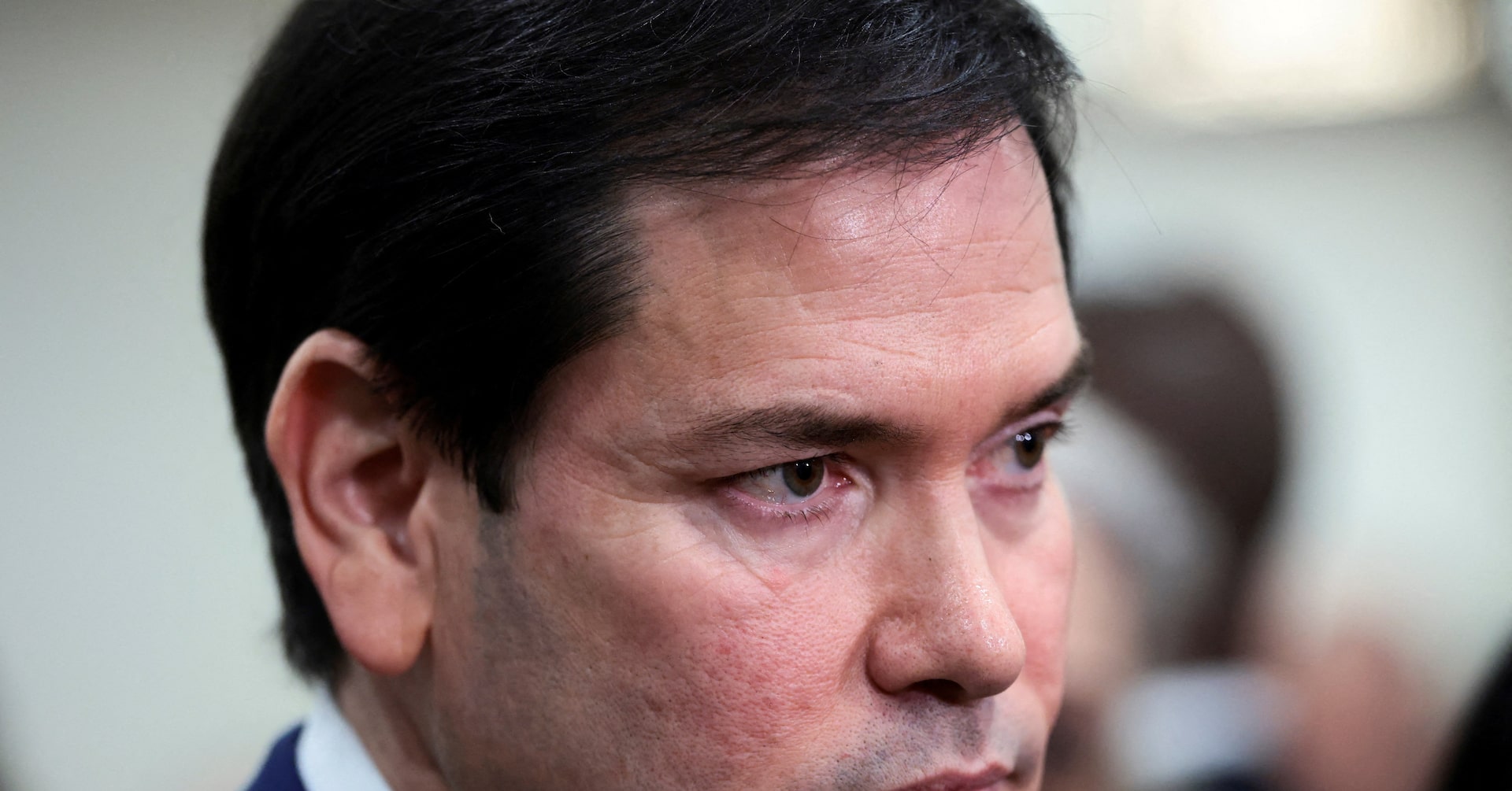ヘグセス米国防長官、同盟巡り日欧に異なるメッセージ-焦点は中国

ヘグセス米国防長官は2度の外遊を通じ、米国の同盟国に大きく異なるメッセージを発した。
2月の訪欧時には北大西洋条約機構(NATO)の欧州勢は防衛力に十分な予算を充てず、米国の軍事力を頼りにロシアをけん制していると強く非難。ヘグセス氏はブリュッセルで、「米国はもはや、依存を助長する不均衡な関係を容認することはできない」と欧州各国の国防相に伝えていた。
対照的に、3月のアジア歴訪では、中国の軍事的圧力に抵抗する日本とフィリピンを称賛。同氏はミサイルシステムや兵力を含むリソースを提供し、中国の拡張主義を抑止すると約束した。
来日したヘグセス氏は30日に中谷元防衛相と会談。「戦闘能力や破壊力、即応性を向上させるに当たり、緊密に協力していきたい」と述べた。
トランプ大統領のディール(取引)重視や、ロシアや中国との取引を求めるスタンスに対する懸念が拭い切れないものの、ヘグセス氏のアジア訪問は、この地域での米国の軍事増強方針を明確に示すものとなった。
ハワイとグアムにも立ち寄ったへグセス氏は、米国はアジア太平洋地域における軍事力を強化し、同盟国による同様の取り組みを支援することで、中国に対する抑止力を「再確立」する必要があると主張した。
同氏はマニラで、米国は今後実施される合同軍事演習のためフィリピンに艦船攻撃ミサイルシステムと無人水上艇(USV)を送り込むと述べたが、詳細はまだ不明だ。
東京では、米国は日本に新設する司令部に人員を追加する方針だと説明。同司令部は、地域の危機に対する米軍の初動を指揮するほか、日本側で陸海空3自衛隊を一元的に指揮する新組織「統合作戦司令部」と緊密に連携するとヘグセス氏は話した。
帝京大学の松岡美里准教授はヘグセス氏のアプローチについて、米国が中国を主要な戦略的競合相手として優先的に対応していることを示すものだと分析。
「米国は欧州の同盟国が自国の安全保障により大きな負担を担うことを期待しており、そうすることで米政府は他の地域に資源を配分することができる。一方、日本とフィリピンは米国が中国を封じ込める取り組みの中心だ」と述べた。
台湾外交部(外務省)の31日の声明で林佳竜外交部長(外相)は、「台湾海峡の平和と安定への日米両国の確固たる支持と世界の秩序に対する中国の挑戦に対する懸念を評価し歓迎する」とコメントした。
シンガポール国立大学(NUS)の荘嘉穎准教授(政治学)は、中国が「黄海から東シナ海、台湾海峡、南シナ海、さらにはオーストラリア周辺に至るまで、現在の軍事および準軍事活動を継続するのではないか」と想定。「中国政府は米国の決意を試そうとしているのかもしれない」と語った。
ヘグセス氏の訪日で驚くべきことは、在日米軍の関連経費を含め、日本に対する防衛費増額要求が全くなかったことだ。
トランプ、ヘグセス両氏が欧州のNATO加盟国に対して、国内総生産(GDP)の少なくとも5%を国防費に充てるよう求めていたことから、日本にも同じような要求が示されると予想されていた。
米国が日本の防衛支出に何を期待しているかという記者の質問に対し、ヘグセス氏は「同盟国として、肩を並べて立つために同盟内でどのような能力が必要か、日本が正しい判断を下すものと確信している」と答えた。
日本は現在、GDPの約1.4%相当を防衛費に費やしており、2027年度までに2%に引き上げるという公約がトランプ政権から一定の評価を得ているようだ。
ヘグセス氏によると、米国が後れを取っているのは、アジアにおける自国の存在感と中国の強硬姿勢に立ち向かう姿勢だ。「ご存じのように、米国は力によって平和を再構築するとトランプ大統領は述べている」とヘグセス氏は東京で強調した。
原題:Hegseth’s Good Cop, Bad Cop Approach to Allies Shows China Focus (抜粋)