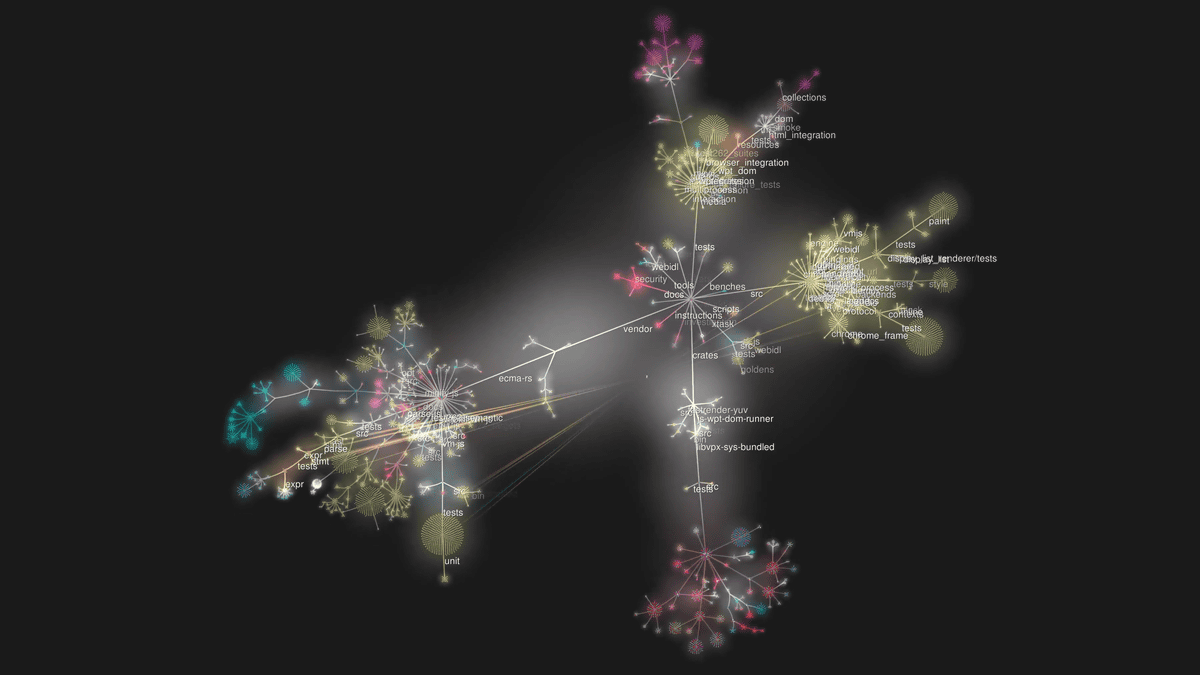「スマホは何歳から持たせる?」担任歴20年の教師が解説「そうなんだ!」と思う意外な実態3選(ナナホシ)

「うちの子、友達がみんなスマホを持っていると言うんですが、まだ早いでしょうか?」「何年生になったら持たせるのが適切なのでしょう?」「持たせるなら、どんなルールを作ればいいのか悩んでいます」
こうした質問や悩みを、保護者会や個人面談で頻繁に耳にします。お子さんのスマホ所持について、「適切な時期はいつか」「他の家庭はどうしているのか」と迷われる方が多いのは自然なことです。
小学校の教員として20年間、スマホ時代の到来とともに変化してきた子どもたちの生活を間近で見てきました。今回は、スマホをいつから持たせるかという問題について、教室から見える子どもたちの様子をもとに、意外と知られていない実態をお伝えします。
1.学年より「目的」で決める家庭が増加―単なる連絡手段から変化する役割
私が5年生を担任していた時のことです。休み時間にA君が「塾の帰りが遅いから、お迎えの連絡用にスマホを持ってるんだ」と話していました。周りの子も「うちもだよ」「GPSで居場所がわかるやつ」など、様々な声が聞こえてきました。気になって保護者会で尋ねてみると、同じクラスでも「連絡用」「防犯用」「学習用」など、持たせる目的は家庭によって大きく異なっていました。
最近の傾向として、「何年生だから」という学年基準ではなく、「どんな目的で必要か」で判断する家庭が増えています。B先生のクラスでの保護者アンケートでは「子どもの行動範囲が広がったタイミング」「習い事や塾の送迎が必要になったとき」「中学受験の勉強で調べ物が増えたとき」など、家庭の状況に合わせた判断をしている例が多かったそうです。
C君(4年生)のお母さんは「最初は留守番用の簡易携帯でしたが、オンライン学習が増えたため、5年生からタブレット機能付きのものに変える予定です」と話していました。一方、D君(6年生)の家庭では「中学校入学まではGPSつきの子ども用携帯で十分」と考えているそうです。
教育工学を研究しているE先生は「スマホは単なる連絡ツールから、学習ツール、娯楽ツール、社会とつながるツールへと役割が拡大しています。その多機能性を考慮した判断が必要です」と指摘していました。
20年間教師をしていて感じるのは、スマホの所持時期は「子どもの年齢」よりも「家庭のニーズや子どもの生活状況」によって決められることが多くなっているということです。以前のような「〇年生になったら持たせる」という単純な基準ではなく、より個別の状況に応じた判断が主流になってきているようです。
2.「全部持たせる」から「段階的に」へ―ルールと機能制限の工夫
6年生を担任していた時、F君が「ぼくのスマホはLINEとゲームができないんだ」と話していました。興味を持って聞くと、「最初は通話とメッセージだけ。半年後にカメラが使えるようになって、学年が上がったらLINEも解禁される予定」とのこと。F君の保護者会で、お父さんから「一度に全ての機能を与えるのではなく、段階的に権限を増やしていく方針です」と聞き、納得しました。
近年増えているのが、このような「段階的アプローチ」です。G先生のクラスの保護者からは「最初から全機能が使えるスマホを持たせるのではなく、子ども用の制限付き端末から始めて、徐々に機能を拡張していく方法をとっています」という声が多く聞かれました。
H君(5年生)の家庭では「平日は1時間、休日は2時間」という使用時間のルールがあるそうです。一方、I君(4年生)の家庭では「家の中の決められた場所でのみ使用可能」というルールを設けていました。J君(6年生)のお母さんは「最初は子ども用のフィルタリングアプリを入れたものを持たせ、ルールを守れるようになったら徐々に制限を緩めています」と話していました。
情報モラル教育に詳しいK先生は「小学生のうちからデジタル機器と健全に付き合う習慣を身につけることが大切。そのためには、いきなり制限のないスマホを持たせるより、段階的に責任と自由を増やしていく方法が効果的です」と話していました。
実際、L君(6年生)は「最初はすごく制限があって不満だったけど、少しずつできることが増えていくから、ルールも守りやすいんだ」と話してくれました。子どもたちにとっても、一度に多くの自由を得るより、段階的に責任ある使い方を学んでいく方が、健全な関係を築きやすいのかもしれません。
長年の教師経験から感じるのは、「いつから持たせるか」と同時に「どのように持たせるか」という視点が非常に重要だということです。
3.意外な事実:早い・遅いよりも「家庭のルール」が鍵―子どもの本音
5年生のクラス会で「スマホについてどう思う?」という話題になったとき、M君は「僕は持ってるけど、あんまり使わないよ。家のルールがきびしいから」と言い、スマホを持っていないN君は「欲しいけど、持ってなくても困らない。友達と遊ぶ時間の方が楽しい」と答えました。意外だったのは、スマホを持っている子の中に「実はそんなに楽しくない」と思っている子もいれば、持っていない子の中に「別に今はいらない」と考えている子もいたことです。
O先生のクラスでは、子どもたちの本音を聞く機会があったそうです。驚いたことに「スマホを持つタイミング」より「家庭でのルールの有無」の方が、子どもたちの使用実態や満足度に大きく影響していたとのこと。ルールが明確で親子でコミュニケーションを取りながら使用している子は、持ち始めた時期に関わらず健全に利用している傾向が見られました。
P君(6年生)のお母さんからは興味深い話を聞きました。「4年生から持たせていますが、最初にしっかりルールを決めたことで、今でも問題なく使えています。大切なのは『いつから』ではなく『どうやって』だと実感しています」と。一方、Q君(6年生)は最近になって持ち始めましたが、明確なルールがなかったため、使いすぎで学校生活に影響が出始めているとご両親が心配されていました。
情報社会に詳しいR先生は「子どもとスマホの健全な関係は、持たせる時期よりも、家庭での対話とルール作りに大きく左右されます。スマホを単なる『所有物』ではなく『責任を伴うツール』と位置づけることが重要です」と話していました。
S君(5年生)の家庭では、スマホを持たせる前に「スマホ契約書」を親子で作成したそうです。S君のお父さんは「使用時間や禁止事項、困ったときの相談方法などを一緒に考えて決めました。そのおかげで、子ども自身も責任を持って使うようになりました」と教えてくれました。
20年間教師をしていて最も印象的だったのは、「早く持たせたから問題が起きやすい」「遅く持たせれば安全」という単純な図式が当てはまらないということです。むしろ、家庭でのコミュニケーションの質や明確なルールの有無が、子どものデジタル機器との関わり方に大きな影響を与えているように感じます。
まとめ
「我が子にいつスマホを持たせるべきか」と悩まれる気持ち、よくわかります。でも、20年間で見てきた多くの子どもたちとその家庭の例から言えることは、「これが正解」という時期は存在しないということです。
スマホを持たせる時期を考える際のポイントをいくつか挙げると:
- 単に年齢や学年ではなく、お子さんの生活における具体的な「必要性」で判断する
- いきなり制限なしで持たせるのではなく、段階的に機能や自由を増やしていく
- 持たせる時期より、家庭でのルール作りと対話を重視する
- お子さん自身の意見も聞きながら、責任ある使い方について話し合う
私だったら、「持たせる・持たせない」の二択ではなく、「どのように持たせるか」「どんなルールを作るか」を家族で十分に話し合うことをお勧めします。
ある卒業生のお母さんが教えてくれた言葉が印象的です。「スマホは道具であり、目的ではないことを子どもと確認しました。『何のために使うのか』という目的意識を育てることが、健全な利用につながったと思います」と。
子どもたちは一人ひとり違います。周囲と比較するよりも、お子さんの生活状況や成熟度、家庭の価値観に合わせた判断をしていただければと思います。教師として20年、多くの子どもたちを見てきた経験から言えることは、スマホとの付き合い方を学ぶプロセスそのものが、現代社会を生きる子どもたちにとっての大切な学びになるということです。
【4/22まで】「すみっコぐらし×選べるニュース」LINEスタンププレゼントキャンペーン実施中
LINEアカウントメディア プラットフォームの中から3媒体以上を友だち追加すると「すみっコぐらし」のLINEスタンプがもらえます。
ナナホシも参加していますので、ぜひこの機会に友だち追加をお待ちしています。
開催期間:2025年4月22日まで
※このご案内はLINEヤフー社の取り組みで特別に掲載しています。