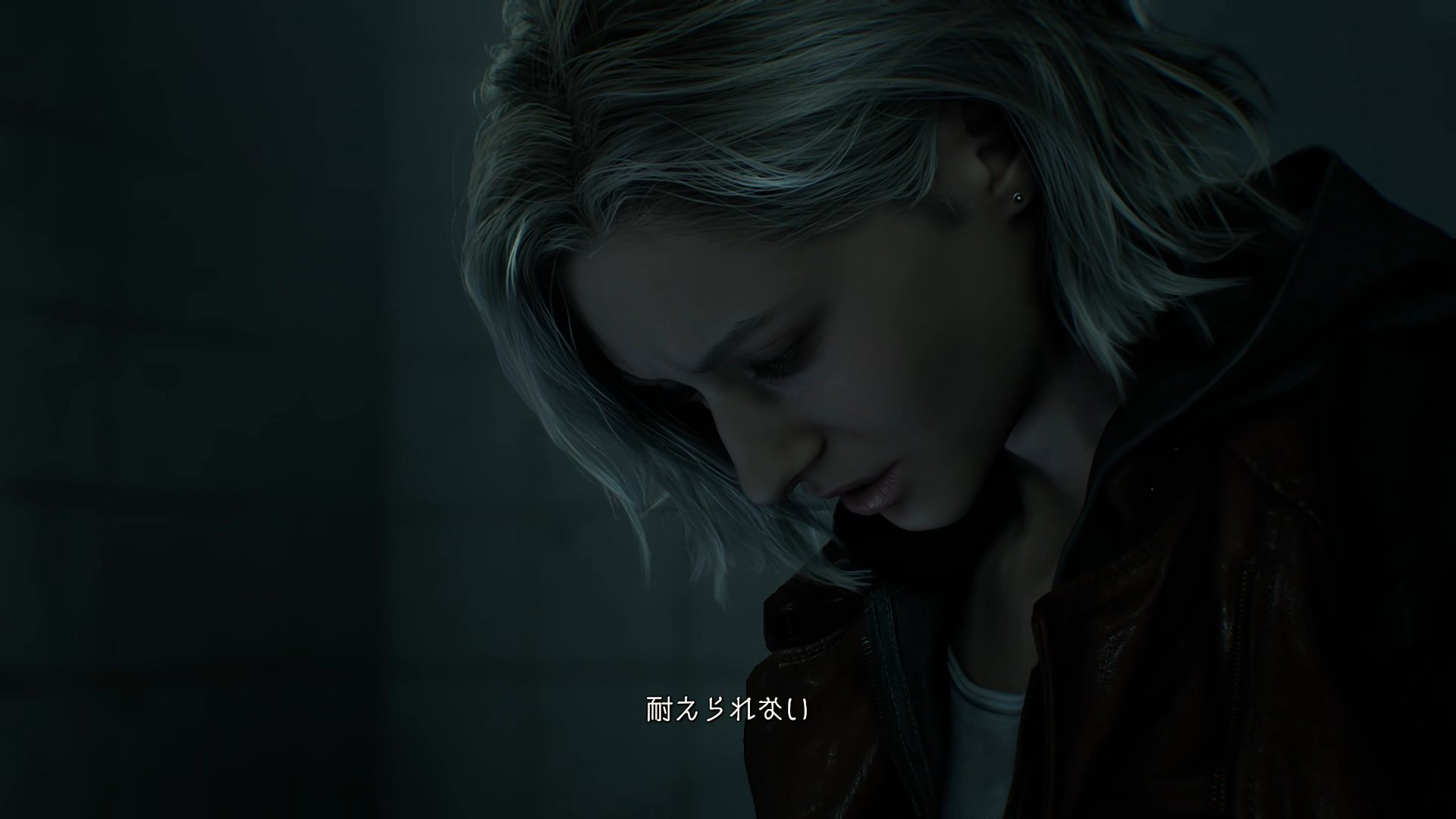【大河ドラマ べらぼう】第20回「寝惚けて候」回想 江戸の街を席巻する天明狂歌 一大ブームに飛び込んだ蔦重 大田南畝らスター勢ぞろい 「身を焦がす」のはウナギ?恋?

大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」。第20回「寝惚ぼけて候」では新たな顔触れやモチーフが次々に登場し、第17回から始まった新章の本格化を印象付けました。その中心は桐谷健太さん演じる大田南畝なんぽ(1749∼1823)、そして一大ムーブメントへと発展していく天明狂歌でしょう。
「江戸の知の巨星」南畝
南畝は江戸時代を代表する文化人のひとりです。狂詩や狂歌、黄表紙や随筆など文芸全般に優れた著作を残しました。同時代の事件、噂話、文芸など目にしたあらゆる出来事を書き残したことも偉大な功績です。彼が遺した記録によって、当時の江戸の姿が分かることが少なくありません。2023年、たばこと塩の博物館(東京)では「没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界」という展覧会が開催されました。まさにその形容どおりの存在だったと言えるでしょう。
大田南畝(四方赤良) 『狂歌百人一首』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100411035南畝は下級の御家人の家の生まれ。漢学に通じ、幼いころから「神童」の名をほしいままにしました。19歳のとき、自著の「寐惚先生文集」が評判になり、一躍江戸の有名人に。ドラマの中でも、蔦重は「あの寐惚先生」として認識していました。序を平賀源内が書いており、源内もその才能を高く買っていたことが分かります。今回のドラマのタイトルの「寝惚けて候」はこの著作と、蔦重が寝惚けるラストシーンから取ったものでしょう。
『寝惚先生文集』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414281「狂詩狂文」というジャンルで、正統派の漢詩や漢文に対して、通俗な題材を漢文で詠んだものです。下級の武士の大半は生活苦に喘ぐようになっていたこの時代。直参ではあっても、南畝の日々の暮しも当然、厳しかったでしょう。こんな詩を残しています。
かせぐに追い付く 貧乏多し
「貧すれば鈍す」「食うや食わず」「地獄の沙汰も金次第」とよく知られた言い回しで畳みかけ、「稼ぐに追い付く貧乏なし」(一生懸命働けば貧乏に苦しむことはない)ということわざを引用して、実際は「いくら働いても、貧乏からは逃れられないよ」と笑ってみせます。
『寝惚先生文集』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100414281この詩は杜甫の有名な「貧交行」を下敷きにしています。
この道 今人(こんじん)棄てて 土の如し
昔と比べ、貧乏になると友情もあっさりと捨てられてしまう最近の風潮を嘆く杜甫の詩です。南畝の歌を目にした当時の人々は、杜甫のメッセージも頭の中で重ね合わせつつ、ユーモアを交えて現実の厳しさを嘆き、そして笑った南畝の思いに共感したことでしょう。漢文や和歌など、古典の知識を前提としていることは、この時代の文芸の常識。庶民層でもそれなりの教養を身に付けている人が多いことも改めて感じさせます。
江戸の狂歌の盛り上がり、「出版」で爆発的に
南畝ら当時の文化人は「狂歌」のジャンルにも積極的に取り組むようになっていきます。当時、武士には和歌の教養も不可欠で、狂詩狂文同様、身に付けた知識を生かし、楽しみたいのは誰しもが思うところでしょう。
「日本古典文学大辞典」(岩波書店)などによると、「狂歌」とはその名のとおり、「狂体の和歌」で、古典的な和歌とは違い、滑稽や諧謔味を強調した短歌のこと。昔から和歌のパロディは存在し、「狂歌」という言葉も鎌倉時代ごろからありましたが、和歌の権威に憚って、記録はせずに言い捨てるのが習わしで、具体的にどんな歌が詠われていたかはあまりよく分かっていません。安土桃山時代になると豊臣秀吉が滑稽な歌を好み、また歌の道に通じた細川幽斎が狂歌を得意にするなど、徐々に文芸シーンの表側に狂歌が現れてきます。江戸時代に入ると、京や大坂では江戸に先んじて狂歌のブームが始まりました。
宿屋飯盛(石川雅望)編 、北尾政演(山東京伝)画「吾妻曲狂歌文庫」東京都立中央図書館 「四方赤良」が大田南畝。「朱楽菅江」は南畝の盟友の幕臣、山崎景貫の狂名。朱楽も当時の狂歌界を代表する存在江戸狂歌の始まりはドラマの時制の約10年前
江戸の狂歌は明和6年(1769)に、大田南畝と同門の唐衣橘洲からごろもきっしゅうが開いた狂歌会が始まりとされ、ドラマで描かれた時期(1781~82年ごろ)の10年ちょっと前ということになります。「初めは四谷・牛込辺りに住む少数の下級幕臣や町人たちによって開かれた狂歌の集まりは、安永期を経て天明期になると山手・下町問わず江戸の各所で開かれるようにあり、そうした集まりは連あるいは側などと呼ばれ、月次の狂歌会なども盛んに催されるようになった」(「没後200年 江戸の知の巨星 大田南畝の世界」図録より、揖斐高氏の寄稿「大田南畝の自由と『行楽』」から)といいます。約10年かけて、じわじわと江戸の町中で盛り上がっていたのです。さらにこのタイミングで優れた狂歌をまとめた出版物が相次いで世に出たことが、ブームに火を付ける形になりました。
技巧、教養、諧謔、情愛 魅惑の南畝の狂歌世界
それでは南畝の狂歌を紹介しましょう。南畝は「四方赤良」(よものあから)の狂名で活躍しました。まずはドラマに出て来た作品です。
「貧しいながら世間の人なみには門松も立て、やぶれ障子も張りかえて、どうにか春がわが家にもやってきたよ」(小学館「日本古典文学全集 黄表紙 川柳 狂歌」から)という意。質素な暮らしぶりながら、正月を迎えた喜びを伝えています。「くれ竹」は「世」の枕詞。ここでは「松」の縁語として門松の竹も連想させます。「春」は障子を「張る」に掛けています。素朴な味わいですが、技巧は見事に散りばめられています。「万載狂歌集 巻第一 春歌上」に掲載。
『万載狂歌集』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100411063「万載狂歌集」は天明3年(1783)正月に出版。須原屋伊八刊。この時代の狂歌集を代表する一冊で、狂歌ブームの盛り上げに大いに貢献しました。書名は平安時代末期に編纂された勅撰和歌集「千載和歌集」(撰者は藤原俊成)から取ったもの。体裁も堂々たるもので、勅撰和歌集にならい、700首余りを四季・離別・羇旅・哀傷・賀・恋・雑・雑体などの部立で分類している本格的なパロディーです。下に示した「千載和歌集」や「古今和歌集」などと合わせて見れば、狂歌が和歌の知識や体系を前提として発展してきたことが分かります。単に言葉の遊びとして面白ければよいわけではありません。
『千載和歌集』(名古屋大学附属図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100272096 『古今集』(広島大学図書館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100302202「くれ竹」の歌は歌集の冒頭3番目という目立つ位置に出てきます。春を寿ぐ秀歌として評価されたわけです。確かに面白いだけではなく、格調の高さも感じられます。
抱腹絶倒「うなぎの恋」
こちらは蔦重でなくともその鮮やかな技巧にハッとさせられる一首。
「万載狂歌集 第十二 恋」から。「どこの山の芋が成ったうなぎだか知らないが、妹背の仲をさかれたうえに、背をさき開かれて蒲焼になりながらも、相手のことを思い焦がれているとは、ああ、なんという情けないことよ」(小学館「日本古典文学全集 黄表紙 川柳 狂歌」から)の意。「山の芋鰻になる」はあり得ないことが起きるという意味のことわざ。「芋」と「妹(いも)」を掛け、「背」と「夫」と掛け、「妹背(いもせ)」、つまり恋人同士の男女の意味を導きます。そして「仲を裂かれる」「背中を割かれる」を掛けます。さらに「身を焦がす」は恋愛の情に苦しむさまと、うなぎが焼かれる姿を掛けました。あまりに見事でかつナンセンスの極みです。
泣かせる親心も歌に
狂歌で描かれるのは皮肉や諧謔の世界ばかりではありません。ドラマで、南畝は泣く子どもをあやす場面で初登場しました。おそらく意図したシーンでしょう。親子の情をテーマにした、しみじみとした作品にも良いものがあるのです。
「狂歌才蔵集」から。「子供は喜んで盆踊りに加わって踊っている。踊りの染めゆかたを着せるための算段に、盆前にどれだけ親がどきつかせて苦労したか、その親心を知らないで」(小学館「日本古典文学全集 黄表紙 川柳 狂歌」から)。もちろん「親の心 子知らず」ということわざがベースですが、味わい深い一首です。
かつてお盆の前は決算勘定の時期でした。「盆暮れ勘定」という言葉もありました。借金だらけの苦しい家計をやりくりしてお盆前にお金の始末をつけ、子どもに恥ずかしい思いをさせないよう、やっとの思いで買った染物のゆかた。「胸の躍る」は盆踊りの縁語で、普通は喜びの感情をいうものでしょうが、ここでは「果たしてゆかたを誂えることはできるだろうか」という親の心配の気持ちを表現しています。真新しいゆかたを着せてもらい、笑顔で盆踊りに加わる我が子。その姿をまぶしく見つめる親の姿。その情景についホロリとする方もいらっしゃるでしょう。貧しさを表わす直接的な言葉は使わずとも、暮らしぶりがじんわりと伝わり、ドラマで描かれた慎ましい南畝宅を思い浮かべます。南畝は男女3人の子どもがいました。長女は2歳で亡くしています。
「羽根をついている子を、一人、二人、三人、四人、五人、とながめわたせば、みんあどけないかわいらしさだが、いつかはお嫁になってしまう少女たちだ」(小学館「日本古典文学全集 黄表紙 川柳 狂歌」から)。「はごのこ」は羽根つきのことを言いますが、ここでは羽根つきをする子の意味を重ね合わせます。羽根つき唄「ひとごにふたごみわたしゃよめご~」を引用。「一人の子」「二人の子」の意味を掛けました。「いつか」は「何時か」「五つ」を掛けます。お正月の羽根つきに興じる娘たちを愛おしく見つめ、彼女たちがいずれ家を離れる日をふと想像します。昔も今も変わらぬ親の眼差しです。
蔦重、狂歌世界にハマる 「オレが流行らせる!」
ドラマの狂歌会で象徴的に描かれたとおり、狂歌のサロンは幕臣や地方の藩士、豪商、町人など階級も貧富も関係なく参加でき、男女も問われませんでした。
智恵内子(水樹奈々さん)夫婦で活躍した人も。女性狂歌師の第一人者として知られた智恵内子ちえのないし(水樹奈々さん)は、夫の元木網(ジェームス小野田さん)とともに座を仕切っていました。
宿屋飯盛(石川雅望)編 、北尾政演(山東京伝)画「吾妻曲狂歌文庫」東京都立中央図書館彼女も狂歌集にイラスト入りで名前が出るほどのスター。湯屋を経営する町人夫婦です。
元木網(ジェームス小野田さん)朱楽菅江あけらかんこう(浜中文一さん)も当時の狂歌の大スター。下級の幕臣でした。
朱楽菅江(浜中文一さん)大田南畝、唐衣橘洲とともに、狂歌三大家の一人としてもてはやされました。
朱楽菅江 『狂歌百人一首』(江戸東京博物館所蔵) 出典: 国書データベース,https://doi.org/10.20730/100411035性別も身分も世代も違う人々が集まり、自由な雰囲気のやりとりの中で形成されたのが、機知にあふれる「江戸好み」の世界でした。
世のトレンドに敏感な出版人である蔦重が、こんな魅力的な世界を放っておくわけがありません。したたかに酔っ払い、歌麿に介抱されながら、「狂歌、ありゃ流行る。おれが流行らせる」と宣言。経験を積み、商売の腕を徐々に上げて来た蔦重、いよいよ狂歌のフィールドでその力量のみせどころです。
世を揺るがす土山宗次郎、登場
狂歌の会のスポンサーとして、羽振りのよさそうな武士が現れました。
旗本の土山宗次郎(栁俊太郎さん)です。田沼政権下で重用され、勘定組頭という要職についていました。吉原の世界や政策面では蝦夷地開発に深くかかわり、様々な意味で世間を大いに騒がせることになります。今後のストーリー展開のキーマンになるのは必至。蔦重や南畝らの人生にも関わってきます。
蝦夷地、政策テーマに浮上
工藤平助(おかやまはじめさん)という男も登場しました。こちらも注目のキャラクターです。
和歌山藩医の家に生まれ、仙台藩医の養子となりました。商売の才能があり、前野良沢ら蘭学者とも交わり、海外事情にも通じていました。
『赤蝦夷風説考』は工藤平助の著作。このころ注目された始めたロシア対策を具体的に論じたもので、蝦夷地の金銀山を開発して蝦夷地を開き、ロシア勢力の南下に備えるべき、と主張しました。この本が意次らの眼に止まり、事態は大きく動いていきます。海外の動向にも神経を使うことが増えたのが当時の幕府。「幕末」の足音が近づきつつある時期です。
地本問屋との戦い、大きな地歩を築いた蔦重
蔦重、したたかです。西村屋(西村まさひこさん)の看板商品、「雛形若菜」のそっくり企画を立ち上げ、西村屋の注意を錦絵に向けさせました。その間に吉原界隈に手をまわして女郎に関する偽情報をひろめ、肝心の「吉原細見」を間違いだらけにさせました。西村屋は細見の発売を中止せざるを得ません。
これを機に、売れ筋の耕書堂の商品が扱えないことにいら立っていた中小の地本問屋は、主流派の鶴屋や西村屋に反旗を翻します。すべて蔦重が書いたシナリオの通りの展開です。中小問屋は組織を脱退し、蔦重と新組織を立ち上げることまで仄めかしてきました。対蔦重との戦いで、旗色の悪さを自覚していた鶴屋(風間俊介さん)は、市中の書店でも耕書堂の商品を扱うことを容認するしか選択肢はありませんでした。
吉原だけでなく、ついに市中にも販路を広げることに成功。蔦重にとって、大きな一歩となりました。
とはいえ、蔦重に「錦絵の商売は簡単ではないぞ」と警告した西村屋。「耕書堂の商品を扱うつもりはない」と取り付く島もなかった鶴屋。鶴屋は早速、才人の山東京伝(古川雄大さん)を呼び、新しい企画を持ちかけていました。どんな本ができるのでしょう。
今も昔も、メディアの世界は油断も隙もない競争社会です。蔦重にとって高いハードルはまだまだ続きます。
「すべては田沼のせい」こちらもしたたかな治済
将軍・家治の後継者は結局、御三卿の一橋治済(生田斗真さん)の長男、豊千代になりました。のちの第11代将軍・家斉です。治済は表面的には後継者争いには関わらず、図らずも家から将軍の世継ぎを出すことになってしまった、といわんばかりです。本音は一切、表に見せません。
豊千代の正室には、同じく御三卿の田安家から種姫迎えたい、というのが家治の意向でしたが、治済は先に縁組していた島津家の茂姫でなければ困る、と難色を示します。薩摩藩主の重豪に手をまわし、正室としての縁組はあくまで島津家の意向である、という形を取ることで、自分自身の権力欲は隠したままで、田安家を政権中枢から排除することに成功しました。
大奥など江戸城では「すべては田沼の差し金」という噂が飛び交い、一橋家が泥をかぶることはありません。鮮やかな治済の権謀術数です。権力の姿をよく知る意次も、治済には警戒感を隠しません。
江戸城の水面下で展開する激しい権力闘争、どういう決着になるのでしょうか。幕府パートもますます目が離せません。(美術展ナビ編集班 岡部匡志)
種姫の婚礼行列を描いた絵、見られます
以下は追伸です。将軍の後継者の正室、と目された田安家の種姫(将軍家治の養女になりました)は結局、紀州の徳川家に嫁入りします。その婚礼行列の様子を描いた作品が現在、サントリー美術館(東京・六本木)で開催中の「酒呑童子ビギンズ」展で見ることができます。6月15日まで。
山本養和筆「徳川種姫婚礼行列図巻 上巻」(部分) 江戸時代 18~19世紀 東京国立博物館蔵紀州徳川家が将軍家から正室を迎えるのは、1685年に五代将軍・綱吉の娘である鶴姫が綱教に降嫁して以来のことで、その婚礼は盛大に行われました。図巻では、豪華な行列が写実的に描かれています。(岡部匡志)
<あわせて読みたい> 視聴に役立つ相関図↓はこちらから
◇【徹底ガイド】大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」 キャストやインタビュー、関連の展覧会、書籍などを幅広く紹介