太陽の30万倍!人類が作り出した史上最高の温度
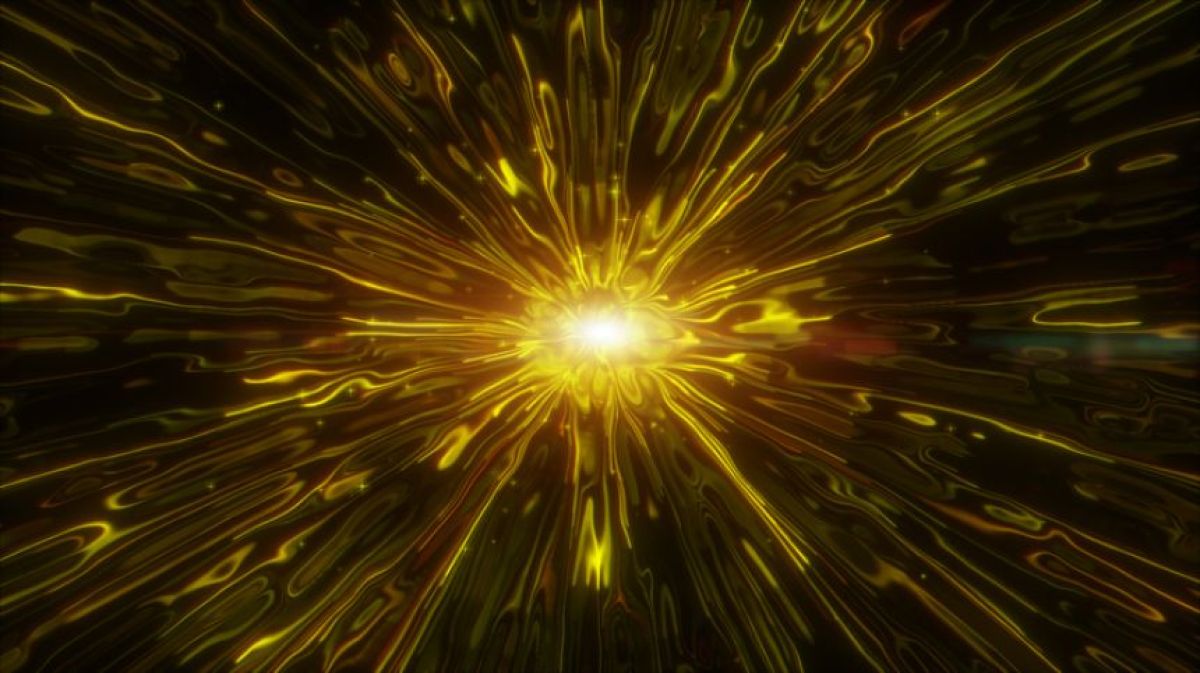
人類は物体を熱くするのが大好きだ。お風呂や日々の料理はもちろんだが、そもそも青銅器時代や鉄器時代などの歴史の節目は、より高い熱を生み出す技術によってもたらされたようなものだ。
ではこれまでに人類が生み出した最高の温度は何度だろう? 答えはおよそ5兆度。これは太陽の30万倍も熱く、この宇宙が誕生した直後の温度に匹敵する。
だが人類はどうやってそんな地獄のような高温を作り出したのだろうか?その謎に迫ってみよう。
人類が高温の最高記録を打ち立てたのは、2012年8月13日のことだ。これはギネス世界記録にも認定されている。
その日、スイスにある「欧州原子核研究機構(CERN)」で行われた「ALICE実験(A Large Ion Collider Experiment)」によって作られた温度は「約5兆ケルビン」だ。
この温度は摂氏に換算しても「5兆度」だ。ケルビンと摂氏は273.15度しか違わないので、もはや差を語ることに意味はない。
「アチッ!」とか言うレベルではない。太陽はおろか、夜空に輝く星々ですら比較にならない。
この画像を大きなサイズで見る大型イオン衝突型加速器実験ALICE 検出器 / Image credit:Antonio Saba / WIKI commons CC BY-SA 3.0ALICE実験のスポークスマンだったカイ・シュヴェダ氏は、「現在の宇宙に存在するどんな物質よりも熱い」と、PBS Be Smartで語っている。
「太陽は1500万度、最も熱い恒星でも1億度です。私たちが作り出した温度は、現在の宇宙に存在するあらゆるものの10万倍以上熱いのです」
これはビッグバンからほんの数マイクロ秒後、すべての物質がクォーク・グルーオン・プラズマでしかなかった誕生直後の宇宙の温度とほぼ同じだ。太陽と比べるなら、その30万倍以上もある。
クォーク・グルーオン・プラズマとは
私たちの身の回りの物質は、原子からできている。原子の中心にある原子核は、陽子や中性子でできている。
さらにその陽子や中性子は「クォーク」と呼ばれるもっと小さな粒子が、強い力(グルーオン)で結びついてできている。
クォーク・グルーオン・プラズマは、極限まで高温になるとこの結びつきが外れ、クォークとグルーオンが自由に動き回る状態のこと。ビッグバン直後の宇宙で存在していたと考えられている。
この超高温を生み出す方法は、原理的にはシンプルだ。ただ物体を凄まじい勢いで衝突させればいい。
粒子加速器を使って鉛イオンを光速の99.9999991%にまで加速し、正面衝突させることで莫大なエネルギーを発生させるのだ。
LHC(大型ハドロン衝突型加速器)では、鉛イオンを加速し、全長27kmのリングを1秒間に約1万1,000周も走らせる。
その超高速のイオン同士が正面衝突することで、ほんの一瞬、きわめて小さな空間に、宇宙誕生直後と同じほどの高温が生み出される。
ちなみに鉛イオンが使われたのにも意味がある。相対性理論の有名な式「E=mc²」が意味するのは、質量が大きいほど、それに対応するエネルギーも大きくなるということだ。
鉛イオンはイオンとしては非常に重い。その分大きなエネルギーを持っており、高温を作り出すのに有利なのだ。
この画像を大きなサイズで見るPhoto by:iStock5兆度という温度は熱すぎて、もはやどんな温度計であっても直接測ることはできない。そこで物理学者たちは、その”倍音”を聞いて温度を推測する。
CERNの理論物理学者ウルス・ヴィーデマン氏は、超高温の計測法について、衝突で発生したクォーク・グルーオン・プラズマの「性質を聞き取るようなもの」と当時のニュースリリースで語っている。
目を閉じていても、同じ音を鳴らす楽器の違いがわかるのは、それぞれの音に独特の倍音が含まれているからです
この倍音が、楽器に固有の音色を与えています(ウルス・ヴィーデマン氏)
それと同じように、鉛イオンが衝突するとプラズマ内に波紋が生じ、それが媒体内を伝わることで倍音を作り出す。
それを読み解くことで、衝突の一瞬に生じた温度を推測することができる。
じつのところ、ALICE実験が行われたのは2010年のことだ。だが、その結果の測定・検証に2年が費やされ、そのために公式記録は2012年8月13日付となっている。
ちなみに、そのほんの2ヶ月前となる2012年6月、米国のブルックヘブン国立研究所の重イオン加速器「RHIC」でも4兆ケルビンという当時として最高の温度を生じさせることに成功していた。
だがせっかくの新記録は、CERNのおかげで短命に終わってしまった。
それでも、ブルックヘブン国立研究所の実験に携わった研究者はそれほど落胆していないようだ。なぜなら、2つの実験によってある興味深い事実が浮き彫りになったからだ。
ヴァンダービルト大学の物理学者ジュリア・ヴェルコフスカ教授は、2つの実験には大きな違いがなかったと、2015年に説明している。
LHCの衝突はRHICの25倍のエネルギーを放出しているにもかかわらず、液滴形成の過程にはほとんど違いが見られません(ジュリア・ヴェルコフスカ教授)
つまり一定の温度にまで達してしまうと、それ以上エネルギーを加えても、ほとんど影響がないだろうということだ。
ヴェルコフスカ教授は「一度しきい値を超えると、エネルギーをいくら増やしてもプラズマの性質はほとんど変わらない」と語っている。
この実験は単なる記録更新ではなく、ビッグバン後の宇宙の理解を深める手がかりとなっている。今後もさらなる研究が進めば、宇宙誕生の謎に一歩ずつ近づいていくだろう。
References: News.vanderbilt.edu / Home.cern / Guinnessworldrecords
本記事は、海外の記事を参考に、日本の読者向けに重要な情報を翻訳・再構成しています。



