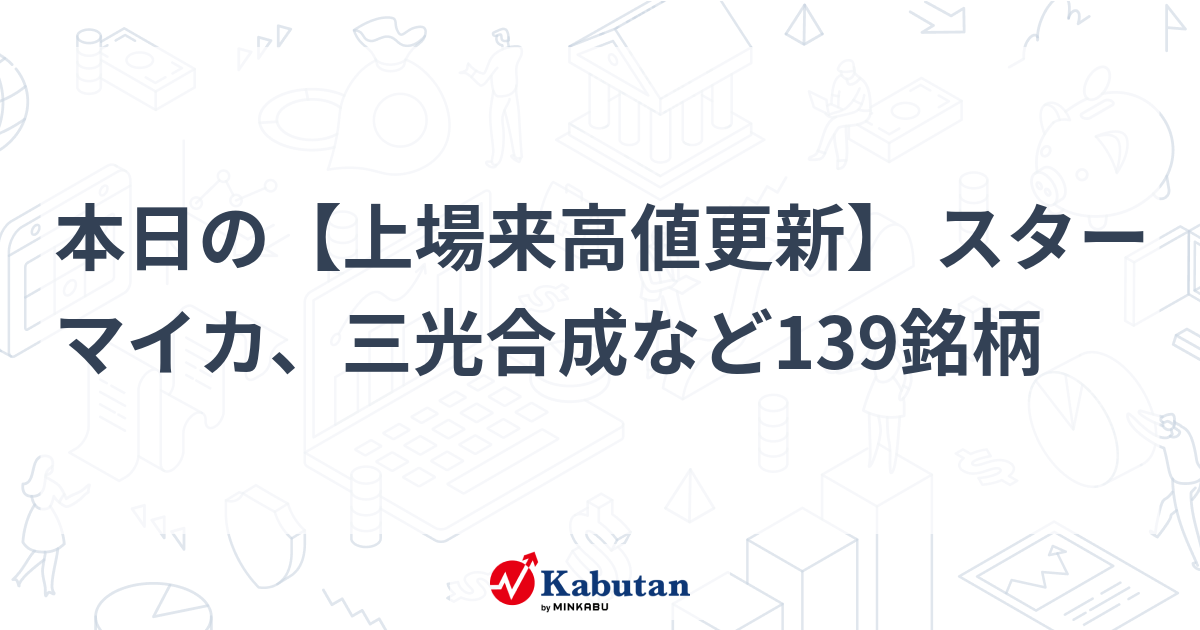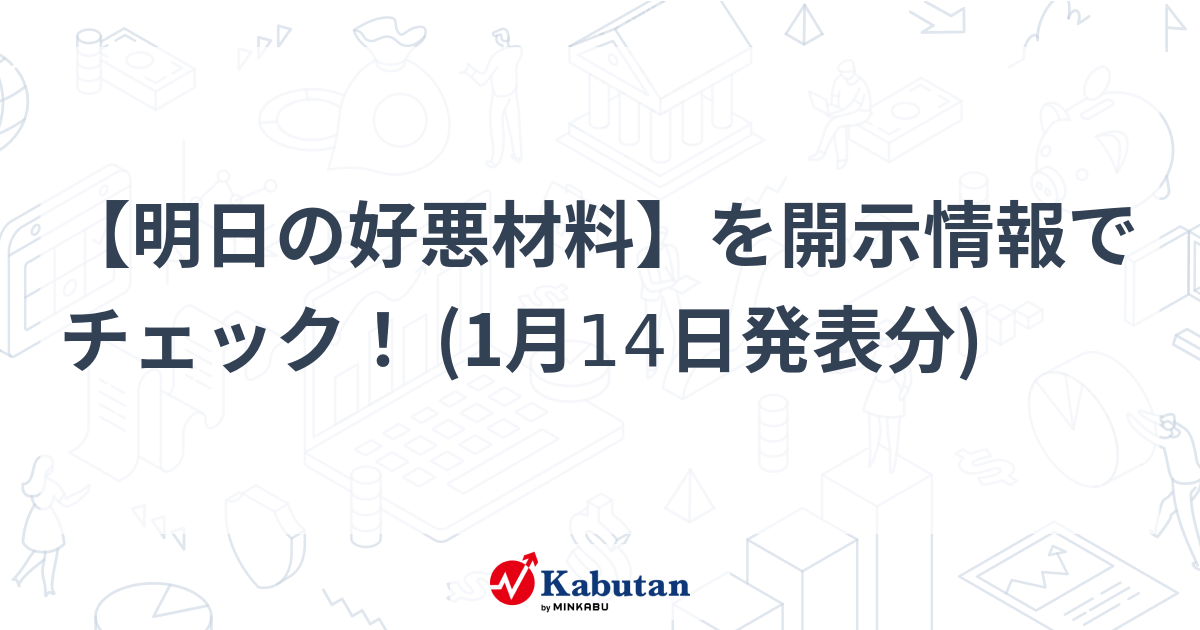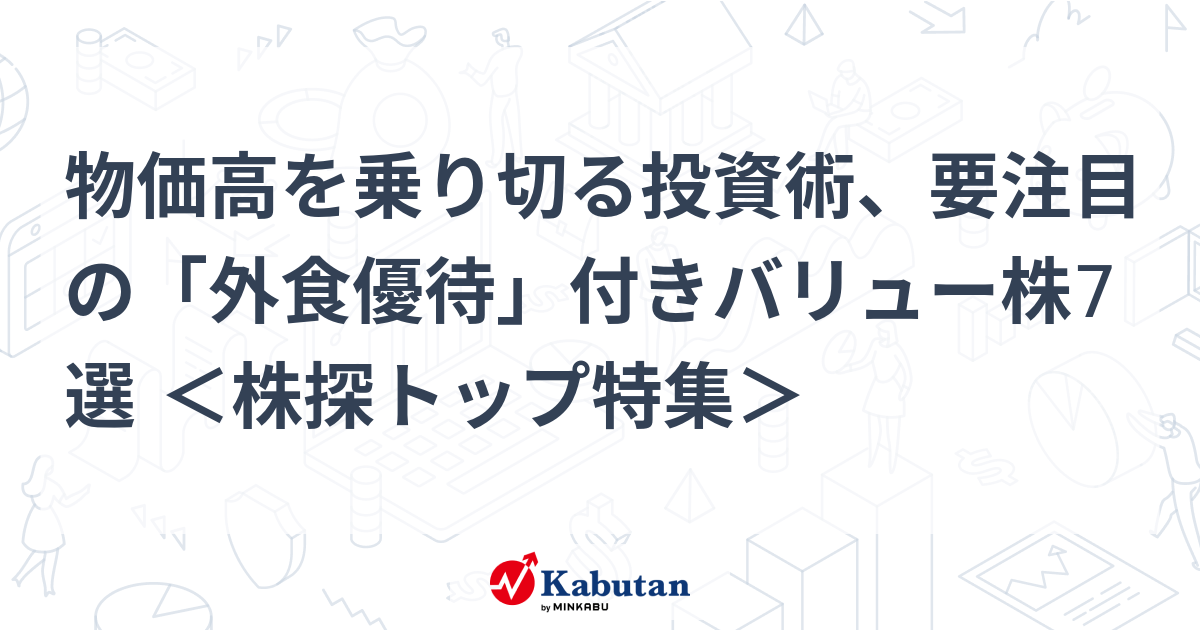知らないことを「ググる」は三流、「コピペ」は論外…現役東大生が「グーグルのかわり」に使っている最新ツール 「答え」を知るためだけに使うのは「もったいない」
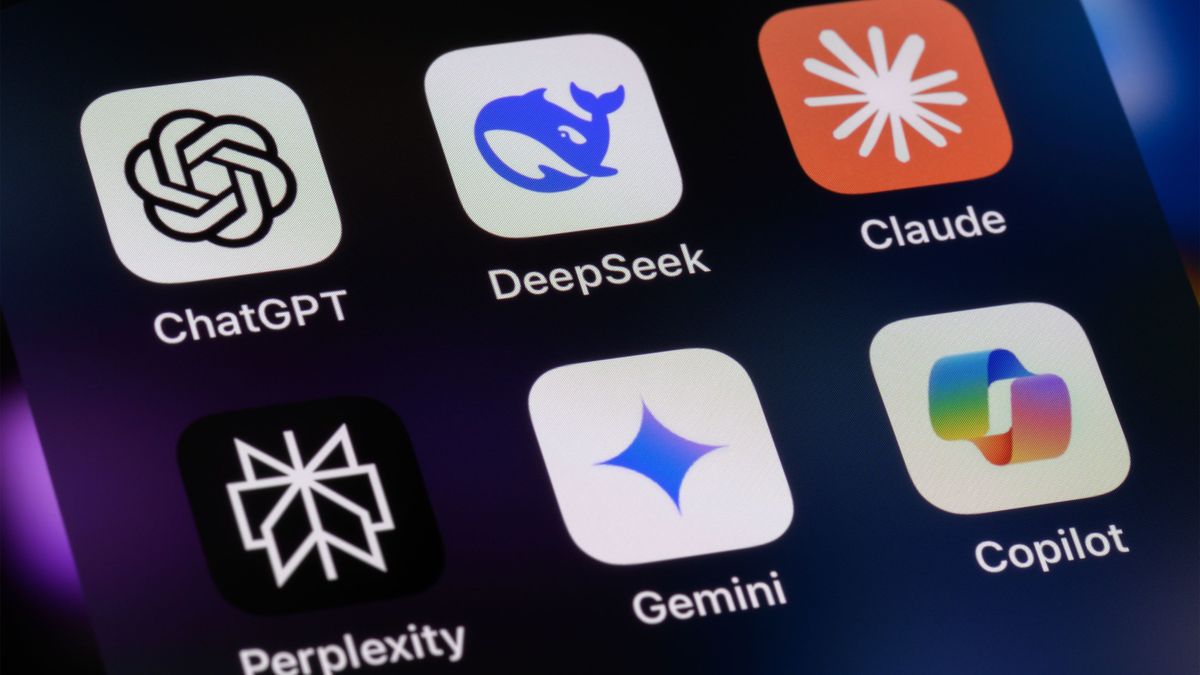
写真=iStock.com/Kenneth Cheung
※写真はイメージです
昨今、「学校の宿題でChatGPTを使う生徒が増えていて、学力の低下が心配だ」「学校は生徒のChatGPTの使用を禁止するべきだ」というような意見を耳にします。ChatGPTは2022年の11月に公開された割と新しいサービスですが、今や様々な生成AIが登場し、生活に浸透し始めています。NHKなどでもChatGPTが世に登場した衝撃についてニュースで報じていました。
親御さんからも「うちの子がChatGPTを使っているんですけど、それを制限したほうがいいんでしょうか?」というような質問をいただくことがあります。しかし最近の東大生たちに話を聞くと、受験生時代にChatGPTを上手に使うことで学力のアップをしている場合が多かったのです。
実際に東京大学では、ChatGPTなどの生成AIは、使用上の注意点を把握したうえで用いるよう学生に求めていますが、利用そのものを完全に禁止しているわけではありません。
また、私立の早稲田大学と慶応義塾大学のホームページを見てみても、“適切な使い方”を求めているようにうかがえます。
では、上手な使い方とは何か――。本稿では、東大生の活用事例をもとに、このChatGPTを使って成績を上げる方法について、お話ししたいと思います。
「レベルに合った問題」を作ってくれる
最近入学した東大生たちに話を聞いてみると、「受験生時代には、ChatGPTから問題を出題してもらっていた」という人が多かったのです。実は生成AIは、問題を生成することもできるのです。
まず、実際の画面を見てみましょう。試しに「中学3年生です。二次方程式の解の公式を使った問題を3問出題してください」と質問すると、このように3つの問題が生成されました(図表1)。
※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はPRESIDENT Online内でご確認ください。
筆者提供
ここでの注意点は、「問題を出題してください」という質問をすることで、答えは後から教えてくれと指示している点です。また、「中学3年生の範囲で〜」とか、「確率の問題を〜」とか、そんな指定もできます。もっと細かく、「偏差値55くらいの公立中学の中3で、確率のテストがあります。どんな問題が出そうかを考えて、出題してもらえませんか?」のように、自分の学力や置かれた状況を細かく指定することもできます。
こうすると、より自分のレベルに合った問題を出してくれるようになり、学力のアップに繋がる問題を解くことができるようになるのです。
Page 2
このような使い方をすれば、勉強中に出てきた問題に対して、応用問題や類似の問題を作ってもらうことができます。つまり、「この問題、難しかったな。もうワンランク低い問題を解けるようになってから再挑戦しよう」と思ったら、その問題の作成をChatGPTに頼るのです。こうすることで、今勉強している内容への理解をより深めることもできますし、間違えた問題をもう一度復習することもできます。
その子のレベルに合わせて問題を出したり、類似の問題を出題したり、ヒントを出してもらったりするというのは、近くに先生や優秀な指導者がいればできることではあります。
でも、家庭教師が四六時中ずっと付きっ切りで指導してくれることはほとんどないでしょうし、親御さんだってずっとその子の側で指導することは難しいでしょう。Google検索でも、ここまで細やかな対応は難しいはずです。そんな時に、お子さんがChatGPTの使い方をしっかりとマスターしていれば、勝手に理解を深めてくれるのです。
ちなみに、ChatGPTは英作文の勉強にも使えます。例えば、自由英作文という出題があったとして「留学についてあなたの考えを述べよ、という英語の問題に対して、こんな回答を作りました。10点満点で採点してください。」というお願いをすることだってできるのです。次の図表4と5をご覧ください。
筆者提供
筆者提供
「答えを書き写す」だけでは学力を下げる
これだけ詳細な解説が、数十秒程度で出てきます。しかも、かなり精度が高いのです。もちろん百戦錬磨の英語の先生から比べれば甘い採点になっている部分や解説が不十分な部分もあるかも知れませんが、しかしそれでもかなりクオリティが高いと言えると思います。人間が添削をしようとすると最低でも30分以上、実際に誰かに頼むとなったらもっと時間がかかってしまいますから、この速度で添削をしてもらえるのは勉強をするお子さんにとっても非常にありがたいツールだと言えます。
一方で、冒頭にも触れたように「学校の宿題でChatGPTを使う生徒がいる」ということが大きな問題になっています。これについては、筆者のカルぺ・ディエムのメンバーも、西岡も「ただ宿題の答えをChatGPTに聞いてその答えを書き写す」ような使い方をしているのであれば学力のアップは望めない、むしろ学力を下げるだけだと考えています。しかし、「宿題にChatGPTを使う」というのは何も、ただ答えを聞くだけの使い方ではないのです。
例えば、解けない学校の宿題を入力して、「この宿題が難しいので、ヒントを教えてください」というお願いをするのは悪いことではないはずです。また、「この宿題が解けるように、類似の問題でもう少し簡単な問題を出してもらってもいいですか?」と自分自身が理解できるようにレベルを下げてお願いすることが悪い、とは言えないと思います。
Page 3
東大生は、このような手法で自分に合った問題を出題してもらうことで、勉強を効率化している人が多いのです。英語でも数学でも、理科でも社会でも、古文単語でも大学の勉強でも、科目を選ばずにこのような使い方をすることができます。
自分の状況に合った問題を生成できる、というのは、生成AIの使い方として非常に効果的だと言えます。親御さんにおすすめしたいのは、お子さんのレベルに合った問題が出題されるように先ほどお伝えした細かい指定の仕方をサポートしてあげることです。生成AIの特性上、入力する情報が多ければ多いほど、お子さんのレベルと問題のレベルがちょうどよく噛み合います。
「でもそれなら、問題集とか参考書を買って、その問題を親が出せばそれで事足りるんじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。実際にそのような質問もかなりの頻度で受けます。しかし、ChatGPTならではの使い方も考慮すると、問題集や参考書には絶対にできないメリットがあります。それは、問題の難易度に対して、細かい調整ができる点です。
例えば、ChatGPTが出してきた問題が簡単すぎるなと感じたときに、「もっと難しい問題を出してください」とお願いすることもできます。実際の画面でやってみると次のようになります(図表2)。
筆者提供
筆者提供
何度もヒントを聞くことができる
このように、問題の難易度は追加で条件を提示することで、調整することができます。文章題や応用問題など、具体的に問題の出し方を調整することも可能なのです。これは、紙の参考書ではなかなかできないですよね。
さらに、難しくてわからないときには、「この問題のヒントを出してください」とお願いすることも可能です。参考書で問題を解いているときにわからない箇所があっても、人がいなければヒントを出してもらうことは難しいです。でも生成AIならそれが可能なわけですね。誰かに頼らなくても、ヒントをもらえるわけです。
しかもヒントを複数個出してもらうことも可能です。「このヒントではまだ問題が解けないので、もっとヒントを出してください」とお願いすることもできますし、「ここまではわかったんですけど、ここから先は難しいです」と聞くこともできます。
また、解説に関しても同様です。「この問題の解説を細かくお願いします」と聞くこともできますし、また逆に「この問題の解説をざっくりでいいのでお願いします」ということも可能です。参考書の解説はワンパターンしかない場合がほとんどですから、このように解説をいくつものパターンで出してもらえるのは大きな利点だと言えます。参考書の解説を読んでも全くわからず挫折してしまう、ということが起きないのです。
Page 4
結局、便利なツールである生成AIをどのように使うか、適切な“うまい使い方”を知っているのかどうか、ということが重要になってくるわけですね。
東大カルぺ・ディエム著、西岡壱誠監修『ぼくたちはChatGPTをどう使うか』(三笠書房)
もちろん、「答え」のみを出すツールとして扱うのであれば、ChatGPTは成績が下がるツールだと断言できます。自分で考える時間が奪われて、問題に対して悩む時間が減ってしまうため、「答え」を知るためだけに使うのであれば、使えば使うほど成績が下がってしまいます。しかし、頭をよくする使い方ができるのがChatGPTの最大の特徴であり、むしろそちらの使い方のほうが“正しい”と言えると考えています。
ChatGPTをはじめとする生成AIに関して、「問題を入力したら答えが出る」程度の理解では、はっきり言って「もったいない」と思います。これだけ便利なツールなのですから、しっかりと“うまい使い方”を教えてあげて、お子さん自身が自分の学習に生かせるようにサポートしてあげるべきだと考えています。ぜひ、参考にしてみてください。