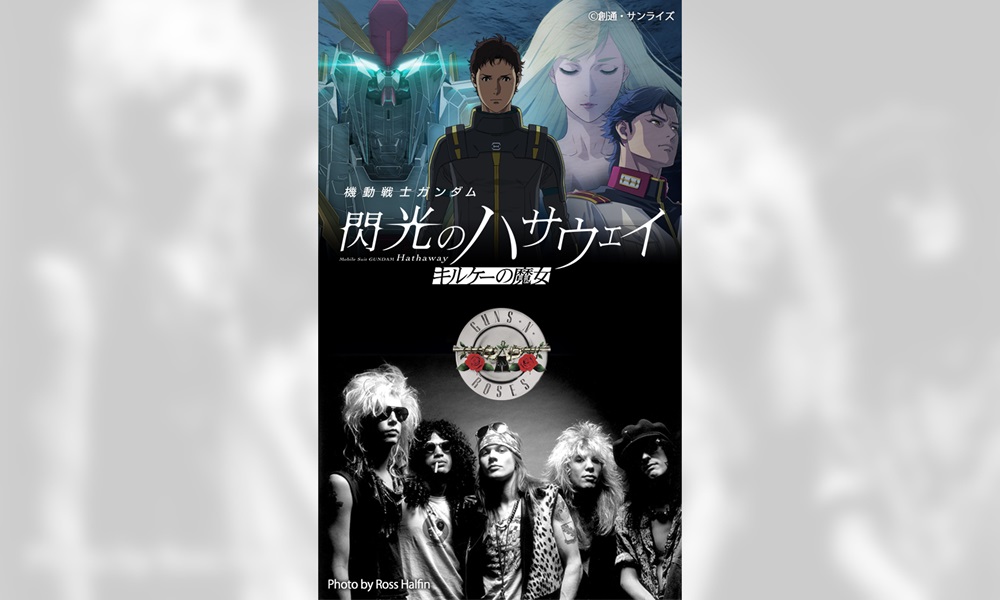『果てしなきスカーレット』の大コケと『国宝』の興行収入記録更新が示唆する「テレビ局と日本映画の幸せな時代」の終焉(東洋経済オンライン)

細田監督の前作『竜とそばかすの姫』は21年7月に公開され、3日間で興収8億9000万円と好スタートを切った。まだコロナ禍に苦しめられていた映画業界で、最終興収66億円をたたき出した。それと比べると、新作は“コケた”といっていい。 ■映画のヒットにテレビ局の力はいらない 『国宝』の記録更新と『果てしなきスカーレット』の不発。この3連休に起きた2つの出来事をつなぎ合わせ、私は痛切に感じた。もう映画のヒットにテレビ局の力はいらなくなったのだ、と――。
昨年10月、『踊る大捜査線』シリーズ久々のスピンアウト作品『室井慎次 敗れざる者』が公開された際、私は「『踊る大捜査線』が日本の映画興行に起こした革命」と題した記事を書いた。 1990年代の日本映画は、ハリウッド映画に押され、風前の灯だった。暗くダサい、世間から見放された存在。そこに98年『踊る大捜査線 THE MOVIE』が公開され、テレビドラマを映画化すればメガヒットになることに、映画業界もテレビ局も驚いた。
さらに2作目が信じられないヒットになり、その後、どの映画も破れなかった興収173億円を稼いで金字塔になった。『踊る』シリーズに続いてフジテレビは次々と映画を世に放ち、他局もそれに続いた。 いま思い返せば不思議だが、当時はテレビドラマを映画化すればメガヒットになるなんて誰も考えもしなかった。それが00年代には当たり前になり、日本映画の興収が洋画を超えるのが常態化していった。もう誰も日本映画を「暗い」とは言わない。むしろ、ハリウッド映画のほうが徐々に日陰に追いやられていった。
Page 2
だが10年代に入ると、テレビは徐々にネットに押され、以前ほど映画に製作費を出せなくなった。一度は映画界を牛耳ったといっていいテレビ局の影響力は後退していく。 16年公開の『シン・ゴジラ』『君の名は。』が立て続けにヒットしたとき、はっきりと潮目が変わった。いずれも東宝が、前者は庵野秀明監督、後者は新海誠監督をフィーチャーして製作した映画で、テレビ局はまったく関わっていない。テレビ局とは関係なくメガヒット作品が生まれうるのだと業界関係者は認識させられた。
それでも、ドラマの映画化は続いていた。ヒット作も出ていた。だが、以前のように次々にヒットはしない。むしろ、興行が振るわない映画のほうが増えた。テレビドラマを映画化する意味が何なのか、わからなくなっていた。 ■テレビ局映画と『国宝』は何がどう違ったか テレビ局映画には欠点もあった。準備にお金と時間をかけない。テレビドラマの、次から次に枠を埋める作り方を踏襲していた。 ハリウッドでは、脚本が「商品」として出回り、いいシナリオは億単位の金額で映画化権を買い取られる。キャストや監督が決まると、脚本にさらに手を加える。優れた脚本が映画になって世に出るまで、何年もかかる。
テレビ局は、そんな作り方をしなくてもドラマを仕上げてしまう。そして、同じように映画も作る。芝居も演出もテレビドラマのやり方だ。主演も、日々テレビに出ているタレントたち。ドラマでするように、大げさに泣いたり怒鳴ったりする。日本映画はテレビ局に救われたが、同時に日本映画が「テレビ化」してしまった。 『国宝』は映画監督として上質な作品を撮り続けた李相日氏が、いつか歌舞伎の映画を作りたいと願って出会った原作だった。その映画化に向けて、脚本作りに2年を費やし、主演の吉沢亮と兄弟役の横浜流星は1年半かけて歌舞伎を稽古したという。テレビ局が絶対やらない作り方を、プロデューサーの村田千恵子氏が通した。
Page 3
製作幹事はアニプレックスと、その子会社であるミリアゴンスタジオ。アニプレックスはアニメ『鬼滅の刃』をプロデュースした会社だ。つまり、『鬼滅』のヒットが『国宝』のクオリティーを生んだといえるのかもしれない。「本物の映画」が漂わせる神々しさは、テレビ局の作り方では出せないだろう。 それでも、映画界の誰も『国宝』が『踊る』の記録を抜くとは思わなかったはずだ。私も、あの時代にあったフジテレビの“勢い”がないと、抜くのは無理だと考えていた。だが『国宝』は、静かに静かに、だが少しずつ着実に記録に近づいていった。
興収が100億円を超えたとき、一部で「ひょっとして抜くのでは?」と言い出す人が出てきた。それでも私は、そんなことがあるはずがないと考えていた。それがついに『踊る』を抜いたことは、時代に対する重要なメッセージと受け止めてしまう。 ■劣化してしまった「日テレ映画」ヒットの法則 くしくもフジテレビが前代未聞のスポンサー離れに見舞われ、過去の栄光がズタズタになった今年、そのフジが打ち立てた金字塔が興収首位から転落したのは、大きな意味がある。テレビ局はもう映画をヒットさせる力を失ったのだ。
前作から一転した『果てしなきスカーレット』の不振にも、どうしても同様のメッセージを重ねて見てしまう。 細田守作品を、いわゆるテレビ局映画と同列で論じてしまうのは失礼ではある。私は00年に幼い長男を初めて映画館に連れていって『デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム!』を見たときの衝撃を忘れない。明らかな「作家性」を感じ、その後の監督作はすべて劇場で見ている。 09年の『サマーウォーズ』以降は、日本テレビが「ジブリの次」のクリエイターとして育ててきた。『踊る』のようなテレビの作り方で作る映画とは違い、日テレは細田監督のパトロンのような存在だった。新作の企画をサポートし、劇場公開時には過去作品をテレビで放送して、局を挙げてバックアップしてきた。
Page 4
今回も、公開2週前から「金曜ロードショー」で『おおかみこどもの雨と雪』『バケモノの子』『竜とそばかすの姫』が立て続けに放送された。ジブリ映画で日テレが培った、新作映画のバックアップ手法だ。 こうして『果てしなきスカーレット』はメガヒットが約束された映画、のはずだった。どんな内容かより何より、日本で最も力のあるテレビ局たる日テレがこれだけ推しているし、細田守ブランドは確固たる存在になっている。『TOKYOタクシー』でキムタクが主演し名匠・山田洋次氏が監督をしたとしても、『爆弾』が比類なき面白さで爆走していても、「細田守の新作」が1位でないはずがなかった。
私は連休中、風邪で寝込み、泣く泣く映画館に行くのを見送った。枕元のiPadで『果てしなきスカーレット』について世間の人々の感想を眺めると、ほとんどが失望投稿だった。口きたなくののしる人も目についた。「初日に行ったら観客は自分一人だった」とぼやく人もいた。失敗しないはずの映画が、失敗してしまったようだ。布団の中で細田守ファンとして打ちひしがれた。 ■映画界が極めて健全で真っ当な世界になった どうやら、日テレがどれだけ推しても、人々の口コミにはあっさり敗退する。そういう時代になった。テレビ局はもう、映画をヒットさせる力などない。テレビ局が映画界を救ったのはまちがいないが、その頃のような関係ではもはやない。
「本物の映画」は、テレビ局の力に頼らなくても、驚くようなヒット作になる。そんな時代になった。才能あるクリエイターも、口コミで失敗作の烙印を押されると、テレビ局がいかに推しても観客は来ない。 これは、映画界が極めて健全で真っ当な世界になった、というだけのことかもしれない。これからの映画をヒットさせるのは、映画そのものの力なのだ。
境 治 :メディアコンサルタント