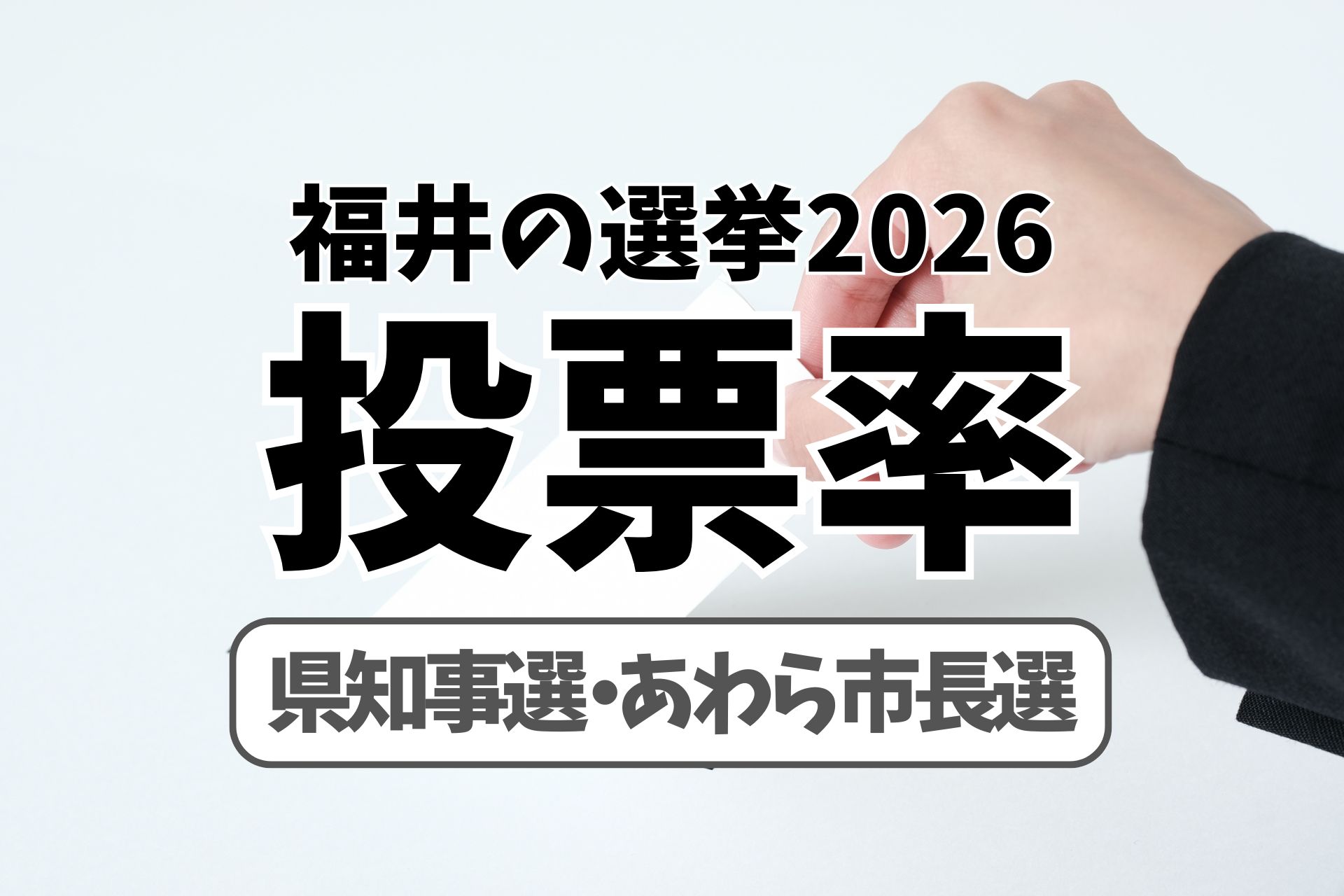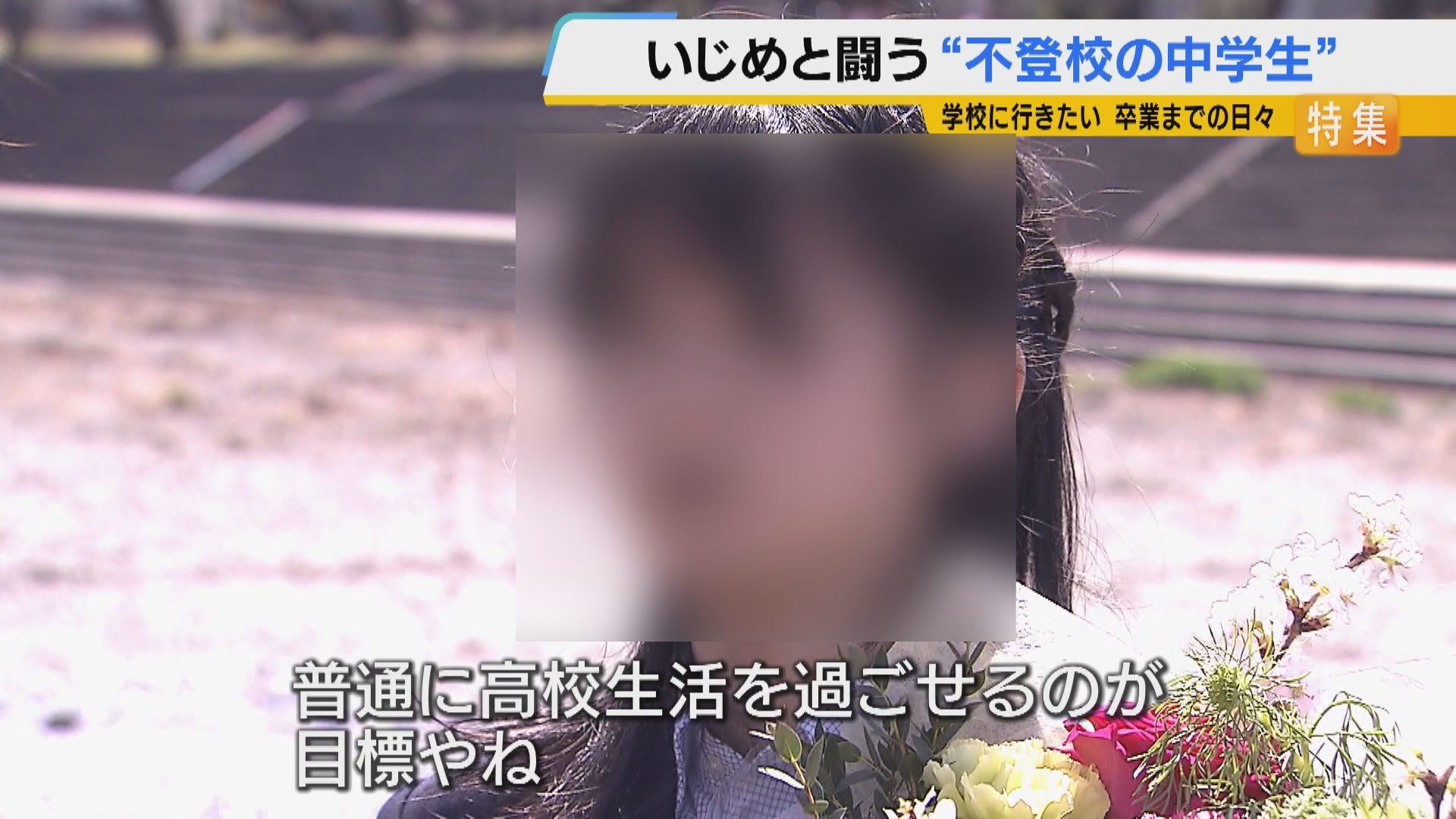流動化し続ける日本政治の新しい日常
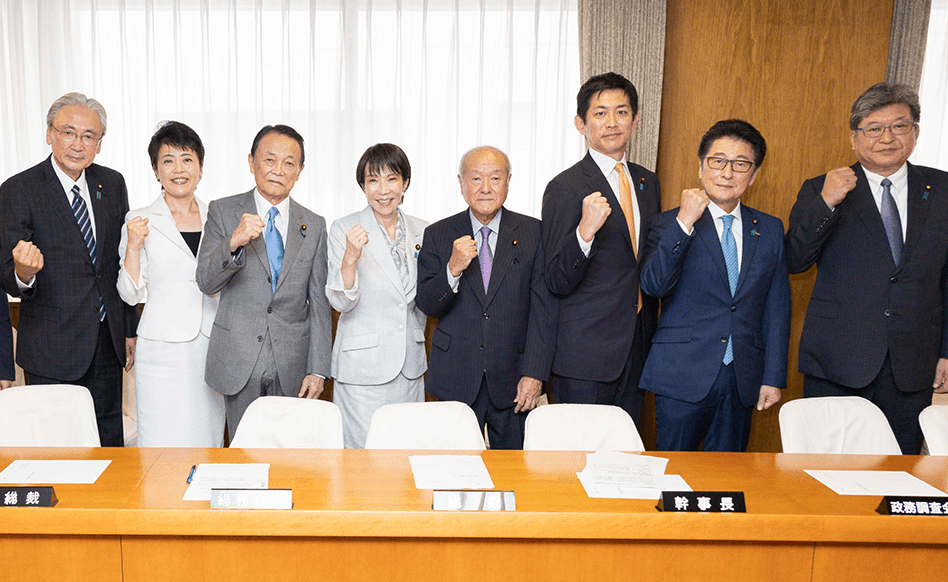
私が、「日本政治はいよいよ本格的な流動化の時代に入ったか」という題名の記事を書いたのは、参議院選挙前の7月上旬だった。
選挙前の世論調査が、参政党などの躍進と、自民党の低迷を、示していた。この状況の構造的な背景に、自民党をはじめとする既存の政党の支持者が、高齢者に偏っている事実がある。
日本が極度の停滞を見せているのにもかかわらず、既存の政党の獲得議席数に大きな変化がなかった背景には、極端な少子高齢化の現象をへた人口構成と、その反映としての高齢者優遇の社会保障制度などがあった。
しかしどんなに極端な少子高齢化であっても、支持者層が高齢者に偏っていたら、やがて勢いが停滞していくのは必然である。
自民党が高市早苗総裁を選出した。支持離れしている若年層が右派層であるとみなして、右旋回を選択した。参政党に取られた票を取り返し、第二次安倍政権時の栄光を再び、という思いだろう。だがそのように簡単に事が進むとは限らない。
高市総裁の下、自民党は結束を誓い合うはずだったが 自民党HPより
公明党が連立政権から離脱することを決めた。細部に関する分析は色々あるとは思うが、高市総裁の自民党についていっても、党勢の回復は望めない、ということだろう。支持者が高齢者に偏っている政党が、生き残りのための手段を模索した結果、過去の「勝利の方程式」を捨てざるを得なくなった。
自民党の高市総裁は、公明党に譲っていた選挙区にも自民党の議員を立候補させる方針を表明した。これは一方で参政党の票を奪いながら、他方で公明党の票を譲り受けていくという二正面作戦であり、いばらの道だろう。
そもそも国会で総理に選出されるかどうかも不明な現段階では、選挙戦略を考えることなどできるはずもない。自民党単独では総理になれないからだ。仮に高市氏が総理になるとして、どのような連立組み合わせで総理になるのかは、全くわからない。
高市氏が自民党総裁に選出された後、過敏に反応した為替・株式市場は、高市総理の可能性が減退したことによって、反転を余儀なくされるようだ。しかしそれでは、次に何が起こると予測すればいいのかというと、全くわからない。
国際政治の動向分析などでは、構造的な事情を理論的に把握して、長期的な見通しを立てる。国内政治でも同じと言えば、同じだ。しかし変転する日本の政党を基礎単位にして、日本の国内政治の長期的な動向分析を行うのは、非常に難しい。
長期的な見通しとして、「流動性が高い」ということを、若年層の支持傾向を、人口動態を兼ね合わせながら見ていくことはできる。おそらくは第二次安倍政権のような安定政権は、過去の遺物となり、非常に流動性の高い状況が続くのではないか。
今まで惰性の常識感覚で進めていたことが、なかなか進めにくくなっていく状況も予想される。他方、だからといって何か新しい展望のある突破口が見えてくる可能性があるかといえば、今のところはそれも乏しいと言わざるを得ない。
7月7日に書いたブログ記事を、私は以下のような文章で結んだ。
「今の日本人にまず必要なのは、閉塞感の中で、なお政治の流動化に耐えていく心構えであると思われる。」
現状を見ると、ますます同じ文章を繰り返したくなる。
■
国際情勢分析を『The Letter』を通じてニュースレター形式で配信しています。
「篠田英朗国際情勢分析チャンネル」(ニコニコチャンネルプラス)で、月2回の頻度で、国際情勢の分析を行っています。
■