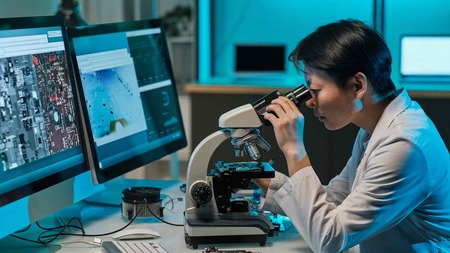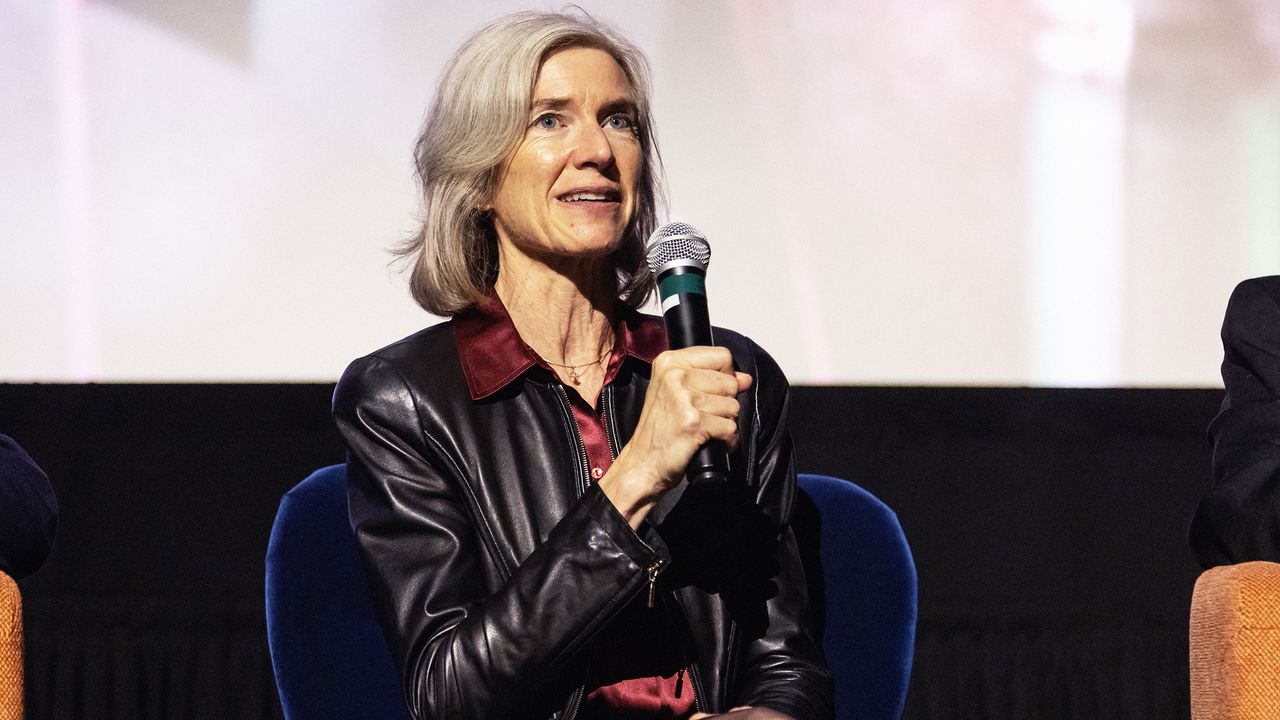男性の主観的幸福度は22歳頃にいきなり下がる…「学生→社会人」のギャップを乗り越えられる若手の共通点 「部活のリーダー経験」は会社ではほとんど役に立たない

学生が社会人に感じるギャップには、それまでの経験が生かせない、というものもあるだろう。
例えば、学生時代に部活やサークルでリーダーだったとしても、社会人になればそうしたリーダーの経験はほとんど役に立たないことに気づく。
学生の活動は年齢的にもせいぜい上下数歳の幅しかないが、社会人になれば自分の親よりも年長の人とも付き合わなければならない。
もちろんそうした場合に学生時代のリーダーシップが生かせるとは誰も思わないだろう。
こうした経験による差は、流動性知能と結晶性知能として説明されている。
流動性知能とは計算能力や推論能力のことで、簡単にいえば学力だ。当然20歳代前半がピークで、最近ではAIやデータサイエンス、プログラミングなど若くても専門性が生かせる分野も多い。
結晶性知能とは、過去の経験や学習によって蓄積された知識のことで、語彙が豊富で、教養があり、深い洞察力を持つようなことを指す。
商品・サービスに対する知識、業務や業界に関する知識など、新入社員には身につけるべき流動性知能はたくさんあり、経験に基づく結晶性知能では上司や先輩には到底太刀打ちできない。
「斜めの人間関係」があるといい
学生から社会人になると人間関係は一度リセットされ、再度人間関係を構築していくことになる。このとき、一緒に入社した同期との人間関係は長く続くことも多く、大切にしたほうがいいことはいうまでもない。また、社会人になった時の最初の上司の影響もとても大きく、いわゆる上司ガチャと呼ばれているらしい。
しかし、そうした与えられた人間関係だけではなく、直接仕事の関係はなくてもいろんなことを相談できるような斜めの人間関係があるといい。
組織にいると、研修やちょっとした飲み会や、仕事関係の打ち合わせなどで、自分の所属する組織以外の人と接する機会は意外と多い。
写真=iStock.com/kazuma seki
※写真はイメージです
そうして出会った人のなかで、この人は面白いな、と思うような人が居れば、自分から積極的に連絡し、関係を作っていくことは将来の大きな財産になる。
こうした斜めの人間関係だけではなく、組織の中で、「誰が何を知っているか」「困ったときには誰に聞けばいいか」を知っていることはとても大事なことだ。
これを専門用語ではトランザクティブ・メモリーといい、集団の中で人間関係を通じて形成される組織全体の記憶システムのことを指す。
仕事の人間関係なんてドライにやっていけばいいと考えている若い人は多いようだが、人間関係とは飲みに行って仲が良くなる、といったことだけではなく、仕事を円滑に進めていくためには必須のものだ。
そして、トランザクティブ・メモリーという人間関係は、人によって、そのネットワークは違い、当然だが多くのつながりがある人のほうが仕事では有利になる。
Page 2
よく「何をやるかより誰とやるか」が大事だと言われる。これは「やりたいこと」が明確にあるひとにはわかりづらいかもしれないが、「やりたいこと」が特にない場合には、とても大切な考え方だ。
何しろ、「やりたいこと」がないのだから、何をやるかを決められないからだ。
「やりたいこと」がなければ、「誰とやるか」を考えればいい。できるだけ楽しくやること。一生懸命やれること。誰といれば、そうなるかを考えると、そもそもの働く場を選ぶ明確な基準ができる。
学生の就活にしろ、社会での人事異動にしろ、外注先の選定にしろ、転職にしろ、起業にしろ、「やりたいこと」が無ければ「誰と働きたいか」を考えればいいわけだ。
そして、同じことをやっていたとしても、誰とやっているかでストレスも満足感も大きく変わる。
「学生→社会人」のギャップに受けるショック
個人が組織の一員になるためのプロセスのことを組織社会化というが、その最初の関門は学生が社会に出た時にある。
学生の間は多少の上下関係はあるものの、同級生としての横の人間関係が中心だったものが、社会に出ると上司部下の上下の人間関係に一気に変わる。
また、勉強の多くは個人プレイだが、社会に出れば仕事の多くはチームプレイになり、新入社員は一番下っ端で自己裁量の余地はあまりない。
一番大きいのは学生の特権を失うことだ。
・学生には授業にでない、グループワークに参加しない、という自由がある。(社会人には与えられた仕事をしない、という自由裁量はない)
・学生は誰にも命令もできないが、誰からも命令されない。(社会の組織は上司が命令し、部下は命令を実行する枠組みになっている)
・学生は学費を払うお客さんである。(社会人は働くことで給料を貰う)
こうした学生から社会人になるときのギャップによるショックは男性のほうが大きいようで、連載の9回目で示した男女・年齢別の主観的幸福度のカーブを見ると、男性は22歳から24歳にかけていきなり主観的幸福度が下がることがわかっている。
図表=筆者作成
Page 3
近年は若者が草食化しているとか、お金よりもやりがいだとか、社会に貢献する仕事をやりたいとか、社会課題の解決に繋がるような仕事をしたいとか、そういった話もよく聞く。
その一方で、「偉くなりたい」「お金を稼ぎたい」「有名になりたい」といったような世俗的な動機を語るのは、格好が悪い、といった風潮があるようにも感じる。
しかし、長く組織で働いてきて、経験的に感じるのは、結局は、働く動機の強い人が生き残る、ということだ。
それが社会問題の解決に対する情熱だろうと、単純な金銭欲、出世欲だろうと、家族のため、単なる興味関心でも、何でも構わない。
働く動機の強い人は、働く対象を限定的に考えない傾向が強いように思え、諦めも悪いように思える。
特に、新社会人には、一度、自分の働く動機を改めて考えてみることをオススメする。
その働く動機は、誰にも話す必要はないし、格好がいいとか悪いとか、そういった外からの評価も関係がない。
その理由がなんであれ、働く動機が強ければ、社会の荒波もきっと乗り越えていけるだろう。