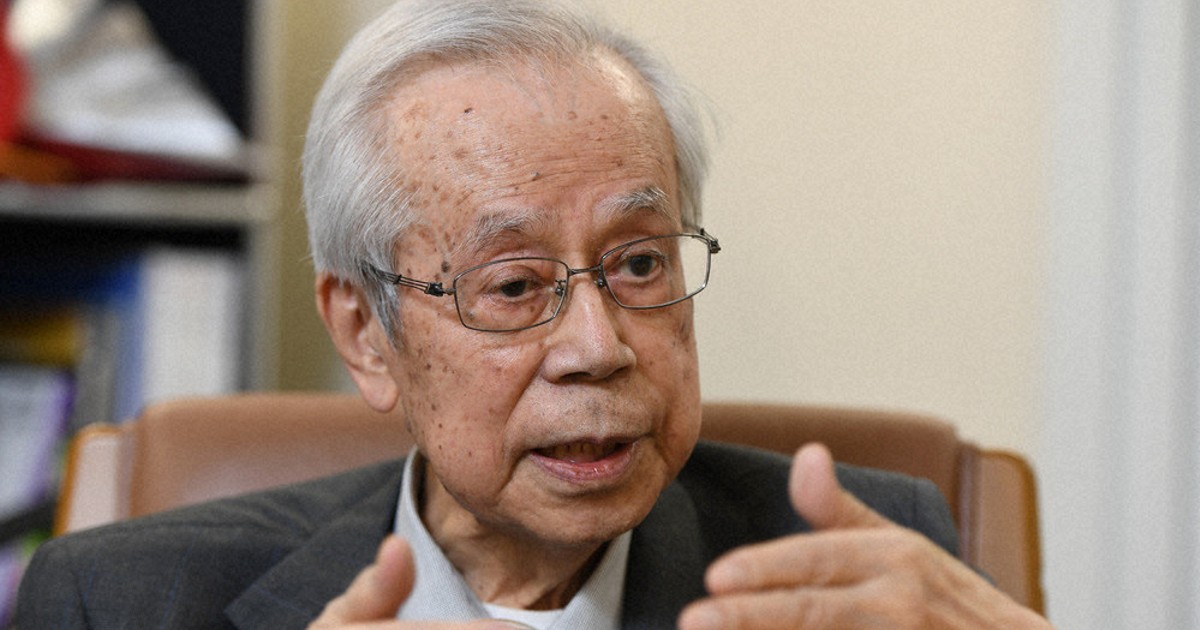「2次関税」とは何か、トランプ氏がインドに課すと表明-QuickTake

トランプ米大統領は政権2期目で、幅広い目標を実現するための手段として関税を使ってきた。
製造業の国内回帰や海外市場へのアクセス強化、連邦歳入の積み増し、さらには政治的盟友であるボルソナロ前ブラジル大統領の訴追に対する報復措置としてブラジル政府に圧力をかける目的にも用いられている。
今回は「2次関税」と呼ぶ新たな手段を使い、各国に米国が敵視する国から距離を置くよう求めている。
トランプ氏は6日、インドからの輸入品に対する2次関税を課すと発表した。発効は21日後。すでに発表されている対インド関税25%に加えて、ロシアから原油を購入していることへの制裁としてさらに25%を上乗せするという。
2次関税とは
2次関税の狙いは、ある国を対象とした制裁措置を通じて、別の国の行動に影響を与えることにある。この考え方は、いわゆる「2次制裁」とも似た構造を持つ。
2次関税と2次制裁の違いは
米国による2次制裁は、ある対象への1次制裁の効果を他国にも波及させることで、制裁の影響力を増幅させることを目的としている。
米国の法域外で1次制裁が科される国や企業・個人との商取引を制限し、企業や銀行、個人に対し、制裁対象との取引を続けるか、米国との関係を維持するかの二者択一を迫る。
1次制裁が罰金や米国内資産の差し押さえといった強制力で執行されるのに対し、2次制裁は、米国の金融システムが国際経済の中核を成し、ドルが基軸通貨として広く用いられているという影響力に依存している。
違反した場合、米国からの輸出規制を受けたり、米財務省の「特別指定国民およびブロック対象者リスト(SDNリスト)」に掲載されたりする可能性があり、これにより米国民との取引が禁じられる。
一方、今回トランプ氏がインドからの輸入品に課すとした2次関税は、1次関税の効果を増幅させるものではない。ロシア産エネルギーに対する米国の関税は、ロシアによるウクライナへの全面侵攻を受け、2022年に輸入自体が禁止されたため、もはや意味をなしていない。
そのため、インドに対して課される追加の25%関税は、インド政府にロシア産原油の禁輸措置を取らせ、最終的にはロシアに戦争をやめさせることを狙った圧力とみられる。
トランプ氏は今年3月、ベネズエラから原油を購入する国からの輸入品に関税を課す仕組みを設けた。同氏は、ベネズエラ政権が米国の国家安全保障に脅威をもたらしていると述べている。
航行中の船舶には識別用のトランスポンダー(送受信機)が搭載されており、衛星を通じて第三者がリアルタイムでその位置を追跡できる。これにより、政府関係者を含む分析担当者は、例えばロシアで原油を積み込み、インドで荷降しを行うタンカーの動きを追跡することが可能になる。
原題:What’s a ‘Secondary Tariff’ Like the One Trump Imposed on India? (抜粋)