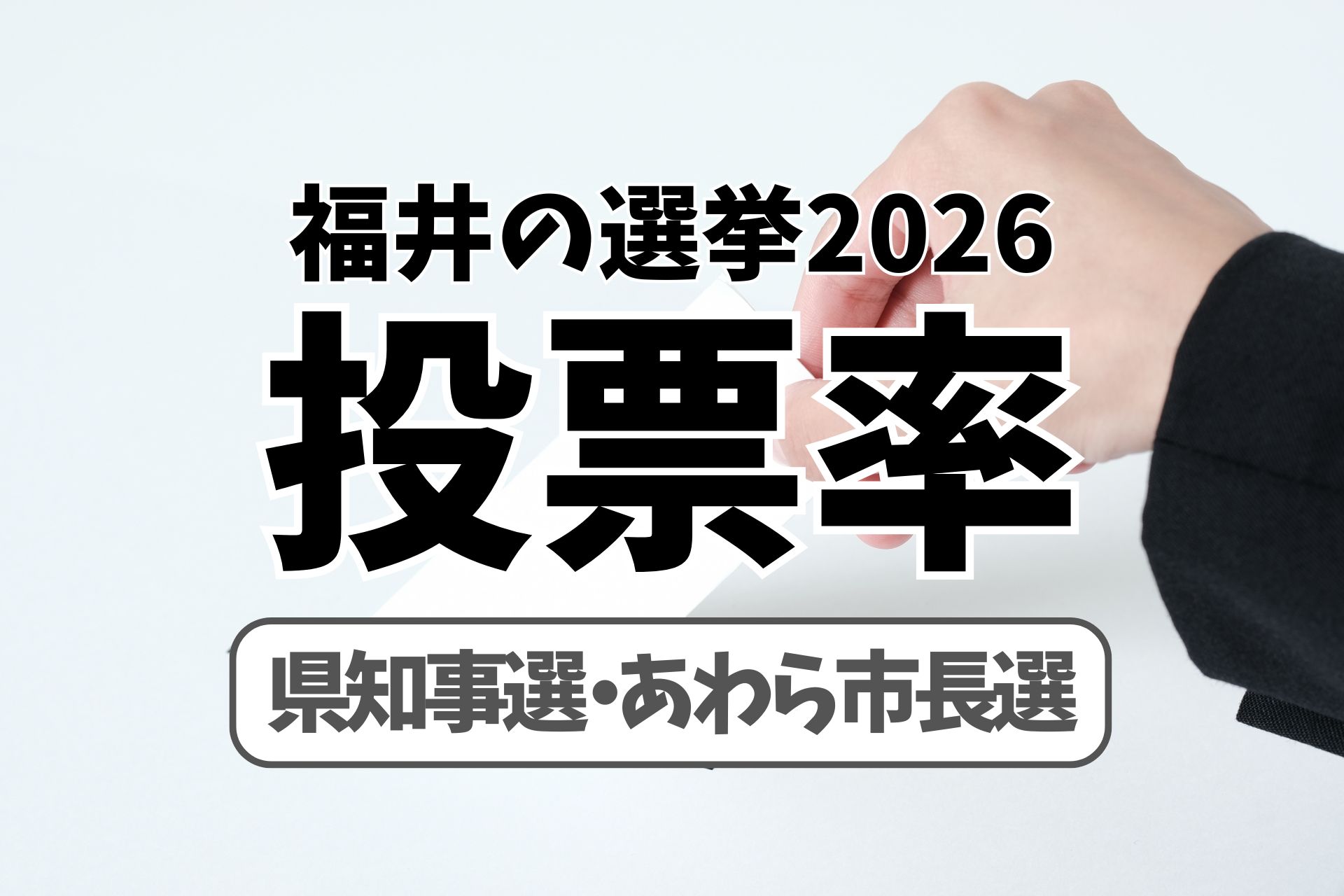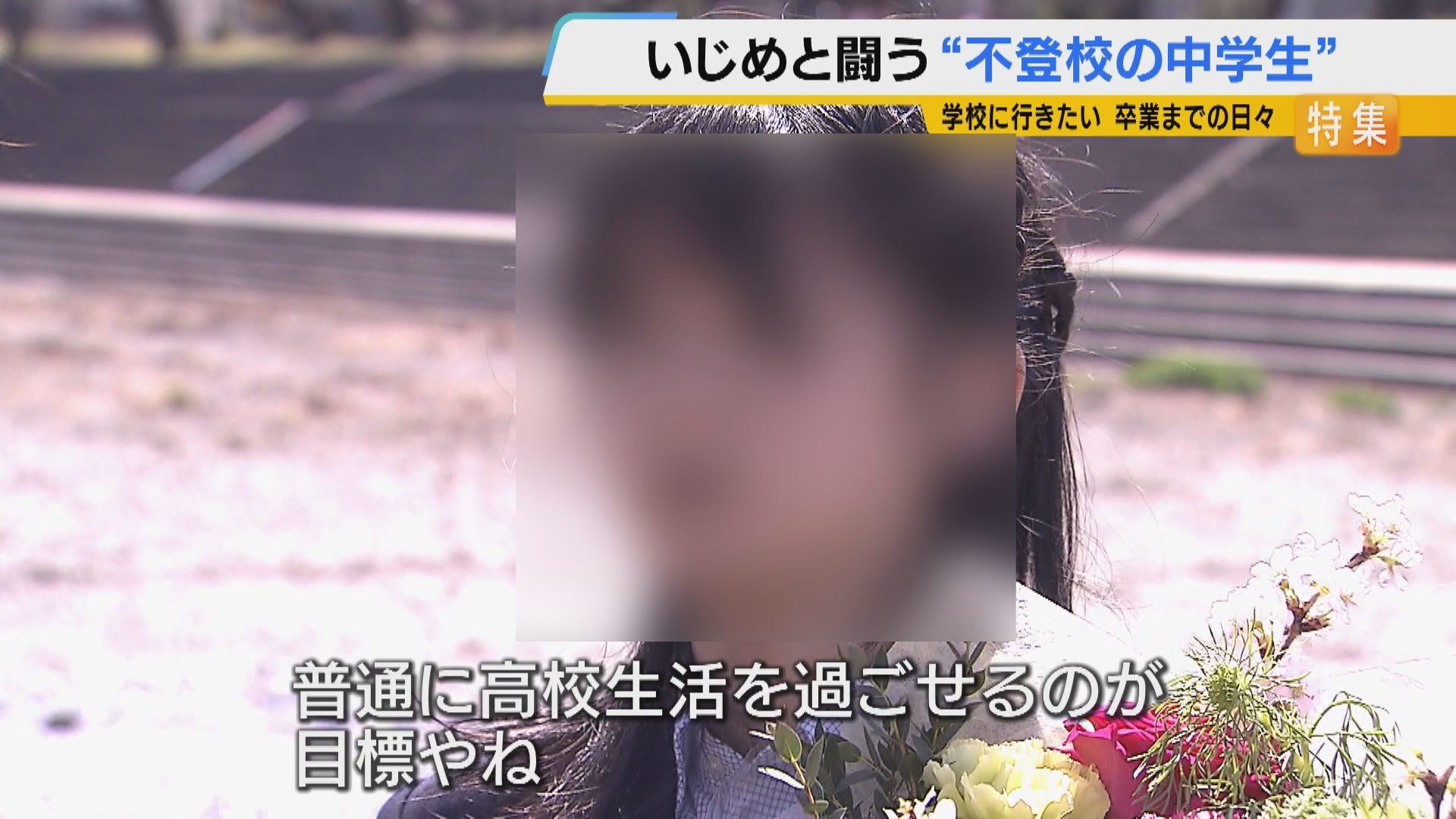第104代首相に高市早苗氏:識者はこうみる

[東京 21日 ロイター] - 自民党の高市早苗総裁が21日午後、衆参両院の指名選挙で第104代首相に選出された。女性の首相は初。高市氏は直ちに組閣に着手、皇居での親任式・認証式後に日本維新の会との連立政権が発足する。
市場関係者に見方を聞いた。
◎参院は決選投票、厳しい政権運営を暗示
<法政大 河野有理教授(政治思想史)>
首相指名選挙が衆院では1回目の投票で過半数を獲得できたものの、参院は1回目で過半数を獲得できず決選投票に持ち込まれ、今後の厳しい政策運営を暗示している。自民と維新が連立しても衆参で過半数に達しておらず、少数与党として厳しい政権運営になりそうだ。
自民と維新は政権合意書を取り交わしたが、維新は閣僚を送り込んでおらず、腰が引けていて今後が心配される。
自自公など過去の連立政権も誕生後1年はしっくりしないことが多く、時間とともになじむもの。しかし自民と維新の枠組みが自公のように強固になるのかみえにくい。自民が関西をあきらめ、維新が全国政党化をあきらめることによる消極的な連立にみえる。
もっとも初の女性首相の誕生は画期的。日本を取り巻く地政学リスクを考慮すれば、新政権が右寄りになる他に選択肢はない。野党も今後安全保障や原発などのエネルギー政策で現実路線に舵を切らなければ政権は取れないだろう。
金融市場における高市トレードの今後の展開は正直わからない。高市氏の積極財政は株高に振れる材料だろうが、財政は国債の(信認、持続性の)問題があり、吉と出るか凶と出るか不透明だ。
◎野党にらみの政策運営続く、大型財政想定せず
<農林中金総合研究所 南武志 理事研究員>
日本維新の会を入れても衆参ともに与党の勢力は過半数に届かず、野党の共感を得られないと政策を進められない。石破茂前政権同様、あるいはそれ以上に厳しい船出になる。
高市早苗新首相は積極財政論者で知られ、アベノミクスの再来を期待する向きもあって株価は上昇で反応している。だが、実際は皆が期待するほど財政をふかしての政策運営とはならないだろう。
財政が悪化の一途をたどる中、仮に高市氏が財政をふかしたくても、自民党の麻生太郎副総裁と鈴木俊一幹事長の元財務相の2人がそれを許さないだろう。新政権で財務相に就任すると報じられている片山さつき氏の政策スタンスはあまり情報がないが、財務省の元主計官でもある同氏がいながらバラマキに走ることはないだろう。
金融政策については、高市政権では日銀を政府に従属させようとの意思は今のところ見られない。米国の様に政策運営で、政府と中央銀行が対立することにはならないだろう。
◎女性首相は画期的、定数削減が試金石
<政治評論家 田村重信氏(元自民幹部職員)>
男尊女卑的文化の残る日本で米国よりも早く初の女性リーダーが誕生したこと自体が非常に画期的。これを契機に日本の各界で女性の活躍が増えることが期待される。
首相指名選挙では衆院の1回目の投票で過半数の得票で首相に選出され、少数与党のため決選投票を経て首相に選ばれた石破茂前首相よりも政権基盤は安定しているといえる。
報道されている閣僚人事をみると、外相に茂木敏充元自民党幹事長、経済産業相に日米交渉を担当した赤沢亮正前経済再生相など適材適所で良い感じだ。防衛相に就任すると報じられている小泉進次郎前農相も米国戦略国際問題研究所(CSIS)研究員を経験するなど米国人脈もあり適任だ。片山さつき財務相は、歯に衣を着せない強さが持ち味で活躍を期待したい。
今後、国会運営などをスムーズにこなせば早期衆院解散による党内基盤の強化も期待できる。政権の試金石は維新との連立交渉の結果取り組むことを決めた議員定数削減だ。物価高などで国民の不満が高まっているなかで、国会議員が維新流の身を切る改革を実現できれば世論の支持も高まる可能性がある。
◎バランス人事でカラー抑制、日銀に介入なさそう
<野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英氏>
日本維新の会は小さな政府、効率的な政府を志向する政党で、積極財政・金融緩和を主張してきた高市早苗総裁とはある意味対極にある政党。維新との連携により高市カラーが抑制されバランスの取れた経済政策運営が期待される。
報道されている閣僚人事をみても、防衛相の小泉進次郎氏はいわゆるタカ派ではない。財務相になる片山さつき元地方創生担当相は、積極財政論者ではあるが極端ではない。
このため、石破政権よりはやや積極的だが極端ではない財政政策運営が期待される。維新は日銀の独立性も重視しており、金融緩和の継続をめぐり政権が介入する可能性は少ないのでないか。
為替・債券市場での高市トレードは修正されつつあり、一時期ドル/円153円台まで進んだ円安も足元151円台にとどまっている。株式市場はご祝儀の期待も含めまだ高水準が続いているようだ。
◎インフレ下のアベノミクス継承に疑問、自維協力に課題
<愛知学院大 森正教授(政治学)>
政治学の連立政権モデルの議論では、政策の似ている自民と維新が連携して過半数を目指すのは合理的だ。
しかし、現状の自民と維新は衆参両院で過半数を獲得できていない。安定した政権運営を行うために委員会で委員長ポストを占めるには過半数以上の議席が必要。
自民と維新の候補者調整は、大阪の小選挙区では楽だが、他の地域での選挙協力は難しい。維新には公明党のような集票組織がないため維新が候補を取り下げても自民候補が勝てる保証は全くないためだ。
さらに、維新側では執行部の党運営に反対する議員がすでに3人離脱している。この3人は今回の首相指名選挙では高市氏に投票したが、今後どれだけの議員が維新に残るのかも疑問が残る。
外交面では政権基盤の弱さがネガティブファクター。米トランプ政権とはトランプ大統領とのケミストリー(相性)次第だろうが、米国が北朝鮮や中国との関係を重視するジャパン・パッシングのリスクもある。
金融市場では高市政権発足期待だけで株価が上がる「高市トレード」が散見されてきたが、実体経済を全く反映しておらず今後が心配だ。
高市氏は財政・金融政策でアベノミクスの継承を提唱しているが、そもそもアベノミクスはデフレ脱却のための財政・金融政策出動。インフレの現在はさらなる円安を招くだけで物価対策としていかがかと思う。消費税減税も需要刺激で物価高対策にはならないのではないか。
◎大幅円安は見込み薄、消費税減税に警戒
<日本総研 主任研究員 松田健太郎氏>
自民党と日本維新の会との協議内容を見ても、高市氏が首相就任後、いたずらに財政支出を拡大するような政策にはなりづらくなったように感じる。新政権が日銀に実際どのような姿勢で臨むのかはまだ図りかねるが、ドルが155円を超えるような円安が進む可能性は後退したとみている。
新政権下の政策では、消費税減税の行方が関心を呼んでいる。時限立法にしても再引き上げが極めて難しく、財政悪化に直結するおそれがあるためだ。しかも、現在の日本経済が抱える課題は供給面での下押し圧力にあり、消費税減税による需要刺激が市場参加者の見方にそぐわないことも、財政悪化懸念が高まりやすい一因だろう。
仮に財政懸念が高まれば、日本の金利が上昇して、円安も進みやすくなる。その際、日銀の金融政策にどう影響するかも確認しなければならない。円相場はしばらく、新政権での政策議論を注視する展開となるだろう。
◎日経平均5年後10万円期待、リスクは「AI不況」
<マネックス証券 チーフ・ストラテジスト 広木隆氏>
日本で初の女性総理が誕生し、日経平均は史上最高値を更新し、非常に記念すべき日となった。これまでの日本の閉そく感・停滞感を打ち破るブレイクスルーになるという期待が込められている。日経平均は「祝砲」の様相となっているが、実体のないものを示す「ご祝儀相場」とは違う。日本はこれから本当に成長軌道に向かっていくのだという期待を込めた株高だろう。
日経平均は初の5万円に迫っているが、通過点にしか過ぎないだろう。高市早苗政権下では株高の地合いが加速し、今のペースでいけば5年後には10万円を突破することも考えられる。リスクは「人工知能(AI)不況」だろう。AIが世の中に浸透していく過程では、失業者の増加や新卒採用の規模縮小といった労働市場の不況が見込まれる。5年の間にどうやってAI不況を乗り越えていくかが重要になるのではないか。
◎金融・財政政策にらみ金利に上昇圧力
<関西みらい銀行 ストラテジスト 石田武氏>
衆議院で思ったよりも票を獲得したことは今後の政権運営の点では安心材料になるのではないか。政治の不安定さがいったん解消されたことから、円債は買い戻しの動きが優勢となっている。
連立を組む日本維新の会が閣外協力となることから、そこまで発言力が強いわけではないものの、自民党は顔色をうかがいながらの政権運営となる。維新が掲げる消費税減税が現実味を帯びてくると、財政拡大に対する懸念が膨らんでくる可能性があり、現物市場の超長期ゾーンを中心に上値の重さが意識されやすい。
金融政策は、日銀が今年度中に追加利上げするとみている。年内の利上げの織り込みは市場で6割程度まで上がっている。
高市首相も金融緩和をする状況でないことは認識しているとみられ、ほとぼりが冷めてくれば、徐々に利上げ方向となるのではないか。高市氏が自民党総裁になってから足元の中短期金利は低下しすぎてしまった面もあり、ここからは金利上昇圧力がかかりやすい。
ただ、高市新政権の支持率が高い場合は、解散総選挙する可能性があり、日銀も1─2カ月程度動けないリスクは残る。
※本文中の一部の説明を明確にしました
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab