ALSの未来を探る―日米権威が語る診療・研究の現状と課題【対談】(Medical Note)
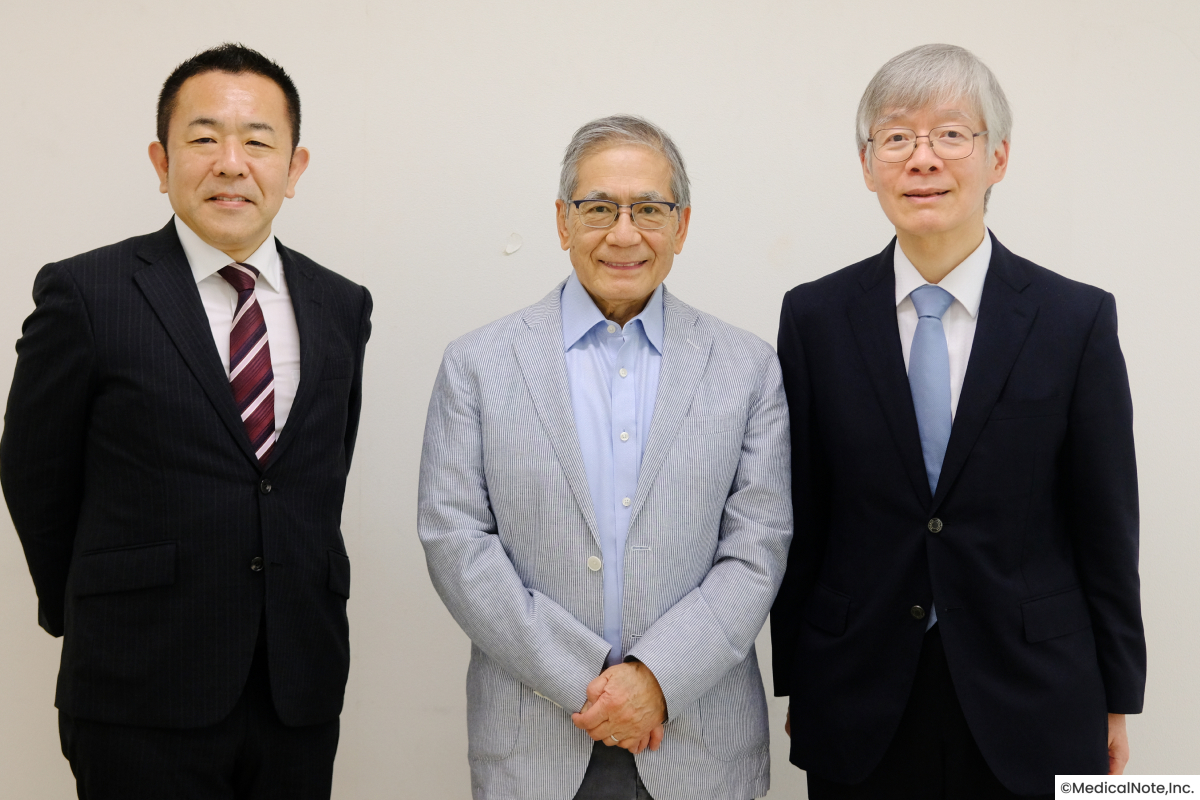
狩野先生: はじめに日本神経治療学会について教えてください。 青木先生: もともと日本には1万人以上の会員が所属する「日本神経学会」があります。神経内科領域の学術的な基盤となる学会で、臨床、研究、教育など幅広くカバーしていますが、学会の特性上、小回りが利きづらいという側面を持ちます。そこで神経疾患の治療に特化した学会として1992年に「日本神経治療学会」が設立されました。 かつて神経疾患は治療が難しい病気でしたが、最近ではさまざまな治療法が登場しています。日本神経治療学会ではそうした新たな治療法の情報共有、さらには新薬開発の推進にも力を入れています。PMDA(医薬品医療機器総合機構)に出向していた神経内科医や、製薬企業で医薬品開発に携わっている神経内科医なども日本神経治療学会の活動に参画していて、さまざまな立場から意見を出してくれています。年に一度の学術集会には企業の方も多く参加してくれているので、今後は産学連携にもフットワーク軽く取り組んでいきたいと考えているところです。 狩野先生: 日本神経治療学会はアメリカのASENT(American Society for Experimental Neurotherapeutics:米国実験的神経治療学会)との交流も活発にしていますよね。私も来年のASENTの年次総会に日本神経治療学会のメンバーとして参加させていただく予定です。 三本先生: ASENTとの交流はユニークな取り組みですね。アメリカには日本神経治療学会のように神経疾患の治療だけに特化した学会はありません。以前、日本神経治療学会から招待をしていただき学術集会に参加した際、とても素晴らしい学会だと感じました。アメリカにも日本神経治療学会のような学会があればよいなと思っています。 狩野先生: アメリカには神経内科領域の主要学会としてANA(American Neurological Association:米国神経学連合)とAAN (American Academy of Neurology:米国神経アカデミー)の2つがありますよね。 三本先生: 2つともアメリカの神経内科領域における主要学会ですが、両者の違いとして、ANAは敷居が高くて誰でも会員になれるわけではありません。大学のポジションや論文の実績など、厳しい諸条件をクリアした医師だけが会員になることができる歴史と権威ある学会です。一方でAANはANAのように会員になるためのハードルはないので会員数が多く、非常に大規模な学会です。医学的にも政治的にも力を持った学会になってきていると感じています。アメリカで日本神経治療学会のような学会がないのは、これらの学会の存在が大きいかもしれませんね。 狩野先生: アメリカにALSに特化した学会はあるのでしょうか? 三本先生: 北米ALSコンソーシアム(NEALS:Northeast Amyotrophic Lateral Sclerosis Consortium)が学会のような役割を担っていますね。NEALSはALSの治験や臨床研究を推進している団体で、アメリカでALSに携わっている施設の多くはNEALSに加盟しているのではないでしょうか。治験や臨床研究をスピーディーに行うためのシステムが非常に整っていて、大変尊敬すべきコンソーシアムだと感じています。 青木先生: 日本にもALSに特化した学会はないので、NEALSのような役割を日本では私たち日本神経治療学会が担っていく必要があると考えているところです。NEALSの取り組みを参考にしながら、さまざまある神経疾患の1つとしてALSの治療薬開発にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。 三本先生: それはとてもよいですね。すでに学会という形になっているので実現しやすいのではないでしょうか。日本神経治療学会の一部として、ALSの創薬を推進できるような仕組みをつくれればよいですね。



