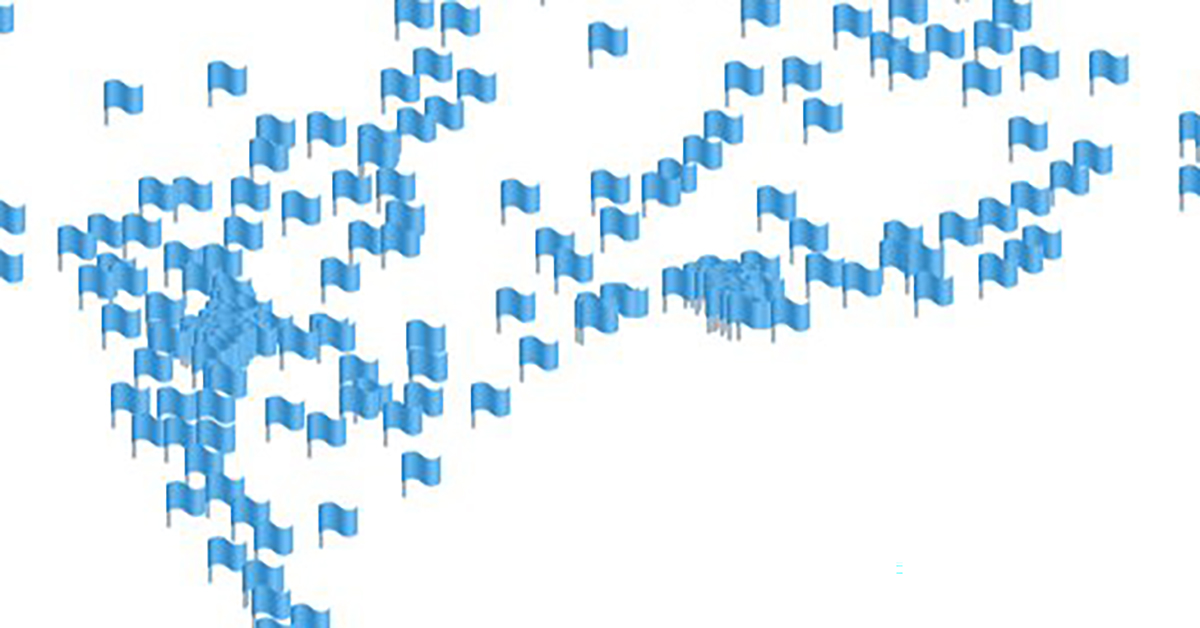どんなにヤバい医者でも一生医者でいられる…それでも医師免許を「更新制」にしてはいけないワケ 「大学病院の先生なら間違いない」の落とし穴

腕の良い医師とそうでもない医師がいるのはなぜか。医師の和田秀樹さんは「日本の医師免許は更新制ではないので、医師として自分を成長させなければというモチベーションがなく、古い知識のまま治療に当たっている医師も少なくない」という――。
※本稿は、和田秀樹『ヤバい医者のつくられ方』(扶桑社新書)の一部を再編集したものです。
写真=iStock.com/koumaru
※写真はイメージです
一度「医師」になったら一生もの
日本では、医師国家試験に受かりさえすれば、犯罪などを起こさない限り、死ぬまで医者でいられます。
各科の専門医の資格は、5年間のうちに指定の講習会などに出てポイントを稼がないと剝奪されてしまいますが、講習会といっても「これまでの理論は正しいのだ」と従来の知識をただなぞるかたちだけのものであるうえ、参加すればそれだけでポイントになるというお粗末さです。
つまり、医者としてスタートしたときから、一切知識のアップデートをせず、過去の常識のまま治療にあたったとしても、免許をとり上げられることはありません。医者が余っているわけではないので、多少評判が悪くても淘汰されることもありません。
だから危機感もなく、医師として自分を成長させなければというモチベーションがわきにくいのです。
医学部に入る頃までは秀才と呼ばれていたであろう人たちも、その多くは医者になった途端、ろくに勉強しなくなります。
「勉強=学会に参加する」ではない
こういう話をすると、「いやいや、学会などにしょっちゅう参加して私はちゃんと勉強しているぞ」と反論する人がいるのですが、私の考える勉強というのは、上から下りてくる話を鵜呑みにすることではなく、「自分から積極的に新しい情報を取りにいく」という意味です。
日本の医者の多くは、上が正しいということはすべて正しいと素直に思い込めるタイプの人です。
彼らにとっては「学会に出る=勉強」なので、海外の最新の論文にこまめに目を通すような人はほとんどいません。
だから、上が正しいと言い張り続ける従来の知識の中に、実はすでに錆びついているものが含まれていたとしても、その事実に気づくことができず、「これはおかしいのではないか?」と疑問を持つこともできません。
これこそがまさに入試面接と、医療界の絶対的なヒエラルキーシステムがもたらした大罪だと私は思っています。
Page 2
ヒエラルキーのトップに君臨する医学部の教授たちの意のままにコントロールされているのが日本の医療界の実態です。
入試面接において医学部の入学者を決めるのも、新しい教授のポストを誰に与えるかを決めるのも教授たちで、どの薬を認可するかとか、どの薬を優先的に使うのか、などを決めているのも実質的には教授たちだと言っても過言ではありません。
物言えぬ空気が生まれるのも、製薬会社との癒着が起きるのも、あらゆる権力を教授たちに集中させているせいでしょう。
しかもそれを取り締まるべき立場にある文科省や厚労省の役人たちは、自分たちの天下り先としてそのポストを狙っているので、あえてそれを問題視することはありません。
教授性善説がまかり通っているせいで、世の中の人たちもそれでいいと考えているようですが、それはあまりにもお気楽すぎます。
例えばアメリカでは、「不正は起こるもの」という前提に立ち、あらゆるシステムが構築されます。
だから、大学の入試面接も教授ではなくアドミッション・オフィスが行い、治験のコントロールもそれを専門とする独立機関が行います。
そのおかげで教授に平気で楯突く人間も入学してきますし、大学病院(メディカルスクールの附属病院)と製薬会社の癒着もあまり生まれません。
日本の医療費がどんどん増えていく背景
何度もお伝えしている通り、大学医学部の教授たちは、医者たちを意のままにコントロールできる環境を見事に整え、自分たちのメンツや利権をずっと守り続けています。
その結果、臓器別診療から総合診療への転換が果たされず、主に高齢者たちに多くの薬が処方され続けています。そのせいで膨らむ薬剤費が日本の医療費を増大させているのです。
当の教授は、人口構成のせいだとか、医療費抑制政策が悪いなどと言い張るだけで、自分たちに問題があるという自覚がないのです。
この状況にあって、それに気づけないなんて、心理学者の立場から言えば彼らにはメタ認知(自分自身を客観的に認識する態度)が全く働いていないとしか思えません。