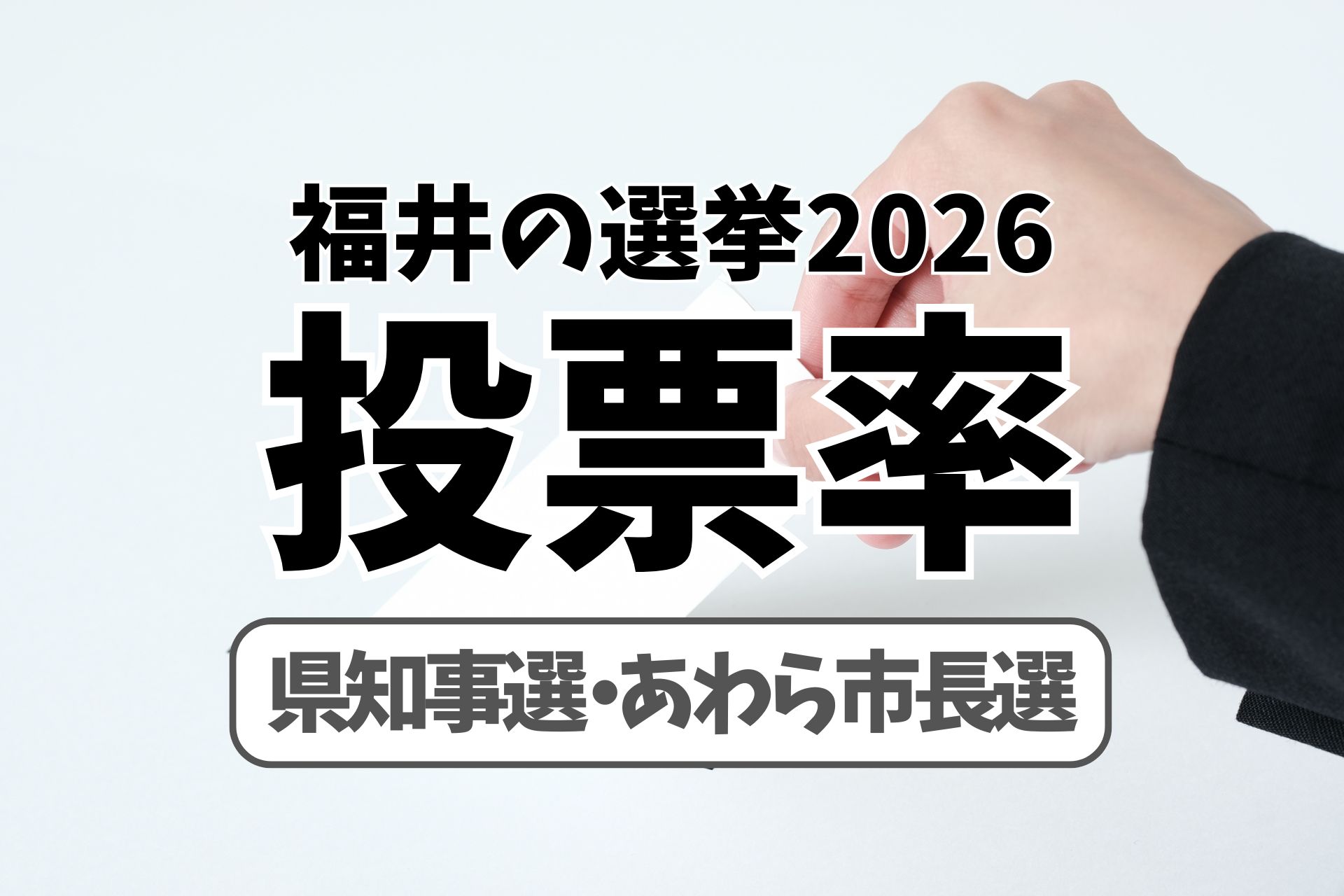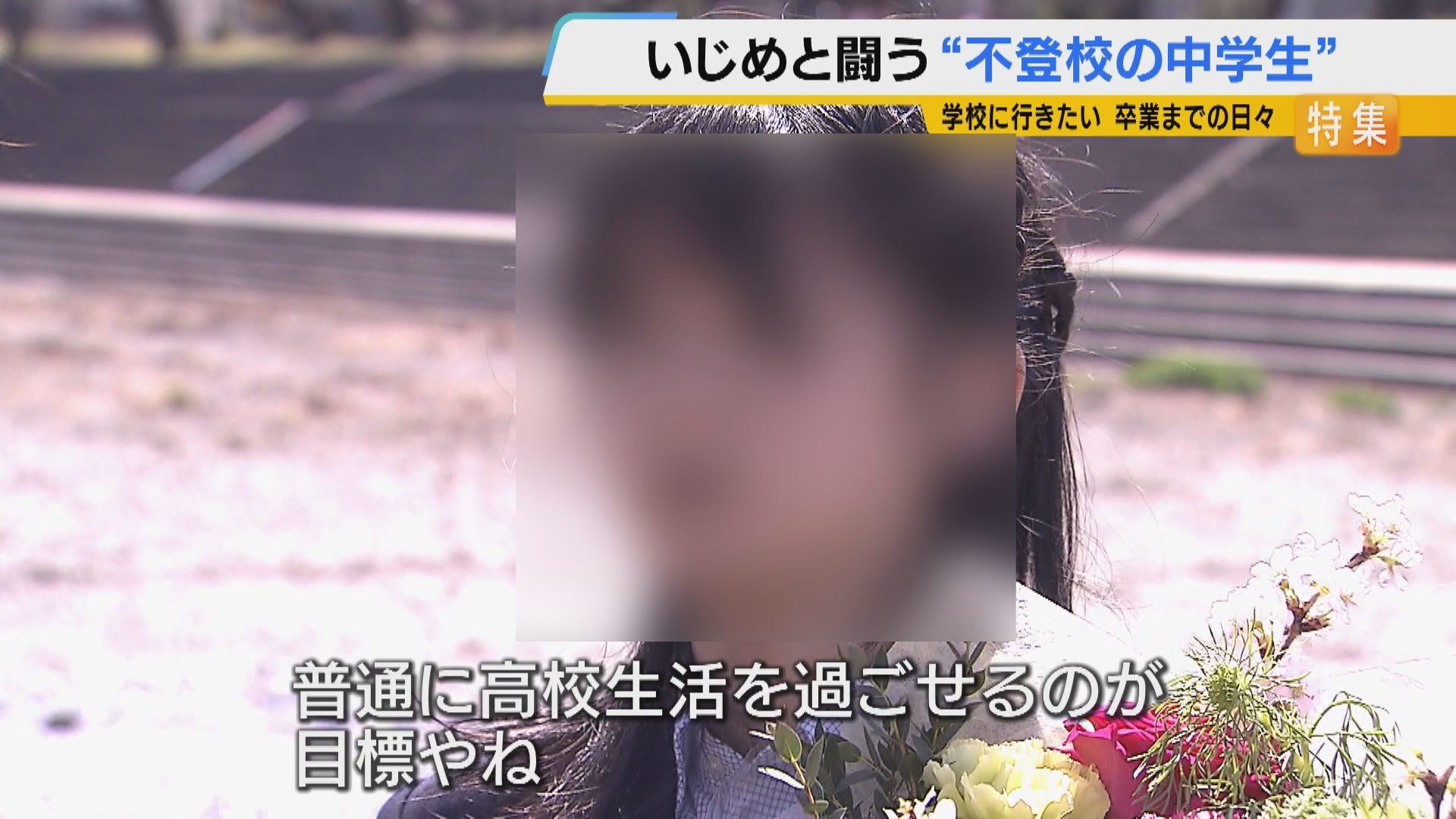仙台の水源の森が失われる。日本最大級メガソーラー建設計画地を歩く(後編)

宮城県・仙台市太白区(せんだいしたいはくく)の戸神山周辺の丘陵地帯で、日本最大級のメガソーラーの建設計画が持ち上がっている。 水の安全、土砂流出の危険に地元住民は脅かされているが、ソーラーパネルの建設業者の実態は分からず、連絡が取れない。自然を回復不能な状態にまで破壊するメガソーラー建設の問題点と、建設区域内のハイキングコース、白沢五山(しらさわごさん)を東北の山に詳しい曽根田さんに解説してもらった。
秋保地区メガソーラーの建設予定地は、国道457号をはさんで東西方向に最大5㎞、南北に最大2㎞の範囲に及び、西側の戸神山(とがみやま)エリアと東側の白沢五山(しらさわごさん)エリアに分かれている。一口に白沢五山エリアと言っても、多くの谷が山奥まで入り込む複雑な地形をしており、その全体像を知る人は少ない。後編ではこの白沢五山エリアの現状を記していきたい。
秋保メガソーラーの建設予定地域(青い線の内側。地図は「ヤマタイム」山岳地図データベースより二次利用して作成)白沢五山エリアの特徴
白沢五山(別名・五ッ森)はJR仙山線陸前白沢駅の南側に、西から箱ノ倉山(はこのくらやま、函倉山)、前山(まえやま)、岩垂山(いわだれやま)、小塚山(こづかやま、小森山)、大森山(おおもりやま)の五山が並んでいる。三角形の箱ノ倉山を除いて、他の4山はどれも円錐形なので、山麓から見て即座に山の名前を指呼するのは難しい。
大針登山口付近から見た白沢五山の岩垂山(左)、前山、函ノ倉山この山々の成因は数百万年前、白沢一帯のカルデラ湖底が隆起してできた陸地だった。旧広瀬川が削って深い谷をつくり、その谷に向かって支沢が形成され、谷の出口に扇状地がつくられて、現在の姿になったといわれる。
かつてこの山域には放置された作業道しか存在せず、赤生木(あこうぎ)地区の南にそびえる前山(346m)だけが登れる山だったが、十数年前、山域の南西側の長袋五山(ながぶくろござん、ゴロ山、二ノ輪山、大旗山、ヤケ山、愛宕山)を含めた山々を結ぶ登山道が地元の登山愛好家の手によって整備され、中青葉丘陵(なかあおばきゅうりょう)という名称で「みやぎ里山文庫」のHPに紹介された。
白沢五山の南面は、戸神山と同様に針葉樹の造林地がほとんどなく、ミズナラを主体とした雑木林に覆われている。豊かな自然が残されているため野生動物が多数生息していて、秋にはミズナラのドングリを目当てにクマが作った熊棚がたくさん見られる。また名取川上流の二口渓谷に生息する国指定特別天然記念物イヌワシが、直線距離で約15㎞離れたこの付近まで飛翔してくるようだ。
山域の随所で見られる熊棚(写真は大旗山東斜面)また前編でも若干触れたが、戸神山から青葉城がある青葉山へ延びる丘陵地には、環境者レッドリストの準絶滅危惧(NT)のヒメシャガが自生していて、花期には薄紫の美しい花園が随所で見られる。特に箱ノ倉山や前山の登山道沿いに多く群生している。
満開のヒメシャガ(箱ノ倉山)メガソーラー建設で起きる問題
ここで忘れてはならないのは、秋保メガソーラーの建設予定地域が、秋保郷の重要な水源地になっている点だ。秋保の田園地帯は名取川の河岸段丘上に作られているため、谷が深い名取川から取水できない。そこで名取川左岸の山々から流入する沢やため池を利用した灌漑が数百年前から行なわれてきた。幹線用水路は秋保大滝付近から山の南麓に沿って境野地区まで延び、大旗山(おおはたやま)と鈴ヶ森(すずがもり)を源流とする杉沢川(すぎさわがわ)にも大堤、新堤、東作の3つのため池が作られている。メガソーラーの建設によって、これらの水源地の森を失うことは、地域の農業に大打撃を与える可能性が高い。
杉沢川最上流の東作ため池。秋保郷屈指の森閑な場所だ長袋五山(ながふくろごさん)は登山ルートが複雑で道標もなく、ガイド記事には向かないため、ここでは白沢五山を歩いた記録とともに、メガソーラー建設の問題点を考えていきたい。
白沢五山の登山コースとメガソーラーの問題点
JR仙山線陸前白沢駅をスタートし、ため池越しに箱ノ倉山を眺めながら生活道路を歩いて箱ノ倉山登山口へ向かう。登山口から送電線巡視路まで登ると西側に戸神山が見える。
箱ノ倉山中腹から戸神山を見る箱ノ倉山山頂から北側へ少し下ると、メガソーラーが作られた畑前草地が見える場所がある。ここは野生動物が遊ぶ牧場だったが、メガソーラーの建設によってすばらしい展望とのどかな牧場の光景は失われた。しかし谷を埋める造成をしなかった点は評価できる。
国道48号の北側にある畑前草地に作られたメガソーラー施設太い木が目印の三方分れの分岐を左折して前山をめざす。葉が落ちて見通しが効く初冬の山歩きは気持ちがいい。この付近はメガソーラー建設エリアのど真ん中。今後消え去ってしまう風景になるのだろうか。
三方分れの分岐。過去にこの場所でカモシカに出会ったことがある前山を往復した後、ゴロ山(五郎山)に立ち寄る。ここは葉が落ちた時期には唯一景色が見渡せる場所だ。船形連峰(ふながたれんぽう)の後白髪山(うしろしらひげやま)や、東に権現森(ごんげんもり)や落合地区の街並みが一望できる。
ゴロ山から見た船形連峰の後白髪山 ゴロ山から権現森と落合地区を望む事業者は土地80%買い上げ。裏側にある地権者の気持ち
現在、秋保メガソーラーの事業者である沖縄の合同会社は、地権者から約80%の土地を買い上げているという。この開発計画は地権者の中でも賛否両論で、賛成を表明する方は「土地としての活用が難しいなか、毎年税金だけ取られ、万が一山火事が起これば自分の責任にもなってしまう。買ってくれる人がいるならば、早く手放したい」というのが本音のようだ。その方の立場から考えればこれは正論だろう。
たしかに、山中には古いブルドーザー道が交錯し、かつて雑木林を伐採した跡が残る手入れされていない二次林が多く、山は放置されたままになっている。この状態では秋の幸のキノコもほとんど生えない。
岩垂山西側の雑木林の二次林岩垂山から小塚山へ向かう登山道はササが登山道を覆っている。踏み跡ははっきりしているが、ヤブ道なので『分県登山ガイド3 宮城県の山』のガイド記事には不適切と感じ紹介しなかった。ここを歩く場合、山慣れたリーダーの先導が必要だ。
一部ササが登山道を隠している箇所もある 雑木林に囲まれた小塚山の山頂あれ、山頂がない!
小塚山から馬ノ神峠(まのかみとうげ)へ下り、白沢五山東端の山・大森山に登る。しかし登ってみて呆然と立ち尽くしてしてしまった。なんと山頂が新東北化学工業のゼオライト採掘のため削り取られてしまい、三角点もなくなっていたのである。ゼオライト(沸石)は火山活動によって約700万年もの年月をかけて作られた多孔質の天然鉱物で、脱臭剤や猫砂などに使われている。山頂がなくなってしまい、はげ山と化した光景は、未来の秋保メガソーラーの建設現場を見ているようで心が痛んだ。私有地なら故郷の原風景である里山を喪失させてよいのか。利益だけを重んじる現代社会の歪みを見たような気がした。
山頂がなくなった大森山から小塚山など西側の山を望む 大森山山頂東側のゼオライト採掘現場を見下ろす大森山はこの時、週末で採掘場が稼働していないため登れたが、重機が動いている時は作業の邪魔になるし、危険なので立ち入りしない方がよいと思う。大森山から松尾観世音の石碑が建つ馬ノ神峠へ下り、そこから大針登山口(おおはりとざんぐち)を経て陸前白沢駅まで歩いてこの日の山行を終えた。
松尾観世音の石碑最後に
「メガソーラー」の建設は必要書類を提出し、開発内容が許可基準を満たしていれば、宮城県および仙台市は許可せざるを得ないという。そこで県は土地の乱開発を防ぐ意味で「再生可能エネルギー地域共生促進税」を2024年4月1日より導入した。この税はFIT価格(再生可能エネルギーの買い取り価格のこと)10円未満の太陽光発電施設に対し、620円/KWの税金を単年度ごとに課すものであるが、税率が低すぎて、乱開発の抑制効果はさほどないという意見が有識者の中にも多い。その他に、カドミウム、鉛、ヒ素などが含まれる太陽光パネルが破損した際の処理について、発電機器の火災が発生した場合、感電の恐れがあるため安易に水をかけて消火できない点など、太陽光発電は多々の問題点を抱えている。
自然を回復不能な状態にまで破壊しながら、急速に日本国内に建設が進むメガソーラー。ここで一度立ち止まって、検証せねばならない時期にきているのではないだろうか。
(山行日=2023年12月)
最適日数:日帰り
コースタイム:3時間55分
行程:陸前白沢駅・・・箱ノ倉山・・・ゴロ山・・・岩垂峠・・・大森山(山頂はなし)・・・陸前白沢駅
総歩行距離:約9,000m
累積標高差:上り 約600m 下り 約600m
Page 2
仙台の水源の森が失われる。日本最大級メガソーラー建設計画地を歩く(後編)
仙台市の戸神山周辺の丘陵地帯で、日本最大級のメガソーラーの建設計画が持ち上がっている。 問題だらけのメガソーラーの建設についてなるべく多くの登山者が知り、行ける人はぜひ歩いてほしい。
2025.10.13
仙台の里山の危機。日本最大級メガソーラー建設計画地を歩く(前編)
仙台市の戸神山周辺の丘陵地帯で、日本最大級のメガソーラーの建設計画が持ち上がっている。 問題だらけのメガソーラーの建設についてなるべく多くの登山者に知ってほしい。
2025.10.12
【インタビュー・中村浩志】ライチョウの命をつなぐ、自然と人が共に生きる未来のヒント
高山の稜線に静かに生きる神の鳥──ライチョウ。中央アルプスを舞台にわずか5年で地域絶滅の危機から奇跡の復活を遂げた背景には、60年に渡る研究者の情熱がありました。
2025.09.29
モンベル|山の保全の今を知る、考える
創業から50年、モンベルが掲げる「7つのミッション」の第一には「自然環境保全意識の醸成」がある。これは企業としての姿勢であると同時に、自然をフィールドとするすべての人々への呼びかけでもある。「自然環境を守ることこそ最大の責任」という信念のもと、環境保全に真摯に取り組んできた。
2025.09.29
[PR]
マムート|山の保全の今を知る、考える
スイス発のアウトドアブランド、マムートは160年以上にわたり革新的なアウトドア製品を生み出している。その一方で、環境保全にも力を注いできた。近年はCO₂削減や炭素除去にも積極的に取り組んでいる。
2025.09.29
[PR]
ファイントラック|山の保全の今を知る、考える
ファイントラックは創業当初から「遊び手=創り手」という理念のもと、アウトドア文化を育む製品づくりを続けてきた。環境負荷の少ない素材開発、時代に左右されない定番商品の展開など、長く使える道具を届けることで自然への配慮を実践している。
2025.09.29
[PR]
ゴールドウイン|山の保全の今を知る、考える
「ザ・ノース・フェイス」などの海外アウトドアブランドと提携し、自然をフィールドに独自のモノづくりを行なってきたゴールドウイン。創業以来、スポーツやアウトドアを通じて、持続可能な社会の実現を使命としてきた。
2025.09.29
[PR]
ゴアテックス|山の保全の今を知る、考える
冷たい雨をはじく。強風を防ぐ。長時間の行動でも蒸れにくい。それでいて地球環境への影響が低い──そんな理想を形にしてきたGORE-TEX ブランド。山で頼れる高性能ウェアを生み出し続けると同時に、「責任あるパフォーマンス」を掲げ、環境負荷の低減にも挑戦してきた。
2025.09.29
[PR]
尾瀬保護財団|山の保全の今を知る、考える
1995年、オーバーユースによる自然破壊の危機感から、設立された尾瀬保護財団。同財団は、尾瀬の自然を守るため、利用者への啓発活動や関係機関との連携による保全を進めてきた。現在でも、登山道の一方通行化や残雪期の登山道閉鎖、携帯トイレやポールキャップの使用推奨など、自然への負荷を減らす取り組みが続いている。
2025.09.29
[PR]
アミノバイタル|山の保全の今を知る、考える
コンディショニングサポートで安全登山を支える「アミノバイタル®」。販売元である味の素株式会社は、アミノ酸を通じて登山者のチャレンジをサポートするだけではなく、山の未来を守る活動にも取り組んでいる。そのひとつが、登山家・花谷泰広さんが代表理事を務める「北杜山守隊」への支援だ。
2025.09.29
[PR]
Page 3
国立公園を知る・考える|山の保全の今を知る、考える
全国に35カ所あり、国土の約6.5%を占める国立公園。環境省からはレンジャーが現地に派遣されるが、その人数は充分ではない。国立公園の保全方法は模索中という状態だ。国立公園内を守るために登山者にできることとは?
2025.09.29
[PR]
日本山岳遺産基金の取り組み|山の保全の今を知る、考える
日本のすばらしい自然環境を次世代に引き継ぐためにはどうすればいいのか。山と溪谷社が日本の美しい山岳環境を次世代へと残すために設立した「日本山岳遺産基金」の取り組みとともに、山の保全について考えてみよう。
2025.09.29
[PR]
山の保全の今を知る、考える
日本山岳遺産基金の取り組みや、山岳環境に配慮した活動をしている企業・団体の活動事例を通して、山の保全の具体的な取り組みについて紹介する。
2025.09.29
[PR]
山と米と私【後編】 足りない米と人
米高騰が続く一方、農家には値上げ分が還元されない異常な状況が続く。そんななかでも「適正な価格で米を腹いっぱい食べてほしい」と願う矢口拓さん。新聞記者、登山案内人、救助隊員、米農家という異色のキャリアを持つ筆者が、新たな視点から山と米のダブルワークの未来を考える。
2025.07.06
山と米と私【前編】 おむすびに願うこと
山での行動食を聞かれたら、「もっぱら、おむすび」と答えている矢口拓さん。信州登山案内人として活躍し、また、年間を通して北アルプス北部遭難防止対策協会の救助隊員として、さらに夏の50日間は稜線で長野県北アルプス遭難防止常駐隊員として、救助や遭難防止活動にも従事している。山で活躍する彼のもう一つの姿は安曇野の米農家。生活の一部に山と田んぼがある矢口さんの米への思いとは。
2025.07.05
都会人も米作りに参加。「山よりな暮らし」で、井水の危機を乗り越える【後編】
米の値段の高騰が続いている。筆者は南アルプス内院、長野県大鹿村の標高1000mで田んぼをはじめて今年で9年目。山小屋や執筆活動と並行して「田んぼ」を続けてきた秘境作家の、トライアンドエラーの米作りレポの後編。
2025.06.27
「山つきの米はうまい」。南アルプス山麓で田んぼをやる【前編】
米の値段の高騰が続いている。筆者は南アルプス内院、長野県大鹿村の標高1000mで田んぼをはじめて今年で9年目。山小屋や執筆活動と並行して「田んぼ」を続けてきた秘境作家の、トライアンドエラーの米作りレポ。
2025.06.26
山の中で見たスミレのお花畑は、自然そのものではなかった。アメリカスミレサイシンが訴える危機感
春の山肌に咲き誇るはずだった可憐な紫のスミレが、いつの間にか外来種のアメリカスミレサイシンの大群落に飲み込まれている――。その光景は、単なる風景の変化を超え、胸に深い危機感を去来させるのだった。
2025.06.08
タイワンリス、最近増えている帰化動物。かわいいけれどワルイヤツ。
神奈川県の三浦半島の山々を歩いていると、リスの姿を目撃するのは珍しいことではない。この多くはタイワンリスという帰化動物で、生態系や自然環境に悪い影響を与え始めている。
2025.04.18
金額は? 使途は? 導入に向けて動き出した南アルプスの入山料
富士山などですでに始まっている入山料制度。南アルプスでも2025年に実証実験が行われることになった。
2025.04.15
Page 4
テントで就寝中にクマが!上高地発、「クマとヒトのいい関係」を考える【後編】
各地でクマの出没と事故が相次いでいる。現代の「クマとヒトのいい関係」とは。日本を代表する山岳景勝地で国立公園、上高地から考えてみた。
2024.12.07
Page 5
登山中に体の異変を感じたら、無理することなく登山を中止しましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第415号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第415号では、登山中に病気で亡くなる遭難が2件発生したことについて言及。体の異変を感じた場合には、無理せず登山を中止することを促している。
2025.10.10
スリップや転倒が命取りにならないよう、ゆとりを持った行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第414号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第414号では、北アルプスで下山中の転倒や滑落の事故が多発している現実を踏まえ、ゆとりを持った行動で事故を未然に防ぐことを促している。
2025.10.02
秋の登山は天気急変に備えることが大切。引き返す勇気を持って入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第413号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第413号では、長野県の山では急速に秋が深まっていることを伝え、天候急変のリスクを意識して入山することを促している。
2025.09.26
北アルプスでの遭難事故が多発。ルートの難易度を確認して準備を入念に行ない入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第412号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第412号では、今年の夏山シーズンの遭難のうち71.3%が北アルプスで発生していることに言及。ルートの難易度を確認して準備を入念に行ない、北アルプスへ入山することを促している。
2025.09.18
秋山シーズンに入っても、滑落や疲労による遭難が多数。ゆとりある計画を 島崎三歩の「山岳通信」 第411号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第411号では、依然として滑落や疲労による遭難が多いことを指摘。レベルに見合った山域を選び、ゆとりある計画を立てることを促している。
2025.09.12
過去最多の遭難件数から考える、季節の変わり目における登山リスク 島崎三歩の「山岳通信」 第410号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第410号では、2025年の夏山シーズンは2年連続で過去最多の遭難件数であったことについて言及。秋山シーズンに入り、季節の変わり目における登山中のリスクについて説明している。
2025.09.05
疲労と安易な行動が招く山岳遭難を避けるために必要な登山者の心得 島崎三歩の「山岳通信」 第409号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第409号では、転倒や滑落、疲労や病気による遭難が大多数だったことを指摘。自分自身の登山計画や装備品を見直しを行ない、安全登山を心掛けることを促している。
2025.09.01
準備不足が招く山岳遭難が多発。登山にはリスクがつきものという自覚を! 島崎三歩の「山岳通信」 第408号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第408号では、16件起きた遭難の多くで準備不足が原因だったことを指摘し、自身の登山を見直し、安全登山を心がけることを促している。
2025.08.21
山では天候の急変により一瞬で命がおびやかされることもあります 島崎三歩の「山岳通信」 第406号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第407号では、天候の急変で起きた遭難事故について言及。山では天候が急変すると一瞬で命がおびやかされる事態が発生することを念頭におき、登山の可否を判断するよう注意喚起している。
2025.08.15
脱水や熱中症、疲労に起因する転倒・転落・滑落が多発。体力レベルに見合った計画を 島崎三歩の「山岳通信」 第406号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第406号では7月の遭難件数が64件(過去ワースト2)に達していることに言及、レベルに見合った登山計画を促している。
2025.08.12
Page 6
ペルーアンデス・ワスカラン遭難に学ぶ山の気象判断:ベテラン登山家を襲った遭難事故の解析速報
登山者にとって安全は常に最優先課題です。しかし、ときにベテラン登山家をも飲み込む予期せぬ事態が起こることもあります。2025年6月、ペルー・ワスカランで起きた日本人女性登山家の遭難事故。その詳細な気象解析から、私たちの山行に生かすべき教訓を探します。
2025.08.11
疲労や気の緩みによって足元がおろそかになりがち、慎重な行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第405号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第405号では北アルプスで下山時に滑落する事故が多発したことを取り上げ、疲労や気の緩みによって下山時はリスクが高まることを説明している。
2025.08.01
暑さと疲労が原因の遭難が増加中。こまめに休憩を取り安全で楽しい登山を 島崎三歩の「山岳通信」 第404号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第404号では疲労や熱中症などのために行動不能や、集中力低下による転倒や滑落が増えていることを説明。暑さ対策の徹底と余裕のある行動を促している。
2025.07.25
危険性が見えない登山道でも漫然と行動せず慎重な行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第403号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第403号では危険性の少ない場所で起きている遭難事故について言及。特に下山中は注意力が散漫にならないように、気持ちを引き締めて行動するよう促している。
2025.07.18
山の上も気温が高く、体調不良や疲労による遭難も多発しています 島崎三歩の「山岳通信」 第402号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第402号では気温上昇と共に体調不良や疲労による遭難が増加する傾向にあり、あらためて、こまめな水分・塩分補給と熱中症対策を行なうよう促している。
2025.07.11
本格的な夏山シーズン到来。暑い日差しを浴びながらの行動に注意を 島崎三歩の「山岳通信」 第401号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第401号では、7月に入り本格的な夏山シーズンの到来となった今、過去の遭難事例を振り返りながら夏山での注意点を挙げている。
2025.07.03
麓では気温30度超えでも山には雪が残っています。最新情報を確認して適切な装備を 島崎三歩の「山岳通信」 第400号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第400号では、雪渓上での滑落事故が多発していることを説明、最新情報を確認して適切な装備品を準備することを推奨している。
2025.06.27
山菜採りのシーズン。入山前・入山中は安全対策の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第399号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第399号では、山菜採り中の遭難について言及。安易な気持ちで入山せず、安全対策の徹底した行動を促している。
2025.06.20
おかしいと思った場合は一度立ち止まり、地図やコンパスで現在位置を確認しましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第398号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第398号では、北アルプス爺ヶ岳で起きた道迷い遭難について言及。現在地の確認の大切さを説明している
2025.06.11
装備品の携行と使い方を熟知して安全を最優先した行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第397号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第397号では、北アルプス霞沢岳における道迷い遭難について言及。アクシデントに対する準備と冷静な判断の大切さを説明している。
2025.06.05
Page 7
道迷い多発、死亡事故の多くは滑落。春の大型連休期間、山岳遭難発生数が過去最多を記録
5月19日にGW期間の遭難発生状況まとめが警察庁から発表された。今年のGW期間はおおむね天候にめぐまれ、登山を楽しんだ人が多かったが、遭難発生も過去の発生数を大幅に上回ることとなった。
2025.06.05
標高の高い山域では残雪あり。滑落、道迷いのリスクを認識して準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第396号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第396号では、残雪が原因の遭難が多いことについて言及。情報確認の徹底とともに、残雪対策の実施と緊急時への備えを呼びかけている。
2025.05.29
八ヶ岳連峰阿弥陀岳で発生した滑落遭難、救ったのは登山計画書だった ~長野県・山岳遭難の現場から
2024年4月17日、八ヶ岳連峰阿弥陀岳で発生した単独登山中の滑落事故は、最悪の結末を回避するための貴重な教訓を提示している。特に、単独での山行を志す登山者にとって、この事案は深く考察すべき事例といえるだろう。
2025.05.25
2件の行方不明が発生中。家族や知人に詳細な予定を伝えてから入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第394号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第394号では、期間中に2件の行方不明遭難が発生していることについて言及。家族や知人に詳細な予定を伝えたうえで、登山計画書の提出を促している。
2025.05.16
101年前のエベレストの天気を再現。『そこに山があるから』……名言を残したマロリーは果たしてエベレスト頂上に辿り着いたのか?
「そこに山があるから」の名言で知られる登山家ジョージ・マロリーは、果たしてエベレストの頂上にたどり着いたのか? NOAA(アメリカ海洋大気庁)による再解析データを使って101年前の気象状況を再現。気象面から登山史上最大の謎に迫る。
2025.05.14
滑落事故が多発、残雪の変化に対応できる技術・体力・装備品の準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第393号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第393号では、連休中に滑落事故が多発したことについて言及。残雪の変化に対応できる技術や体力、装備品の必要性を説明している。
2025.05.09
残雪登山中の滑落事故が多発、実力に見合った登山計画を 島崎三歩の「山岳通信」 第391号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第391号では、残雪登山で滑落するケースが大半を締めている状況に言及。体力と技術に見合った登山をするように促している。
2025.05.02
落石の発生しやすい季節。休憩時でも常に細心の注意を 島崎三歩の「山岳通信」 第390号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第390号では、八ヶ岳で起きた遭難事故について取り上げ、残雪期の落石には充分な注意を払う必要性を説明している。
2025.04.24
日中の寒暖差が大きい季節、雪質の状態を把握して行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第388号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第388号では、県内でも本格的な春が訪れ、日中と朝夕の温度差が大きくなっていることを説明。雪質の変化を把握して行動することを促している。
2025.04.11
単独で入山する場合は家族や会社の同僚との情報共有の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第387号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第387号では、単独で入山して行方不明になる事案について言及。万が一に備え、家族や会社の同僚との情報共有を行なうことを促している。
2025.04.05
Page 8
春の気象の特徴を理解して、安全登山の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第386号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第385号では、長野県の山岳地帯の気象の特徴ついて説明し、悪天候が予想される場合は登山の中止も検討することを促している。
2025.03.28
長野の山では天候が崩れれば一瞬で真冬に戻ります。適切な装備品の選定を 島崎三歩の「山岳通信」 第385号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第385号では、3月16日に八ヶ岳赤岳で起きた遭難について言及。春山気分で登山をするのではなく、状況や天候を必ず確認して適切な装備を用意することを促している。
2025.03.21
雪山では「キホン」をしっかりと学び、身につけてからの入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第384号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第384号では、中央アルプスの千畳敷でパトロールを行った救助隊員の言葉を例に、キホンをしっかりと学び、身につけてからの入山を強くお願いしている。
2025.03.13
一日の寒暖差が大きくなる時期、雪の状況をしっかりと見極めて行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第383号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第383号では、3月に入り気温が上昇してきていることから、雪山を楽しむ際には雪の状況をしっかりと見極めて行動する必要性を説明している。
2025.03.06
冬山の最大のリスクは「寒さ」。日帰りの予定でも最低限の備えを 島崎三歩の「山岳通信」 第382号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第382号では、遭難して救助要請をしても、山では救助まで時間がかかることを指摘。最低限の備えを用意しておくことの大切さを説明している。
2025.03.03
積雪が非常に多い今年の冬山、対応した装備の携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第381号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第381号では、県内では積雪が非常に多い状況を説明、雪に埋まったり、雪崩に巻き込まれたりするリスクを認識した装備の携行を促している。
2025.02.21
スキー場の管理区域外へ出ることは大きなリスクを背負うことになる認識を 島崎三歩の「山岳通信」 第380号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第380号では、期間中に起きた遭難事故がすべてバックカントリーでの遭難となっている状況に、スキー場の管理区域外へ出るリスクをあらためて説明している。
2025.02.13
バックカントリーに出る場合、アクシデントに対応できる知識・技術・装備の準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第379号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第379号では、バックカントリーでの遭難が続発している状況を説明し、あらためてアクシデントに対応できる知識・技術・装備が必要なことを説明している。
2025.02.07
【緊急レポート】下山したら車のガラスが割れていた! 登山中の車上ねらい被害を防ぐために
駐車中の車の窓を割ったり、ドアロックを解除したりして、車内に残された金品を盗む「車上ねらい」。車上荒らしとも呼ばれるこの犯罪、マイカー派の登山者にとっては他人事ではない。被害者による詳細レポートとともに、われわれ登山者が実践できる対策について考えた。
2025.02.01
目に見えないリスクが多数潜んでいるバックカントリー、遭難事例を確認して安全最優先の行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第378号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第376号では、期間中に起きたバックカントリーでの遭難事故を取り上げ、スキー場のゲレンデとバックカントリーエリアのリスクの差を理解し、入山することを説明している。
2025.01.30
Page 9
スキー場のゲレンデとバックカントリーの「リスクの差」を理解して入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第376号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第376号では、期間中に起きたバックカントリーでの遭難事故を取り上げ、スキー場のゲレンデとバックカントリーエリアのリスクの差を理解し、入山することを説明している。
2025.01.20
登山道の状況に応じてアイゼンやチェーンスパイクなどを適切に選択しましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第375号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第375号では、下山中に足を滑らせて転倒、負傷した事例について言及。登山道の状況に応じて、適切に装備を選択して歩行する技術を身につけることの大切さを説明している。
2025.01.15
不世出の単独行登山家、加藤文太郎の命を奪った豪雪。原因は近年でも豪雪をもたらすJPCZだった
新田次郎の小説『孤高の人』のモデルとして知られる登山家の加藤文太郎。1936年に槍ヶ岳北鎌尾根でその生涯を閉じるが、そのとき何が起きていたのか? 過去のデータを丁寧に分析して浮かび上がってきたキーワードは「JPCZ」だった。
2025.01.15
登山では天候は非常に重要な判断材料のひとつ。入山前や行動中に的確な判断を 島崎三歩の「山岳通信」 第374号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第374号では、年末に北アルプス・爺ヶ岳で起きた遭難事故について言及。事前および行動中の天候の確認と的確な判断の大切さを説明している。
2025.01.10
年末年始も要注意! 滑落・道迷い・悪天候・低体温症・・・初冬期にはどんな山岳遭難が起きているのか
山が本格的な冬を迎える12月から1月にかけては、年末年始の休暇などを利用して雪山に登る人が増える季節。しかし、初冬期特有の事故も起きている。
2024.12.27
バックカントリーエリアは命の危険を伴う場所という認識をもって入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第373号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第373号では、北アルプス中遠見山でのバックカントリー中に起きた遭難事故について取り上げ、入山前の判断の大切さを説明している。
2024.12.26
雪の少ない今の時期、アイゼン着脱のタイミングや足の置き方は慎重に 島崎三歩の「山岳通信」 第372号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第372号では、充分に雪の量がない今の時期の雪山の注意点について言及。アイゼン装着のタイミングや足の置き方などでは、特に慎重な行動が必要と説明している。
2024.12.24
冬山装備は正しい使い方を学び、しっかりとした訓練を積みましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第371号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。 第371号では、冬山に向けて準備について言及。雪山の必須装備である、アイゼンとピッケル、そして雪崩対策の三種の神器、ビーコン、プローブ、ショベルについて、事前に使い方やメンテナンスを行なっておくよう促している。
2024.12.16
テントで就寝中にクマが!上高地発、「クマとヒトのいい関係」を考える【後編】
各地でクマの出没と事故が相次いでいる。現代の「クマとヒトのいい関係」とは。日本を代表する山岳景勝地で国立公園、上高地から考えてみた。
2024.12.07
クマ事故はなぜ起きた?私たちができることとは?上高地発、「クマとヒトのいい関係」を考える【前編】
各地でクマの出没と事故が相次いでいる。現代の「クマとヒトのいい関係」とは。日本を代表する山岳景勝地で国立公園、上高地から考えてみた。
2024.12.01
Page 10
グレーディングの低い山でも、相当の標高差があることを留意しましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第369号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第369号では、横尾山で起きた遭難について言及。難易度の低い山でも、油断のないよう説明している。
2024.11.29
コース選びは距離だけではなく、コースタイムや難易度など情報を多面的に確認しよう 島崎三歩の「山岳通信」 第368号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第368号では、上高地~涸沢間を通るパノラマコースで起きた遭難について言及。距離だけを見るのではなく、コースタイムなど多面的に情報を確認する必要性を訴えている。
2024.11.25
登りたい山と登れる山の選択、撤退の見極め、現在地の確認方法の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第367号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第367号では、期間中に起きた南アルプス池口岳の事例を取り上げ、「登りたい山と登れる山の選択」、「撤退の見極め」、「現在地の確認方法」の3点の確認を促している。
2024.11.19
入山前の計画段階で下調べをしっかり行うことは安全登山の秘訣 島崎三歩の「山岳通信」 第366号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第366号では、期間中に起きた北アルプス焼岳の事例を取り上げ、入山前に登山道の状況を下調べしておくことの大切さを説明している。
2024.11.15
富士山測候所の手書き観測記録が語る真実。1954年11月28日雪崩大量遭難事故の検証と将来予想
1954年の初冬の時期、富士山で雪山訓練をする登山者40人を襲った雪崩。これほどの規模の雪崩を、なぜ予測できなかったのか。その理由を読み解くとともに、暖冬が続く近年においても、雪崩の危険性は高まっている理由を説明する。
2024.11.05
きのこ採り目的の遭難が続発、危機感を持って入山・行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第365号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第365号では、きのこ採り中の遭難事故が続発している状況から、あらためてきのこ採りのリスクを説明、注意点を列挙している。
2024.11.01
登山経験の浅い方は、入山も下山も同じコースを通ってリスクの軽減を。 島崎三歩の「山岳通信」 第364号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第364号では、期間中に起きた遭難事例の詳細から、特に登山経験の浅い人に対してリスクを軽減するような計画や行動の具体例を指南している。
2024.10.28
高齢登山者による遭難事例から、長く安全に登山を楽しむためのポイントを学ぶ ~長野県・山岳遭難の現場から
夏山期間中、長野県内の遭難者125人のうち、6割を占めているのが高齢登山者となっている。高齢登山者による転倒や疲労の遭難が多発傾向にあるなか、9月に北アルプスで発生した2件の高齢登山者による遭難事例を取り上げ、長く安全に登山を楽しむためのポイントについて考察する。
2024.10.18
これからの季節の稜線歩きや縦走登山は上級者向けと考えて計画・入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第363号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第363号では、北アルプスの稜線の山小屋からは初氷や初雪の便りが届いている現状を説明し、安易な気持ちでの入山は控えるよう呼びかけている。
2024.10.17
登山は体への負担が大きいという認識をもって計画・入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第362号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第362号では、体調不良による遭難事故について取り上げ、「登山は体への負担が大きい」という認識をもつように促している。
2024.10.15
Page 11
富士山の遭難者数は減少。今夏の関東近郊の山々の状況を探る
今年の夏山シーズンも、ゲリラ豪雨や酷暑など厳しい気象条件に見舞われた。富士山では一部入山規制が実施され、効果が問われる年に。関東近郊の山々においても登山者の様子どうだったのか、現地の方に話を伺った。
2024.10.14
トレッキングポールの持ち主はどこへ? なんでもない普通の登山道で事故は起こった
南アルプス茶臼岳から下山していた男性が、急傾斜の登山道から滑落した。滑落リスクなどは低いと思われる場所で、なぜ事故が起こるのだろうか。
2024.10.13
今夏の山岳遭難、全国では減少も長野県は増加。北アルプスではなにが起きていたのか
今年も夏山シーズンが終わり、山にも街にも秋の訪れを感じるようになってきた。このタイミングで、今夏の山の様子を振り返ってみよう。今夏、山では何が起き、どのような登山者たちが増えてきたのか、北アルプスの山小屋主人たちに話をうかがった。
2024.10.04
ヘルメットを着用して安全を確保して登山を楽しみましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第361号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第361号では、「山岳ヘルメット着用奨励山域」について説明。区域以外でも、積極的に着用して安全を確保することを勧めている。
2024.10.03
パーティ登山では下山まで行動を共にすることが大原則。共に助け合い登山を楽しみましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第360号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第360号では、パーティーが別行動後に起きた遭難事案について言及。パーティ登山中は行動を共にすることが大原則であることを重ねて強調している。
2024.09.27
ファミリー登山では、子どもの安全・体調・装備の管理を大切に 島崎三歩の「山岳通信」 第359号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第359号では、ファミリー登山中の子どもの負傷遭難について取り上げ、子どもの安全・体調・装備の管理を慎重に行なうことを促している。
2024.09.21
日帰り・山小屋泊・高山・低山を問わず、ビバーク装備は必ず携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第358号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第358号では、「装備がないのでビバークができない」という遭難者が今週は複数人いたことについて言及。山行形態や山域にかかわらず、最低限のビバーク装備を携行するよう促している。
2024.09.18
中央アルプス、濃霧に包まれた登山道で一人きり。誤った方向に下山してしまい―― ~長野県・山岳遭難の現場から
この夏山シーズン、長野県では116件の山岳遭難が発生した。さまざまな事例がある中で、未然に防げた可能性の高い事故も少なくなかった。そこで今回は、リスクに備えることの重要性を伝える、中央アルプスでの遭難事例について考察する。
2024.09.12
日没時間が早まっている今、入山時刻を早めてリスクの回避を 島崎三歩の「山岳通信」 第356号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第356号では、浅間山で発生した日没に起因した道迷い遭難について言及。入山時刻、装備など、あらためて準備を万全にすることを促している。
2024.08.30
登山中にトラブルが発生した場合、まずは冷静に状況の確認を 島崎三歩の「山岳通信」 第355号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第355号では、登山中にトラブルが発生した後の行動について言及。冷静になって状況を確認して、救助要請の判断を行なうように促している。
2024.08.23
Page 12
登山コースとのミスマッチに起因する遭難事例が散見、適切な山選びを 島崎三歩の「山岳通信」 第354号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第354号では、登山コースとのミスマッチに起因する遭難事例が多いことを説明。コース選びには、「標高差」というファクターにも注視して山選びをすることを促している。
2024.08.15
登山中の体調不良が多発、疲労の原因となる脱水やカロリー不足とならないための行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第353号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第353号では、疲労から来る遭難事故が多発していることについて言及。疲労の原因となる脱水やカロリー不足とならないための行動を促している。
2024.08.09
本格的な夏山シーズン。山岳遭難&救助活動の実態を動画で知り安全登山を! 山岳遭難の現場から
長野県警では、山岳遭難の実態を多くの登山者に知ってもらうため、実際の救助活動の様子を「長野県警察YouTube 公式チャンネル」で公開している。その中から3つの事例をもとに、夏山登山中の注意点について解説する。
2024.08.06
なぜ夏の富士山で死ぬのか。過去の事例から考える
富士山で夏山遭難が多発している。過去の事例から夏の富士山で発生する遭難パターンを紹介し、それぞれの反省点を考えてみよう。
2024.08.03
【書評】遭難者たちの行動を追体験するドキュメント『ドキュメント 生還2 長期遭難からの脱出』
(評者=春日太一)どこにでもいそうな人たちが、誰でも登れる山に入る。だからこそ生じる心の隙に、自然環境が容赦なく襲いかかり、人々は遭難へと巻き込まれる。
2024.08.03
気象遭難を防ぐために、あらかじめ複数プランを準備しておきましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第352号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第352号では、気象遭難を防ぐために山岳遭難救助隊が行なっているノウハウを披露。あらかじめ複数プランを準備しておくことの大切さを説明している。
2024.08.02
「リーダーにおまかせ」や「ツアーガイドがいるから」という考えは大変危険です 島崎三歩の「山岳通信」 第351号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第351号では、パーティ登山やツアー登山でも遭難事故が発生していることや、忠告を聞き入れずに登山を続行して行動不能になった事例に言及。自分自身の体力や技術を把握し、判断するよう呼びかけている。
2024.07.26
濡れている木道や石の上を歩く場合は気を抜かずに足を置きましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第350号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第350号では、木製の橋で足を滑らせた遭難事故について言及。注意するポイントでは、気を抜かずに歩くことを説いている。
2024.07.19
こまめに休憩や補給をして、集中力を切らさず安全登山を 島崎三歩の「山岳通信」 第349号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第349号では、遭難の多くが疲労が蓄積する下山時に発生していることを指摘。こまめな休憩、補給をして、集中力を切らさないことを促している。
2024.07.12
突然の鉄砲水で流されてしまう|子どもとの外遊びで気をつけたいことを死亡事例から紹介③
お泊り保育で遊びに来ていた川で急な増水が発生し、流された5歳の男の子が死亡。
2024.07.09
Page 13
高山病で命を落とす|子どもとの外遊びで気をつけたいことを死亡事例から紹介②
父親と北アルプス・蝶ヶ岳(2677m)に登っていた16歳の男子高校生が、高山病が原因と見られる肺水腫で死亡。
2024.07.02
リスクを伴うコンディションが予想される場合、登山の中止や延期の検討を 島崎三歩の「山岳通信」 第347号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第347号では白馬大雪渓で起きた滑落遭難事例を取り上げ、リスクを伴う登山が予想される場合、登山の中止や延期、出発時間の変更などを検討するよう促している。
2024.06.28
早出早着、体力に見合ったルート選びなどの基本の徹底で安全登山を 島崎三歩の「山岳通信」 第346号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第346号では高妻山で起きた遭難事例を取り上げ、早出早着、体力に見合ったルート選びなどの基本をしっかりと守った計画・行動を促している。
2024.06.21
ひとりで先に行ってしまい転落|子どもとの外遊びで気をつけたいことを死亡事例から紹介①
家族と登山に来ていた11歳の男の子がひとりで山頂に向かい、行方不明に。
2024.06.21
スマホのバッテリーも食料も尽きた・・・不帰ノ嶮に消えた男性の運命は③【ドキュメント生還2】
幾日も山中で孤独に耐えて命をつなぎ、生還を果たした登山者たち。彼らは遭難中になにを考え、どうやって生き延びたのか。サバイバーたち4人の遭難に迫った書籍『ドキュメント遭難2 長期遭難からの脱出』から、北アルプスの不帰ノ嶮の遭難事例を紹介する。
2024.06.19
6月の遭難は残雪が影響。滑落や道迷いに注意
梅雨の長雨によって雪解けが急速に進む6月。しかし、残雪はまだまだ豊富で、滑落などの事故が起きやすい時期でもある。2023年6月の事故事例を見ていこう。
2024.06.16
道迷い遭難を防ぐために地図の携行とGPS機器の活用を 島崎三歩の「山岳通信」 第345号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第345号では中央アルプス木曽駒ヶ岳での道迷い遭難事例を取り上げ、地図とコンパスの携行とGPS機器の積極的な活用を勧めている。
2024.06.12
登山中は自身の登るルートをしっかりと地図で確認を 島崎三歩の「山岳通信」 第344号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第344号では八ヶ岳連峰赤岳の遭難事故について言及し、自身の登るルートをしっかりと確認することの大切さを説明している。
2024.06.06
手持ちのウェアをすべて着込んでも寒さは厳しく・・・不帰ノ嶮に消えた男性の運命は②【ドキュメント生還2】
幾日も山中で孤独に耐えて命をつなぎ、生還を果たした登山者たち。彼らは遭難中になにを考え、どうやって生き延びたのか。サバイバーたち4人の遭難に迫った書籍『ドキュメント遭難2 長期遭難からの脱出』から、北アルプスの不帰ノ嶮の遭難事例を紹介する。
2024.05.31
悪天候が予想される場合、登山計画そのものを中止する決断を 島崎三歩の「山岳通信」 第342号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第342号では槍ヶ岳で起きた遭難事故について取り上げ、悪天候が予想される場合は、登山の中止や延期の決断を促している。
2024.05.24
Page 14
登山歴の浅い方は、有名な山や標高の高い山から挑戦せず、少しずつレベルアップを 島崎三歩の「山岳通信」 第341号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第341号では、「遭難者の実力と山のレベルのミスマッチ」の事案を例に、有名な山から挑戦せずに、少しずつレベルの高い山へと挑戦することを促している。
2024.05.20
着実にステップアップしたはずの登山が・・・不帰ノ嶮に消えた男性の運命は①【ドキュメント生還2】
幾日も山中で孤独に耐えて命をつなぎ、生還を果たした登山者たち。彼らは遭難中になにを考え、どうやって生き延びたのか。サバイバーたち4人の遭難に迫った書籍『ドキュメント遭難2 長期遭難からの脱出』から、北アルプスの不帰ノ嶮の遭難事例を紹介する。
2024.05.19
滑落による死亡事故が多発。GWの山岳遭難を振り返る
毎年山岳遭難が多発する大型連休。2024年は大量遭難こそ発生しなかったものの、中部山岳などで死亡事故が相次いだ。
2024.05.17
連休中の遭難件数が過去10年で最大、体力・技術に見合った登山の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第340号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第340号では、連休中の遭難件数が過去10年で最多になったことについて言及。転倒や滑落による遭難が大多数で、あらためて体力・技術に見合った登山を促している。
2024.05.10
春の大型連休中、もしもの時のための装備を携行して万全な準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第339号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第339号では、北アルプス奥穂高岳周辺で起きた遭難を例に出して、標高の高い山では冬山装備が必要で、「もしもの時のための装備」も携行することを促している。
2024.05.02
雪解けで落石が発生しやすい時期。休憩中でも油断せず警戒を 島崎三歩の「山岳通信」 第338号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第338号では、落石による負傷遭難の事例を取り上げ、休憩中でも落石への警戒を怠ることのないよう説明している。
2024.04.26
雪山で遭難が多発するGW。昨年の事故事例から、注意点を考える
いよいよ大型連休が始まるが、例年雪山登山の事故が多発する。
2024.04.25
氷漬けのザックが問いかけること。ゴールデンウィークの気象遭難の教訓とは?
ゴールデンウィークといえば、初夏の陽気の中で過ごすイメージがあるかもしれない。しかし、強い寒気が入り込み、山岳地帯では猛吹雪となる例は過去に何度も起きている。今回は悲劇に見舞われた2例を紹介し、気象判断の重要性について考えたい。
2024.04.25
どんなときでも、どんな山でも「油断は禁物」という言葉を忘れずに 島崎三歩の「山岳通信」 第337号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2024年4月19日に配信された第337号では、写真撮影中に転倒した事案を取り上げ、「油断は禁物」という言葉の大切さを説いている。
2024.04.22
2023−24年シーズンの雪山遭難、件数は前年並み。BCや初級ルート、雪崩遭難多く
2023-24年の雪山シーズンはほぼコロナ前の状況に戻ったが、山岳遭難も同様だ。
2024.04.18
Page 15
“令和の山岳救助”のプロフェッショナル 、長野県警察山岳遭難救助隊 隊長、岸本俊朗さんインタビュー
長野県警察山岳遭難救助隊の隊長、岸本俊朗さんのインタビューをお送りする。岸本隊長を含めた山岳遭難救助隊の普段の活動内容や、活動時のエピソードなどについてうかがった。
2024.04.17
登山道が岩と氷のミックスとなる難しい状況の時期、慎重な歩行を 島崎三歩の「山岳通信」 第336号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第336号では、八ヶ岳連峰赤岳で起きた滑落事故について取り上げ、雪解けが進む登山道のコンディションの難しさについて注意を呼びかけている。
2024.04.12
いざというときの備えのために、ビバークセットの携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第335号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2024年4月4日に配信された第335号では、八ヶ岳・赤岳で発生した2件の遭難について取り上げ、いざというときの備えの重要性を強調している。
2024.04.08
単独での登山はリスクをよく理解し、技量に見合った山域への入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第334号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2024年3月22日に配信された第334号では、中央アルプスで起きた2件の事故がいずれも単独登山で、行方不明のままとなっていることについて言及。単独で入山するリスクの理解と対策について、あらためて説明している。
2024.03.25
【書評】志半ばで遭難した6人の軌跡を辿り人生と時代を回顧『未完の巡礼 冒険者たちへのオマージュ』
(評者=長谷川昌美)植村直己、長谷川恒男、星野道夫、山田昇、河野兵市、小西政継。「昭和」という時代の後半に活躍したこれらの著名な冒険家、写真家、登山家に共通するものといえば、いずれも志半ばにして海外で遭難、生還できなかったという事実だ。
2024.03.22
雪山では雪面状況が変わりやすい時期。特に急斜面の下りやトラバースの際は滑落に注意 島崎三歩の「山岳通信」 第333号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2024年3月14日に配信された第333号では、期間中に発生した2件の遭難事故はいずれも雪山から下山中にスリップして起きた事故であったことから、雪の状況の変化をしっかりと確認する大切さを説明している。
2024.03.15
【書評】山の危険と救助のリアルに迫る『剱の守人 富山県警察山岳警備隊』
(評者=木元康晴)富山県警察山岳警備隊は60年に近いその歴史のなかで、ノウハウを積み重ねてきた。山の危険を熟知した上で、二重、三重のバックアップも講じ、確実な登山者の救助をめざしている。
2024.03.15
2月10日の日没後、八ヶ岳・天狗岳で3件連続で救助要請。現場で起きていたこととは? 長野県警察山岳遭難救助隊レポート
2024年2月10日の日没後まもなく、長野県警では3件連続で山岳遭難の通報を受理した。いずれも八ヶ岳連峰の天狗岳周辺・・・。連休中、かつ冬型の気圧配置が強まる状況だったとはいえ、このとき何が起きていたのか、そしてその際の救助の実際は? それぞれの遭難の原因には、ある共通する「理由」があった。
2024.03.13
雪崩が発生しやすくなっている今、事前に雪の状態や雪崩注意報の発出状況の確認を 島崎三歩の「山岳通信」 第332号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第332号では、雪崩遭難事故について言及。寒暖差や急な降雪により雪崩が発生しやすくなっている今、事前に雪の状態や雪崩注意報の発出状況を確認して、入山を控える判断の必要性を説いている。
2024.03.08
ホワイトアウトで方向感覚を失い身動きが取れず。最悪の事態を回避できた冷静な判断―― 長野県警察山岳遭難救助隊レポート
「ホワイトアウトにより道に迷い行動不能。翌日に無事救出」。2024年1月7日に、中央アルプスの宝剣岳で起きた山岳遭難事故は、そんな短い言葉では語り尽くせないさまざまな要因が重なって起きたものだった。客観的に状況を把握したからこそ生還できた当時の様子を、長野県警察山岳遭難救助隊の目を通してレポートする。
2024.02.15
Page 16
「アプローチしやすい」という落とし穴。スキー場隣接のバックカントリーエリアで遭難相次ぐ
2月最初の週末に長野県で相次いだバックカントリースキーの遭難。いずれもスキー場隣接エリアでの道迷いだった。たとえアクセスが簡単な山でも、雪崩やルートミスといったバックカントリーのリスクは山深いエリアと変わらない。
2024.02.08
軽アイゼンで厳冬期の冬山登山縦走へ―― 2023年12月25日、八ヶ岳連峰で発生した遭難事例。長野県警察山岳遭難救助隊レポート
2023年末、八ヶ岳連峰で山岳遭難事故が発生した。「凍結した登山道で滑落して行動不能、救助された」という一言では説明できない実際の救助の様子を、実際に救助に当たった長野県警察山岳遭難救助隊が掘り下げ、遭難事故が起きた背景を検証。登山中のリスク対策や事前準備の重要性について、あらためて問いかける。
2024.01.22
県内の積雪量は増加中。雪のコンディションを確認して入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第327号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第327号では、積雪量の増加に伴いバックカントリーでの遭難が増加している現状を分析。天気予報を確認して、リスクの高いコンディションでは入山を控えるよう呼びかけている。
2024.01.19
「先に山小屋に行く」と言って雪の雲取山で消えてしまったリーダー
2024.01.13
冬山特有の遭難事故が増加中。コンディションや積雪量を考慮した行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第326号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2024年1月11日に配信された第326号では、冬山特有の遭難事故が増加していることについて取り上げ、事前準備、積雪量を考慮した行動に加えて、登山口やスキー場などへ移動する際の車の運転などにも注意することを促している。
2024.01.12
低体温症の恐ろしさ――、強風が退路をはばんだ3つの事例から学ぶ(1902八甲田山、1963薬師岳、2009鳴沢岳)
登山中のリスクで、季節を問わず気をつけたいのが「低体温症」。気温、風、そのほかの3つの要因で発生するといわれる低体温症だが、今回は特に「強風が退路をはばんだ事例」について注目。過去に取り上げた遭難事例から、低体温症の恐ろしさを考える。
2024.01.12
埋没から3時間1分。ついに救出! 北アルプス・白馬乗鞍岳裏天狗の雪崩事故③
捜索終了時刻の4分前、埋没から3時間1分。ついに救出!
2024.01.06
1月の奥多摩で行方不明になった夫。春になっても、妻は交番に情報を求めに訪ね続けた
2024.01.06
雪崩トランシーバーの信号がない。「ほんとうにまずい事態になってしまった・・・」北アルプス・白馬乗鞍岳裏天狗の雪崩事故②
雪崩が発生し、スノーボーダーが埋没した。雪崩トランシーバーの信号が捉えられず、プロープ捜索が始まった。
2024.01.05
絶対に逃れられないジェットコースターに載せられたようだった・・・北アルプス・白馬乗鞍岳裏天狗の雪崩事故①
2020年2月28日 北アルプス・白馬乗鞍岳裏天狗の雪崩事故を事故当事者たちの証言から検証し、紹介する。
2024.01.04
Page 17
コロナ以前の事例を中心に、年末年始の遭難パターンを振り返る
雪山で年越しをする登山者で山がにぎわう年末年始。首都圏近郊の山などでも、冬休みを利用したハイキングに出掛ける人が増える時期だが、毎年少なくない数の山岳遭難が起きている。コロナ前の事例を中心に、年末年始の事故のパターンを見てみよう。
2023.12.30
早めの行動、早めの判断で安全確保し、安全登山の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第325号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第325号では、期間中に起きた2件の遭難事例について紹介するとともに、早めの行動と判断の大切さを説明している。
2023.12.28
道迷いからの滑落。重傷を負いながらも13日目に生還。当事者が6年ぶりに現場再訪
道迷いから滑落し、13日後に生還した男性が、遭難現場を再訪問した。
2023.12.27
「急に目の前が真っ白になりフラフラに・・・」登山者の遭難・ヒヤリハット体験 体調不良編
山と溪谷オンラインで実施したアンケートで集めた、遭難・ヒヤリハット体験の中から、体調不良に関する体験談を紹介。
2023.12.21
スキー場での滑走ではコース外のリスクを知り、ルールを守った行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第324号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第324号では、本格的なスノーシーズン幕開けの今、スキー場での滑走ルールの遵守をあらためて促している。
2023.12.18
「思い込みって恐ろしい・・・」登山者の遭難・ヒヤリハット体験 道迷い編
山と溪谷オンラインで実施したアンケートで集めた、遭難・ヒヤリハット体験の中から、道迷いに関する体験談を紹介。
2023.12.12
「フラッと意識が遠のき、崖下へ転落・・・」登山者の遭難・ヒヤリハット体験 転倒・滑落編
山と溪谷オンラインで実施したアンケートで集めた、遭難・ヒヤリハット体験の中から、転倒・滑落に関する体験談を紹介。
2023.12.05
「もしもーし、遭難しました」。携帯電話普及による安易な救助要請の増加に懸念
2023.11.19
日没後の行動やアクシデントに備えて計画を行い装備品の準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第322号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第322号では、期間中に起きた遭難がいずれも日没による道迷いが原因だったことを説明。事前の下調べと必要な装備品の携行の重要性を説いている。
2023.11.14
奥多摩に滝を見に行き、道迷い。深夜2時まで続いた83歳リーダーの奮闘
奥多摩に滝を見に行った高齢者パーティの悲惨な山行の顛末。
2023.11.13
Page 18
山岳遭難はいっこうに減らず、増えるばかり——それでも、ライターの羽根田治さんが取材を続ける理由
長年、遭難事故の取材を続けている羽根田治さんへのインタビュー。なぜ遭難事故の発信を続けるのか。
2023.11.07
家族に場所も告げずに山に行き、行方不明になった男性。せめてメモ一枚だけでも残してくれていたら…
家族に場所も告げずに山に行った男性が行方不明に…わずかな手がかりで行なわれた捜索は難航する。
2023.11.06
道迷いや日没などのアクシデントに備えて、携帯電話やヘッドライト、防寒着等の携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第321号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第321号では、期間中に起きた道迷い遭難について言及。アクシデントに備えて、携帯電話やヘッドランプ、防寒着などの装備品の携行を強く促している。
2023.11.02
山で道に迷っても沢に降りてはいけない理由とは?
奥多摩で人気のバリエーションルートでの道迷い遭難・・・。捜索の結果、沢で遺体が発見された。「道に迷っても沢に降りてはいけない」理由とは?
2023.10.27
奥多摩の山中で滑落。重傷を負い、飲まず食わずで5日間過ごした女性
5月10日、午前8時。ボロボロになった女性が山から下りてきた。彼女は山で滑落し、5日間飲まず食わずで救助を待っていたという。
2023.10.23
日没時間が早まっている現在、どんな山行でもヘッドランプの携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第319号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第319号では、冬が近づくにつれて日没時間が早まっていることを説明。樹林帯では日没前から暗くなりやすいため、どんな山行でもヘッドランプの携行を強く推奨している。
2023.10.20
標高の高い稜線では積雪する時期。夏山登山の延長では入山不可 島崎三歩の「山岳通信」 第318号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。寒気の流入で県内の標高の高い稜線では、みぞれや吹雪となり、低体温症による行動不能遭難が相次いだことについて言及。夏山登山の延長では入山できないコンディションとなっていることを説明している。
2023.10.18
八甲田山雪中行軍遭難事故の検証 ~雪中行軍ルートを辿り、強風で飛ばされそうになりながらも紅葉が始まった八甲田山に登る~
2023年6月に発表し、大きな反響を呼んだ「NOAA(アメリカ海洋大気庁)による再解析データを用いた八甲田山雪中行軍遭難事故の検証記事」。その再検証のために八甲田山に訪れた山岳防災気象予報士の大矢康裕さん。地形や当時の資料を確認すると、あらためて事故当時の状況が見えてきたのだった。
2023.10.12
過去の体力を過信せず、現在の体力や体調を考慮した上での登山を 島崎三歩の「山岳通信」 第317号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第317号では、高齢の登山者の遭難事故について言及。過去の体力を過信せず、現在の体力や体調を考慮した上で登山を楽しむようお願いしている。
2023.10.06
寒さや防風対策のために、ダウンやフリース、手袋などの装備を携行しましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第316号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第316号では、県内は徐々に気温が下がり、標高の高い山域では氷が張るほど冷えてきていることを説明。寒さや防風対策のために、ダウンやフリース、手袋などの装備を携行を促している。
2023.09.28
Page 19
【書評】当時の常識を覆した34年前の裁判に迫るノンフィクション『天災か人災か?松本雪崩裁判の真実』
「雪崩は人災だった」。34年前の雪崩死亡事故裁判について、その一部始終をまとめたノンフィクション。
2023.09.24
緊張が緩んだ瞬間に遭難は発生しやすいことを理解し、下山まで慎重な行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第315号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第315号では、遭難の多くは緊張が緩んだ時に発生しやすいことを指摘し、慎重な行動を意識することを促している。
2023.09.22
2023年夏、ついに山岳遭難が史上最多に。夏山シーズンになにが起きていたのか
コロナ禍で減少傾向が続いていた夏山遭難だが、2023年は山岳遭難が多発。発生件数・遭難者数とも過去最多となった。しかし、死亡事故は必ずしも多くはない。今年、夏山ではなにが起きていたのか。
2023.09.22
北アルプスで滑落や転倒による遭難が続発、集中力を切らさずに行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第314号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第314号では、北アルプスにおける滑落や転倒による遭難が相次いでいる現状について取り上げ、集中力を切らさないようにゆとりを持った行動をすることを提言している。
2023.09.15
日帰り登山であっても、万一に備えた装備の準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第313号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第313号では、特に四方原山で起きた遭難事故について取り上げ、日帰り登山であっても万一に備えた装備を準備しておくことの大切さを説明している。
2023.09.12
あなたは切り抜けられるか? 予期せぬアクシデントの襲来! マンガで楽しくわかる『失敗から学ぶ登山術』
トラブルを防ぐカギは計画と準備にあり! 登山の計画と準備の重要性を、マンガで解説する連載です。連載第14回は「山の装備の応急処置」。登山用具にも、「もしも」のケースがあることを認識して計画するのは、なかなか難しいものですが・・・。
2023.09.08
穂高連峰で滑落による遭難が増加傾向、危険箇所では落ち着いて行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第312号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第312号では、とくに北アルプス穂高連峰で滑落による遭難が増えていることについて言及。危険箇所を通過する際は一呼吸を置くなど、落ち着いて行動をすることを推奨している。
2023.08.31
天気が急変して突発的な雷雨となる天気に注意、「早出・早着」を。島崎三歩の「山岳通信」 第311号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第311号では、突発的な雷雨となる天気が続いている状況を説明。「早出・早着」を心掛け、余裕を持った日程で行動することを促している。
2023.08.29
下山中の滑落・転倒が多数発生、休憩・エネルギー補給などで集中力を高める対策を 島崎三歩の「山岳通信」 第310号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第310号では、下山中に滑落・転倒により発生した遭難事故が大半を占めている状況を説明し、慎重に行動するための対策(休憩・エネルギー補給)をとるように推奨している。
2023.08.21
脱水や熱中症と思われる疲労遭難が多発。暑さ対策を万全に 島崎三歩の「山岳通信」 第309号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2023年8月14日に配信された第309号では、脱水や熱中症と思われる疲労による遭難が非常に多いことに言及。また、北アルプスの一部の山小屋では水不足が生じていることにも触れ、多めの飲料水携行と事前の情報収集を呼びかけている。
2023.08.15
Page 20
いよいよ盆休み、夏山遭難は多発中。 リスク情報をしっかりと把握しよう
新型コロナウイルスの5類移行と梅雨明け前から続いた好天により、多くの登山者が山に戻ってきた2023年の夏山シーズン。しかし、登山者の増加と同時に遭難が急増している。
2023.08.11
疲労・体調不良による遭難が増加傾向、ゆとりある計画とこめまな休憩で対策を 島崎三歩の「山岳通信」 第308号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第308号では、疲労や体調不良による遭難が多発している状況を踏まえ、ゆとりある計画、こまめな休憩、意識して水分やカロリーを補給するなどの対策をすすめている。
2023.08.07
重大事故につながる「滑落」が増加傾向、普段以上に慎重な行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第307号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2023年7月26日に配信された第307号では、急峻な岩稜での事故が増加傾向にあることから、登山者には普段以上に慎重な行動をお願いしている。
2023.07.27
捜す、寄り添う―山岳遭難捜索6つのドキュメント『「おかえり」と言える、その日まで』【書評】
捜索は、目に見えない足取りを追うことである。家族や山仲間から当日の服装や持ち物はもちろんのこと、登山者の行動パターンや登山の志向なども聞かせてもらいプロファイリングをしていく。
2023.07.18
夏山を安全に登山を楽しむために伝えたい「7つのお願い 」 島崎三歩の「山岳通信」 第305号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第305号では、熱中症や疲労による遭難が多発する時期となっていることを説明。事前の体調管理や早出・早着など、基本的な対策方法について改めて伝えている。
2023.07.14
夏山診療所からの提言⑥外傷・障害の診療事例と対策
雑誌『山と溪谷』2023年7月号より、山岳診療所を取材した企画を紹介。外傷・障害の診療事例から、予防・対処法を学ぶ。
2023.07.12
夏山シーズン初めに多い遭難とは? 事故事例に見る夏山の危険
梅雨明けと共に本格的な夏山シーズンが始まる。2022年の遭難事例を振り返って、夏山期の初めに起きがちな事故のパターンを考えてみたい。
2023.07.11
夏山診療所からの提言⑤ 突然死の診療事例と対策
雑誌『山と溪谷』2023年7月号より、山岳診療所を取材した企画を紹介。突然死の診療事例から、予防・対処法を学ぶ。
2023.07.07
夏山シーズンは「体調不良」が多発、疲労・熱中症・病気による遭難を回避する準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第304号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第304号では、夏山シーズンに多い「疲労・熱中症・病気による遭難」について言及。事前の準備・計画・トレーニングの大切さを説明している。
2023.06.30
2022年の山岳遭難、件数・遭難者数とも過去最多に
警察庁のまとめによると、2022年はついに山岳遭難件数、遭難者数とも過去最多となった。一方で無事救助されるケースも多いことなどから、体力不足が原因の事案も多いとみられる。
2023.06.27
Page 21
余裕を持った登山計画と最低限のビバーク装備携行の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第303号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第303号では、疲労による山岳遭難について言及。余裕を持った登山計画の大切さを説明すると同時に、最低限のビバーク装備の携行を促している。
2023.06.23
夏山診療所からの提言④ 低体温症の診療事例と対策
雑誌『山と溪谷』2023年6月号より、5つの山岳診療所を取材した企画を紹介。低体温症の診療事例から、予防・対処法を学ぶ。
2023.06.20
1902年1月の八甲田山雪中行軍遭難事故の真実/鮮やかに蘇った120年前の天気図と気象状況
登山者ならずとも、冬山での遭難事故として、多くの人が知っている『八甲田山死の彷徨』。1902年(明治35年)に199名が凍死した大惨事の原因は大寒波と異常低温とされているが、実際に当時のデータを紐解いてみると、意外な事実が浮かび上がってきた。
2023.06.16
梅雨の時期、悪天候のリスクを理解して状況に応じた登山計画と判断を 島崎三歩の「山岳通信」 第301号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第301号では、梅雨入りして悪天候のリスクが高まる可能性を理解して、状況に応じて登山計画の中止や延期などの判断を行えるようにしておくことを促している。
2023.06.09
夏山診療所からの提言③ 熱中症の診療事例と対策
雑誌『山と溪谷』2023年6月号より、5つの山岳診療所を取材した企画を紹介。
2023.06.08
北・南アルプスで遭難頻発、 若年~中年世代の滑落などが増加。GWの遭難を振り返る
天候に恵まれた今年のGW。昨年までは敬遠された北・南アルプスなどの本格的雪山に出かける人が増えたとみられ、これらのエリアで遭難事故が頻発した。
2023.06.03
行き先の積雪状況やルート状況を確認して残雪期登山のリスクを念頭に慎重な行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第300号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第300号配信を迎え、令和2年~4年の3年間について長野県内の日本百名山における山岳遭難発生状況を長野県警察本部山岳安全対策課の山岳遭難統計を併せて発表している。
2023.05.29
夏山診療所からの提言②高山病の予防・対処法
登山者にとって、深刻なトラブルとなるケガや病気。雑誌『山と溪谷』2023年5月号より、5つの山岳診療所を取材した企画を紹介したい。夏山シーズンを前に、主な傷病の事例、および予防法や対処法を解説する。第1回の高山病の診療事例に続いて、今回は医師たちが提案する予防と対処の方法を見ていこう。
2023.05.16
GW中は滑落事故が多発。装備を整え、余裕のある日程で登山を楽しみましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第299号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第299号では、GW中に多くの滑落事故が起きたことについて言及。装備を整え、余裕のある日程で登山を楽むことの重要性を説いている。
2023.05.15
GWの山小屋の惨状。あらためて問われる入山者の良識
ゴールデンウィークの日本アルプスの山小屋で起きた「事件」。登山の常識からは考えられないような行為にどう対応すればよいのか、山小屋関係者は当惑を隠せない。
2023.05.13
Page 22
夏山診療所からの提言① 高山病の診療事例
登山者にとって、深刻なトラブルとなるケガや病気。雑誌『山と溪谷』2023年5月号より、5つの山岳診療所を取材した企画を紹介したい。夏山シーズンを前に、主な傷病の事例、および予防法や対処法を解説する。今回は実際に医師たちが体験した、高山病の診療事例を見ていこう。
2023.05.12
残雪登山の事故が多発!2022年の事例に学ぶGWの遭難対策
大型連休に合わせ、各地で山開きが行なわれるが、高山や豪雪地帯の山は、まだまだ雪山シーズン真っ只中。気温が上がって冬山シーズンよりも登りやすいと考えられがちだが、毎年天候の急変などに起因する気象遭難が多く起きる時期でもある。
2023.04.27
パーティで入山した以上は下山するまで行動を共にしましょう 島崎三歩の「山岳通信」 第298号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第298号では、期間中にあった1件の遭難事故について取りあげ、パーティで入山した以上は、下山するまで行動を共にすることを推奨している。
2023.04.26
13年を振り返りいま一度見直す山との向き合い方『山のリスクとどう向き合うか 山岳遭難の「今」と対処の仕方』【書評】
「登山者の山への向かい方も変わった。特に影響したのは、スマートフォンの普及だ。初めて見たときはいかがわしいとすら感じた地図アプリが、今や必須のものになった。さらに情報収集や登山届の提出、記録の作成と公開、仲間との交流まで、スマホやインターネットで行なうようになったのだ。」
2023.04.24
身近な低山での遭難事例から教訓を学ぶ『侮るな東京の山 新編 奥多摩山岳救助隊日誌』【書評】
タイトルのとおり、東京の山は侮られがちなのだろう。よく界隈の山岳関係者がヘッドランプも持たない登山者に対して苦言を呈している。
2023.04.23
山での遭難……「遭難救助費用」の請求が発生するケースとは?
Q. 遭難した後、無事に下山したら遭難救助費用を請求されました。自分から救助を依頼したわけじゃなくても支払う必要はあるんですか?
2023.04.20
長野県警察山岳遭難救助隊長からの「7つのお願い」 島崎三歩の「山岳通信」 春の特別号
長野県の山岳地域で発生した遭難事例をお伝えし、「安全登山」のための情報提供をしている島崎三歩の「山岳通信」今回は、春の特別号として県警救助隊長の岸本俊朗さんからの「7つのお願い」を掲載します。
2023.04.19
1965年ゴールデンウイークに起きた「メイストーム」による大量遭難事故――、東シナ海低気圧によって想像できないほどの暴風雪が襲う
GWの時期、「メイストーム」と呼ばれる現象で、急な天候変化が起きることがある。過去にもGWに気象遭難は多発しているが、なかでも1965年には、このメイストームにより死者62名にものぼる事案が発生していた!
2023.04.18
春山特有の日中の寒暖差について理解して、安全に行動できる技術を身につけてから入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第297号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第297号では、春山特有の標高の高い山域での日中の寒暖差について言及。アイゼンやピッケルを使って安全に行動できる技術を身につけて入山することを推奨している。
2023.04.14
気象変化や寒暖差が激しい時期、雪の状態が変化による転倒・滑落に注意を 島崎三歩の「山岳通信」 第296号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第296号では、この時期の残雪の山では雪の状態が変化しやすく、アイスバーン状の雪面で滑落や転倒に注意が必要なことを説明している。
2023.03.30
Page 23
雪山遭難が続発した2022〜23年の冬を振り返る
2022〜23年の冬山シーズンは山岳遭難が相次ぎ、発生状況はコロナ禍前に戻ってしまった。
2023.03.23
雪解けが進んで岩と氷雪が混在したコンディションでは特に滑落に注意を! 島崎三歩の「山岳通信」 第295号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第295号では、雪解けが進んだ稜線付近では岩と氷雪が混在したコンディションとなり滑落や転倒のリスクが非常に高くなっていることを説明。安全第一の行動を心掛けることを推奨している。
2023.03.16
気象遭難、滑落…前年の事例から考える、春の雪山のリスク
春は気温差が大きく周期的に天気が変化する、気象などの判断が難しい季節。2022年の事例から、春の登山で起きやすい事故のパターンをピックアップしてみた。
2023.03.11
気温上昇の時期、寒暖の差から起きる雪面状況の変化に対応できる準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第294号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第294号では、今後の気温上昇予測に関して言及。一日の寒暖差が大きくなることで起きる雪面状況の変化に対応できる準備を促している。
2023.03.03
安易な入山が招く表丹沢の遭難事例|神奈川県警山岳救助隊活動ファイルから③
塔ノ岳をはじめとする表丹沢はアプローチがしやすいこともあり、安易な入山が招く事故も多発している。秦野署山岳救助隊が対応した救助の実例について聞いた。
2023.03.03
バックカントリーで滑走する際は、事前に気象・装備・計画など各方面から安全対策の徹底を 島崎三歩の「山岳通信」 第293号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第293号では、4件の山岳遭難のうち3件がバックカントリーでの遭難だったことについて言及。事故を回避するために、気象、装備、計画など各方面から安全対策の徹底を呼びかけている。
2023.02.22
積雪期の登山では体力と時間が相当に必要。余裕を持った登山計画を立てることが大切 島崎三歩の「山岳通信」 第292号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第292号では、十分余裕を持った登山計画を立てるとともに、現在地と時間をこまめに確認して引き返すことも考慮した行動を促している。
2023.02.13
雪崩注意報が発出されている場合は雪山への入山を中止する判断を 島崎三歩の「山岳通信」 第291号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第291号では、相次いだバックカントリーでの事故について言及。入山前に降雪状況、温度の変化、風雪の状況などをを確認し、雪崩注意報が発出されている場合は入山を中止する判断を促している。
2023.02.06
冬山シーズン本格化、遭難も多発中。遭難事例から雪山のリスクを考えよう
本格的な冬山登山シーズンを迎え、各地で雪山での事故が相次いでいる。2022年1月の事例を振り返りながら、雪山のリスク管理について考えてみよう。
2023.01.31
日高山脈で起きた国内最大級の雪崩と、感動を呼んだ『雪の遺書』。1965年3月の北海道大学山岳部の雪崩遭難事故。
雪山での重要なリスクの一つである雪崩。1965年3月に起きた「国内最大級の雪崩規模」とされる『北海道大学山岳部の雪崩遭難事故』と、感動を呼んだ『雪の遺書』を資料に、雪崩のメカニズムを読み解き、その教訓を考える。
2023.01.30
Page 24
人気の観光地・大山登山の落とし穴|神奈川県警山岳救助隊活動ファイルから②
観光客と登山者が多い丹沢の大山(1252m)。気軽に訪れやすい山ならではの遭難について、伊勢原署山岳救助隊に実例を聞き、回避策について考えてみた。
2023.01.29
登山では一緒に入山した以上は最後まで一緒に下山することが大原則 島崎三歩の「山岳通信」 第290号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。2023年1月26日に配信された第290号では、昨今のパーティ登山について言及。一緒に入山した以上は最後まで一緒に下山することを大原則として行動することを推奨している。
2023.01.27
クライミング事故の責任は誰にある? 登山の娯楽性と危険性に切り込むノンフィクション【後編】
1986年に起こったクライミング事故を通して、訴訟社会アメリカの姿を浮き彫りにするストーリーを、前後編に分けて紹介。
2023.01.24
クライミング事故の責任は誰にある? 登山の娯楽性と危険性に切り込むノンフィクション【前編】
1986年に起こったクライミング事故を通して、訴訟社会アメリカの姿を浮き彫りにするストーリーを、前後編に分けて紹介。
2023.01.17
冬山特有の山岳遭難が増加中。十分な準備と慎重な行動を! 島崎三歩の「山岳通信」 第289号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第289号では、アイスクライミング、バックカントリーなど、冬山ならではの山岳遭難が発生していることを挙げて、十分な準備と慎重な行動を促している。
2023.01.13
丹沢・檜洞丸の滑落に見る、山岳遭難の現在|神奈川県警山岳救助隊活動ファイルから
神奈川県では、このところ山岳遭難が急増している。気候は比較的温暖で、標高もさほど高くない神奈川の山で山岳遭難が後を立たないのはなぜなのか。山岳救助隊員のインタビューを通して、遭難の実例とその背景を考えてみたい。
2022.12.30
雪山では悪天候時の登山は命取り、アクシデントに対応できる準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第288号
長野県が県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第288号では、冬山の厳しいコンディションについて改めて言及。自身の体力・経験に見合った山選びをすることの大切さを説明している。
2022.12.28
慎重過ぎるぐらいの計画と日頃のトレーニングにより安全な登山を 島崎三歩の「山岳通信」 第287号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第287号では県内の山は厳冬期に入り、厳しいコンディションとなっていることを説明。慎重過ぎるぐらいの計画と日頃のトレーニングにより、安全な登山を心掛けるよう促している。
2022.12.16
晩秋・初冬の登山の落とし穴。山岳遭難の事例を振り返る
本格的な雪山登山シーズンを迎えるまでの短い間、山は静けさを取り戻す。しかし、そうした季節の狭間の山でも遭難が相次いでいる。この季節の登山でどんな事故が起きているのか、過去事例を振り返りながら事故の回避策を考える。
2022.11.29
冬山となった県内の山では厳しい環境下での判断力が求められます 島崎三歩の「山岳通信」 第286号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第286号では、冬山では厳しい環境下での判断力が求められることを指摘。自身や仲間の技量に見合った登山をすることを促している。
2022.11.25
Page 25
1980年12月逗子開成高八方尾根遭難事故の真相――二つ玉低気圧のちドカ雪のち晴れ、動かなければ助かったかも
1980年12月に起きた逗子開成高校八方尾根遭難事故の真相と過去のデータを紐解くと、さまざまな教訓が見えてくるという。その中でも特に重要なのが「内陸部にある山岳では12月のドカ雪に注意、しかし12月のドカ雪は待てば止む可能性が高い」ということである。
2022.11.17
凍結路で致命的な転倒や滑落遭難を防ぐために装備および技術的な準備を 島崎三歩の「山岳通信」 第285号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第285号では冬山シーズンとなりつつある今、凍結路で致命的な転倒や滑落遭難を防ぐための装備および技術的な準備をすることを促している。
2022.11.10
日に日に冷え込みが厳しくなる県内の山。降雪・凍結対策を行って入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第284号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第284号では、県内の山では日に日に冷え込みが厳しくなり、日没時刻も早くなっている状況に対応した準備を促している。
2022.11.04
日没時間の早まりによって行動時間は限られています。ヘッドランプなどは必ず携行を 島崎三歩の「山岳通信」 第283号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第283号では、日没時間が早まり、行動できる時間が短くなっていることについて言及。何かしらのアクシデントに備えて、ヘッドライトやビバーク装備、防寒具などは必ず携行するように促している。
2022.10.28
道迷い遭難を避けるためにも、こまめな休憩&現在地確認を 島崎三歩の「山岳通信」 第282号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第282号では、道迷い遭難について言及。こまめに休憩を取って地図で現在位置を確認するなどの対策で、着実にリスクを減らせることを伝えている。
2022.10.24
実は危険な秋山登山。遭難事例からリスクを考える
紅葉のシーズンを迎えて、登山計画を立てている人も多いことだろう。しかし、秋山は遭難が多い季節でもあり、今秋も事故が多発している。2021年秋に発生した事例を振り返りながら、秋山で注意すべきポイントを考えてみよう。
2022.10.21
降雪も記録し夏山とは違うコンディションに。状況を確認して計画・行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第281号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第281号では、降雪を記録するほど冬が近づいてきている状況を説明。夏山とは違った状況になっていることを理解して、計画・行動することを促している。
2022.10.14
県内の山は急激な気温低下。気象状況に見合った計画と行動を! 島崎三歩の「山岳通信」 第280号
長野内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第280号では、県内の山では急激に気温が低くなっている状況を説明。それに伴うリクスを挙げて、事故につながらないような行動・計画を行うよう呼びかけている。
2022.10.11
台風通過後も続いた暴風雨――、北海道では常識は通用しないこともある。1999年9月羊蹄山登山ツアー遭難事故の教訓
「台風の進行方向(北東)の右側は危険半円」とよく言われるが、すべての台風において当てはまるわけでもなく、また地域によってもその実情が変わるケースもある。1999年9月に北海道・羊蹄山で起きた遭難事故を紐解くと、常識だけでは判断できないことが見えてきた。
2022.10.03
登山中に何らかの体調不良の徴候があった際には、早めに決断・対処を 島崎三歩の「山岳通信」 第278号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第278号では、疲労や病気に起因する遭難事故について言及。登山中に何らかの体調不良の徴候があった際には、遭難の一歩手前にいると自覚して早めに対処することが重要と説明している。
2022.09.26
Page 26
北アルプスでは滑落事故が多発。2022年夏山の山岳遭難を振り返る
withコロナの動きが進んだこともあり、登山者が増加に転じた2022年の夏山シーズン。しかし、それに伴って増加したのが山岳遭難だ。このほどまとまった警察庁の夏山遭難の統計をひもときながら、『山と溪谷』で山岳遭難を定点観測するライターが北アルプスで発生したこの夏の遭難を振り返る。
2022.09.21
スリップ・転倒の事故が急増、行動中はリスクが潜んでいることを念頭に行動を 島崎三歩の「山岳通信」 第277号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第277号では、スリップや転倒で滑落するケースが多く見られることを説明。行動中はリスクが潜んでいることを念頭に、慎重な行動をすることを促している。
2022.09.16
疲労や病気での行動不能遭難者が多発、今現在の自分の体力を把握した上で入山を 島崎三歩の「山岳通信」 第276号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第276号では、中高年登山者の疲労や病気による行動不能遭難も多発している現状について、今現在の自分の体力を把握した上での入山を呼びかけている。
2022.09.08
秋が訪れている長野県内の山、装備の見直しをしてから入山を! 島崎三歩の「山岳通信」 第275号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第275号では県内の山間部では秋の気配を感じるようになっており、装備を見直してから登山をすることを促している。
2022.09.01
「もしも」に備えた準備を万全にして、早出・早着の心掛けを 島崎三歩の「山岳通信」 第274号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第274号では、「もしも」に備えた準備を万全にしておくことの大切さを説明。十分な装備の携行と早出・早着を心掛けることを促している。
2022.08.26
もしも今、伊勢湾台風が襲ってきたら山の天気はどうなるのか? JRA-55を使って当時の状況を再現
台風災害としては明治以降で最多の死者を出した、1959年の伊勢湾台風。この台風は、大台ヶ原の原生林を一夜で立ち枯れ林としたほど、山岳地帯にも甚大な被害を出したことでも知られているが、はたしてこの規模の台風が再び上陸したら――。そんなシミュレーションを、JRA-55を使って再現する。
2022.08.24
他人事ではない生還へのヒント『山はおそろしい 必ず生きて帰る! 事故から学ぶ山岳遭難』【書評】
山での遭難といえば、道迷い、転・滑落、雪崩などを連想する方が多いと思うが、過去の常識では考えられない「まさか」ということが近年の山では起きている。本書では数々の「まさか」が紹介され、興味深い事例がいくつか取り上げられており、あらためて山に存在する隠れたリスクについて考えさせられた。
2022.08.23
コース選びの失敗! 本当にあった谷川岳の悲劇―― マンガで楽しくわかる『失敗から学ぶ登山術』
トラブルを防ぐカギは計画と準備にあり! 登山の計画と準備の重要性を、マンガで解説する新連載。第1回は「コース選びの失敗」。初心者のいるパーティで、谷川岳の難路を下ってしまい・・・。
2022.08.04
樹林帯での雨具着用時に落雷が発生――。2002年8月2日の塩見岳落雷事故の教訓
夏山のリスクの1つとして挙げられるのが「落雷事故」。回避するのに最も大切なのは「早出早着」となるが、いざ山中で雷鳴を聞いたとき、どうすればよいのか? 2002年8月、南アルプス塩見岳で起きた落雷事故の当時の気象状況を教訓に、夏山を楽しむ知識を指南する。
2022.07.22
登山計画時に行き先の残雪状況や、迷いやすい分岐点について十分な確認を 島崎三歩の「山岳通信」 第269号
長野県内で起きた山岳遭難事例について配信している「島崎三歩の山岳通信」。第269号では、残雪でのスリップ事故について言及。登山計画を立てる際には、行き先の残雪状況や、迷いやすい分岐点について、十分な確認を促している。
2022.07.15