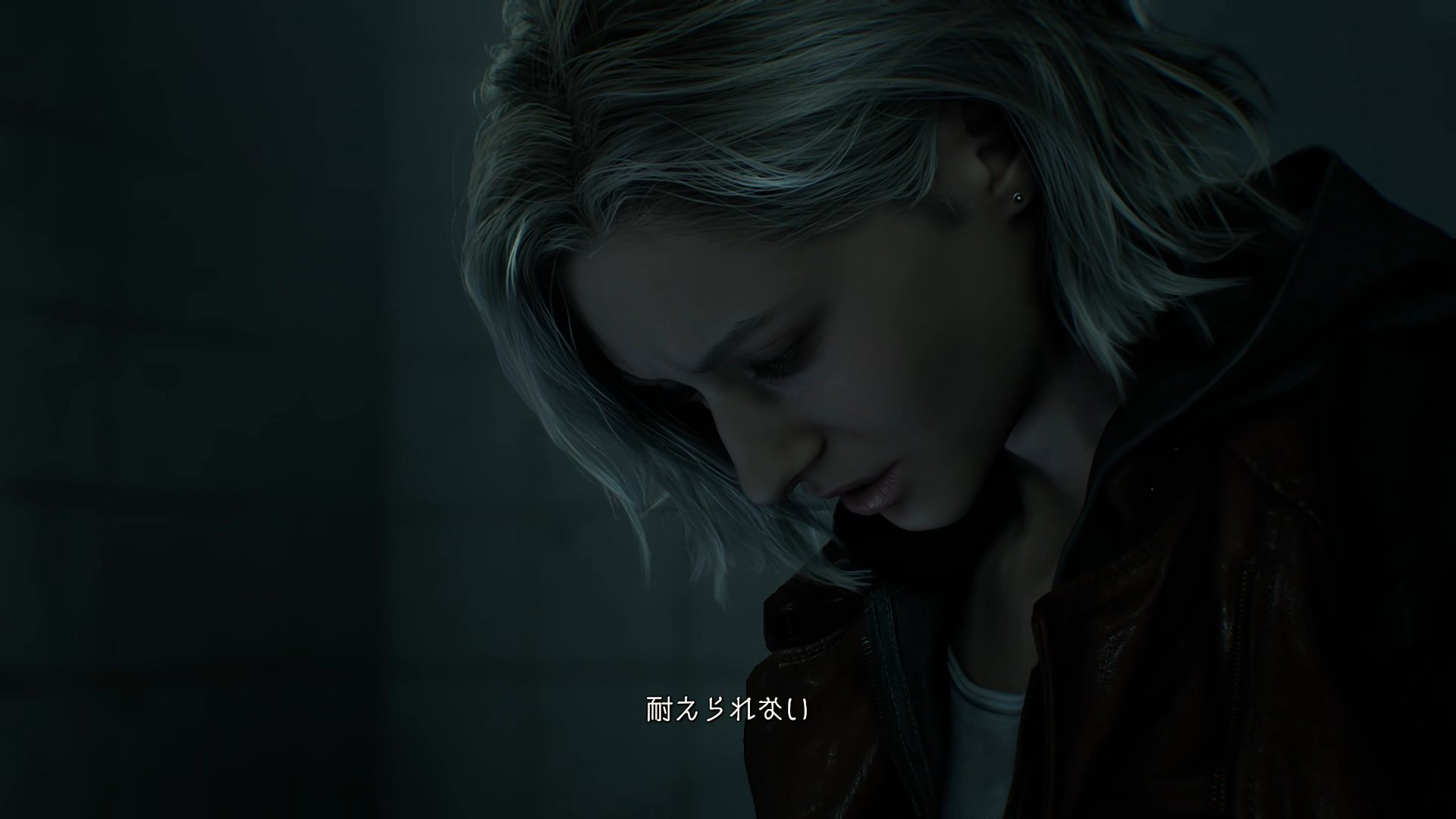スーパー戦隊50周年 東映・白倉伸一郎が見据える未来 「ゴジュウジャー」に期待する“歴代戦隊の再定義”

スーパー戦隊シリーズ最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」(テレビ朝日系・毎週日曜午前9時30分~)は、シリーズの元祖「秘密戦隊ゴレンジャー」(1975)から50年目を迎える節目の作品として、各方面から注目を浴びている。シリーズ第15作「鳥人戦隊ジェットマン」(1991)以来、数々の東映特撮作品に携わり、多くの話題作、人気作、異色作を生み出してきた東映の白倉伸一郎(キャラクター戦略部担当)がインタビューに応じ、スーパー戦隊50年のふりかえりと、さらなる未来に向けての展望を語った。
【動画】「ゴジュウジャー」激アツ!座談会 話題の第1話を振り返り!
スーパー戦隊との出会い
白倉とスーパー戦隊を結ぶきっかけとなった「バトルフィーバーJ」 - (c)東映 (c)Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved白倉は「鳥人戦隊ジェットマン」第30話「三魔神起つ」より「プロデューサー補」として東映特撮作品に初参加した。奇しくも、白倉が東映のプロデューサーを志望するきっかけとなったのが、同じ「スーパー戦隊シリーズ」だった。そもそも、白倉と「スーパー戦隊」の出会いはどんなものだったのだろうか。
ADVERTISEMENT「あれは高校生のときでした。とあるアニメ作品の録画ビデオを見せてもらう機会がありまして、たまたまそのテープに録画されていた『バトルフィーバーJ』(1979)を先に観てしまい、すごくビックリしたんです。もう、何コレ!? こんなテレビ番組がこの世にあるのか! ってくらい。これがきっかけとなり、ちょうど再放送されていた『電子戦隊デンジマン』(1980)を観たら、これがまた想像を絶するとんでもない内容! と衝撃を受けました」
若き日の白倉が「バトルフィーバーJ」および「電子戦隊デンジマン」を観て、驚いた一番のポイントはどこだったのだろう。
「等身大ヒーローが5人そろって戦っている。そして怪人がやられるとなぜか巨大化して、なぜか巨大母艦がやってくる。その中から巨大ロボットが……もう、理屈がわからない(笑)。そのとき思ったのは、言い方は悪いですが、頭のネジが何本か抜けていないとこういう作品は作れないなってこと。それ以来、こんな番組を作る『東映』とはどんなところだろうと興味を持ちはじめ、東映製作の刑事ドラマや時代劇、映画などを観まくるようになるんです。それまでは普通の映画ファンで、どちらかといえばクラシックな映画、MGMのミュージカル映画などが好きでしたが、東映の方向性はそれらとは真逆。ウェルメイドじゃない『とんでもないメイド』ですからね(笑)。そのまま東映作品を追いかけていたら、あれやこれやがあっていつの間にか自分が東映に入っていた、という感覚でした」
ADVERTISEMENT 白倉がプロデューサー補を務めた「鳥人戦隊ジェットマン」 - (c)東映石ノ森章太郎・原作の2作「秘密戦隊ゴレンジャー」と「ジャッカー電撃隊」(1977)はチームで戦う仮面のヒーローと、彼らが乗り込む巨大メカの活躍が大きな見せ場だったが、八手三郎・原作で仕切り直した「バトルフィーバーJ」ではそこに「巨大ロボット」という新たな要素が加えられた。白倉が面食らった「等身大ヒーローに巨大ロボまで出てくる」といった盛りすぎともいえる作品の基本スタイルは、現在の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」までずっと、形を変えながらも踏襲されている。かくして東映に入社した白倉は、「鳥人戦隊ジェットマン」で鈴木武幸プロデューサーのもと、プロデューサー補として初のテレビドラマを担当。作品づくりの現場に触れることとなった。
「入社する前後はすでに東映マニアと化していましたから、毎年『戦隊』と名のつく作品がずっと続いているのは知っていました。『ジェットマン』の中盤からプロデューサー補になって痛感したのは、製作スタッフの関係性が外から想像していたものとは違うぞ、ということです。何も知らない学生のころは、監督や脚本家といった独立したクリエイターがまず存在し、スポンサーやテレビ局といった『高い壁』を乗り越えながら作っていくものだと想像していたのですが、実際にそんなことは全然なかった。各パートのスタッフがそれぞれの役割をこなし、そうやってできたものを組み立てて、ひとつの作品として完成する集団作業なんだってことです」
ADVERTISEMENTスーパー戦隊史における「挑戦」
「ジェットマン」に続いて制作された「恐竜戦隊ジュウレンジャー」 - (c)東映脚本に井上敏樹、監督に雨宮慶太と、どちらも若手を大抜擢した「ジェットマン」は、それまでの「スーパー戦隊」の基礎的な要素こそ踏襲していながら、今まで試みていなかった意欲的なキャラクタードラマを見せようと、工夫が凝らされた。このころの「挑戦」について、白倉は以下のように振り返った。
「製作スタッフには、昭和からずっと作品に携わっているベテランの方々と、井上さん、雨宮監督、テレビ朝日の梶淳さんといった(若手)世代がはっきり分かれていました。いかにして上の世代からの“圧”をかいくぐって、新しい世代の感性を通し、発展させるのか、という部分に終始してしまったかな、というのが『ジェットマン』全体の感想ですね。しかし、そういった世代間の壁みたいなものは、われわれの勘違いだったことに気づくんです」
ADVERTISEMENT「ジェットマン」の次に制作された「恐竜戦隊ジュウレンジャー」(1992)は、それまで未来的技術で製造されたメカニックという側面が強かった「巨大ロボット」を「神」と位置づけることにより、作品世界の自由度を大幅に広げる役割を担った。一億年前の古代人類が現代でヒーローになるという、ファンタジー色を極めた作風もそれまでにない意欲的なもので、以後の「スーパー戦隊」にも多大なる影響を与えた、ターニングポイント的な作品だといえる。
「若い奴にやらせたら『ジェットマン』みたいなものができた。ああいうものを作らせてはいかん、ということで『ジュウレンジャー』ではベテラン勢が戻ってくることになったんです。しかし、メイン脚本を務めるベテランの杉村升さんが、われわれ若手の味方についてくれた。若手とか上の世代とかは関係なく、今までにない新しい作品を作ろうぜ、という感じでしたね。そもそも、同じ世代だけで固まっているのなら、学生時代と変わらない。年齢とか世代とか関係なく、自分の想像もつかないバケモノのような才能を持った人は存在していて、そんな人たちと一緒なって作るのが、学生とプロとの違いだと思います。『ジュウレンジャー』をやったことによって、自分の考えがガラリと変化しました。『ジェットマン』と『ジュウレンジャー』のいいところを組み合わせたのが、次の『五星戦隊ダイレンジャー』(1993)だと思います。ここで試みたのは、全50話あるエピソードの中で、脚本と監督がペアを組み、亮、大五、将児、知、リンそれぞれの主役回を作っていったこと。どういう組み合わせがどんな効果を生み出すか……って実験をやったんです。まあ、番組を使って実験をするなよと言われると弱りますが(笑)、そういった挑戦がいろいろとできる現場だったんです」
ADVERTISEMENT歴代スーパー戦隊の“再定義”
白倉がチーフプロデューサーを務めた「機界戦隊ゼンカイジャー」 - (c)2021 テレビ朝日・東映AG・東映スーパー戦隊は元祖というべき「ゴレンジャー」から50年。そして巨大ロボットという最強の味方を加えて再スタートした「バトルフィーバーJ」以降は46年間「1年に1作」というペースで作品が作られ続けている。複数の変身ヒーローがチームワークを武器に、邪悪な軍団から人々を守って戦うという骨子の部分は忠実に守られながら、ヒーローの誕生背景や悪の出現場所、全体を貫くストーリー構成といった各要素について毎年さまざまな工夫が凝らされている。あまりスーパー戦隊シリーズを熱心に見ていない人にはどのヒーローの外見にも差異がないように思えるかもしれないが、ストーリーの内容やテーマ、各キャラの個性について各作品でしっかりと変化がつけられているのが大きな魅力といえる。しかし、シリーズ45作目のアニバーサリー作品「機界戦隊ゼンカイジャー」(2021)を手がけることとなった白倉には「スーパー戦隊がこれからも続いていくにあたっては、もっと思い切った構造改革をする必要がある」という強い考えがあったようだ。
「『仮面ライダー』が革新路線なのに対して、『スーパー戦隊』は安定路線だと言われていますが、そんな流れに甘んじていると、安定どころか消滅するぞ、みたいな危機感は常に感じています。まだやれることがあるんじゃないか、もっとやれないか、今の作品を作っているプロデューサーには、まだまだ考えることがたくさんあると思います。等身大ヒーローという側面では、仮面ライダーとやっていることは変わらない。ではスーパー戦隊の独自要素は何かと考えると、それは『巨大ロボット』ではないかと。等身大ヒーローと巨大ロボットのハイブリッドこそスーパー戦隊の独自性なのですから、映像技術の面も含めて、いかに魅力的に見せることができるか、を考えてもらいたいんです」
ADVERTISEMENT白倉がチーフプロデューサーを務めた「機界戦隊ゼンカイジャー」は、1人の人間(五色田介人)と4人のキカイノイド(ジュラン、ガオーン、マジーヌ、ブルーン)がチームを組んだ、過去のシリーズに例のない変則的なキャラシフトを取りながら、スーパー戦隊の「魂」というべき「友情・団結」のヒーローという部分は受け継がれており、いまの時代を生きる子どもたちから熱烈に愛された。また、従来のスーパー戦隊の常識を根底からかきまわした異色作「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」(2022)でも、この独特な世界観でなければ成立しえない感動的なストーリーがラストを飾ったほか、毎回のアクの強いエピソード群が癖になり「ドンブラ中毒」と呼ばれる現象を起こすほどの人気を獲得した。昔ながらのオーソドックスな「スーパー戦隊」を作るのではなく、戦隊ならではの「魂」部分を大事にしつつ、常に新しい試み、ここまでするかといった大胆な「構造改革」を行っていくのが、白倉の考える「未来を目指すスーパー戦隊像」といえるのかもしれない。
最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」 - (c)2021 テレビ朝日・東映AG・東映最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」のチーフプロデューサーは、かつて「機界戦隊ゼンカイジャー」「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」のプロデューサー補として白倉と組んだ松浦大悟。白倉はスーパー戦隊50周年記念作品として「ゴジュウジャー」のどんな部分に期待を寄せているのか。
ADVERTISEMENT「アニバーサリー作品ということで歴代戦隊レッドを出すにあたり、このヒーローは戦士としてどういう特徴があるのか、ひとりひとりの個性をはっきり打ち出してほしいと思います。過去作品ではこんなことをやって、こんなセリフを言って……みたいなオールドファン目線ではなく、いま『ゴジュウジャー』を観ている子どもたちに向けて、クワガタオージャーならこんな戦い方をする戦士なんだ、どういう敵に強くて、どんなシチュエーションに弱いか、もう一回とことん問い詰めないといけない。私が『ゴジュウジャー』に期待しているのは、歴代スーパー戦隊の『再定義』です。過去の作品内容にこだわらず、何なら設定の上書きをしてもいいから、各ヒーローの個性・特徴を出す。50年の間に出てきた歴代レッド戦士を最新キャラのように描いてくれないと、出す意味がないんです」
50年、49作品を迎えてもなお、未来に向かって進歩・発展し続けていく「スーパー戦隊シリーズ」。歴代作品からのバトンを受け継ぎながら、歴史や伝統といったものをぶっとばす勢いで駆け出していく最新作「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」の躍進に期待していきたい。(取材・文:秋田英夫)
ADVERTISEMENT「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」
最高最強のナンバーワンを目指し、子どもたちに圧倒的な人気を誇る動物や恐竜=獣(けもの・ジュウ)をモチーフにした5人のヒーローが活躍する物語。脚本は「仮面ライダーガッチャード」の井上亜樹子、演出は「仮面ライダーガッチャード」「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」などの田崎竜太(崎はたつさきが正式表記)が担当する。
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」テレビ朝日系にて毎週日曜午前9時30分~放送中
「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」激アツ!座談会 話題の第1話を最速振り返り! » 動画の詳細Page 2
大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の30日放送・第13回から新たに登場する出演者5名の場面写真が公開された。
「べらぼう」片桐仁、宮尾俊太郎ら新たな出演者5名のビジュアル
第13回「お江戸揺るがす座頭金」では、蔦屋重三郎(横浜流星)が、地本問屋・鱗形屋(片岡愛之助)が再び偽板の罪で捕まったことを知る。一方、江戸城では田沼意次(渡辺謙)が長谷川平蔵宣以(中村隼人)に座頭金の実情を探るよう命じる。
ADVERTISEMENT場面写真が公開されたのは、日野陽仁、ドンペイ、片桐仁、新井美羽、宮尾俊太郎。日野は西の丸小姓組・森忠右衛門、ドンペイは座頭、片桐は平賀源内(安田顕)やひさ(東雲うみ)とともにエレキテルを作る手先の器用な町人・弥七役。
バレエダンサーの宮尾俊太郎が、意次のおいである意致(おきむね)に。10代将軍・家治(眞島秀和)の嫡男・家基(奥智哉)について西の丸目付となり、その後一橋家の家老に。田沼と一橋をつなぐ役目を果たし、治済(生田斗真)の子・豊千代の11代将軍就任に尽力する……という役どころ。
そして、本作と同じく森下佳子が脚本を手掛けた大河ドラマ「おんな城主 直虎」(2017)で天才子役と絶賛された新井美羽が、女郎屋・松葉屋に売られてきた武家の娘・さえにふんする。「直虎」では当時10歳で、主人公・井伊直虎(おとわ/柴咲コウ)の幼少期を演じた。現在は18歳。
第13回では、先ごろ扮装ビジュアルが公開された古川雄大演じる北尾政演(山東京伝)が初登場。また長谷川平蔵宣以(中村隼人)が久々に再登場する。(石川友里恵)
※VODサービスへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれており、リンク先での会員登録や購入などでの収益化を行う場合があります。
Page 3
第77回カンヌ国際映画祭で審査員賞と女優賞(ゾーイ・サルダナ、カール・ソフィア・ガスコン、セレーナ・ゴメス、アドリアナ・パズ)を受賞、第97回アカデミー賞で最多13部門12ノミネーションを果たし、ゾーイが助演女優賞を獲得するなど賞レースを賑わした『エミリア・ペレス』。日本公開を迎えた本作について、監督・脚本のジャック・オーディアール(『預言者』『ゴールデン・リバー』)が、全米公開を前に行われた合同取材で製作裏話を語った。
メキシコ・シティで働く優秀な弁護士リタ(サルダナ)は、犯罪を犯した裕福な顧客が、刑務所入りを逃れる手助けをしていた。ある日、悪名高い麻薬カルテルのボス、マニタス(ガスコン)の依頼を受け、彼の妻ジェシー(ゴメス)にも隠して、性適合手術をできる世界最高の医者を探すことになる。そしてマニタスは、エミリア・ペレスという女性として新たな人生を送り始めるのだが……。
ADVERTISEMENT脚本を書き進めるうちに、オペラの台本に近いと思ったというオーディアール監督だが「私はミュージカルというジャンルについての知識があまりないんです。その理由は、そのジャンルが私を特に魅了しないから。本当に素晴らしいと思ったミュージカルを5、6タイトル挙げることができますが、それくらいです。そこにはミュージカルというジャンルに対する、私の暗黙の批判があるんです」と話したのには驚いた。
従来のミュージカルならば、主軸となるストーリーがあり、登場人物の感情の説明に歌が使われたりするものだが、今作における歌の使い方は異なるものだ。「ソングライターのカミーユと共同脚本家であるトマ・ビデガンとともに、この映画では歌が説明的なものにはならないことにすぐ気がついたんです。説明的な曲がないわけではありませんが、何よりも歌は、アクションを前進させるためにあるんです」というオーディアール監督。「リタが歌う『エル・マル』や、リタとワッサーマン医師が歌う『レディ』がその例です。オープニングの曲も、登場人物の気持ちではなく、政治的な怒りを歌った曲なんです」と続けた。
(C)2024 PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHE FILMS - FRANCE 2 CINEMA COPYRIGHT PHOTO:(C)Shanna Besson俳優たちとの仕事の進め方に関してオーディアール監督は、キャストに多くのアイデアを映画に持ち込むことを要求するのだという。「私の映画では、アイデアを持つ『権利』があるだけでなく、アイデアを持つ『義務』があるんです。俳優たちには、私の考えを批判する権利もあるし、その義務があります」。
ADVERTISEMENT弁護士のリタを熱演し、自身初のアカデミー助演女優賞に輝いたゾーイも、彼女独自のアイデアを役柄に持ち込んだ。「ゾーイはかなり役づくりをすませた状態でフランスに来て、彼女なりのキャラクターを提案してきました。必ずしも全てに同意したわけではないですが、それを調整したり、修正したりすることができました。またゾーイは、歌って踊ることもできるため、劇中の歌と踊り、そして演技を流動的なものにしてくれたんです。彼女のもつ“威厳”もとても気に入っています。彼女は本当に私の指示に耳を傾けてくれました」。
「私が初めて長編映画を監督したのは42歳のときで、それまで家で一人で脚本を書いていたんです」というオーディアール監督は「映画作りを通して、私は世界と接触するようになり、自分自身を社会化することができたと思います。もしそうしていなかったら、私は少しうつ状態で、自殺願望もありましたが、おそらく気が狂っていただろうと思います」と明かす。
そして「(人は)ある時点で、変化を起こすリスクを負わなければならないんです」というと続けると、今作には、彼自身の人生に重なる部分があることをほのめかした。と明かした(直前に“明かす”とありますので)。 「クレイジーにならないといけないかもしれません。その方が、じっとしているよりもいい。この映画のキャラクターたちは、リタもエピファニア(パズの役名)もみんな、私たちにそう語りかけているんです。彼らは絶え間なく変化し、進化している人々です。そして、多分それが、この映画のが伝える教訓なのだと思います」。
ジャンルにとらわれないオリジナリティーあふれる今作は、オーディアールにしか作れない稀有なエンターテインメント。存分に楽しんでもらいたい。(吉川優子/Yuko Yoshikawa)
※VODサービスへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれており、リンク先での会員登録や購入などでの収益化を行う場合があります。
Page 4
フランスの名優カトリーヌ・ドヌーヴが主演を務め、竹野内豊、堺正章、風吹ジュンら日本人俳優が共演に名を連ねる映画『SPIRIT WORLD -スピリットワールド-』が、10月10日よりTOHOシネマズ シャンテにて先行公開、10月31日より全国公開されることが決定した。
父の死をきっかけに群馬県高崎市を訪れたハヤト(竹野内)は、離婚した母に思い出のサーフボードを届けてほしいという父・ユウゾウ(堺)の遺言と、フランス人歌手・クレア(カトリーヌ)のコンサートチケットを見つける。しかし翌日、ハヤトはクレアの突然の死を知る。ハヤトは父の遺言を果たすため、家を出ていった母を探す旅へと繰り出す。一方、死後の世界で彷徨うクレアはユウゾウと出会い、見えない存在としてハヤトの旅を見守ることに。家族、仕事、人生、様々な葛藤を抱える中、旅路でハヤトが辿り着く答えとは。
死後の世界で出会うカトリーヌ・ドヌーヴ&堺正章 - (c)L. Champoussin /M.I. Movies /(c)2024「SPIRIT WORLD」製作委員会日本・フランス・シンガポールの国際共同合作である本作は、2024年に高崎市と千葉県いすみ市で撮影された。昨年10月に韓国・釜山国際映画祭のクロージング作品として上映され、同年10月から11月に開催された東京国際映画祭ではガラ・セレクションに選出。日本公開に先立ち、フランスでは今年2月26日から上映されている。監督は、『家族のレシピ』で知られるシンガポールの鬼才エリック・クー監督が務めた。(編集部・倉本拓弥)
ADVERTISEMENT※VODサービスへのリンクにはアフィリエイトタグが含まれており、リンク先での会員登録や購入などでの収益化を行う場合があります。