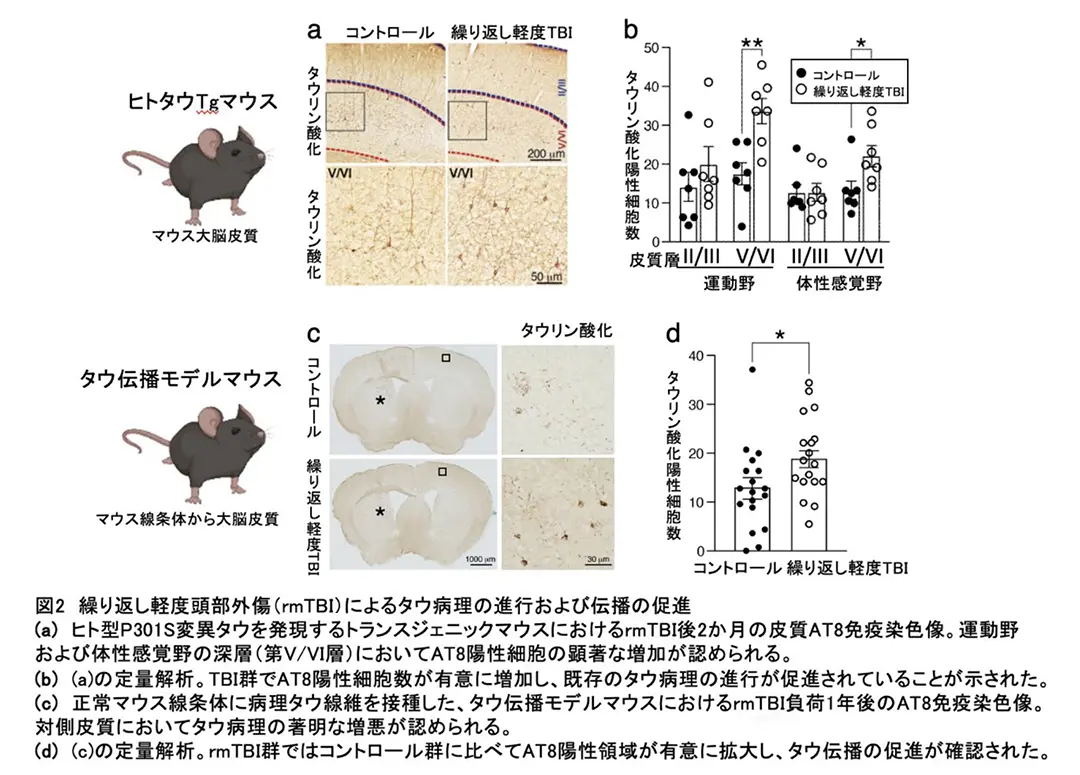どれだけピンピンでも便秘や肩こりがあれば「不健康」…平均寿命より10年短い"健康寿命"の知られざるカラクリ たった1つの質問で健康か不健康かが決まってしまう

厚生労働省が3年に一度発表している「健康寿命」はどのように算出されているのか。ジャーナリストの小林一哉さんは「寝たきりや要介護の高齢者を『不健康』としているかと思いきや、たった1つの問いで健康か不健康かを判断している」という――。
写真=iStock.com/miniseries
※写真はイメージです
「健康寿命」は、WHO(世界保健機関)が2000年に提唱した健康指標で、「日常的・継続的な医療・介護に依存しないで、自分の心身で生命維持し、自立した生活ができる生存期間」を指す。日本では、厚生労働省が2010年から3年ごとに都道府県別の健康寿命を発表している。
昨年12月24日に発表された2022年の健康寿命では、全国1位は男性73.75歳(全国平均72.57歳)、女性76.68歳(同75.45歳)で、静岡県が初めてトップに輝いた。
同県の鈴木康友知事はその結果を受けた12月27日の記者会見で、「生活習慣病の発症予防、重症化予防や居場所づくりの推進など長年の取り組みの成果」などと静岡県の「日本一」を手放しで喜んだ。
10年間も「寝たきり・要介護」は本当か
ところで、2022年の平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳だった。男性で8.48歳、女性で11.64歳、平均で約10年間は、寝たきりなどの状態で介護が必要となるのだろうか。
静岡県が作成した記者会見資料でも、健康寿命は杖をついたりしても「自立した生活ができる期間」とあり、不健康期間は「障害・要介護の期間」で、高齢者が寝たきりの介護生活を送るイラスト入りで紹介している。
出典=静岡県健康福祉部健康局 健康政策課・健康増進課「令和6年12月25日 記者会見資料」
高齢者になると、70代半ばころまでにふつうの生活ができなくなるというメッセージと誰もが受け取るだろう。
寿命を迎える約10年前までに健康寿命が尽き、その後は介護を受けながら暮らすことになる。本当に、そんな考え方で正しいのだろうか?
「静岡県の健康寿命は男女ともに日本一(2022年)」と赤字で誇らしげに強調した記者会見資料を読み解いていくと、びっくりするような事実が明らかになった。
その透けて見えた事実から、「健康寿命にだまされるな!」と筆者ははっきりと言いたい。
「健康寿命にだまされるな!」とはどういうことか。
Page 2
質問1で生年月を問われた後、まず質問2で、「あなたは現在、病院や診療所に入院中、又は、介護保険施設に入所中ですか」と尋ねられる。
この質問に「はい」と回答すれば、この時点で自動的に「不健康」に分類される。
質問2で「いいえ」と回答すると、次の質問3で「あなたはここ数日、病気やけがなどで具合の悪いところ(自覚症状)がありますか」と問われる。
自覚症状には、「うつ病やその他のこころの病気」「眠れない」「いらいらしやすい」「もの忘れする」「頭痛」「鼻がつまる」「かゆみ」「便秘」「下痢」「食欲不振」「肩こり」「手足の冷え」「頻尿」「けが」など42項目が例示されている(41番目は「その他」、42番目は「不明」)。
これだけ具体的で多岐にわたっていれば、誰もが1つくらいの自覚症状を思い浮かべるかもしれない。
「眠れない」「便秘」「下痢」「肩こり」などの症状は、高齢者に限らずともふつうに起こり得る。だから、何らかの自覚症状が「ある」と回答する人も多いだろう。
質問3で「ある」と答えれば、質問5の「健康上の問題で日常生活に何か影響があるか」は、ダイレクトに「ある」となり、「不健康」に分類される。
不必要に「不健康」と回答している可能性
質問3で「いいえ」と答えると、「ここ数日」ではなくても、「糖尿病」「高血圧症」「目の病気」「歯の病気」「アトピー性皮膚炎」などで、病院や診療所、鍼灸院などに通っているのかを質問4で尋ねてくる。
ここで「病院等に通っている」と答えれば、やはり質問5では「ある」と答えることになる。こうなると、若い人たちでも「不健康」に分類される可能性も出てくるだろう。
40代、50代の中年世代ともなれば、何らかの症状を訴えなくても、高血圧などで定期的に病院通いをする人も多い。
中年世代が「不健康」に分類されれば、平均寿命まで20年、30年以上もあるから、健康寿命の年齢は押し下げられてしまう。