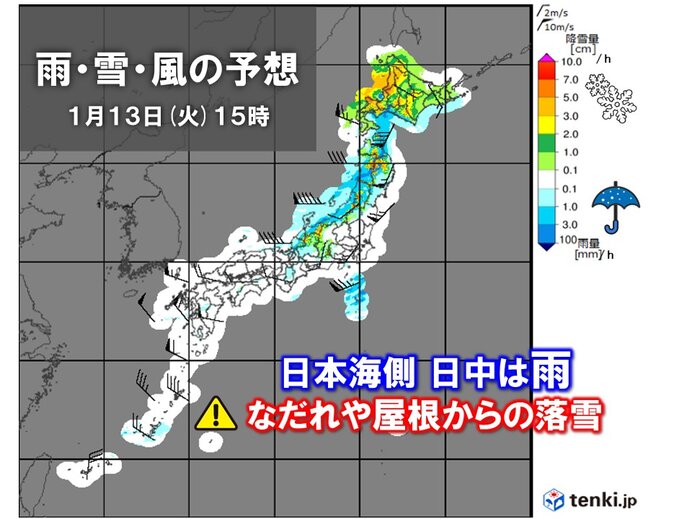迫る津波、助かった570人と亡くなった162人 岩手・釜石「二つの出来事」を訪ねて

2011年3月11日、東日本大震災で広範囲が津波に襲われた岩手県釜石市鵜うの住すま居い町。あの日、中学生が小学生の手を引いて高台へ逃げ、約570人が助かった。一方、近くの防災センターでは、集まった160人以上が犠牲になった。2月下旬、復興が進む現地に「二つの出来事」を訪ねた。(中西是登)
「街は完全に『海』になっていました」。14年前、釜石東中2年生だった川崎杏樹さん(28)は、高台からの光景を振り返る。夢中で駆けた坂道には、保育園児を背負った小学生や、お年寄りの車椅子を押して逃げる中学生もいた。
学校から約1・6キロ。避難の道のりを実際にたどった。西寄りの冷たい向かい風が吹き付け、九州から1000キロ以上離れた東北の厳しい寒さを思い知らされる。
旧鵜住居小から1・6キロほど離れた高台。震災当日、子どもたちはここまで避難した=2月19日、岩手県釜石市
同じように寒かったあの日、子どもたちはまず、海抜4メートルの高齢者施設に逃げた。しかし裏山が崩れる危険があったため、海抜15メートルの駐車場へ。真下にまで津波が押し寄せ、さらに走った。最後に逃げ着いた海抜44メートルの「恋ノ峠」は傾斜10%の急坂の上。駆け上がるとすぐに息が上がり、足が痛んだ。
◇ ◇
釜石東中と隣の鵜住居小の児童生徒は、保護者が迎えに来た1人を除く約570人が助かり「釜石の奇跡」と言われた。だが川崎さんら当事者の多くは「『奇跡』ではない」と語る。
「復興のシンボル」として岩手県沿岸部を走る三陸鉄道=2月18日、釜石市
震災の5年前、元社会科教諭の森本晋也さん(57)は釜石東中で防災教育の担当になった。当時、「津波は30年以内に99・9%の確率で来る」と言われていた。昭和三陸大津波を経験した人への聞き取りや、避難を呼びかけるヒーローの寸劇などさまざまな方策で、子どもたちに伝えた。
「もっと楽しく訓練ができないか」とも考えた。陸地での津波の速さに近い時速36キロで車を走らせ、校庭で生徒たちを追いかけた。川崎さんもよく覚えている。「人間の足ではどうやってもかなわない。『遠い』だけではなく『高い』ところに、と実感しました」
◇ ◇
釜石東中からわずか500メートルほど。「鵜住居地区防災センター」には地震直後、196人が避難した。海抜4メートルの建物は津波にのまれ、推計で160人以上が犠牲になった。なぜ、こんなに低い場所に-。そう思わずにはいられなかった。
震災から14年、鵜住居には住宅や学校が再建されている=2月20日、岩手県釜石市
「誤った認識が、被害につながった」。岩手大の齋藤徳美名誉教授(地域防災学)は指摘する。
センターは中長期の避難生活を送る場所で、緊急避難場所ではなかった。本来の避難場所は高台の神社だったが、訓練への参加者は少なかったという。震災1年前に完成した防災センターで訓練をすると、多くの人が参加した。「結果的に、センターが避難場所だと染みついてしまった」。齋藤さんは表情を曇らせた。
事態の全容が分からない中、わずかな時間で迫られる判断。自分もその場にいたら、多くの人に付いて行ったかもしれない。
◇ ◇
防災センターがあった場所には現在、災害伝承施設「いのちをつなぐ未来館」が立つ。釜石東中を卒業した川崎さんは大学卒業後の20年4月から、スタッフとして防災学習や企業の研修などで経験を伝えている。
震災当時、この場所にあった釜石東中に通っていた川崎さんは、現在「いのちをつなぐ未来館」のスタッフとして経験を多くの人に伝えている=2月19日、岩手県釜石市
「子どもたちにとっては教科書の中の出来事で、大人も思い出すことが減る。そんなときに災害が起きれば、犠牲者が出てしまう。同じような被害を出さないために、いろんな方の知識になりたい」
釜石市の犠牲者は1064人。未来館の隣地には円弧状の慰霊碑があり、遺族の了承を得た1003人の名前が記されている。周囲には新しい住宅が並び、その上で海鳥の声が響く。
160人以上が犠牲になった「鵜住居地区防災センター」跡地に建立された慰霊碑。後方には、津波の高さを示す海抜11mのモニュメントも立つ=2月19日、岩手県釜石市
釜石東中の跡地には、ラグビー競技場の「釜石鵜住居復興スタジアム」が整備されている。そこに立つ石碑には、釜石の人たちが一番伝えたいメッセージが刻まれていた。
〈あなたも逃げて〉
鵜住居の空を舞う海鳥=2月20日、岩手県釜石市
読者との双方向型の報道に取り組む地方紙連携の枠組み「JODパートナーシップ」は、2021年から、東日本大震災の記憶の継承を目的にした協働企画「#311jp」に取り組んでいます。23年からは主に震災以降に入社した記者の参加を募り、被災地を取材するプロジェクトを実施。今年は本紙など16紙が参加しました。