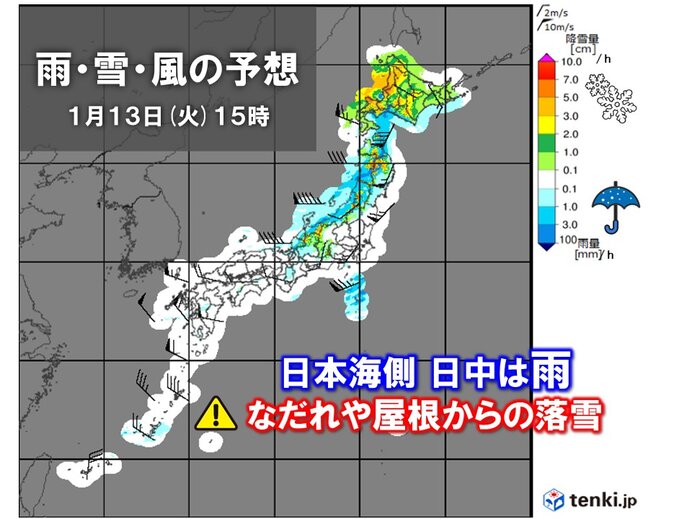長生炭鉱の遺骨収容「自分しかできない」 水中探検家が進む未開の道

そこには82年間、誰も入ったことがなかった。崩れた木材がジャングルジムのように行く手を阻む。水は濁り、視界はほとんどない。
それでも水中探検家、伊左治(いさじ)佳孝さん(36)は「自分しかできない仕事」と、手応えを感じている。
始める前は何がリスクかすら分からなかった。しかし今は、何をすべきかが見えてきた――。
太平洋戦争下の1942年2月3日、山口県宇部市の長生(ちょうせい)炭鉱で水没事故が起き、朝鮮半島出身の労働者と日本人労働者計183人が亡くなった。政府による遺骨収容はおろか調査も行われていない中、地元の市民団体が収容のための調査に乗り出している。
海底坑道の閉鎖環境で、極めて困難な潜水調査を行っている伊左治さんにこれまでの成果や課題を聞いた。
「試行錯誤」が楽しく
――伊左治さんは「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(刻む会)に協力を申し出て、難しい調査に着手されたそうですね。そもそもダイビングを始めたのはいつでしょう。
◆レジャーのダイビングのライセンスを取得したのは12歳の時です。両親が遊びとしてやっていて、誘われたのがきっかけでした。
――なぜ水中探検家に?
◆ただ潜水するだけでなく、試行錯誤しながら道を切り開く。この作業そのものが楽しく、魅力を感じています。
長生炭鉱でいえば、「こうしたら遺骨の収容に一番近づくのではないか。コストを下げるためにはどうしたらいいのか」といったことを、常に考えています。
2023年12月に開かれた刻む会の集会を偶然ユーチューブで拝見し、実地調査の見込みが立っていないと知りました。でも私からみると、海から突き出た2本のピーヤ(排気口)から潜水が可能で、潜ってみればリスクや現状が分かり次の段階に進めるのではと思い、連絡を取ったのが始まりです。
遺骨収容、最短ルートは
――これまでの調査成果は。
◆まず予備調査として、24年7月に沖側のピーヤに入りました。…