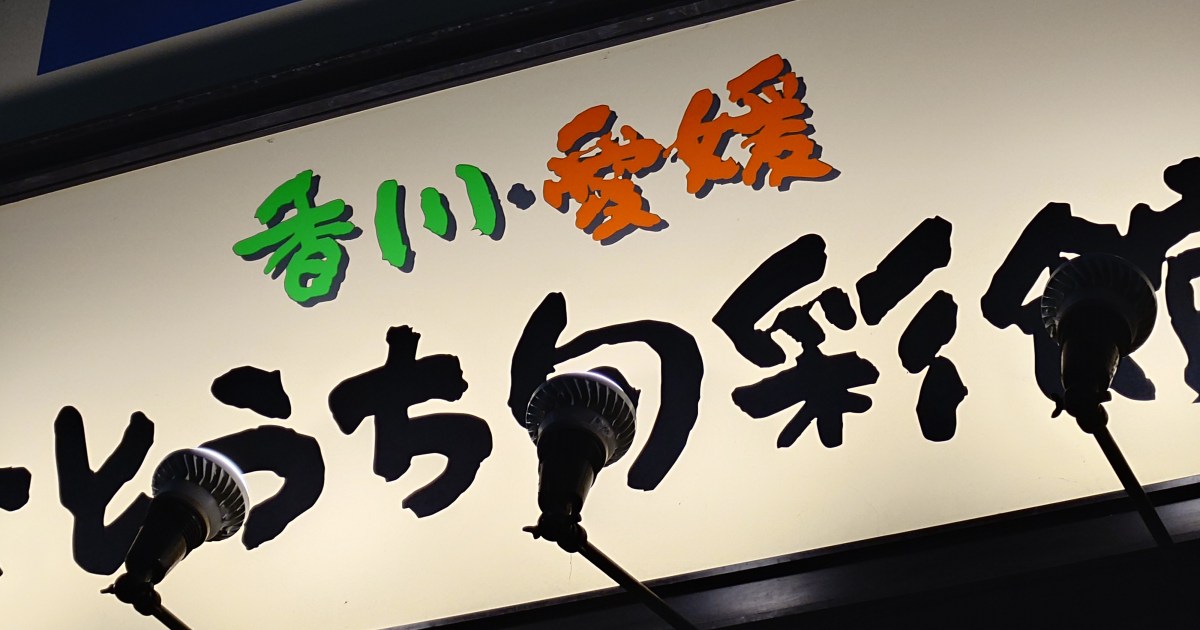通商問題が穏当推移なら「利上げ再開」と複数委員=日銀6月会合要旨

[東京 5日 ロイター] - 日銀が6月16―17日に開いた金融政策決定会合では、利上げの再開を意識した発言が多くの委員から出ていたことが明らかになった。複数の委員が、堅調な賃金や若干上振れ気味の物価を念頭に置けば「通商問題が穏当なかたちで推移する見通しになってくれば、現在の様子見モードから脱却し、利上げプロセスの再開を考えることになる」との見方を示していた。国債買い入れ額の着地点やバランスシートの望ましい規模感を巡る議論も展開されていた。
決定会合では、不確実性の高さを踏まえれば当面は利上げを休止する局面だが「米国の政策動向によって、再び利上げ局面へ回帰する柔軟かつ機動的な対応も求められる」(1人の委員)といった声も出された。ある委員は、インフレが想定対比上振れて推移する中で「たとえ不確実性が高い状況にあっても、金融緩和度合いの調整を果断に進めるべき局面もあり得る」と述べた。
こうした意見に対して、別のある委員は、経済の先行き不確実性は非常に高く、下方リスクの厚い状況が続いていると指摘。「企業業績や日米通商交渉の方向性が見えてくるのはまだ先であり、政策金利は当面、現状の水準を維持することが適当」と述べた。
経済を巡り、複数の委員が、不確実性は依然として高いものの「米国の関税政策に伴う経済の減速圧力は、前回会合時点で想定していたほど強くない可能性がある」との見方を示した。物価については、何人かの委員がコメなどの食料品価格の上昇を主因に前回展望リポートの見通しに比べて「強めの動きとなっている」と指摘した。
<保有国債の減少早く進め、「相応規模の量的緩和の余地を」との声>
決定会合では、国債買い入れの減額計画が議論された。2026年3月までの計画を維持した上で、26年度は市場安定への配慮から減額幅を四半期当たり2000億円に鈍化させることを賛成多数で決めた。
田村直樹審議委員は、26年4月以降も四半期4000億円の減額ペースを維持すべきと主張し、反対票を投じた。議事要旨によれば、田村委員と見られる委員は、長期金利の形成は市場と市場参加者に委ねるべきであり「可能な限り早く、日銀の国債保有残高の水準を正常化することが必要」と述べた。国債保有残高を早めに減らすことで「市場機能に悪影響を与えない範囲で、相応のインパクトがある規模の量的緩和(QE)を実施し得る余地を確保しておくことも重要だ」とも主張していた。
<国債の月間買い入れ額、着地点で意見分かれる>
日銀は来年6月に再び中間評価を行う。月間買い入れ額の着地点に加え、バランスシートの望ましい規模感が議論の焦点になるとみられる。
月間買い入れ額の着地点については、意見の違いが見られた。1人の委員は「市場の安定性を確保する観点から、ある程度の額の国債買い入れは続けていくべきだ」と述べた。ある委員は、今後、例えば月間の国債買い入れ額が1兆円程度にまで減少すれば、日銀の国債買い入れが市場で話題になることもなくなるとして「買い入れ額をゼロにすることに強くこだわる必要はないのではないか」と主張した。
これに対して、別の1人の委員は「国債買い入れ額はゼロまで段階的に減額していくことが望ましい」と話した。
バランスシートの規模を巡って、ある委員は、将来的に超過準備はある程度減少するにせよ、発行銀行券の残高と合わせると、長期国債を含めそれらに見合う「相応の規模の資産が必要になる」との見解を示した。これに対し、別のある委員は「国債の買い入れだけではなく、中長期の資金を市場に供給することも検討すべきだ」と主張した。この委員を含む何人かの委員は、中央銀行のバランスシートは資産・負債の両面から日本の金融経済に影響を及ぼし得るため「最適なバランスシートの規模や構成については、今後、多面的に検討していく必要がある」と述べた。
決定会合では、政府側の出席者が会議の一時中断を申し出た。議長を務める植田和男総裁はこれを承諾し、17日午前11時58分に中断、午後0時7分に再開した。
財務省の出席者は国債買い入れの減額について「債券市場の安定等に十分に配慮し、必要があれば状況に応じた柔軟な対応をすることを含め、適切に行われることを期待する」と発言した。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab