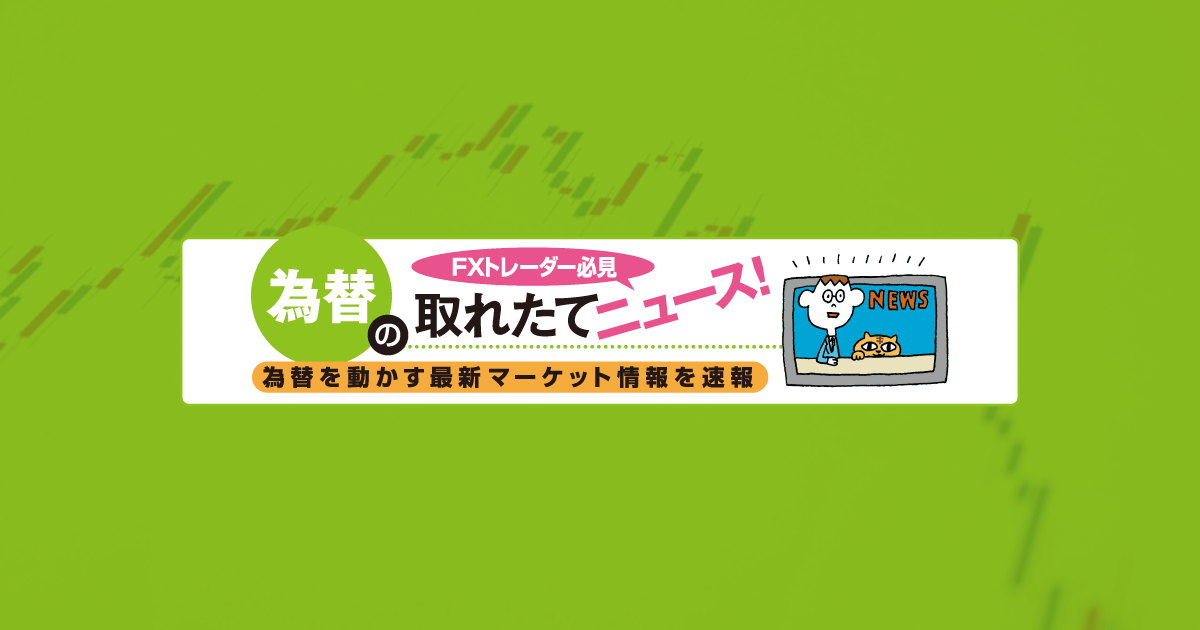コラム:日銀の5月利上げと円相場、それでも遠い円の反転シナリオ=内田稔氏

[東京 26日] - 日銀は、3月に開催された金融政策決定会合で大方の予想通り、政策金利を据え置いた。記者会見で植田和男総裁は、トランプ政権の掲げる関税政策を念頭に、不確実性が高い点を繰り返し強調した。一方、政策金利からインフレ率を差し引いた実質金利がなお大幅なマイナス圏にある点を挙げ、金融緩和度合いを調整していく利上げ方針も堅持した。
<追加利上げ、7月から前倒しへ>
こうした中、市場ではおおむね半年ごとの利上げペースが想定されており、7月の利上げ確率が約8割程度織り込まれている。しかし、夏の参議院選挙後の政治的な情勢は見通しにくい。日銀は政府とデフレ脱却に向けた共同声明を締結していることから、選挙の結果次第で政策判断が難しさを増すおそれがある。このため、日銀も選挙前の追加利上げを模索する可能性が高い。その際、4月30日―5月1日会合での利上げは、前回1月の利上げおよびトランプ関税の詳細が判明するとみられる4月2日からの日が浅い。従って、消去法で6月16日―17日に開催される会合での利上げ観測が今後高まっていくのではないか。
<利上げと為替相場の関係>
一方、これまでの正常化プロセスを振り返ると政策変更のタイミングに為替相場が強く影響した可能性が疑われる。例えば、マイナス金利解除は決算期末月を避けるとみられたが、昨年3月に決まった。当時、能登半島地震を受け、市場では日銀のマイナス金利解除が大きく後ずれするとの見方が急浮上していた。前年末に140円割れ目前まで下落したドル円が、年初から3月にかけて150円の大台まで急反発していた。
続く追加利上げも、国債買い入れ減額が始まる7月との重複を回避するとの見方が裏をかかれた。結果的にこれが歴史的な株価の暴落を伴うサプライズ利上げとなったが、昨年7月はドル161.95円と2022年以降の最高値を更新したタイミングである。さらに今年1月の利上げも、日銀が重視する米新政権の政策や国内の賃上げの継続性がある程度見通せる3月との見方が覆された。やはり年初からドル円が堅調に推移し、再び160円の大台が意識された局面で利上げが決まったようにも映る。
<政策変更に展望レポートは必要か>
こうしてみると、足元で150円の大台を回復したドル/円が再び騰勢を強めた場合、5月1日に利上げが早まる可能性は低くないだろう。関税の影響に関して言えば、会合後の記者会見にて植田総裁は、次回会合や展望レポートで「ある程度、消化できる」とも発言している。確かに、関税の詳細はなお不明ではあるものの、既に税率25%の自動車関税や相互関税など概要が判明しているものも多く、日銀内でも相応の分析が進んでいると考えられる。実際、トランプ大統領が自動車関税について日本も含まれる方針を示した後も、植田総裁や内田副総裁らが金融緩和度合いを調整していく姿勢を重ねて表明しているのは早めの利上げに向けた地ならしである可能性もある。さらに、次回の利上げで日本の政策金利は0.75%と1995年以来、31年ぶりの新たな領域へと踏み出すことになる。その説明責任が展望レポートのない6月会合における公表文と総裁会見だけで果たされるのかと言えば疑問だ。
以上を踏まえると、今後の為替相場の動向によっては、5月会合で利上げが決まるか、あるいは据え置きの場合も、6月の利上げが事実上、宣言されるシナリオがあり得よう。そこで、最近のドル/円相場の動きを振り返り、目先の注目材料を整理しておく。
<ドル/円12円下落も依然弱い円>
ドル/円は1月の高値158円台から3月の安値146円台まで約12円も下落した。トランプ政権の関税政策に関する不透明感が嫌気され、市場のセンチメントが著しく悪化した。米長期金利の低下と株安、ドル安が進み、いわゆるトランプトレードが巻き戻されている。これに対し、日本の長期金利は17年ぶりの水準まで上昇し、なお先高観もくすぶる中、約3年間続いた円安相場の転換が意識されたとみられる。日米の株式相場の下落も相まって、投機筋の活発な円買いも進んでいる模様だ。さらに、トランプ大統領による名指しでの円安批判も円高期待を高めた可能性があるだろう。
もっとも、主要通貨全体でみると円はそれほど強くない。むしろ3月に入ってからの円は主要通貨の中でドルと同程度に弱く、クロス円が堅調に推移している。ドル/円にしても、投機筋の円ロングが過去最大規模にまで積み上がったとの報道を踏まえると、逆に150円割れでは底堅さを示したと評価することもできる。依然として極めて低い実質金利が円の弱点として残っており、貿易赤字や活発な対外直接投資といった円売りも円の弱さを助長している。欧州中央銀行(ECB)やイングランド銀行(BOE)の利下げプロセスの終わりがそろそろ話題に上り始める中、日銀の次なる利上げが円高転換のきっかけになるとは考えにくい。
<ドルにも持ち直しの兆し>
加えて、ここへきてドルにも持ち直しの兆候がみられつつある。2月の小売売上高では、自動車、ガソリン、外食、建設資材を除いたコア(コントロールグループ)が事前予想を上回った。低調だった1月分が悪天候などの影響を受けた可能性があり、過度な米経済の先行きへの懸念が和らいだ。ドイツの財政拡張に沸いたユーロ/ドルの反落も、間接的なドル高要因として機能したはずだ。
もっとも、ドルの一段高のカギを握るのは、上院へと審議の場が移った予算決議案の行方だろう。これは2月25日に下院で可決されたもので、トランプ減税の延長4兆5000億ドル、債務上限の引き上げ4兆ドル、歳出の削減2兆ドルなどを含む内容だ。仮に、上院でも下院案に近い内容で成立すれば、リスク回避姿勢が和らぎ株式相場の上昇が見込まれる。財政拡張の方向性が明らかとなれば、米国の長期金利が上昇し、ドル高を促す公算が大きい。当然、その影響はドル/円にも及ぶ上、投機筋による円ロングの解消がドル/円上昇を加速する可能性もある。そうなれば、日銀も利上げ判断の前倒しを迫られるはずだ。
<根強い不確実性>
とは言え、米国経済を巡っては、引き続きトランプ政権の政策に関する不透明感から、消費者マインドや企業センチメントが悪化しており、株安をもたらす危険性は侮れない。株式の含み益の縮小や消滅は個人消費を直撃し、実体経済へと容易に波及しよう。予算案を巡っても、上院共和党の財政タカ派の説得が不可避であり、その過程でトランプ減税が規模縮小を余儀なくされる可能性もある。過去1カ月の値動きからドル/円の底堅さが示されたものの、反発力の程度や上値目処はまだ未知数と言える。
編集:宗えりか
*本コラムは、ロイター外国為替フォーラムに掲載されたものです。筆者の個人的見解に基づいて書かれています。
*内田稔氏は高千穂大学商学部教授、株式会社FDAlco外国為替アナリスト、公益財団法人国際通貨研究所客員研究員、証券アナリストジャーナル編集委員会委員、NewsPicks公式コメンテーター(プロピッカー)。慶應義塾大学卒業後、東京銀行(現・三菱UFJ銀行)に入行し、マーケット業務を歴任。2012年からチーフアナリストを務め、22年4月から高千穂大学商学部准教授、24年4月から現職。J-money誌東京外国為替市場調査では2013年より9年連続個人ランキング1位。国際公認投資アナリスト、日本証券アナリスト協会認定アナリスト、日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト、経済学修士(京都産業大学)。YouTubeチャンネル「内田稔教授のマーケットトーク」では解説動画を公開している。
*このドキュメントにおけるニュース、取引価格、データ及びその他の情報などのコンテンツはあくまでも利用者の個人使用のみのためにコラムニストによって提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。このドキュメントの当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。このドキュメントの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。ロイターはコンテンツの信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、コラムニストによって提供されたいかなる見解又は意見は当該コラムニスト自身の見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。
私たちの行動規範:トムソン・ロイター「信頼の原則」, opens new tab