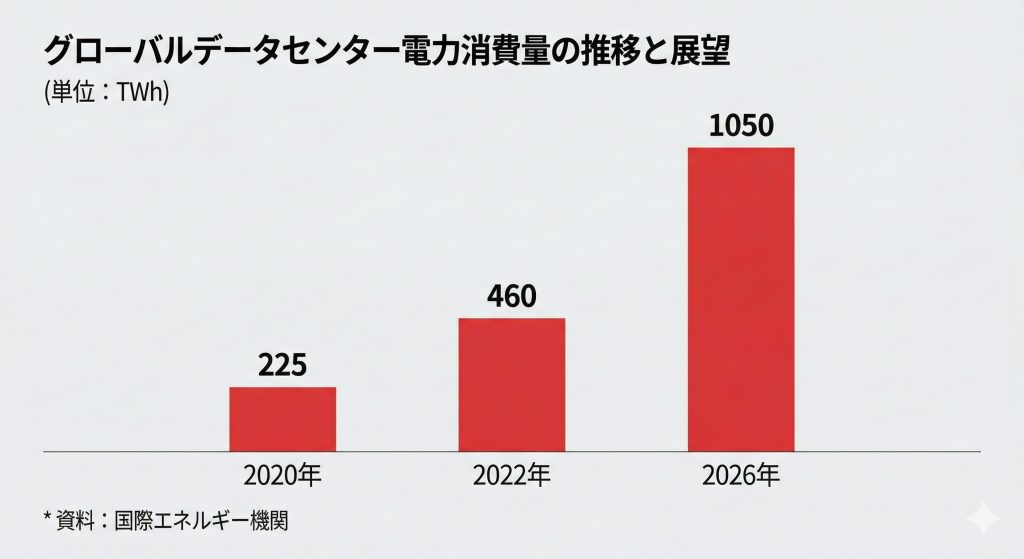元社員がOpenAIの社内文化について語る、メールはほぼナシのSlackメインで超ボトムアップ型の実力主義

AI業界のリーダーカンパニーであるOpenAIに2024年5月に入社し、2025年6月末で退職したカルビン・フレンチ・オーウェン氏が、自身が約1年間にわたって働いてきたOpenAIの社内文化について語っています。
Reflections on OpenAI
https://calv.info/openai-reflections オーウェン氏は、OpenAIの開発するサービスやソフトウェアに関するウワサは大量に飛び交っているのに対して、社内文化についてはあまり情報を目にすることがないことに気づいたそうです。そこで、OpenAIで働いていた記憶が鮮明なうちに、自身の経験を共有しようとブログに同社の社内文化に関する自身の知見をまとめたと説明しています。オーウェン氏は顧客データプラットフォーム企業「Segment」の共同創業者として10年近く勤務した人物です。Segmentが買収されたタイミングで同社を去り、2024年5月からはOpenAIのいち社員として働いていました。 OpenAIを離れることになった決断について、「正直に言うと、退職の決断に個人的な葛藤があったわけではない」と記し、未練はないと説明しました。さらに、「一度自分で事業を立ち上げた人が、3000人規模の組織の社員になるのは大変です」と、自身の退職理由を説明しています。 ただし、「仕事の質の高さが私を再びひきつける可能性は十分にあります。汎用人工知能(AGI)ほど影響力があるものを作ることは想像しがたく、間違いなくここ10年で最も革新的な技術となるでしょう。その発展の一部を直接見ることができるのは、非常に幸運です」と述べ、OpenAIで働くことの魅力についても理解を示しました。
OpenAIについてまず知っておくべきことは、「急激な成長」を経験しているという点です。オーウェン氏がOpenAIに入社した2024年5月時点では、同社の従業員数は1000人強だったそうです。しかし、1年後には従業員数が3000人を超えており、ほぼすべてのリーダーが2~3年前とは別の仕事をこなさなければいけなくなったとオーウェン氏は指摘しています。これにより、企業としてのコミュニケーション方法、報告体制、製品出荷方法、人材管理、組織化、採用プロセスなどすべてが崩れたとオーウェン氏は指摘。 また、「OpenAIの珍しい点は、本当にすべてがSlack上で動いているという点です」とオーウェン氏は主張しています。メールは一切利用されておらず、オーウェン氏の在籍期間(1年強)に受け取ったメールの件数はせいぜい10通程度だそうです。Slack上ですべてのコミュニケーションが完結する点について、オーウェン氏は「整理整頓ができていないと、非常に気が散ることになるかもしれませんが、チャンネルや通知を整理していれば、かなり快適です」と自身の見解を述べました。
この他、意思決定方式が研究分野においては「信じられないほどボトムアップ型」であるとオーウェン氏は記しています。オーウェン氏がOpenAIに入社したばかりの頃、次の四半期のロードマップについて質問したところ、「そんなものは存在しない」という回答が返ってきたそうです。なお、記事作成時点ではOpenAIにも四半期ごとのロードマップが存在するとのこと。OpenAIに四半期ごとのロードマップが存在しなかったことについて、オーウェン氏は「良いアイデアはどこからでも生まれますが、どのアイデアが最も実りあるものになるかは、事前にはっきりと分からないことがよくあります。壮大な『マスタープラン』が実を結ぶのではなく、新しい研究が実を結ぶにつれて徐々に物事の成否が明らかになっていくのです」と記し、OpenAIの成果を出したアイデアに注力する方法に理解を示してます。 また、ボトムアップ型の意思決定が好まれているため、OpenAIは実力主義文化が根付いているとオーウェン氏は指摘。OpenAIのリーダーは優れたアイデアを思いつき、それを実行する能力に基づいて昇進してきた人物たちです。通常、有能なリーダーであってもプレゼンテーションや政治的駆け引きを苦手とするケースがありますが、OpenAIは他社と比べてそういった要素があまり重視されないため、優れたアイデアがより高く評価されるとのこと。また、その優秀なアイデアをすぐさま実現するべく、すぐにチームを構成するなど「とにかく行動を重視する傾向」もOpenAIの特徴のひとつであるとオーウェン氏は指摘しています。 他にも、OpenAIは瞬時に方向転換することがあるそうです。これについてオーウェン氏は、「新しい情報を入手した場合、すぐに正しい行動をとる方が、現状維持よりもはるかに優れた選択です。OpenAIのような大企業が今でもこの精神を維持していることは驚くべきことです。Googleはもはやそうではありません。対して、OpenAIは迅速に意思決定を行い、方向性を決めたら全力で取り組みます」と語りました。
一方で、B2B企業で働いた経験のあるオーウェン氏にとっては衝撃的なレベルで厳しい監視が行われているとも言及。OpenAIが未発表のニュースをメディアが先に報じることがしばしばありますが、それゆえOpenAIは非常に秘密主義的な場所になっており、「自分が何に取り組んでいるのかも話せなかった」とオーウェン氏は述懐しています。 OpenAIはAGIの構築という目標を掲げていますが、その実現には多くの課題をクリアする必要があります。一方で、何億人ものユーザーがさまざまな用途で利用できるような製品を開発しようともしており、その最たる例がChatGPTです。さらに、OpenAIはMetaやGoogle、Anthropicといった企業との競争にも直面しています。なお、OpenAIは報道で中傷されることもありますが、オーウェン氏は「私がOpenAIで出会った人々は、皆正しいことをしようとしていました」と語りました。 さらに、「OpenAIは最先端の科学を探求する科学者や技術者の集団でした。その集団が偶然にも、史上最も話題になった消費者向けアプリを生み出しました。そして、政府や企業への販売という野心を持つようになりました。在籍期間や組織内の部署によって、目標や視点は大きく異なります。長くいるほど、物事を『研究室』や『社会貢献のための非営利団体』というレンズを通して見るようになっていた気がします」と述べ、OpenAI社内を一枚岩のように捉えるべきではないと指摘しています。 また、オーウェン氏はOpenAIを最も高く評価している点として、「AIの恩恵を社会に還元する」を挙げました。OpenAIの提供する最先端のAIモデルは、年間契約が必要なエンタープライズグレードのサービスに限定されているわけではありません。世界中の誰でもChatGPTにアクセスし、アカウントを作成しなくても利用可能です。他にも、スタートアップでも利用できるようほぼすべてのAIモデルがすぐにAPIに組み込まれるなど、あらゆるAIをあらゆるユーザーが利用できるようサービスを展開していると指摘。OpenAIの体制はわずか1年で大きく変化したかもしれませんが、「AIの恩恵を社会に還元する」という点において、OpenAIは多大な功績を残しており、「この考えは今も同社のDNAの中核を成している」とオーウェン氏は指摘しています。 オーウェン氏はOpenAIを「私がこれまで見てきた中で最も恐ろしいほど野心的な組織」と表現。「世界トップクラスのコンシューマー向けアプリをひとつ持っているだけで十分と思うかもしれませんが、OpenAIはAPI、ディープラーニング、ハードウェア、コーディングエージェント、画像生成、そしてまだ発表されていない複数の分野など、数十もの分野で競争したいという意欲を持っています。OpenAIはアイデアを採り入れ、実行に移すための豊かな土壌です」と語っています。
人材採用においては「景品を惜しみなく配る他社とは異なる」とオーウェン氏。ただし、在庫商品を販売する「ドロップ」と呼ばれるイベントが定期的に開催されているそうで、オーウェン氏が経験した最初のドロップではShopify上に構築された専用ストアがアクセス過多でダウンするほど人気だそうです。 OpenAIはX(旧Twitter)を非常に重視しているそうで、オーウェン氏の同僚が「この会社はTwitterのバイブスで動いている」と冗談を言ったこともある模様。 他にも、OpenAIの社内チームは非常に流動的で、エンジニア数名の協力が必要と上司に訴えた次の日には優秀なエンジニアがチームのサポートに駆けつけてくれたこともあるそうです。また、リーダーシップについて「OpenAIのような企業では当然のことかもしれませんが、幹部全員が非常に集中しているように感じました。リーダーはSlackで定期的に交流しており、不在ということはありませんでした」と語っています。
・関連記事 OpenAIの知られざる実態がわかる詳細調査レポート「The OpenAI Files」リリース、非営利の理想と営利の現実がもたらす危険性について - GIGAZINE
高性能AIの有料提供を進めるOpenAIはそもそも非営利団体だった - GIGAZINE
OpenAIが多様性・公平性・包括性のページを削除 - GIGAZINE