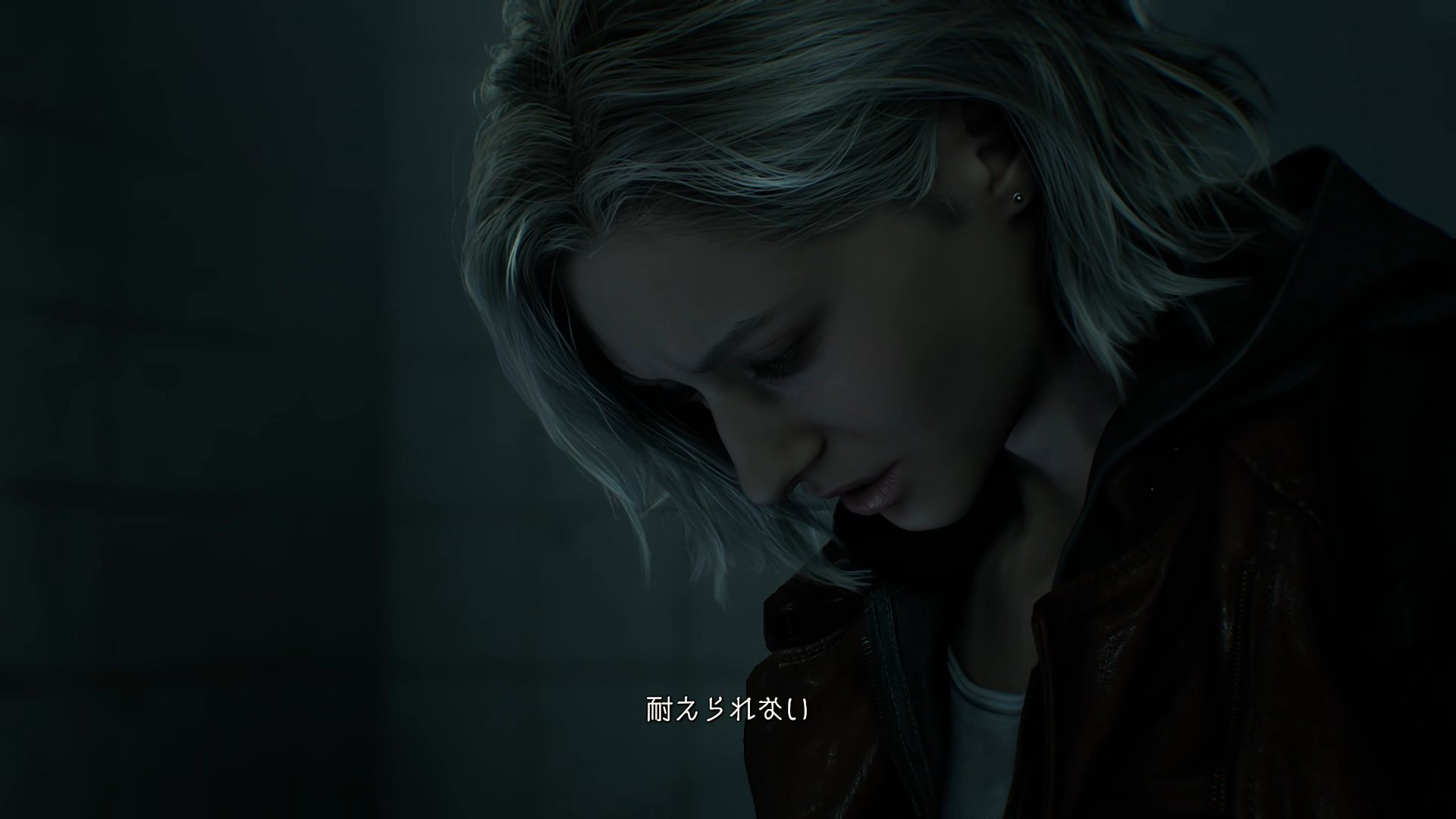【大河ドラマ べらぼう】第15回「死を呼ぶ手袋」回想 「そなたも世の者も、金の力を信じ過ぎている」現代にも響く武元の警告、意次の転機に 「博覧会」も先駆けていた源内 吉原に変革の機運

将軍家治(眞島秀和さん)の嫡子、家基(奥智哉さん)の不審死。陰謀の匂いがぷんぷんする一件の真相解明をめぐり、茶室で差し向かいになった松平武元たけちか(石坂浩二さん)と田沼意次(渡辺謙さん)の両老中です。共に大河ドラマで主演も含めて何度も主要キャストを演じている名優の共演に相応しく、これまでの「べらぼう」とは趣きを大きく変えた重厚なクライマックスとなりました。
武元の深い政治哲学、意次にも一目置いていた
これまで一貫して幕府内の守旧派の頭領という位置づけ。ドラマの中ではむしろヴィランというイメージさえあった武元ですが、ここでは一転、その地位に相応しい人としての器を見せつけます。家基の謀殺の手段となった手袋の調達に一役買っていたことから、武元に疑われていると思い込んでいた意次に対して、武元は「みくびるな」と威厳のあるひとこと。「そなたを気に食わぬとはいえ、この機を使い追い落としなどすれば、まことの外道を見逃すことになる。わたしはそれほど愚かではない」と語り、黒幕は意次以外の人物であることをすでに見抜いていました。さらに、もともと「疑っておらなかった」と明かした上で、「検校捕縛の折の西の丸様への諫言。あのようなことをするのは忠義のある者しかせぬ」と、実は意次に一目置いていたことも打ち明けます。
武元について伝統や格式にこだわり、現実を見ない分からず屋と思い込んでいた意次は、自らの不明を恥じるばかりでした。そして、ここからの武元の言葉が出色でした。石坂浩二さんならではの見事なセリフ回しにしびれました。
「金の力を信じ過ぎてはいないか?」 現代への警鐘も
「世の大事はまず金、それが当世であるのは、わしとて分かる。しかし、金というものは、いざという時に米のように食えもせねば、刀のように身を守ってもくれぬ。人のように手を差し伸べてもくれぬ。左様に頼りなき物であるにもかかわらず、そなたも世の者も、金の力を信じすぎておるようにわしには思える」。
現代の私たちも武元のような迫力でこう言われたら、思わず胸に手を当てるでしょう。今、まさに世界を揺るがせている様々な出来事や為政者に対する警告とも言えそうです。「べらぼう」全体のテーマとも深く関わってきそうな武元の問題提起でした。そして武元の考え方に共感した意次。それぞれの考え方の違いを理解した上で、もう一つ上の次元の協働に進める予感を漂わせた2人でした。しかし、事態はあっという間の暗転。
何者かが、真相に近づいた武元を危険視したのでしょう。間髪入れずここで再びの謀殺。そして証拠物件である手袋の隠滅まで。なんという手際の良さでしょうか。
近年注目の治済 今回も影の主役?
御三卿のひとり、一橋治済はるさだ(生田斗真さん)の関与を深くにじませて、ドラマはひとまず着地しました。近年、この時代の“影の主役”として注目を集める存在である治済。よしながふみさんの名作『大奥』はひときわ印象的で、この作品をドラマ化(脚本はやはり森下佳子さん)したNHK『大奥』でも、仲間由紀恵さんが演じた鬼気迫る治済は忘れられません。
実際、家基が亡くなったことで、世継ぎ候補となり得る男子、豊千代(のちの将軍家斉)がいる治済は大きなアドバンテージを獲得したことは間違いなく、その後の所業も含めて作り手の創作意欲を刺激する人物なのでしょう。一方、生田さんの大河ドラマといえば、『鎌倉殿の13人』の源仲章の際立ったキャラクターが見事でした。今度はどのような治済像を描いてくれるのでしょうか。
健康だった家基の急死については以前から疑問視する見方があり、諸説あるものの謀略があったとする確たる証拠はありません。武元の死のあり様も含めてドラマの見立てはもちろんフィクションですが、想像力豊かに幕府の権力争いをドラマチックに描いた森下佳子さんの巧みな脚本でした。この権謀術数渦巻く江戸城内で、そのど真ん中にいる意次はどう動くのでしょうか。
源内、地に足のついた業績も豊富
起死回生の切り札だったはずのエレキテルはバッタもんが出回る始末。江戸の町中どこに行ってもイカサマ師扱いです。やることなすこと上手くいかない平賀源内(安田顕さん)は市中で竹光を振り回すなど、明らかに様子がおかしくなりました。
意次の知遇を得て、日の出の勢いだったころを思い出し、「おれはこんなはずではなかったのに」とため息をつく源内が哀れでした。
彼の脳裏に浮かんだのは「物類品隲ぶつるいひんしつ」。学者としての源内を代表する重要な書籍です。ドラマで描かれた時期(1779年)から遡ること15年以上。1763年(宝暦13)に著されました。
「博覧会」の先駆けを主催、その成果をまとめた
このころ、源内は全国各地の物産を集めた「薬品会」を精力的に開催し、大いにその名を高めました。日本における博覧会や博物館のはしりと言われます。ここに集まった約2000種の産物のうちから、重要と思われる360種について解説を加えたのが「物類品隲」でした。
平賀国倫 編『物類品隲 6巻』[1],柏原屋清右衛門[ほか],宝暦13 [1763]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555265平賀国倫 編『物類品隲 6巻』[1],柏原屋清右衛門[ほか],宝暦13 [1763]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555265このように外来のものも含めて収録しており、和漢名以外に、オランダ語の名前のものも登場しています。源内の広範な知識が示されます。 平賀国倫 編『物類品隲 6巻』[6],柏原屋清右衛門[ほか],宝暦13 [1763]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555270第6巻では朝鮮人参と甘藷(サツマイモ)の栽培法や精糖法を挿絵も交えながら詳述しています。 平賀国倫 編『物類品隲 6巻』[6],柏原屋清右衛門[ほか],宝暦13 [1763]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555270平賀国倫 編『物類品隲 6巻』[6],柏原屋清右衛門[ほか],宝暦13 [1763]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2555270当時、朝鮮人参や砂糖は海外からの輸入に頼っていました。自給体制を構築することによって、国益の増進を図ろうという狙いがありました。意次との会話でも常々、自国の産業振興の重要性を訴えていた源内の実践例です。高い理念と実証精神に裏付けられた源内の面目躍如の一冊です。現代の万歩計にあたる量程器も自作しました。その行動力、独創性とも破格の人だった源内。意次に売り込んだ蝦夷地の砂金は、危うい橋のように見えますが果たして……。
「解体新書」の成立にも助力した源内
源内とは縁の深い杉田玄白(山中聡さん)も登場。こちらもこの時代を語る上で不可欠な人物です。
玄白らによる「解体新書」(1774年刊)の偉業にも源内は助力しました。「解体新書」の図版を描いたのは秋田藩士の小野田直武です。鉱山指導のために秋田に来ていた源内から西洋画の技法を学んでいました。その後、小野田は藩命で上京。源内の紹介で歴史的な「解体新書」の仕事に関わったとみられます。
キュルムス 著 ほか『解體新書 4巻序圖1巻』[1],須原屋市兵衛,安永3 [1774]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887キュルムス 著 ほか『解體新書 4巻序圖1巻』[1],須原屋市兵衛,安永3 [1774]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2558887杉田玄白も、恩人である源内の最近の言動に懸念を隠しませんでした。破天荒でも周囲が放っておけなくなるのが源内の人徳だったのでしょう。“早く生まれ過ぎた天才”の悲哀を色濃くしながら、源内の人生の終着点が否応なく近づいてきます。「芸者」を管理、吉原改革の一歩に
忘八の主要メンバーで、蔦重の理解者でもある大黒屋のりつ(安達祐実さん)が「女郎屋をやめて、芸者の見番をやる」と言い出し、忘八の間で波紋が広がりました。どういう意味でしょう。これは史実に沿った展開でした。
そもそも女郎と芸者を混同する向きもあるかもしれませんが、2つは別のものです。「江戸花街沿革誌(下)」(1894年、六合館弦巻書店刊 関根金四郎編)などによると、三味線の流行とともに遊女の中にも演奏をするものが現れ、徐々に役割が分担されて若手の女郎の中で得意な者が、座敷で披露するようになりました。宝暦(1751‐1763)の末期になると、女郎が技芸を行うことはなくなり、踊りや演奏を行う芸者が専門化されました。
喜多川歌麿筆「青樓仁和嘉女藝者部・大万度 荻江 おいよ 竹次」江戸時代・天明3年(1783) 東京国立博物館蔵 出典:ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)安永7年(1788)には芸子(長唄、豊後節、一中節、義太夫節など格段の技芸に達した女性の芸人)が16人、芸者(三味線を弾いて流行の小唄などを歌う女性)50余人、男芸者20余人の約100人の芸者が吉原にいて、お座敷を盛り上げました。りつが「見番をやる」と言ったのは、この人たちのマネジメントを専門に行う、ということなのです。史料によると安永8年(1779)、吉原の角町で女郎屋を経営していた大黒屋が同業者と相談した上で見番所を設置、女郎屋を廃業して見番所の運営に専念しました。吉原にとって、それほど重要な案件だったということでしょう。
保護された芸者、人気高まる
りつが「建前で禁じても、女芸者が色を売っちまう、売れされちまうというのはあとを絶たない」と言っていたとおり、現実には一部の芸者は身体を売ることが常態化していたため、見番の導入によって女郎との違いを明確にしました。報酬の透明化や華美な服装の禁止、複数人での接客を義務化するなどの措置が取られました。
一連の対策は、吉原の最優先事項である女郎の職域を侵害させない、という意味がありました。一方、吉原芸者は技芸に通じた者しかなれない別格の存在として江戸中で認知され、吉原挙げての祭り「俄」でも主役を張る人々になります。年々人気も高まり、明治直前の慶應年間には男女合わせて379人もの芸者が吉原で活躍しました。
蔦重の夢、前進するか
忘八たちの議論は、蔦重の諫言を受けた駿河屋(高橋克実さん)が「女郎や女芸人にとって、吉原をましな場所にしていこう」と呼びかけ始まりました。「吉原を、女郎がいい思い出をいっぱい持って出ていける街に」という蔦重の夢にはまだ程遠い現実ですが、これから吉原は変わっていくのでしょうか。
(美術展ナビ編集班 岡部匡志) <あわせて読みたい>
視聴に役立つ相関図↓はこちらから