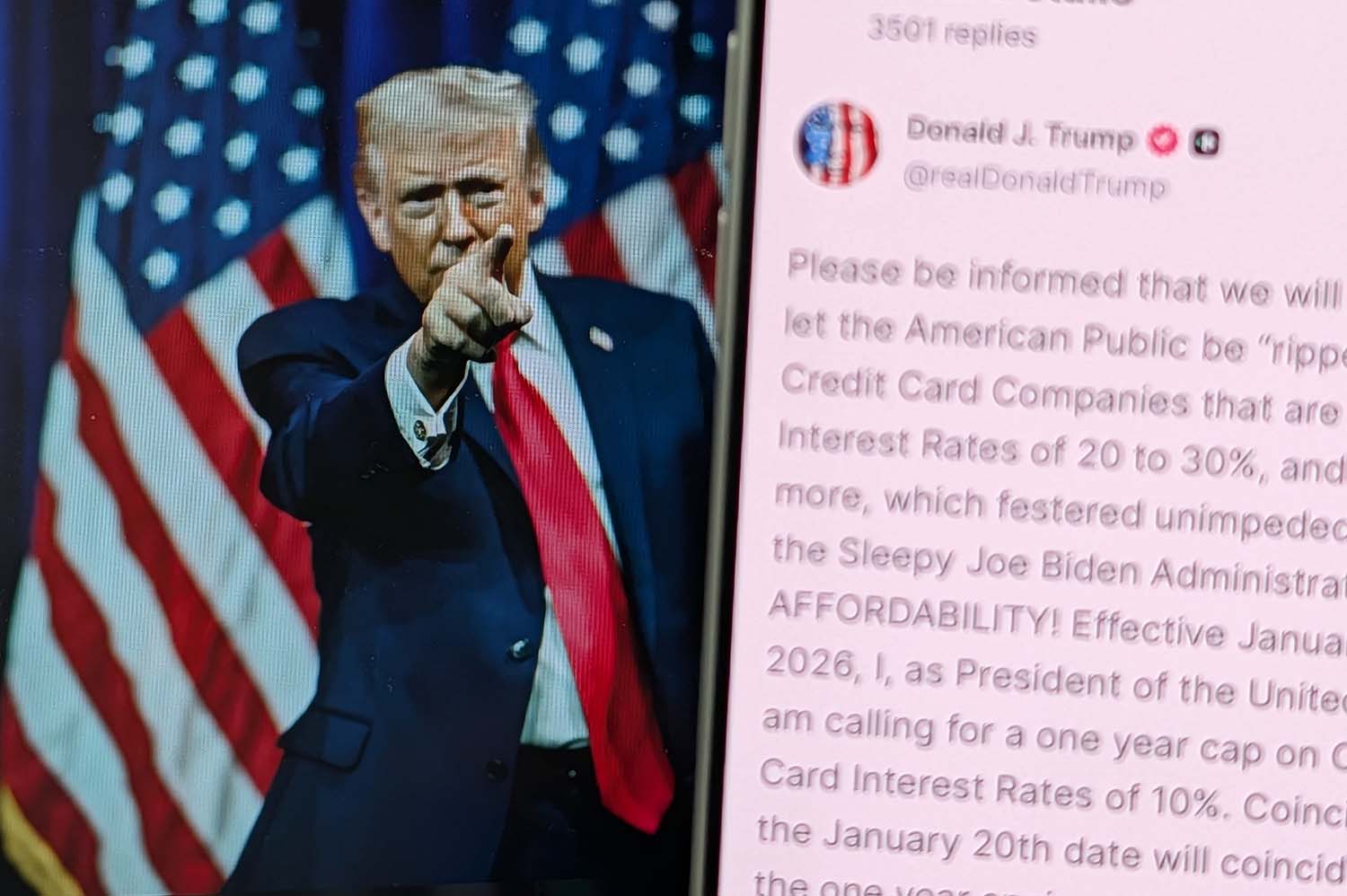【コラム】トランプ関税の行き着く先、中国を再び偉大に-バスワニ

同盟国には親切にすべきだと、米国の駐中国大使を退任したニコラス・バーンズ氏は言っていた。米国が世界の覇権争いで中国に勝つにはどうすべきかという質問に対する答えだ。アジアで米国が影響力を維持したいのであれば、トランプ大統領はこの助言に従うべきだ。
アジアの国々は今のところ「トランプ関税」を回避するための交渉に臨もうと躍起だが、長期的にはアジア各国同士で協力関係を強化する方向に動くだろう。
また、新たな関税で罰したりしない中国に再び接近することのメリットも検討するだろう。ただし、インド太平洋地域における拡張主義的な言動によって中国の魅力は損なわれている。米政府は、中国の行動に対してこの地域が抱く不安をうまく捉える機会を逃している。
トランプ氏は貿易相手国が米国に与えたと認識しているダメージを是正しようとしており、中国のようなライバル国を追い詰めることは理にかなっている。しかし、その他の幾つかの決定は不可解だ。
トランプ関税はほとんどの国がその影響を免れることはできない。オーストラリアやインド、日本、韓国といった同盟国でさえ例外ではない。
そして、インドネシアや台湾、ベトナム、シンガポール、フィリピンなど米国がこの地域における中国の台頭に対抗する上で、重要な役割を担ってきた国・地域を関税の標的とすることは逆効果だ。
以前のコラムで指摘したように米国への信頼が一夜にして損なわれることはないが、トランプ関税の影響は今後数十年にわたり続くことになるだろう。
どの国と貿易を行うか、どの国と安全保障同盟を結ぶか、どの国から武器を購入するか、どの国に開発援助を求めるか、どの国と情報を共有するかといった決定に、その影響が表れることになる。
米国は、こうした結び付きから最大の恩恵を受けてきた。米海軍大学校のサリー・ペイン教授によれば、米国は海洋大国として開かれた国際貿易と海上交通路を維持することで自国経済を発展させた。そしてそのことが世界の安定に貢献してきたという。
米国とその同盟国は豊かになり、同時に全体としてより安全になった。このことが、インド太平洋地域における米国の戦略的優位性を維持するのに寄与してきた。これは、最近アジアを訪れたヘグセス国防長官も認めている。
米国は今、この優位性を失うリスクに直面している。
トランプ関税が発表される前に実施されたシンガポールのシンクタンク、ISEASユソフ・イシャク研究所が東南アジアの2000人余りを対象とした最近の調査が、この問題を浮き彫りにしている。
同調査では、米国と中国のどちらかを選ばざるを得ない場合、米国を選ぶとの回答が多かった。これは昨年とは逆の結果だ。主に南シナ海などにおける中国の軍事力誇示に対する懸念が背景だ。
だが、もし今、同じ質問を投げかければ、かなり異なる回答になる公算が大きい。アジア各国はすでに選択肢を検討している。10カ国から成る東南アジア諸国連合(ASEAN)の経済担当相は今週、クアラルンプールでの会合で協調的な対応策を探る予定だ。
マレーシアやシンガポールなどはグローバル化から大きな恩恵を受けており、米国の関税賦課による悪影響についてすでに懸念を表明している。
シンガポールのウォン首相は、「1930年代」のような、より危険な世界になる可能性を警告。「貿易戦争が武力衝突にエスカレートし、最終的に第2次世界大戦へとつながった」時代に入り得るとの懸念が浮上している。
中国の攻勢
トランプ政権と対照的に、中国は友人たちへの対応の仕方を心得ていることを示している。昨年12月には外交関係を持つ全ての途上国から輸入する特定品に対する関税をゼロに引き下げた。
中国は地域的な包括的経済連携(RCEP)の推進役も担う。RCEPは15カ国から成る世界最大級の自由貿易協定(FTA)で、2022年のデータに基づくと世界全体の国内総生産(GDP)で29%相当を占める。米国が進める経済政策の影響を和らげるために、さらに多くのアジアの国々が参加を希望する可能性が高い。
中国は今、攻めに出ている。3月末に開かれた日本と韓国との3カ国の経済貿易担当閣僚会合では、開放的かつ公平な貿易をあらためて呼びかけ、経済関係を深めると誓った。
何か取り決めが結ばれたわけではないが、歴史認識や対米関係の違いにもかかわらず、会合が開催されたという事実自体が日中韓が関係強化に意欲的であることを示す兆しだ。
米国に代わる市場はない。23年の米家計支出は19兆ドル(約2790兆円)に達し、欧州連合(EU)の倍、中国の3倍近い規模だ。そうした中で、中国は世界貿易の変化を乗り切るために切羽詰まった国々に必要なものをまさに提供しつつある。
アジア各国はさらなる経済的打撃から自国を守るため、米国との関係を維持しながら、より緊密に協力していく以外に選択肢はないだろう。
アジアでは米国との同盟・協力が所得と生活水準の向上に寄与してきた。そのため、現在は予測不可能な状況であるにもかかわらず、各国はこれを続けていきたいと考えている。
米国の気まぐれな政策の影響を受けているEUのような他のパートナーと手を組むことも、共通の不満を踏まえれば賢明な策だ。防衛・軍事関係も再調整できるだろう。すでに日本と北大西洋条約機構(NATO)は情報共有と防衛産業協力の強化について協議している。
トランプ氏の貿易戦争は始まったばかりだ。米中という2つの超大国が共に悪あがきをする中で、そのはざまに立たされた国や地域は損失を最小限に抑えようとしている。
アジア各国は何とかこの状況を切り抜けようと模索しているが、長期的には中国を視野に戦略的優先順位の再編が行われるだろう。世界貿易を巡る対立が招いたトランプ関税が、インド太平洋地域における地政学の地図を中国を中心に塗り替える可能性がある。
(カリシュマ・バスワニ氏はブルームバーグ・オピニオンのコラムニストで、中国を中心にアジア政治を担当しています。以前は英BBC放送のアジア担当リードプレゼンテーターを務め、BBCで20年ほどアジアを取材していました。このコラムの内容は必ずしも編集部やブルームバーグ・エル・ピー、オーナーらの意見を反映するものではありません)
原題:American Tariffs Are Making China Great Again: Karishma Vaswani (抜粋)