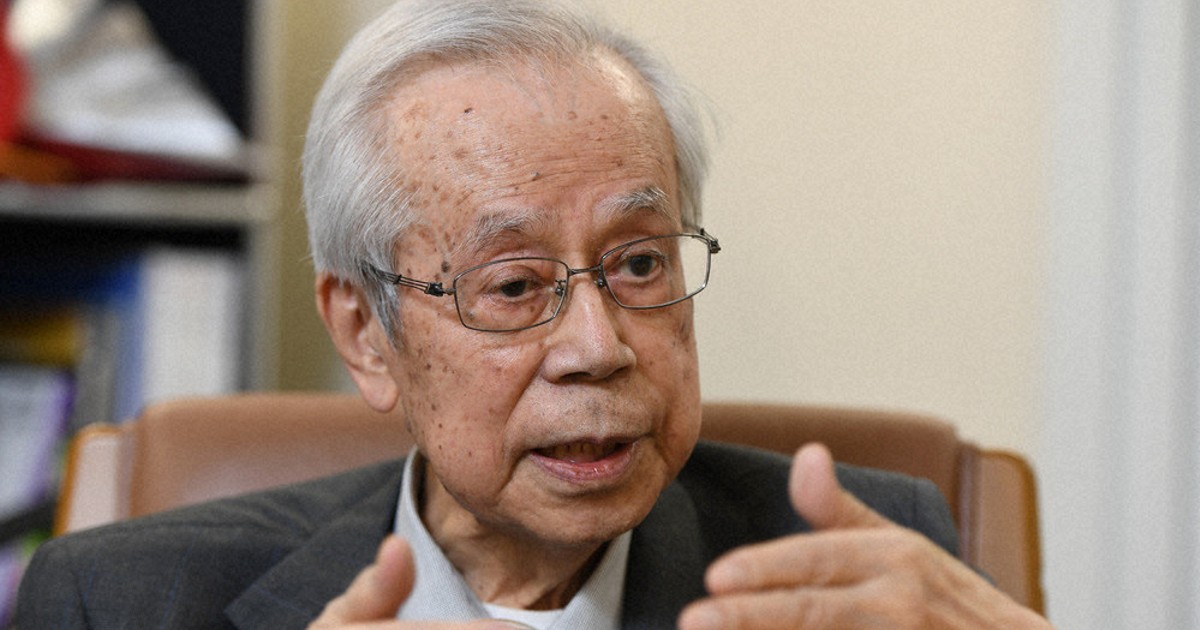戦争を肯定するフェミニズム、イスラエルの虐殺を止めることができないG7…西欧の民主主義の死(集英社オンライン)

李 僕の本や『PLURALITY 対立を創造に変える、協働テクノロジーと民主主義の未来』(サイボウズ式ブックス)という本は、AIとかSNSというテクノロジーに注目が行きがちなんですけども、三牧先生はそれだけではなく「民主主義の脱欧米化」というところに注目してくださいました。それは現在の世界の状況を考えるにあたって、実に時宜にかなった着眼点であると思います。 イスラエルによるイランへの攻撃に対して、イスラエルの元首相が現ネタニヤフ政権を批判したり、それにもかかわらず、ドイツの首相が「イスラエルは汚れ仕事をしてくれた」と発言したり。イスラエルが一方的にイランに勝利できるとわかった途端にアメリカが介入しようとして、その介入に関してもトランプ支持者の中で賛成・反対が分かれたり……。 戦後秩序、すなわち「人道主義」とか「法の支配」というような理念を自分たちが体現していると誇ってきた欧米の秩序が、もはや信頼を失ってしまっている。現状において、三牧先生が書評で書かれていた「民主主義の脱欧米化」という問題がシリアスになってきていると思います。その点について、先生の御意見をお伺いしたいと思います。 その前提として、まずはSNSや生成AIというテクノロジーの話をしたいのですが、先生と竹田ダニエルさんとの共著『アメリカの未解決問題』(集英社新書)を読ませていただきまして、それによると、アメリカのZ世代って結構左派寄りというか、バーニー・サンダースの支持者が多かったりする。 実際僕もコロンビア大学にいた頃は、まわりの学生はサンダース支持者が多くて、自分のノートPCにサンダースのステッカーを貼ったりしていたんですけど、同時にZ世代のトランプ支持者もそれなりの数がいました。 AIやSNSというテクノロジーは、アメリカをはじめとしてリベラルに対して有利に働くのか不利に働くのか? どうお考えでしょうか。 三牧 この対談をしている今日は6月20日ですよね。カナダで開催されていたG7サミットが数日前に終わったところですが、まさかトランプ大統領が途中で帰ってしまうとは……確かに1期目のときからトランプ大統領の多国間協調への嫌悪は明らかであり、2期目がスタートしてからの5か月間を見ても、トランプ大統領が、民主主義や「法の支配」を共有しているはずの日本やヨーロッパなどの同盟国より、中国やロシアといった権威主義的な大国、トランプ大統領が言うところの「カードを持っている国」とのディールを好むことは明らかでした。 ですから、相当な紛糾とか、そもそも停滞が予想されたサミットではありましたが……。 しかし、問題はトランプ大統領だけにあるわけではありません。G7という枠組みそのものの欺瞞性も明らかになりました。 イスラエルはイランへの攻撃を「存亡の危機を打開するための先制攻撃」と位置付けましたが、国際法上、許されない「予防攻撃」と位置付けるべきだと思います。「先制攻撃」は、他国からの攻撃の脅威に直ちに直面している場合、これを阻止するために攻撃することで、これが国際法上の自衛権の範囲として認められるかは議論を呼ぶところです。しかし、「予防攻撃」は、他国が自国を攻撃する兆候もないのに、「将来的に脅威になりうる」として攻撃することです。これは国際法上、認められていません。 ところが、イスラエルによる攻撃の直後にカナダで開催されたG7サミットで、こうした法的な議論はまったくなかった。それどころか、トランプ大統領の意向が全面的に反映されたという共同声明は、イスラエルを批判することなく、イランの核開発の脅威をもっぱら強調し、イスラエルの安全保障上の懸念はもっともだとその軍事行動にお墨付きを与える内容のものでした。 そして、「自衛権」という言葉で法的に擁護できないのは明らかだからでしょう、イスラエルには「自国を守る権利がある」と不可思議な表現が用いられていました。他方、イランにも当然自衛権があるはずですが、それへの言及はゼロ。結局、イスラエルによるイランの核施設攻撃に対する行動を容認して、イスラエルの自衛権だけを認める不均衡なものとなりました。 当初石破首相は6月13日の攻撃について厳しい言葉で批判していたのですが、こうした日本の立場もG7の共同声明にはまったく反映されませんでした。声明には、「双方に自制を求める」という言葉すら盛り込まれなかった。「法の支配」を理念として掲げてきたG7も、イスラエルのことになると完全にその声を潜めてしまう、その欺瞞が再び露わになりました。 私たちは、ガザにおける人道危機が極限化しても、イスラエルに武器を送り続け、批判することすら及び腰なG7を見てきました。 そうした意味で今回のG7共同声明は、驚くべきものではないのですが、その上で、「知ってはいたけど、ここまであからさまに、無理筋なイスラエル擁護を通すのか!」という驚きを伴うものでした。 「法の支配」という理念は、結局、欧米にとって都合の良い時だけ掲げられるものに過ぎない。ウクライナ戦争のように自分たちのフレームワークにはまりやすい問題に関しては、「法の支配」を掲げてロシアを批判するけれども、「法の支配」や「民主主義」を共有しているイスラエルが、そうした理念を踏みにじった行動を取っても、理念を掲げて批判することはしない。そして今回のイランも同様に、「西洋と敵対する国」への軍事行動の場合は、明らかに国際法に反していても批判すらしない。むしろ踏みにじっている側に法的な根拠とか道義的な根拠があるような主張をしています。